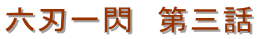
「分担して頂くまでもありません、普段の警護は私が責任をもって勤めさせて頂きます。」
「術の方は私に任せろ。結界を張り直し、式神を置いておく。神子と頼久には護法をかけておく。」
「はい?」
張り切る頼久と泰明の二人とは裏腹に、あかねはきょとんとした顔で一同を見渡した。
「神子殿、敵が証拠になるようなものを残すような失態を犯すまで待つということは、その間、神子殿の身が危険にさらされるということです。こちらは守りを固めなくてはなりません。」
「あ、ああ、そうですよね……。」
「私も色々と調べてはみますが、そう簡単に尻尾を見せるような相手ではなさそうですし、長丁場になるかもしれません。」
そう言って鷹通はメガネの位置を直した。
「俺もちょくちょくこっちに顔出すし、市なんかで情報収集もしといてやるよ。」
「わたくしは主上に一応事情を説明申し上げておきます。時間が許す限り、こちらにも参上しますので。」
イノリと永泉がそう言って微笑むのを見てあかねは悲しそうにうつむいてしまった。
自分の判断が仲間達に負担を強いているということに気付いたからだ。
「ごめんなさい、みんなに迷惑かけちゃって……でも、私……。」
「神子殿、我ら八葉は神子殿のお心にかなわぬことをするつもりはございません。お気になさいませんよう。」
そんな頼久の優しい言葉さえ今はつらくて、それでもどうしても拷問とか呪殺とかいうことを許すことはできなくてあかねは泣き出しそうになるのを必死にこらえる。
「さて、では私も情報収集とやらをしてこようか。」
「友雅殿……このような状況で女性のもとへでも行かれるおつもりですか?」
「情報収集だよ、鷹通。では頼久、神子殿のことは頼んだよ。まぁ、許婚なのだし、昼夜問わず神子殿のお側近くでお守りして差し上げてくれ。」
「昼夜問わずお側近くとは…その……そういうわけには……。」
「許婚なのだしかまわぬだろう?神子殿と御簾の内で睦言を言い交わすいい口実ができたじゃないか。」
「友雅殿っ!そのようなことを言っている場合ではっ!」
「ね、神子殿。せっかくだから頼久に守ってもらいながら睦言の一つも贈ってもらうといいよ。」
「むつごとってなんですか?」
真っ赤になっている頼久をからかうのが楽しくてしかたないらしい友雅だったが、このあかねの問いに笑みを深めた。
この無垢で素直な神子殿にはかなわない。
「まぁ、それも頼久に教えてもらいなさい。では、私は失礼するよ。」
「友雅殿っ!」
からからと笑いながら友雅は退場してしまい、後に残された頼久はというとあかねの「むつごとってなぁに?」と言いたげな視線に冷や汗をかき始めた。
「で、では、わたくしも主上のもとへ……。」
「あ、お、俺も情報収集いってくるわ。」
「私も仕事に戻りながら情報を集めてみます。」
このままだと自分達の方へ「むつごとってなぁに?」の視線が回ってくると予感した三人は一斉に立ち上がり、そそくさと立ち去ってしまった。
残った泰明はというと…。
「では、私は賊に話を聞いてみよう。忠誠心のない者ならばあっさり吐くかも知れぬからな。」
「拷問はダメですからっ!」
「承知している。一応、式神を庭の隅に置いておく。あとで結界も張り直す。夜になる前には護法をかけにくる。」
そうとだけ言って泰明もやはりそそくさといなくなってしまった。
顔には表さないものの、どうやらやはり「むつごとってなぁに?」とあかねに聞かれることを避けたらしい。
そして結局二人きりになった頼久とあかねはというと、静かな局の中で隣り合って座っているという状態になってしまった。
「頼久さん。」
「は、はい…。」
「それで、友雅さんが言っていたむつごとってなんですか?」
「それは、その……なんと申しましょうか………。」
できることなら頼久もこの場から逃げ出したかったが、一人でも神子を警護すると断言したばかりで逃げ出すこともできない。
だいたい、いつ次の賊があかねを襲ってくるかわからないこの状況で側を離れることなどとうていできるはずもなかった。
「何か言いづらいことなんですか?」
頼久があまり言いよどむものだから、あかねはとうとう心配そうな表情で頼久を見上げた。
隣で自分を見上げる愛しい人のつぶらな瞳を見てしまっては頼久の緊張は増すばかりで、赤い顔のまま凍りつく頼久にあかねは更に顔を近づける。
「顔、赤いですよ?具合悪いんですか?」
「い、いえ、ご心配頂くほどのことでは……。」
「ひょっとして私、ものすごく聞いちゃいけないこと聞いてます?」
「そ、そういうわけでもないのですが…その……私は元来の口下手ですので……。」
「そうですよね…ごめんなさい、苦手なことお願いしちゃって。今度、鷹通さんにでも説明してもらいますね。」
自分を気遣ってくれている許婚の愛らしい笑顔を見て、それから今目の前にいる愛しい人が鷹通に「むつごと」について質問している様を想像した頼久は、急に隣に座っているあかねの肩を抱き寄せた。
無邪気に質問するあかねと、それにテレながらも的確に答える鷹通を想像してしまった頼久は、自分の脳内でいい雰囲気になっている二人に焦ったのだ。
「頼久、さん?」
顔を上げようとするあかねの頭を軽く抱きしめて頼久はその耳元に口を寄せた。
「お慕いしております、神子殿。」
「は、はい?ど、どうしたんですか?急に。」
「睦言です。」
「はい?」
「今のが睦言です。」
「あ、あぁ…なるほど……。」
やっと言われていることがわかったあかねは頼久の腕の中で真っ赤になった。
何故、友雅が面白がっていたのかも、頼久がいつになく言いよどんでいたのかも納得した。
時にとんでもなく恥ずかしいことをさらりと言ってのける頼久だが、こんなふうにストレートに想いを表現してもらえることはそうそう頻繁にはないから、あかねも嬉しいような恥ずかしいようなで何もいえなくなってしまう。
「友雅殿ならば、もっと気の利いた睦言をお贈りするのでしょうが…。」
「私…私は頼久さんの言葉の方がいいです。すごく真剣で、すごく大切な想いが伝わってくるから…。」
「お分かり頂けて光栄です。」
頼久の腕から力が抜けたのであかねがふっと視線を上げると、そこには心の底から幸せそうに微笑んでいる紫紺の瞳があった。
思わずあかねはその瞳に見惚れてしまう。
許婚とはいうものの、まだ婚儀を済ませてないという理由で頼久はいまだにあまりあかねに必要以上には近づかない。
だから、こんなに近くで愛しい人の顔を見つめるのは久々で、あかねはそのままうっとりと頼久の顔を見上げ続けてしまった。
結果、それに気付いた頼久が今度は自分達の状況に気付いてさっと顔を赤くすると、軽い身のこなしですっとあかねから離れてしまった。
「頼久、さん?」
「いえ、その……神子殿がその…あまりお美しいので……。」
「そ、そんなことは……。」
いつもの調子で二人で微妙な距離をとったまま赤くなってうつむいて、そのまま静かな時間が流れ始める。
昨日、賊に襲われたとは思えないほど静かで平和な時間。
だが、そんな二人を庭の隅で見つめる泰明の姿をした式神だけが、普段とは違っていることを物語っていた。
あかねがしくしくと泣いている。
目の前にいるのは神妙な面持ちの八葉の面々だ。
夕暮れ時、泰明によって招集された面々は頼久の隣で泣き崩れるあかねを見ることになってしまった。
怨霊と戦う時に見せた気丈さなど微塵も感じられないほど弱々しく泣いているあかねは、それはそれで愛らしく、八葉一同どうやって慰めようかと思案に暮れる。
だが、不機嫌そうな泰明の口からどうしてあかねがこうして泣いているのかの説明が始まるに至って、八葉一同は我に返った。
「賊が死んだ。」
なんの前触れもなくいきなり泰明が語ったのはそれだけ。
わけがわからないと一同の目は頼久へ向いた。
ずっと神子の側につききりだったはずの頼久ならば何が起こったのかよくわかっているだろうと思ったからだ。
だが、こちらは元来の口下手な上に今は隣で泣いている許婚が気になってしかたがないようで、仲間達の視線に一向に気付く気配がない。
深い溜め息をついた友雅は今度はその視線を永泉に向けた。
言葉のたりない相棒を促すにはこの天の玄武に頼むのが一番だ。
そんな友雅の視線に気付いて永泉が口を開いた。
「泰明殿…その、もう少々わかりやすくご説明頂けると……。」
「昨夜、神子を襲ってきた賊を捕らえておいたのだが、それが死んだ。」
「はぁ…。」
「まだわからぬのか?」
訝しげに顔をしかめる泰明に永泉が涙目になる。
「そ、その事実はわかりましたが、何故…。」
この屋敷には再び泰明が結界を張った。
武士団の警護もあるし、今度は泰明の式神もこの屋敷の警護に当たっている。
二度も同じような賊に入り込まれることなどあり得ない。
だというのに何故賊は死んだのか、それが一同の一番の疑問だった。
だが、その疑問に泰明はいとも簡単に、そして簡潔に答えた。
「自害した。」
事情を知っていた泰明と頼久を除く八葉全員が凍りついた。
暗殺されたのでも呪殺されたのでもない、自殺。
その事実は少なからず一同に衝撃を与えた。
しばらく皆が黙って驚いていると、説明がたりないと思ったのか再び泰明が口を開いた。
「忠誠心が薄ければ事情を吐くかと昼間のうちにいくつか質問をしたのだが、何も答えなかった。だから縛り上げて放っておいたのだがさきほど再び質問しようとしたところ舌を噛んで自害していた。」
泰明がやっとそう淡々と事情を説明すると、あかねが今度は頼久の胸にすがって声をあげて泣き始めた。
「私が…放してあげて、くださいって…お願いして…いれば……。」
しゃくりあげながらそう言って泣き崩れるあかね。
そしてそのあかねの肩を優しくかき抱いて慰めるように髪をなでる頼久。
二人の姿を見ていた泰明以外の八葉の面々は状況が状況であるにもかかわらず、思わず苦笑をもらした。
「神子殿のせいではありません。不埒をはたらいた賊を何もせずに解放する者などいはしません。」
「そうそう、頼久の言う通りだよ、神子殿。そう神子殿が自分を責めて泣いてばかりいては我々もどうしていいかわからなくなってしまうよ。どうか、泣き止んではくれないかい?」
優しい友雅の声を聞いてあかねはやっと頼久から離れて、なんとか涙をこらえる努力を始めた。
「しかし、己の口から主の情報を漏らさぬために自害とは…敵はずいぶんと忠誠を捧げられた相手のようですね。」
「そう、とも限らないけれどね。」
鷹通の言葉に友雅は不敵な笑みを浮かべて見せた。
とたんに鷹通の顔が不機嫌そうに曇る。
「何をご存知なのですか?」
「何をと言われれば、大人の汚い一面を、だろうねぇ。」
「友雅殿、ふざけている場合ではありません。」
「ふざけてなどいないよ、鷹通。自害した賊は人質をとられていたのかもしれない、と言っているだけだ。」
「人質…。」
鷹通はそうつぶやいてうつむいた。
他の八葉達も一様に苦しげに表情を崩す。
もし、家族を人質にとられていたりしたら、自分が拷問にあって何か話してしまわぬように自害してもおかしくはない。
万が一、神子が敵方の手に落ち、人質とされてしまったら…
八葉達は一瞬そう考えて顔色を青くした。
「人質なんて…そんな…ひどすぎます…。」
一度涙をおさめたあかねが再び涙を袖で押さえる。
「そうと限った話ではないよ、神子殿。鷹通の言うとおり忠誠心から自害したのかもしれないからね。」
そう言いながらも友雅が本気でそう言っていないことは誰の耳にも明白だった。
特に内裏の事情をよく知っている永泉などは友雅の言う人質を取られているという可能性の方が高いだろうと判断して更に暗くふさぎ込んだ。
「どっちなのかは黒幕とっつかまえりゃわかるだろ。もし人質なんかとってたら、ぶっとばしてやりゃいいじゃん。」
「人質、だろうな。神子をさらおうなどという不埒な考えを起こす者が忠誠の対象となり得るはずもない。だが、そのようなことはどうでもよかろう。」
イノリに続いて発言したのは泰明だ。
どうでもいいという泰明の言葉に一同はすっと視線を厳しくした。
「泰明殿、どうでもよいということは…。」
「どうでもよいことだ。今重要なのは、神子が狙われ続けているといこと、賊の正体を明かすだけの証拠が何もないということ、その証拠の一端だった賊が自害して手がかりが絶えたということだけだ。」
いつものように冷静な、だがどこか怒りを含んでいるようにも聞こえる泰明の言葉にあかねが視線を上げた。
残酷とも言える泰明の発言にいつも怒るのはあかねの役目だ。
「泰明さん。」
「なんだ?」
「自殺した人達、放ってあるんですか?」
「ああ、今のところは。」
「じゃぁ、永泉さん、お弔い、お願いしてもいいですか?」
あかねの視線を受けて永泉は弱々しく微笑みながら一つうなずいた。
「承知致しました。」
こんな時まで自害した賊のことを思う神子。
その尊さに一時すさんだ八葉の心はどこか暖かく満たされた。
「それから、泰明さん、結界なんですけど、少しだけ隙を作ってもらえませんか?」
思いがけないあかねの言葉に白虎の二人を除く全八葉が目を大きく見開いた。
そして驚きを見せなかった白虎の二人は、互いに顔を見合わせて深い溜め息をついた。
「まさか神子殿、囮になるつもりかい?」
「そのように危険なこと、賛成致しかねます。」
友雅と鷹通にあかねはきりりと凛々しい表情を浮かべて見せた。
それは龍神の神子として怨霊と戦っていた時のあかねを彷彿とさせる顔だ。
友雅と鷹通は顔を見合わせて苦笑した。
「このままじゃいられないじゃないですか。このまま放っておいたらもっとたくさん犠牲者が出ちゃうかも…。」
「ですが、神子を危険にさらすようなことはできません。」
「永泉の言うとおりだ。敵にいくら犠牲が出たところで、所詮はくだらぬ輩どもだ。神子の命の尊さに比べればどうということはない者達だ。」
「違います。命にくだらないも尊いもないんです!命は命、みんな尊いんです!だから、これ以上誰も犠牲にしたくないから…。」
永泉と泰明が最後の抵抗を試みたが、どうやら尊き龍神の神子はこの二人の言葉も却下らしい。
次に口を開いたのは玄武組二人が撃沈したのを見て苦笑を浮かべている友雅だ。
「神子殿の言いたいことはわかるがね、永泉様と泰明殿の言うことももっともだよ。他人に不利益をもたらそうとたくらむような輩の命の心配までしてはいられないというのが本音だ。」
低く響く友雅の声はいつになく真剣で、あかねよりも遥かに年上の大人の言葉はやはり重みがある。
だが、口答えはしなくともあかねが友雅を見つめる眼差しには抗議の色がはっきりと見て取れた。
そしてそんなあかねの視線の意味に気付いて友雅は苦笑を深くした。
「まぁ、我ら八葉は神子殿の従者だ。神子殿の決定には従うがね。相手がどんなにくだらない輩であろうと神子殿は彼らを危険にさらしたくはない。彼らを守るために御自らの命を危険にさらしても。と、そうおっしゃるのかな?我が姫君は。」
「みんな何か勘違いしてます。」
そう言って軽く溜め息をつくあかねに八葉の一同が小首を傾げた。
何を勘違いしているというのだろう?
「いいですか、まず、みんなは従者なんかじゃありません、仲間です。いいかげん覚えてください。」
そう語り始めたあかねの顔には穏やかな微笑が浮かんでいて、八葉の面々は驚きを隠せなかった。
この状況で、自分の命を危険にさらすと断言した龍神の神子は慈愛に満ちた笑みを浮かべているのだ。
「それから、私は別に危険にさらされたりしませんよ。」
「神子殿、どう考えても危険です。敵は泰明殿の結界を破るほどの術を使う陰陽師を抱えているかもしれないのですよ?」
「それはわかってます。そういうことじゃないんです。」
「神子殿?」
自分の説明にも全くひるまないあかねに鷹通が訝しげな視線を向ける。
「私は危険にさらされたりしません。だって…。」
そこまで言ってあかねは隣にきちんと正座している許婚の顔を見上げた。
何を要求されているのかわからない頼久はというとキョトンとした顔でただ見上げてくる愛しい許婚を見つめ返す。
「頼久さん、ちゃんと守ってくれるでしょう?」
さっと頼久の目が大きく見開かれた。
自分の腕を疑われていると感じたことは一度もない。
だが、ここまで完全に信頼して下さっているとはっ!
心の中で感激しながらも頼久はその顔に笑みを浮かべて深く一つうなずいた。
「もちろんです。この命に代えましても必ずお守り致します。」
「命に代えちゃだめですけど……。」
「御意。」
相変わらず命を引き合いに出した頼久に釘をさすことを忘れないあかね。
そして、許婚になった後もあかねの言いつけには絶対服従の返事をした頼久。
二人は互いにくすっと笑って熱い視線を交わし合い…
「二人とも、そういうことは二人きりの時にしてくれないかい?」
あきれたような友雅のこの一言で我に返った二人は真っ赤になってうつむいた。
そうだった、この二人は恋仲だったと改めて思い返した八葉達はひきつった苦笑を浮かべる。
普段は以前と変わらず龍神の神子とその警護の人、という関係に見える二人だからついつい二人が婚儀を控えた許婚同士なのだということを失念してしまうのだ。
「と、とにかく、私のことは頼久さんがちゃんと守ってくれますし、みんなだってもちろん守ってくれるでしょう?だから私は危険なめになんてあわないんです。怨霊や鬼からだってみんなで私のこと守ってくれたじゃないですか。」
ニコッ
あかねの必殺無邪気な笑顔が炸裂して、自分達も頼られているらしいと実感した八葉達があかねの言葉に逆らえるはずもなく…
「では、結界を少々不安定にしておこう。術での攻撃は防げるように神子には護法をしっかりとかけ直す。」
「俺もなるべくちょくちょく顔出すようにするな。」
「神子殿のお覚悟はよくわかりました。私もなるべくこちらに参上します。」
「わたくしなどでは戦力にはならないかもしれませんが…笛で神子のお心をお慰めするくらいはできましょう。なるべくこちらへ参上することに致します。」
「私はどうするかな…。」
急にそう言って扇をぱちりと鳴らす友雅に残る八葉の抗議の視線が集中した。
事ここに及んでサボる気か?と言いたげな空気がひしひしと伝わる。
だが、友雅は艶な笑みを浮かべて頼久の視線だけを受け止めた。
「私は武官だからね、それこそ神子殿の身辺警護ならお手のものだが…神子殿をお守りするためにはお側にいなくてはならないだろう?神子殿の側には頼久がいるのだろうし、あてられっぱなしでは割に合わぬからね。」
「と、友雅殿っ!」
急に引き合いに出されて真っ赤になりながら動揺する頼久。
「それこそ神子殿が囮になろうというのだ、頼久は四六時中張り付いてお守りするつもりだろう?」
「そ、それはそうですが…。」
「私は二人の恋路を邪魔する無粋な男にはなりたくないのでねぇ。」
「……。」
元来が口下手の頼久、とうとう友雅のからかい攻撃に硬直状態に陥ってしまった。
第四話へ
管理人のひとりごと
というわけで(笑)5000Hit御礼でございます(^^)
第三話、いかがでしたでしょうか。
今回も、書きたかったチャンバラは書けず…
そのかわりにちょっと甘い感じになったような気がします(マテ
今回も頑張っちゃってるのは少将様だったり…
頼久さんからかうのは少将様の専売特許となりつつありますな、うち(’’)
次こそっ!次こそは頼久さんがかっこよく戦うところをっ!
と思ってはいます(’’;
プラウザを閉じてお戻りください