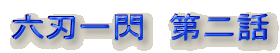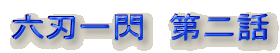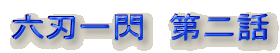
イノリは息を切らせてあかねの屋敷へ飛び込んだ。
見慣れた警護の人間が一人もいない。
友雅の使いの者から受け取った文には緊急事態が発生した、すぐにあかねの屋敷へくるようにと書いてあった。
屋敷の警護が一人もいないのが何よりの緊急事態発生の証とばかりにイノリは庭を突っ切り、すぐにあかねの局へと駆け込んだ。
ところがそこには誰もいない。
さては更に何か起こってみんなどうにかなったのかとイノリが顔色を青くしたその時、一匹のネズミがその足下に駆けて来た。
「何をしている、こっちだ。」
「げっ、や、泰明か?」
自分を見上げるネズミを見つめて驚いたイノリは、次の瞬間、ネズミが溜め息をついたような気がした。
「神子はこっちにいる。私も友雅も頼久もだ。来い。」
なんともいえない気持ちでイノリは先を行くネズミの後を追った。
聞こえてきた声は確かに泰明のもので、その抑揚のない口調も間違いなく泰明だった。
そうとわかっていてもやはりネズミの後をついて歩くのには抵抗があるものだ。
「おや、早かったね、イノリ。」
ネズミが入っていった部屋にはネズミが言ったとおり、四人の姿があった。
イノリを案内したネズミはすぐに庭に飛び出して縁の下へと姿を消す。
声をかけてきた友雅を一瞥してイノリは柱にもたれて座った。
「で、何があったんだよ、緊急事態って。」
「まぁまぁ、何度も同じ話はしたくないからね、それは永泉様と鷹通がくるまで待ってくれないかい。」
「なんだよ、使いの話じゃすっげー急いでるみたいだったのに、そうでもないんじゃね?」
「まぁ、緊急事態ではあったのだがね。」
「なんだよ、何が起こったんだよ。」
「神子が襲われた。」
キョトン。
イノリは目をまん丸に見開いて声の主、泰明の顔をマジマジと見つめた。
「襲われたって、あかねはここにいるじゃねーか。」
「あのね、さらわれそうになったんだけど、すぐ頼久さんが助けに来てくれて、それで泰明さんと友雅さんも駆けつけてくれて大丈夫だったの。」
ニコッ。
いつものように普通に微笑んでいるあかねを見て、やはりキョトンとしたイノリは次の瞬間、顔を真っ赤にして大声を張り上げた。
「あかねっ!大丈夫だったのじゃねーだろっ!それ、思いっきりもんのすごくとんでもなく危ねーじゃねーかよっ!」
「で、でも大丈夫だったし…。」
「だいたい、何のために泰明が結界はって、武士団が警護してんだよっ!」
「予期せぬ賊だった。陰陽の術を使って結界を破り、警護していた武士団の者を術で眠らせた。」
「術って……。」
頼久が眉間にシワを寄せて黙り込んだのとは対照的に、不機嫌そうな顔をしてはいるが必要最低限の情報をくれた泰明の言葉を聞いてイノリはさっと顔色を青くした。
術を使うのは陰陽師と決まっている。
もちろん、陰陽師を頼るのは貴族だけとは限らない。
病や穢れが相手であれば庶民でも陰陽師を頼ることはある。
陰陽寮に属していない陰陽師ならば高額な報酬を要求することもないので庶民でも十分に頼ることができる。
だが、今回の相手はあの希代の陰陽師、安倍晴明の愛弟子で八葉の一人でもある泰明の張った結界だ。
流れ者の陰陽師風情にやぶれるとは思えない。
ということは、それ相応の腕を持つ陰陽師がおそらくはそこそこの権力や身分を持つ人間に雇われて泰明の張った結界をやぶったということになるわけで…。
「イノリ、詳しい話は皆が集まってからにするつもりだから、今一人で悩む必要はないよ。」
クスクスと笑い声をたてて面白がっているらしい友雅を一瞥してイノリは溜め息をついた。
怨霊が出たから戦えと言われればいくらでも戦うが、相手が貴族だの陰陽師だのとなると何をどうしていいかわからない。
貴族の複雑な事情など庶民のイノリには無縁のものだ。
「久々ですね、このように皆が集まるのは。」
「本当に。」
そこへ並んで姿を現したのは鷹通と永泉だ。
これで、やっと全員集合したというわけだ。
「これは珍しい、鷹通と永泉様がご一緒とは。」
笑って迎えた友雅に相棒の鷹通が笑顔を向けた。
「たまたま表で一緒になっただけですよ。」
鷹通は笑って応えながらすっと友雅の隣に座り、永泉も泰明の隣に腰を落ち着けた。
「文には神子殿の身に危険が及ぶやも知れぬと書いておいででしたが、どういうことでしょうか?」
「このように八葉の一同をお集めになったということは友雅殿には何かお考えがおありなのでしょうか?」
鷹通と永泉の二人に立て続けに質問されて友雅は苦笑した。
この二人、イノリとは違って外見は落ち着いて見えるが、実は神子の身に危険が及んだと聞いてかなり内心は焦っているらしい。
「では、やっと全員そろったし、最初から説明しようか。」
友雅がそう言って姿勢を正すと、八葉の一同も姿勢を正して友雅を凝視した。
それにつられてあかねも真剣なまなざしで友雅を見つめる。
「神子殿にそのように見つめられては照れてしまうね。」
思わずそう言って、次の瞬間、友雅は苦笑した。
一同の真剣なまなざしが非難の視線に変わったからだ。
「わかったわかった。真剣に話をするから、もう少しくつろいで聞いてもらえないかい。こちらの肩がこりそうだ。」
友雅に言われて初めて力が入りすぎていることに気付いた一同は、ピッタリ同じタイミングで深呼吸をして互いに微笑み合った。
「さて、まずは昨日の話からだね。昨日の深夜、この屋敷に賊が侵入した。目的はどうやら神子殿をさらっていくことだったらしいがそれは頼久と私と泰明殿とで防いだ。皆知っていると思うが、この屋敷には泰明殿の結界が張られていた。賊はこの結界を術で破って侵入している。」
「ということは、敵はそれ相応の腕を持つ陰陽師を雇うことのできる者ということですか?」
「そうなるねぇ。」
相棒の言葉にうなずいて友雅は一同を見回した。
あかねがキョトンとしている他は皆一様に真剣な顔をしている。
事の深刻さがわかっているのだ。
「それで、お前は何を知っているのだ?」
いつもより幾分低い泰明の声が不機嫌そうに響いた。
「知っているというほどでもないのだが、少々小耳に挟んだ話があってね。最近、左大臣殿が頻繁に帝に呼び出されているのは知っているかな?」
「知らねーよ。」
「噂には聞いていますが…。」
「警護で内裏にお送りすることが増えているとは思っていましたが…。」
「左大臣が帝に呼び出されるのと神子がさらわれるのとどう関係があるのだ?」
イノリ、鷹通、頼久、泰明がそれぞれに友雅の質問に答えたところで、友雅は視線を永泉へと向けた。
これ以降は永泉の方が事情を詳しく知っているということだ。
「それは、その……神子が怨霊からこの京を守って下さり、京には平和が訪れました。今までは怨霊や鬼を相手に一致団結していた内裏ですが、共通の敵がいなくなった今、どうやら不穏な動きが出ているらしいのです。」
「不穏な動き?」
同じ玄武の相棒に泰明が疑問の声をあげる。
「はい。貴族達の間で権力争いが起きているらしく…主上にはそのような噂を耳にするたびにお心を痛めていらっしゃるようで、京の平安を守るため、左大臣殿に助力を請うているということのようです。先日、はっきりとはおっしゃいませんでしたが、わたくしにも愚痴めいたことをおっしゃっていらっしゃいました。せっかく平和になったというのに今度は政で争わねばならぬと。」
永泉が悲しげにうつむいた。
優秀な兄を慕う永泉にしてみれば、帝の心痛は己のことのようにも思えるのだろう。
「政となるとわたくしにはもう……。」
「しかし、内裏に今、左大臣殿と対等に争えるほどの権力を持った者などいるでしょうか…。」
果てしなく落ち込み続ける永泉の代わりに思考を巡らせたのは鷹通だ。
「気付かないかい?鷹通。」
「そう言う友雅殿にはお心当たりがおありですか?」
「まぁ、これも噂で小耳に挟んだのだがね。」
そう言って友雅はまだうつむいている永泉をちらりと盗み見る。
視線に気付いた永泉は一瞬驚いたような顔をして、次の瞬間には再び苦しそうにうつむいた。
「そもそも、左大臣殿とて始めから今の権勢を誇っていたわけではないからね。今までだって敵がいなかったというわけではない。神子殿のおかげで左大臣殿の権勢は揺るがぬものになったように見えるが、もちろん今でも敵はいる。」
「その敵とやらが神子を狙ったと言うのか?」
「まぁ、おそらくはそうだろうということですよ、泰明殿。」
「あのぉ、どうして私のおかげで権勢が揺るがなくなって、左大臣さんに敵がいると私が狙われるんですか?」
張り詰めたような泰明と友雅のやり取りの間に挟まったあかねの発言はあまりにもあっけらかんとしていて、一瞬、場の空気が凍りついた。
あかねがキョトンとすること数秒、八葉の面々は皆一様に優しい笑みを浮かべた。
「まったく、このかわいい姫君ときたら相変わらず自分がどれほど尊い天女かわかっておいででないようだね。」
「と、尊いなんて…友雅さんはいつもそうやってからかうんですから…。」
「からかってなどいないさ、そうだろう?頼久。」
「はい。」
こればかりは意見が一致したのか間髪入れない頼久の返事に驚いてあかねは目を丸くする。
大きく見開いた目で許婚を見てみれば、そこには満足そうに微笑んでいる秀逸な笑顔があってあかねは更に驚くばかりだ。
「神子殿、考えても見てください。神子殿がもし、龍神の神子としてこの京を救って下さらなければ、この京は滅亡していたかもしれないのです。つまりは神子殿はこの京の救い主ということになります。神子殿の存在は一応は秘されていた事実ではありますが、それでも帝の側近くにはべる貴族達には知らされていました。左大臣殿が神子殿の後ろ盾になっていたということもです。」
「えっと、つまり?」
「左大臣殿が後ろ盾となっていた神子殿が京を救った。故に左大臣殿の名声は高まり、また、左大臣殿と敵対する者としては左大臣殿の名声の源たる神子殿を狙う、といったところですか?友雅殿。」
「さすがは鷹通、慧眼だね。」
満足そうに微笑む友雅を今度は泰明がにらみつける。
どうやらここまでの話は想像がついていたらしい泰明は話の展開の遅さにいらつきだしたようだ。
「そこまではいい。よくある話だ。それで、誰が左大臣と神子を狙っているのだ?」
「泰明殿、私とて、そう何から何までわかっているというわけではないのですがね。」
「そうか?知っている、と顔に書いてあるぞ。」
神子に会うまでは感情というものをほとんど顔に出さなかった泰明だが、今はみるみるうちに機嫌が悪くなっていくのがよくわかった。
泰明本人がその自分のいらつきを持て余している様子だ。
「まぁ、噂によると左大臣殿を狙っているのは以前からの仇敵、右大臣殿、ということらしいがね。」
永泉、鷹通、頼久の表情が一気に険しくなった。
右大臣と言う人物が以前にどれだけ権勢に執着していたかを知っているからだ。
「なぁ、俺にはよくわかんねーんだけど、その右大臣ってヤツ、そこそこ偉いんだろう?そんな偉いヤツがなんかたくらんだとして、そんな簡単にわかるもんか?友雅の情報ってあてになんのかよ?」
こちらはそもそもが友雅の人間性を信用していないらしいイノリだ。
それももっともだと言わんばかりに頼久、泰明、鷹通の視線が友雅に集中する。
友雅は苦笑を浮かべて脇息にもたれた。
「まぁ、普通は漏れないだろうねぇ、そういう情報は。ただ、私の耳は特殊だからねぇ。」
「……あなたに情報をもたらしたのは女性、ですか?」
「さすが鷹通、鋭い推察だ。」
鋭くないと一同が一斉に心の中でつぶやいたのに気付いているのかいないのか、友雅は何やら楽しげに微笑んでいる。
「通っている女性にならば寝物語に本心を語ることもある、というわけですか?」
「まぁ、私が最近親しくしている女性が最近右大臣家に使えている男から聞いた話だそうだから、全くの噂、ということはないだろうと思ってね。警戒しておくに越したことはないと思って昨夜、こちらに参上してみたら賊と出くわしたというわけさ。泰明殿の術を破って侵入した辺りから見ても、賊はずいぶんと用意周到だったようだし、やはりただの噂というわけではなさそうだからね。こうして久々に八葉に集まってもらったというわけだよ。」
「相手が誰であれ、京を救うために命をかけた八葉ならば信用できるというわけですか。」
そう言って鷹通が満足そうに微笑むと、その微笑は他の八葉達にも広がった。
怨霊との戦いを終え、鬼が姿を消し、彼らの手によって京には平和がもたらされた。
八葉達はそれぞれ、その身分も優遇されるという話がちらほらでてきて、忙しい身の上になって以前のように頻繁に会うこともままならなくなっていたが、仲間という意識はいまだに根強く残っているらしい。
それもこれも、身分など関係ない、皆、自分の仲間だと言い続けてきた龍神の神子、あかねの影響なのかもしれないが。
今となってはそれぞれの身分や立場で忙しくしている一同は、どうやらそんな現状を少しばかり寂しく感じていたようだった。
あかねは久々に集まった仲間達が以前と変わらない様子を見て嬉しそうに微笑んでいた。
あかね自身も毎日のように会いにきてくれる許婚以外の八葉とはなかなか会えなくなっていたから、疎遠になってしまうのは寂しいと思っていたのだ。
「鬼や怨霊から神子殿も京も守りぬいた我々だ、人の手から神子殿をお守りするくらいどうということはないだろう?」
煽るような友雅の物言いに、八葉の面々は力強く一つうなずいた。
「敵がわかってんならぶっ飛ばしに行こうぜ、二度とあかねに手をだすんじゃねーって。」
「それは無理だよ、イノリ。」
「なんでだよ。」
「証拠がないからね。」
「友雅が話聞いた女を証人にすりゃいいじゃねーかよ。」
「寝物語はその場のみの物語、夜が明けてから公でするなど無粋のきわみだよ。」
「無粋とか何とか言ってる場合かよっ!」
いらつくイノリの肩に永泉が優しく手を置いた。
「そのようなことをしてはその女性のお立場がなくなりましょう。」
「あ……。」
さすがのイノリも優しく諭すような永泉の言葉は心に届いたらしく、後悔したような顔でうつむいた。
「証拠などなくとも…。」
「や、泰明殿!それもダメです!」
不穏な気配を感じて永泉が玄武の相棒を必死に止める。
その様子を泰明は訝しげな表情で見つめた。
どうやらこの希代の陰陽師の愛弟子は、右大臣という身分ある人物を呪殺しようと本気で考えていたようで、何故それを止められたのかがわからないのだ。
「永泉、何故止める?」
「そ、そのようなこと、神子殿がお認めになるはずがありません。」
泰明と永泉の視線があかねに集中した。
泰明は何故永泉が止めたのかを問い詰めるような視線で、そして永泉はまるで助けを求めているかのような視線であかねを絡め取る。
「え、えっと……泰明さん、何をしようとしてたんですか?」
「右大臣を呪殺すれば事は簡単に片付く。」
「……………………ダメですっ!!」
サクっと発言した泰明の言葉の意味をよーーーく考えたあかねは顔を真っ赤にして怒りをあらわにした。
それでもひるまない泰明にあかねはびしっと人差し指をつきつける。
「いいですか、泰明さん!呪殺って殺すってことじゃないですかっ!いくらなんでも殺すなんて絶対ダメです!」
「何故だ。」
「何故って、ダメなものはダメです!人はそんなに簡単に殺したりしちゃダメなんですっ!私だって別に怪我させられたわけじゃないし、殺されそうになったわけでもないんですから。」
「しかし、神子に危険が及ぶようならばあらかじめ亡き者にしておいた方が……。」
「亡き者にしちゃだめですっ!絶対ダメですから!もし殺しちゃったりしたら、もう……えっと……泰明さんなんて絶交です!」
「………。」
泰明のような人間にどういう罰を与えれば効果的かが思いつかなくて思わず絶交といってしまったあかねだったが、このあかねの一言が泰明には絶大な効果を見せた。
急に黙り込んだ泰明は、悲しそうにうつむくとまるですがるような目であかねを上目遣いに見上げたのだ。
あかねはとりあえずほっと安堵の溜め息をついて落ち着きを取り戻した。
「神子…絶交は……。」
「右大臣さんを殺したりしなければ絶交しませんから。いいですか、泰明さん。右大臣さんにだって家族がいるんです。亡くなったら悲しむ人だっているはずです。それに、人を殺すなんてこと、泰明さんだってつらいことなはずです。だから、絶対殺したりしちゃだめです。」
「わかった。殺さない。」
「わかってくれたならいいんです。」
ニコッ。
ここであかねがいつもの優しい微笑を浮かべて見せたものだから、泰明はほっと安堵の溜め息をついてからつられるように微笑を浮かべた。
「さて、神子殿がそう言うだろうということは予想できたが、ではどうするね?」
「どうって?」
「敵を排除せずにどうすればいいか?という話だよ、尊き神子殿。」
心の底から楽しんでいる様子の友雅に流し目されて、あかねは難しい顔で考え込んでしまった。
さて、人を殺すのは絶対にいけない。
それはまぁ、自分が殺されそうになるというのなら正当防衛はありかもしれないが、それでも殺すというのは最終手段でなきゃいけないはずだ。
敵だからといって簡単に排除して解決というのはあかねの主義ではない。
できれば穏便に、みんなが幸せになれるように解決したい。
「ん〜、話し合いとかダメでしょうか?」
おずおずと切り出したあかねに八葉の面々は軽くためいきをついた。
やはり。
皆が心の中でそうぶつやいていた。
「話し合いですむような相手ではないだろうと思うがね。第一、右大臣殿が神子殿を狙ったという証拠がない。シラをきられて終わりだろうね。」
「じゃぁ、証拠をつかみましょう!」
友雅の返答に両手を握り締めてやる気たっぷりのあかねだ。
だが、八葉の面々はあまり乗り気には見えなかった。
「神子殿、どうやって証拠をつかむおつもりですか?」
「それはやっぱり、私を襲ってきた人達から聞きだすとか……。」
そう言ってあかねは泰明を見つめる。
昨夜あかねを襲ってきた賊は泰明が捕らえてあるはずだったからだ。
「昨夜の賊から聞き出せと?」
泰明の問いにあかねはコクコクとうなずいて見せる。
「やってみるのはかまわないが…。」
「何か問題がありますか?」
あかねの視線を受けた泰明はそのまま頼久を見つめた。
自然とあかねも頼久の方を見やると頼久はつらそうな顔をしていた。
「やってみてもよいとは思います。ですが、泰明殿に何かよい案がなければ…その……拷問することになるかと…。」
「…………………………ダメです!そんなの、拷問なんて絶対ダメです!」
再び「やはり」と言いたげな溜め息をつく一同。
その優しさこそがあかねの尊い所以だとわかってはいても、これでは問題解決の糸口さえつかめない。
いつもなら、賊を拷問して敵の正体を暴く努力をし、たいていの場合自害されてしまうので、最終的に泰明が右大臣を呪殺、という段取りになりそうなものだが、この心優しき神子が主とあってはそれらの手段は全て否定されてしまうのだ。
「私が術をかけて聞き出すとう手もないとは言わぬが、結界を破るほどの腕の陰陽師が敵についていることを考慮すれば、簡単にはゆかぬと思った方がよいだろう。術に抵抗されるか、最悪の場合…。」
「最悪の場合?」
「敵の術者の術によって賊が殺されることもあり得る。」
「……………………術もダメですっ!」
六人の八葉はここで同時に深い溜め息をついた。
これでは本当に手のうちようがないではないか。
「では、神子殿はどうしたらいいとお考えですか?」
素早く冷静さを取り戻した鷹通の言葉にあかねはうつむいてしまった。
「えっと…その……証拠になるようなものが出てくるまで、待つ?」
再び八葉の面々が溜め息をつく。
待つということがどういう事態を引き起こすのかこの神子にはわかっているのだろうか?
それはすなわち神子自身の身が危険にさらされ続けるということなのだが。
そう考えて一同は再び深い溜め息をついて互いに顔を見合わせた。
「まぁ、神子殿の仰せとあれば我々八葉としては従うけれどね。なるだけ負担は皆で分担したいところだが…。」
そう言って友雅はすっと頼久へと視線を向けた。
第三話へ
管理人のひとりごと
4000Hit御礼でございますm(_ _)m
ということでキリ番更新御礼連載第二話、お届け致しました。
まだまだ助走段階ですが、京残留八葉全員集合をお楽しみ頂ければ(笑)
主があかねちゃんだと八葉のみんなもなかなか大変そうです(爆)
頼久さんがかっこよく戦うところとか、同じように少将様が武官ぽいところとか…
全然出てきませんでしたね(’’;
書く気はありますので、長い目で見守ってやってください(礼)
プラウザを閉じてお戻りください