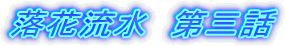
あかねと頼久はイノリが言っていた屋敷をすぐに見つけることができた。
都の外れまで行って辺りを行く人に聞いてみれば、今では怨霊が出る屋敷として有名なのだという。
おかげで迷うことなくイノリが言っていた屋敷へ到着できた二人だったが、その屋敷のあまりの惨状にあかねは屋敷の前で立ち尽くしてしまった。
「ひどい…。」
崩れた築地はもう古びていて全く修理されていないし、そのせいで庭はほとんど丸見えだ。
のぞき込んでみれば御簾も破れていて、破れた所が風にはためいてさえいる。
そんな状態だから外からのぞきこめるところに人の気配はなかった。
この京の貴族の女性は他人に姿を見られることを嫌う。
だから御簾で姿を隠しているのだが、その御簾が使い物にならないのでもっと奥に息を潜めているのだろう。
土御門の豪華な屋敷で生活しているあかねにはそれは想像もできないほどの惨状だった。
「こんなところに一人で藤姫ちゃんみたいなお姫様が住んでるなんて…。」
今にも泣き出しそうな顔で屋敷を見つめるあかね。
だが、後ろに立つ頼久にはその気配がわかっていてもどうすることもできない。
あるいはここに友雅がいたなら、涙をそっとぬぐってやることができたのだろうかと、そんな考えが頼久の脳裏をよぎる。
「ひどすぎます、こんなの…。」
こんなところで一人で生活するなんて、きっと庶民の生活よりひどい。
そう思えばどうしても止められなくて、あかねはこぼれる涙をぬぐった。
「神子殿…。」
「ごめんなさい!すぐ泣き止みますから!」
背後で頼久が困り果てている。
それが気配でわかるだけにあかねは必死に涙をぬぐった。
そんな姿もいじらしくて、頼久は頼久で何もできない自分を呪うしかない。
「怨霊の話、聞きに行きましょう!」
すっかり涙をぬぐって、あかねは後ろを振り返ると頼久に微笑んで見せた。
泣いたせいで赤くなった目が痛々しかったが、頼久には何もできない。
ただ、頼久は先を行くあかねについていくのみだ。
「こんにちわ〜?」
あかねがそういいながら庭へと足を踏み入れても、屋敷から人の気配はしない。
それこそお化け屋敷のような屋敷にさすがのあかねも少々ひるんだ。
「い、いきなり怨霊がでてきてバサッってことはない、ですよね?」
「そのような不審な気配は致しませんが…。」
「そ、そうですよね…。」
頼久に確認してほっと安堵の溜め息をついて、あかねは気を取り直して縁まで歩み寄ると、中をのぞき込んだ。
「こんにちわ、ちょっとお話を聞かせてもらいたいんですけど…。」
あかねがどんなに中をのぞいてみても、中は暗くて何も見えない。
これは自分が中へ入って様子を見てくるべきかと頼久が思案をめぐらせたその時、中から衣擦れの音が聞こえた。
「どちらさまでしょうか…。」
それはか細い女性の声で、だいぶ屋敷の奥のほうから聞こえる。
きっと御簾が敗れている上に築地もぼろぼろだから、几帳などを立てて奥のほうへ引きこもっているのだろう。
あかねは奥から聞こえた声が優しそうな女性の声だったのでとりあえず安堵の溜め息をついた。
「えっと、私…。」
どちらさま、と問われてもあかねが龍神の神子であることは公には伏せられている。
龍神の神子ですが、怨霊の話を聞かせてもらえませんか?と言えればそれは簡単なのだが、そうはいかない。
あかねが困って口ごもるのを見て、頼久はあかねをかばうようにその身をあかねと屋敷との間へ滑り込ませると中の様子をうかがいながら口を開いた。
「我らはこの辺りに怨霊が出るという噂を聞き、左大臣家から派遣されてきた者です。よろしければお話をうかがえないでしょうか?」
凛とした頼久の声は御簾の向こうへと確かに響いた。
そのどうどうとした様子にあかねが目を丸くする。
いつもはあまり大声を出すことがないし、こんなふうに機転の利く頼久を見ることも珍しい。
普段はあかねを守るために常に黙って辺りに気を配り、その背でかばって戦ってくれるのみだからだ。
機転をきかせるのはたいてい友雅や鷹通たちの仕事で、こんなふうに頼久が振る舞うのを見ることはあまりない。
「まぁ、左大臣様の…。」
そう言いながらずいぶんと奥の方から姿を見せたのはもうかなり年配の女性だった。
髪はほとんどが白髪になっているし、どうやら腰も曲がっていて伸ばせないようだ。
それでもどことなく上品に見えるのは、もとは身分高き人に仕えているせいだろうか。
「このようなお見苦しいところへよくぞおいで下さいました。」
「突然訪問する無礼、お許し下さい。私は左大臣家に使える武士、源頼久と申します、こちらは左大臣家の信頼もあつい神子殿でいらっしゃいます。怨霊の類がどの辺りで姿を見せるものか御存知でしたらお教え頂きたく。」
「まぁまぁ、左大臣家から巫女様までお遣わし下さるとはもったいない…。」
そう言って老女はあかねに深々と一礼した。
どうやら神子ではなく巫女だと理解してくれたものらしい。
あかねは慌ててぺこりとお辞儀を返しながら、凛とした対応の頼久に見惚れていた。
「わざわざおいで頂きましたのに申し訳ありませんが、怨霊などというものの話はとんと…。」
知らない、と老女が答えそうになったその時、屋敷の奥で衣擦れの音が聞こえた。
そして次の瞬間…
「お待ちなさい、左大臣家からわざわざ調べに来て下さったお方に嘘偽りを申し上げてもしかたがないでしょう。」
「姫様…。」
奥の方から聞こえてきたのはまだ若い女性の声だ。
声から推測するとあかねより少し年上といったところか。
老女が姫様と呼ぶからには、やはり元は身分が高い人であったようだ。
「我らは怨霊の類を排除すべく参っただけのこと、一切他言は致しませんので怨霊について御存知でしたらお話し頂けないでしょうか。」
元からこの屋敷の主であるらしい女性は隠し立てするつもりはないようだったから、頼久のこの一押しで老女は黙り、奥の方からぽつりぽつりと若い女性が話す声が聞こえてきた。
「怨霊が出るというのは、この屋敷でございます。……この屋敷に一月ほど前から…月の明るい夜などに…。」
あかねは頼久と顔を見合わせた。
一ヶ月も前から怨霊が出ているというのに、こんな心細い屋敷で暮らしていけるものだろうか?
「その怨霊はどのような…。」
「髪が長く、美しい衣を着た、女人の姿を…。」
ここでまたあかねと頼久は顔を見合わせた。
今までもそんな姿の怨霊に遭遇したことがないわけではないが、姿をはっきり見ることができるほど近づいて無事でいられるとは考えがたい。
怨霊は人を見れば襲ってくるからだ。
それとも、龍神の神子と八葉以外は襲わない怨霊がいるとでもいうのだろうか。
「お怪我などは…。」
「今のところはまだ…今は亡き母がこの屋敷に存命でした頃に、高名な陰陽師にお頼みしてこの屋敷には結界とやらがめぐらされていると聞き及んでおります。おそらくはそのおかげでこのような様に成り果てましても怨霊に襲われることはないのかと…。」
なるほど、とあかねと頼久は同時にうなずいた。
陰陽師のはる結界の強力さは泰明のおかげでよく知っている。
「月の美しい夜に、時折、わたくしが琴など奏でておりますとその怨霊を見ることがございます。」
「琴、ですか…。」
そうつぶやいたのはあかねだ。
あかねの中ではたまに友雅などが聞かせてくれる綺麗な琴の音色と怨霊とが結びつかない。
「偶然かもしれませんが…。」
と、女性に言われてしまってはそうかもしれず…
あかねは小さく溜め息をついた。
「はっきりと申せますのは、その怨霊は夜にしか姿を現さぬということくらいで…。」
「夜しか…。」
「はい。昼間現れたことはございません。今のところは、でございますけれど…。」
どうやら聞きだせることはこれくらいのようだ。
夜現れる怨霊、結界に阻まれて家主には手が出せないらしい。
女性の姿をしていて、琴を弾いていると現れることがあるが偶然かもしれない。
あかねは頭の中で情報を整理して溜め息をつくと、そっと頼久の様子をうかがってみた。
この情報だけではどうしようもない気がする。
怨霊を退治するためにはこの屋敷で怨霊が姿を現すまで見張っているしかないのではないだろうか?
だが、その怨霊はいつ姿を現すかわからないわけで、しかもあかねは明日、物忌みで屋敷から外へ出ることができない。
ではどうすべきか、あかねも困ってしまったのだ。
「どう致しましょうか。」
やっぱりそうだよねぇ、と心の中でつぶやいてあかねは苦笑を浮かべた。
「どうしましょうか。」
「……。」
「頼久さんはどうしたらいいと思いますか?」
「神子殿の御心のままに。」
「……。」
やっぱりそうきたかぁ、と心の中でつぶやいて、あかねは溜め息をついた。
いきなりここで泊めてくださいなんてお願いしてもいいものだろうか?
いやいや、たとえ泊まったとしても怨霊が出るとは限らない。
「ん〜、どうしよう…。」
こんなとき、いつもなら友雅なり鷹通なり泰明なりが一緒にいていい助言をくれるのだが…
「ここは一度、屋敷へ戻ってはいかがでしょうか?」
「へ。」
突然の頼久の言葉に思わずキョトンとするあかね。
頼久はそんなあかねの前に方膝をついて頭を垂れ、言葉を続けた。
「一介の武士である私などが意見することではないとわきまえてはおりますが、神子殿がもし何か迷っておいでなのでしたら、一度屋敷へ戻り、八葉の皆の意見に耳を傾けられてはいかがかと存じます。」
ポンッとあかねは手を打った。
そう、わからないなら相談すればいいのだ。
今のところこの屋敷は結界に守られていて無事なようだし、今日はアクシデントがあって二人きりなのだから焦る必要もない。
どうしたらいいのかわからないのなら、帰って仲間と相談すればいいのだ。
一人焦っていたことに気づいたあかねはほっと安堵の溜め息をついて、それからひざまずいている頼久の前に自分もかがみ込んだ。
「頼久さんの言うとおりです。今のところは大丈夫みたいだし、私がここで一人で焦ったってろくなことにならないですよね。帰ってみんなに相談してみます。」
「はっ。」
「頼久さん。」
名を呼ばれて頼久が視線を上げる。
すると予想していた以上の近さに主の笑顔があって、頼久はその微笑に見惚れた。
「有難うございました。」
「は?」
何やらあかねが嬉しそうなのは頼久にとってもいいことなのだが、頼久自身は何を言われているのかわからない。
キョトンとしている頼久にあかねはペコリと頭を下げた。
「頼久さんのおかげで焦って変なことしないですみました。だから、有難うございました。」
「……いえっ!とんでもございません!出すぎたまねを致しました…。」
「出すぎてなんかないですよ。私はまだ全然子供で、考えなしだから頼久さんにも今みたいに言ってもらえると凄く助かります。」
そう言って微笑むあかねを見て、頼久の表情が厳しくなった。
そう、この少女はいきなり異世界からこの京へ飛ばされて、いきなり龍神の神子をやらされているのだ。
それでも笑顔を絶やさず、思いやり深く、清らかであり続けている。
それがどれほど大変なことか頼久には想像もつかない。
そんな大変な思いをしている主を思えばこそ、力の限りお仕えしようと心に決めたのではなかったか。
頼久は主に従うことしかできない己の不甲斐なさを思うと、どうしてもうつむかずにはいられなかった。
「頼久さん?どうかしたんですか?」
「いえ……私のような者ではとうてい神子殿のお役には立てぬと、改めて己の不甲斐なさを…。」
「そんなことありません!頼久さんは今だってちゃんと私を助けてくれたじゃないですか!」
「そう、でしょうか…。」
「そうです!助けられた私が言うんだから間違いありません!」
「神子殿…。」
ビシッと頼久に指を突きつけて断言するあかね。
その顔は真剣そのものだ。
「さっ、帰ってみんなと作戦会議しましょう!そうと決まれば急いで帰ります!」
「御意。」
きりっとした表情であかねが立ち上がると、つられるように頼久も立ち上がった。
屋敷の主に頼久が事情を説明し、今日のところは土御門の屋敷へと帰ることに決まった。
二人並んで荒れ果てた屋敷を出て、ゆっくりと歩き出す。
先を行くあかねとはやはり距離を置いていた頼久だったが、あかねはすぐに足を止めて振り返った。
その顔にはかなり不機嫌そうな表情が…
「神子殿?」
「屋敷に帰ってから作戦会議しますけど、屋敷に帰るまでの間に今日の情報をまとめるというか、確認するというか、先に頼久さんと打ち合わせしながら帰りたいんですけど?」
「はぁ…。」
「私に後ろ向きで歩けって言うんですか?」
「い、いえ、そのようなことは…。」
「じゃ、はい、隣を歩いて下さい。」
そういうが早いかあかねはすたすたと頼久の隣まで移動すると、その左腕をつかんで歩き出した。
「み、神子殿っ!」
「腕をつかまれるのが嫌だったら自分で隣をちゃんと歩いて下さい、いいですか?そうじゃないと離してあげません!」
「しょ、承知致しました…。」
顔色を青くしながらやっと頼久がそう答えるとあかねはにっこり微笑んで頼久の左腕を解放した。
頼久の方はというと腕を解放されてほっとはしたものの、主の隣を歩くという前代未聞の出来事に戸惑うばかりだ。
しかも、隣を歩いている主はといえば今日あった出来事をそれこそ物凄い勢いで話している。
頼久はもう話を集中して聞くことなどできなくて、上の空で返事をしながらただひたすら主に歩調を合わせて歩くことだけに集中していた。
そうしなければどうしても隣を歩き続けることができなかったからだ。
「頼久さん、ちゃんと聞いてます?」
「は?」
土御門の屋敷が見えてきた頃、とうとうあかねは溜め息をついた。
だが、これはまずいと青くなる頼久を見て、あかねは怒るどころかクスッと笑みをもらした。
これには頼久の目が驚きで大きく見開かれる。
立ち止まって笑みを浮かべたあかねは下から覗き込むように頼久を見上げて口を開いた。
「聞いてくれてなくてもいいです。今日のところは。」
「申し訳ありません…。」
「隣を歩いてくれたから許してあげます。でも、次からはちゃんと隣を歩いてお話もしてくだださいね?」
「…善処致します…。」
まだこの主の望みどおりにできるとは断言できなくて…
頼久は情けないと思いながらも歯切れの悪い返事しかできなった。
それでも満足らしい主はニコニコと微笑みながら屋敷へ向かって歩き出し、頼久は慌ててその隣を歩いた。
「二人で怨霊退治なんてどうなるかちょっと心配でしたけど、楽しかったかも。」
「は?」
「ああ、心配って言っても怨霊にやられちゃうんじゃないかとかそういうこと心配してたわけじゃないですよ?頼久さんが強いのはよく知ってますから。でもほら、頼久さんって普段はあまり自分のこととか話してくれないし、隣を歩いてくれることもなかったからちょっと緊張しちゃうというか、そんな気がしてたんですけど、もう大丈夫!」
「はぁ…。」
「頼久さんとだったら二人でも大丈夫です。」
そう言ってにっこり微笑んだあかねは土御門の屋敷へと駆け込み、すぐに藤姫の局へと姿を消してしまった。
頼久はというと、もちろん藤姫の局まであかねを追いかけていくことができるはずもなく…
また、その必要もないわけで、結局のところいったん武士溜まりへ戻ることにした。
一度武士団の仕事を片付けてから主の警護につけばいい。
だが、武士溜まりへ戻る道すがら、頼久の脳裏には最後にあかねが見せた楽しそうな微笑が焼きついて離れなかった。
主と二人きりでの初めての一日はあまりにも早く、そしてあまりにもめまぐるしく終わろうとしていた。
唯一つ、頼久の胸に暖かい想いを残して。
第四話へ
管理人のひとりごと
お待たせ致しました、第三話でございます(^^;
ハイ、二人きりでのお出かけ終了いたしました♪
なんだかぎこちなくもありますが、なんとか乗り切りましたよ(笑)
頼久さんの方がかなり苦悩してますが、それは結婚してからもあまり変わってないかな(’’)
まだまだ話は続きます、次回をお待ちくださいませm(_ _)m
プラウザを閉じてお戻りください