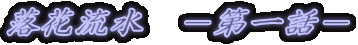
「じゃ、二人ともお疲れ様でした。ゆっくりお休みしてくださいね。」
「神子殿もね。」
あかねは目の前にいる二人の男性にぺこりと一礼して微笑を浮かべた。
あかねの言葉に朗らかに答えて軽くウィンクさえ残して去っていったのは地の白虎、友雅だ。
そして、あかねの言葉には何も答えずにただ深々と一礼してその場にたたずんでいるのが天の青龍、頼久。
頼久はただ一礼しただけで去ろうとしない。
怨霊と戦って一日を終えて帰ってきてもこの天の青龍は、いまだにあかねが御簾をくぐり自分の局で休むのを見届けるまでこうして控えているのだ。
「えっと…頼久さんもちゃんと休んで下さいね?」
「御意。」
これ以上なんと言ってもたぶん自分より先には休んでくれないだろうとわかるから、あかねは御簾をくぐって座りながらほっと溜め息をついた。
すると、御簾の向こうで気配が動いた。
どうやらやっと頼久が武士溜まりへ戻ったらしい。
武士だからなのかそれとも藤姫に命じられたからなのかはわからないけれど、とにかく頼久はあかねを護るという義務感が人一倍強い。
だからいつもこうしてあかねが無事に自分の局に戻るのを確認するまでは絶対に側を離れたりはしないのだ。
最初に会った頃は、すぐ刀を抜くし、死ぬの生きるのという話をするし、ちっとも笑わないし、笑うどころか話もしてくれなくて正直、少し恐い人だと思っていた。
でも、一緒に戦いを重ねて、少しずつ親しくなって、今では八葉の中で一番信用している人になっている。
すぐに刀を抜くのは護るべきものを護るためにしていること。
命をかけると口にするのはそれだけ覚悟が真剣だということ。
笑わないのは笑うような心持になれないような悲しい過去があったから。
話をしてくれないのはもともとが口下手だから。
どれも理由がわかってしまえばもっともなことで、全てわかってしまえば実直で腕の立つ武士である頼久は誰よりも頼りになった。
自分のせいで兄を失ったのだという過去を聞かせてくれてからはだいぶ打ち解けたとも思う。
口の端が少し上がって、うっすら微笑む顔も見せてくれるようになった。
だから、もう恐い人だなんて思わないし、側にいてくれれば安心できるのだけど…
それでもこうして自分が休むまでは休まないとか、絶対に自分から御簾の中には入ってこないとか、自分を助けるために抱きとめたりした時でもまるで触れたことがそもそも悪いことみたいに謝られたりする。
仲間なのだからそんなふうに気を使わなくてもいいと何度言ってもやめてくれなくて…
そうやって臣下の礼を見せ付けられるたびにあかねは悲しくなる。
自分は一緒にいない時は頼久がどうしているか気になるし、助けてもらった時は心から感謝している。
それなのに頼久の方はというと常に従者として至らぬことはないかとそればかりを気にしているようなのだ。
そんなことは気にしないで、仲間としてもっと一緒に、怨霊との戦いのない時は何かを楽しんでくれたっていいのに。
あかねがそんなことを考えながら寝るときに着ている単に着替えて褥の上にちょこんと座ると、カタリと御簾の向こうで音がした。
このタイミングで人の気配。
さっき休んでくださいと言って別れたはずの頼久が夜の警護をするために戻ってきたに違いなかった。
はぁ、と小さく溜め息をついてあかねは袿を上着代わりに羽織ると、御簾をくぐって縁へ出た。
するとそこには怨霊との戦いで見慣れたあの広い背中が。
「やっぱり。」
「神子殿…どうかなさいましたか?」
「どうかなさいましたか?じゃないです。ちゃんと休んでくださいて言ったじゃないですか。」
「休息でしたらとって参りましたので。」
「……。」
あかねはあきれて深い溜め息をついた。
休んだといったって自分がちょっと休憩をして夜着に着替えるまでの間のことだ。
いくら武士溜まりが同じ敷地内にあるからといって頼久が満足に休んでいないのは明らかだ。
「神子殿?」
「今日は朝からずっと怨霊を退治してあちこち歩き回ったんですから、夜くらいちゃんと休んでください。」
「ですが、夜の警護がございますので。」
ここであかねは再び深い溜め息をつくと、階に座っている頼久の隣へ腰を下ろした。
すると頼久は何気ない仕草ですっと立ち上がり、庭へと下りてしまう。
これも主であるあかねと同じ場所に座ってはいられないという頼久なりの気遣いなのだが、あかねはやはり少し悲しくなってうつむいた。
「この建物はそれこそ頼久さんの仲間の武士団の人達が護ってくれてるんですし、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。それに、頼久さんだって休まないと倒れちゃいます。」
「……。」
うつむいて言い募るあかねの言葉に今度は頼久は答えなかった。
そう、この天の青龍を相手に話をするとこうして途切れることもしばしばなのだ。
しばらくたっても頼久が口を開かなくて、あかねはすっと視線を上げて長身な青年武士を見上げた。
「頼久さん?聞いてました?」
「…はい……。」
「じゃぁ、ちゃんと自分のお部屋に戻って休んでください。」
「……。」
「頼久さんはこのお屋敷を護ってくれてる武士団の仲間のみんなを信じてないんですか?」
「そのようなことは…。」
そう言ったきり頼久は黙り込み、何を話そうとも去って行こうともしない。
ただ、うつむきかげんに地面を見つめて眉間にシワを寄せて考え込んでいるようだ。
「私なら大丈夫です。前は暗いのとか恐かったけど、今は慣れましたし、大声出したらすぐ誰かがちゃんと駆けつけてくれるし。」
「……神子殿は…。」
「はい?」
やっと自分の言葉への返事ではない言葉を紡いでもらえそうで、あかねは思わず身を乗り出して頼久の顔をのぞきこんだ。
だが、そこにはとても苦しそうにゆがむ頼久の顔があって…
「私がお側にいてはお邪魔なのでしょうか?」
「……はい?」
「…私の警護は気に障ると仰せなのでしたら……。」
「……………違いますっ!」
最初は何を言われているのか全くわからなかったあかねだったが、頼久の言葉をゆっくり噛み砕いて理解して、思わず大声を出していた。
何を勘違いしたものか、どうやらこの実直な青年武士は主が自分を邪魔だと言ったものと理解したらしい。
「もう、どうしてそうなっちゃうんですか…。」
「…申し訳ございません…。」
「謝って欲しいんじゃないです…。」
「はぁ、申し訳……。」
ここであかねにきりりと睨まれて頼久は最後の言葉を飲み込んだ。
今、謝って欲しいわけじゃないと言われたのに頼久には謝ることしかできない。
この目の前の尊い主が自分に何を望んでいるのかがわからないのだ。
頼久にとってこの龍神の神子という尊い主は、護るべき尊いお方であると同時に理解できない一面を持った、だが、その理解できない部分が魅力的な人物でもあった。
「私は、頼久さんがいらないとか邪魔だとか、頼久さんに警護して欲しくないとかそういうことを言ってるんじゃないです。頼久さんは大事な仲間だから倒れたりしてほしくないから、ちゃんと休んでほしいだけです。」
「はぁ…私は普段より鍛えておりますので、特にお休みを賜らずとも倒れたりは致しませんので…。」
「そうじゃなくて…賜るとかそういうことじゃないんですけど…。」
いつまでたっても話がかみ合わない。
あかねはまた深い溜め息をついた。
「神子殿が他の者の警護をお望みでしたら腕の立つ者と…。」
「だから違いますってば。そりゃ、私だって頼久さんに護ってもらえたらそんなに安心なことないです。頼久さんがどんなに強い人かはもう私が一番よく知ってるんですから。」
これでもまだわかってもらえないんだろうなとあかねが溜め息をつきながら頼久の様子をうかがうと、頼久がうっすらと微笑んでいて、その笑顔があまりにも綺麗であかねは思わず一瞬見惚れてしまった。
これは今までで一番はっきり笑ってくれてるんじゃなかろうか。
「神子殿にご信頼頂けるとは光栄です。」
「こ、光栄とかそんな…おおげさな…。」
「いえ、主に信用して頂くことほど嬉しく思うことはございません。それほどご信頼頂いているのでしたら、是非、夜の警護はこの頼久にお任せ下さい。」
「だから…はぁ。」
何やら浮かれてさえいるような頼久の言葉を聞いてあかねは再び溜め息をついた。
これはもう、どうあっても夜の警護の話は譲ってくれそうにない。
「神子殿?」
「もういいです。わかりました。私も頼久さんに護ってもらえたらそれは確かに安心ですし、警護、お願いします。」
「御意。」
たった一言「御意」と言ったその声さえもいつもより何故か楽しそうな気がしてあかねは目を丸くした。
「神子殿?」
「あ、な、なんでもないです。そうだ、じゃぁ、警護はこのまましてもらってかまわないんで、そのかわり、お願いがあります。」
「はい、なんなりと。」
「疲れて眠くなったらちゃんと自分のお部屋に戻って休んでくれること、次の日一緒に怨霊退治にって言われても、疲れていたらちゃんと私にそう言ってお休みしてくれること、この二つ、約束してください。」
「ご命令とあらば。」
「だーかーらーーーっ、命令じゃないです!お願いです!きいてくれますか?!」
少しだけ怒った顔であかねがそういうと、頼久は一瞬驚いたような顔をして、それから真剣な表情でうなずいた。
「御意。」
頼久がやっとそういうのを聞いてあかねは安堵の溜め息をついた。
「頼久さんは従者とか主とかそういうの気にしすぎです。私は全然そんなふうに思ったことないのに…って私が変わってるっていうのはわかるんですけど、でも、せっかく出会えた仲間なんだし、一緒に戦うんだし、もうちょっとこう、親しくというか…。」
「神子殿のお心の広さにはこの身に余るご好意を賜っております、どうか、そのようにお気遣いなく…。」
「……もうちょっと仲良くなってほしいなって思うの、頼久さんは迷惑ですか?」
あかねに悲しそうにそう聞かれて頼久は大きく目を見開いた。
今までも従者と主ではなく仲間だと何度となく言われてきたが、こんなふうに言われるのは初めてのことだ。
「め、迷惑ではありませんが…その…神子殿のように尊き身分のお方が私のごとき卑しき身分の者にそのようにおっしゃって頂いたことがなく…どのようにお返事していいものか…。」
「頼久さんは卑しくなんかないですっ!」
思わぬ主の大声に頼久の目が更に大きく見開かれた。
よくよく見ると頼久の大切な主はどうやら目に涙さえ浮かべているようだ。
頼久は全身の血がさっと冷たくなるのを感じながら何を言えばいいのか全くわからない自分を呪った。
「頼久さんは卑しくなんかないし従者でもありません。私は仲間だと思ってるし、もっと仲良くなりたいと思ってます。でも迷惑だったらあきらめますから迷惑だってはっきり言ってください。」
ここで迷惑だと言ってしまえばこの心優しき清らかな主が自分のような者に心を砕く必要がなくなるのだということが頼久にはよくわかっている。
たとえそれが無礼な発言だと言われて八葉の任を解かれようともここは迷惑だと言った方がこの主のためなのかもしれないとも思う。
だが、頼久にはどうしても迷惑だとはいえなかった。
武士として八葉の任を解かれることに耐えられなかったというわけではない。
ただ、この主にこうして言葉をかけてもらうことが二度とできなくなる、そう思うとどうしても迷惑だということはできなくて…
「迷惑だなどと…思ったことは一度も……ございません。」
躊躇しながらそれでもやっとそう言って、言ってしまってから頼久は自分の言葉に驚いていた。
ここは神子の身だけを護ればよい武士の自分は迷惑だと言って主の心を安らかにするべきだったのではないのか?
どうしてそれができなかった?
「本当に?従者だから遠慮とかなしですよ?」
「……はい…真実、迷惑だなどと思ったことは…。」
「よかったぁ。」
そう言ってほっと溜め息をついて、それから頼久を見上げたあかねはその顔にとても優しく輝く笑みを浮かべていた。
その清らかな美しさに見惚れて頼久が目を見開く。
「あ、ごめんなさい、私が長々お話してたらそれこそ疲れちゃいますよね。」
「いえ、そのようなことは…。」
そんなことは断じてない。
この主の鈴の音のような美しい声は聞いているだけで頼久の心を安らかにする。
兄を死なせたという自責の念にとらわれていた暗闇の中で聞こえたその声は、今でも頼久の心をいつだって優しく癒す声なのだ。
この優しく美しい声を護るためならば命も惜しくない、そう思っているのだ。
だが、そんなことをこの主に告げるだけの言葉を頼久は持ち合わせていない。
「もう寝ますね。また明日も怨霊退治頑張らないとだし。」
「はい、お休みなさいませ。」
「お休みなさい、頼久さんもさっきの約束忘れちゃだめですよ?眠くなったらちゃんと休んで下さいね?」
「御意。」
今度はしっかりと答えてくれたのであかねは嬉しそうに笑みを浮かべて見せると、御簾の向こうへと姿を消した。
残った頼久は階に腰を下ろしてほっと安堵の溜め息をついた。
どうやら今夜は大切な主の機嫌を損ねずにすんだらしい。
異界からやってきたという龍神の神子はこの京の常識では考えられないようなことをたくさん言ってくる。
本来であれば直接口をきくことさえ許されないだろう頼久に仲間だ、仲良く、などと言ってくれる。
だが、そうは言われても武士として生きてきた頼久に、はいそうですかと言って武士団の仲間に接するように主に接することは不可能だ。
ところが、そんな頼久の態度は時々尊い主を怒らせてしまうようで…
誰でもない自分が側で護り通したい大切な主をどうやら自分の不器用さで怒らせてしまうことがあるらしい、これが目下、武士としては貴族にさえ一目置かれる源頼久の一番の悩みだった。
命を投げ出すことも惜しくはないと思う主の機嫌を損なうことは、それこそ自分の命が失われることよりも恐ろしいというのに、頼久にはどうすればこの異界からやってきた主の機嫌を損なわずにすむのか全くわからない。
とにかく今は、自分にできることを全力で行い、神子を護りぬく。
それしか自分にできることはないのだと心の内で決意を新たにしながら頼久は天を仰いだ。
こうして警護をしていても、武士団へ戻っても、いつでもその胸の内には小さく儚いのに輝いて見える主の姿がある。
そんなふうに主を想うのは初めてのことで、頼久はこのような主に出会えた幸福を思って微笑を浮かべた。
背後でかさりと神子が褥にもぐりこむ気配がする。
こうしてその気配を背に感じることができることさえもが今は幸せに思えて。
そんな自分に驚きながら、頼久は警護を怠るまいと居住まいを正した。
空には綺麗に輝く月が昇り始めていた。
第二話へ
管理人のひとりごと
見切りで始めました一周年記念連載でございます(’’)
時間軸としてはゲーム内、頼久さんにお兄さんの話を聞いた直後くらいです。
二人とももう両思いではありますが、天然なため無自覚みたいな(マテ
そこからちょっとずつ自覚して近づいていく感じを書けたらいいなぁと。
そんな技術あるのかな、自分(’’)(オイ
ちょっと時間をかけて長々とやろうかと思っております。
まったりとお付き合いいただければ幸いですm(_ _)m
プラウザを閉じてお戻りください