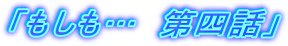
あかね、天真、蘭、詩紋の4人は頼久の家でテレビの前に座っていた。
そんな4人の背中を眺める感じで頼久は一歩引いた場所に座っている。
何故かというと前に座っている4人とはテンションが違うからだ。
この4人、何故テレビの前に並んで座っているかというと、これからイノリがテレビに出るという話を聞いたからだった。
テレビにかじりつかんばかりに正座している4人はさきほどから終始無言だ。
頼久はそんな4人の背中を苦笑しながら見つめていた。
実はこれからスポーツ番組でイノリがスケボーの技を見せるところが映るというのだが、どうやら4人はイノリが失敗しやしないかとハラハラしているらしいのだ。
だが、頼久はイノリのことだからうまくやるだろうと信じている。
ああ見えてイノリは器用だし度胸もある。
本番で失敗ということはまずないだろう。
頼久はそう思っているのだが、どうやらテレビの前の4人はそうではないらしく、さっきからそわそわしていた。
「ストリートスポーツっていうコーナーだよね?」
「そうそう、大丈夫かなぁイノリ君。」
「ボク、お守り渡しておいたんだけど…。」
「お前ら、心配しすぎだろ。」
「そういうお兄ちゃんの方が心配してるじゃない。めったにしない正座なんかしちゃって。」
4人はそれぞれにそわそわとしながらテレビ画面をちらちらと見ている。
頼久はそんな落ち着かない4人のために飲み物でも用意しようと立ち上がった。
「あ、ごめんなさい!私がやります!」
さすがに気付いたあかねが振り返って立ち上がろうとしたのだが、頼久は微笑と共にそんなあかねを手で制した。
友人達と騒いでいるときくらい、気遣いなく過ごしてもらいたい。
それでなくても、年の離れた自分と共にいる時は何かと気遣ってくれるのだから。
「テレビの方が気になるでしょう、今回は私が。神子殿はどうかそのまま。」
そう言って頼久はあかねが動く前に台所へ立った。
あかねの好きなローズティを選択して湯を注いでいるうちに背後で歓声があがる。
どうやらイノリが出るというコーナーが始まったらしい。
だが、頼久は慌てることなくゆっくり紅茶をいれた。
イノリならば心配ないだろう。
今はただあかねにおいしい紅茶を飲ませたかった。
5人分のティーカップに紅茶を注いでリビングへ戻ると、さっきまで騒いでいた4人はすっかり静かになってかじりつかんばかりにテレビ画面を見つめていた。
テーブルの上にティーカップを置いて頼久もテレビを眺めてみれば、ちょうどイノリが映っていた。
頼久の予想通り、イノリは何やら器用にスケボーに乗ったままくるくると回っていて、少しも危なげがない。
それどころか楽しそうでさえある。
イノリが映っていたのは3分ほどなのだが、その放送が終わると4人はテレビを消して同時に大きな溜め息をついた。
「イノリ君、上手だったねぇ。」
最初に我に返ったのはあかねだった。
やっと緊張を解いて頼久に微笑んで見せたあかねがあまりに愛らしくて頼久の頬がゆるむ。
「あ、お茶有難うございます。」
そう言って嬉しそうに微笑んでもらえれば、それだけで頼久は幸せだ。
「上手っていうか、あれはもうプロ目指せるんじゃない?」
「そこまで簡単な世界じゃねーだろ。」
「そうかもしれないけど、でも、失敗しなくてよかった。ボク、こんなに緊張したの初めてだよ。」
苦笑しながらもほっとした様子の詩紋を誰もが暖かく見守った。
イノリがテレビに出るというので一番緊張していたのが詩紋だったのだ。
詩紋はイノリと一番親しいだけに心配も尽きなかったのだろう。
そう思えばこそ、安堵している詩紋を見ると皆、自然と微笑が浮かぶのだった。
「でももったいないよねぇ、あれを公園とかでやってるだけなんて。やっぱりプロ目指すように勧めてみた方がいいんじゃないかなぁ。」
「お前なぁ、プロってのはそんなに簡単じゃねーの。」
「そうかなぁ。」
蘭が助け舟を求めるようにあかねの方を見たその時、ドアチャイムが鳴った。
一同が誰かと小首を傾げながら頼久を見つめる。
「お仕事とかありました?」
あかねが恐る恐る尋ねてみれば、頼久はあっさりと首を横に振った。
「来客の予定はないのですが…。」
頼久はそういいながら玄関へ出て行くと、すぐにイノリをつれて戻ってきた。
「よっ!」
さっきまでテレビ画面に映し出されていた人物が急に目の前に現れて4人はきょとんとしている。
頼久は苦笑しながら台所に立った。
イノリの分の紅茶をいれるためだ。
「あ!ごめんなさい!私やります!」
我に返ったあかねが慌てて頼久の後を追おうと立ち上がったが、頼久に手で制されてしまった。
「あかね、茶くらい頼久にいれさせろ。お前、あいつあまやかしすぎ。」
「あ、あまやかしてなんてないよ!」
「お前ら相変わらずだなぁ。」
じゃれあっているあかねと天真を眺めてイノリは苦笑しながら詩紋の隣に座った。
「イノリ君、見たよさっきのテレビ、凄かったね。」
「たいしたことねーよ。言われたことやっただけだしな。」
「っていうことは、もっと凄いこともできるってこと?」
「ああ、俺より長くやってる有名なやつが不機嫌になるからってやらせてもらえなかった。」
「うわぁ、そういう世界なんだ。」
「違うと思ってたんだけどな。」
詩紋とイノリのやり取りを聞いて残る3人は顔を見合わせた。
スポーツの世界でもそんなことがあろうとは。
「ったく、やってらんねーよ。」
「それでここへきたのか?」
不貞腐れているイノリに声をかけたのはちょうど紅茶を持って戻ってきた頼久だった。
この面々の前ではどうしても年長の頼久はこうして面倒を見る方へ回ることになる。
「ま、そういうことだな。ここにくればお前らがいると思ったし。お前らといると退屈しないからな。」
そう言ってイノリがニッと笑ったので、この場の全員がほっとした微笑を浮かべた。
「ねぇイノリ君、今みんなでプロになったらどうだろうって話してたところなんだけど。」
「プロ?スケボーのか?」
「うん、そう。なれないものかな?テレビで見てたら凄く上手だったし、もっと凄いことができるならなれるんじゃない?」
「ん〜、なれんのかもしれねーけど…。」
てっきり無理だと否定してくるかと思ったのに、どうやらイノリは自分が乗り気ではないらしくて、あかね達は互いに顔を見合わせた。
なれるのならなってやるとイノリなら言いそうなものだ。
「イノリ君はなりたくないの?プロには。」
そう尋ねるあかねをじっと見つめてイノリは真剣な顔で口を開いた。
「プロになったらあかねが頼久からオレに乗り換えるっていうならなってもいい。」
「ちょっ!」
あかねが慌てふためくのを見たイノリは深い溜め息をついた。
「冗談だって。」
そう、何があったってそんなことになるわけがないとイノリ自身よくわかっている。
「イノリ、お前、その手の冗談かましてると命がいくつあってもたりねーぞ。」
「ん?」
天真がイノリに顎で背後を示したのでイノリが恐る恐る振り返ってみると、そこには一同を少し離れたところから見守る頼久の姿があった。
もちろん、腕を組んで眉間にシワを寄せてイノリを睨んでいる。
「だから、冗談だって。プロになる気なんかねーし。」
「どうして?イノリ君ならプロになって世界一目指すって言い出しそうなのに。」
「詩紋、お前はオレをどんなふうに見てんだよ。」
イノリは苦笑しながら詩紋を肘で小突いてから小さく溜め息をついた。
「なんていうか、しっくりこねーんだよな。オレ、もともと鍛冶屋になりたかったわけだし、まわりがなんかキャーキャーいってんのもなんかなぁ…。」
「キャーキャー言われてるんだ…。」
「なんか、スポンサーがどうのとか次のテレビ番組の話されたりとか、大会がどうしたとか、雑誌の取材とか、さっきからやたらうるせーんだ。で、結局スケボーはやめることにした。」
『えーーーー!』
頼久以外の一同が声をあわせる。
イノリは不機嫌そうに顔をしかめて腕を組んだ。
「やっぱオレは職人目指す方が向いてると思うんだ。完全実力主義だろ。それに師匠について修行ってのがやっぱ向いてる。」
「職人って…イノリ君、何になる津もりなの?」
「鍛冶屋ってのはこっちの世界じゃ無理そうだからな、大工にした。」
『大工ぅ?』
また一同が合唱する。
「そう、大工。もう弟子入りしてきた。」
『……。』
今度は一同が絶句した。
テレビ出演や雑誌で取り上げられるというような話まで来ているのに断るとは…
「いいのか?イノリ。スポンサーって話がきてるってことはもうプロになれるってことじゃねーかよ。そんな簡単にやめちまっていいのか?」
さすがに頼久の次に年長の天真がいつになく真剣な表情で訪ねると、イノリは力強くうなずいた。
「プロになれそうだからって簡単になったって、気に入らねーのに長続きするわけねーし、やっぱオレ、何かを心を込めて作るってのがいいんだ。」
「そっか、お前がそこまで考えて決めたんならいいんじゃねーの、な。」
「うむ。」
天真の視線の先にはさきほどまで不機嫌そうにしていた頼久がいた。
だが今は、イノリの決意を聞いて、頼久の表情にはどこか保護者のような暖かな表情が浮かんでいた。
「うん、私もそれでいいと思う。イノリ君なら自分で決めたことはきっとやりぬくと思うから。」
「あかね…。」
優しく微笑みかけるあかねにうっとりと見惚れてから、はっと我に返ってイノリが後ろを振り返ると、先程まで保護者の顔をしていた頼久が案の定自分をにらみつけていた。
「と、とにかく、オレは大工を目指して明日から修行するからな!ちゃんと家を建てられるくらいの腕前になったらあかねに家、建ててやるな!」
「うん、楽しみ。」
「どんな家がいいか考えておけよ。」
「うん、頼久さんも一緒に考えましょうね。」
「はい。」
『はぁ。』
楽しそうに見詰め合うあかねと頼久を見て残る全員が深い溜め息をついた。
「な、何?みんな。」
「お前ら一緒に住む家確定なんだもんなぁ。」
「そ、そういうわけじゃ…。」
「そういうわけだろ。あぁ、もうやってらんねぇ、オレ帰るわ。」
「お、俺達も帰るか。見るものは見たしな。」
イノリと天真がそういって立ち上がると、蘭と詩紋もうなずきながら立ち上がった。
「ちょ、みんなそんな急に帰らなくっても。」
あかねが慌ててそう言っても4人はもう何も言わずに軽くてだけ振ってさっさと帰ってしまった。
後に残されて少しばかり広くなった部屋であかねが同じく残っている頼久を見れば、頼久はやわらかい笑みを浮かべてあかねの隣へ座った。
「急に寂しくなっちゃいましたね。」
「いえ、私は神子殿さえいて下されば。」
「ま、またそういうことを…。」
あかねとしてはなんだか急に寂しくなったような気がしたのだが、どうやら頼久はそれでかまわないようなのであかねもその顔に笑みを浮かべた。
そして心の中でイノリの成功を祈るのだった。
「ん〜、やっぱりイノリ君はアイドルにはならないですよねぇ。本人が嫌がりそう。」
「確かに。」
イノリがもしこちらの世界へやってきたらというあかねの想像を聞きながらその様子を想像していた頼久は、ほっと安堵の溜め息をついた。
それこそこちらの世界では人気のアイドルなんかにイノリがなったりしたら、自分はイノリにも嫉妬しなくてはならなくなる。
そんなことを考えていたからだ。
「頼久さん?」
「い、いえ…イノリならば大工というのはありそうな話です。」
「ですよねぇ。職人になりたがる気がします。」
「そうかもしれません。」
「えっと、あと残ってるのは鷹通さんかぁ。」
「……。」
「鷹通さんは19歳って言ってたし、勤勉な人だからきっと大学生やってますよねぇ。」
「はぁ…。」
「将来は学校の先生か学者さん!きっとその卵です!」
あかねは両手を握り締めて目をキラキラさせながら次の妄想を始めた。
第五話へ
管理人のひとりごと
お待たせしました(><)
第三話、イノリ君編です。
外見的にはね、アイドルって路線もないとはいいません(’’)
でもたぶんイノリには向かないだろうと(笑)
やっぱり尊敬する師匠について職人っていうのしか想像できませんでした(’’)
もう頼久さんが恐くてあかねちゃんにはなかなかかまえませんでしたね(爆)
次回は鷹通さん。
有終の美を飾っていただきましょう(笑)
プラウザを閉じてお戻りください