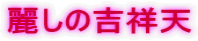
あかねは暗闇の中でゆっくりと目を開けた。
夏の夜。
目覚めてしまえば思わず顔をしかめるほどに暑い京の夜だけれど、あかねはとうにその暑さには慣れていた。
だから、目が覚めたのは暑さのせいじゃない。
寝返りをうってみれば、そこにはいつもすぐに自分を気遣って目を開けてくれる人の姿はなくて、あかねは今、一人で眠っていたことを思い出した。
いつもなら隣で眠っている人、夫である頼久は目下、お仕事の真っ最中のはずだった。
左大臣の警護で少しばかり遠出をしているのだ。
そういうことはよくあることで、もちろん頼久のいない夜にもあかねはもう慣れている。
ということは、これも目が覚めた原因じゃない。
じゃあ、どうして?
と気になり始めると際限がなくて、あかねはとうとう半身を起こすと、辺りを見回しながら耳を澄ませた。
京の夜は暑さもさることながら、静けさや暗さもあかねが暮らしていた世界と比べると尋常ではない。
月のない夜の暗さは本当に鼻をつままれないと目の前に人がいることさえわからないほどだ。
静けさも同様で、かすかな衣擦れの音さえ響いて聞こえるのがこの京の夜だった。
だから、あかねがよくよく耳を澄ませると、屋敷のここかしこで人が動いているのがすぐにわかった。
何やら遠くに話し声も聞こえる。
これは何かあったのだと気付いて、あかねは唐衣を一枚羽織ると、そっと御簾の外へ顔を出してみた。
すると、さっきまで微かに聞こえていた人々の足音や衣擦れの音が少しはっきり聞こえるようになった。
どうやら騒いでいるのは門の向こう、つまり屋敷の外らしい。
何があったのか誰かを探して聞き出そうとあかねが立ち上がったその時、奥から女房が一人慌ててやってきた。
「あの…。」
「神子様、お目覚めでございましたか。」
「あ、はい、何かあったんですか?」
この屋敷にいる女房はつまるところあかねの使用人ということになるのだけれど、あかねはいまだに彼女達に対しても敬語を使う。
年上の人に対して何かを命じるということがあかねにはどうしてもできなかったからだ。
本当は夫の立場を考えるとこの態度も改めないといけないのかもと考えたこともあったけれど、その夫の頼久があかねのいいようにと言ってくれたので現在も敬語は続いていた。
そんなあかねにふわりと上品な微笑を浮かべてから、女房は小さくうなずいた。
「はい。賊が入り込もうとしたようです。」
「賊…。」
「おおかた、お屋敷の中にある金目のものを盗み出そうとでも考えたのでしょう。ここを何方の御屋敷かも心得ず。愚か者ですわ。」
女房が怯えたりしていないところを見ると、どうやら大事にはなっていないらしい。
「あの、それで…。」
「賊は警護の者が捕縛致しましたのでご安心を。」
「それで、あの、武士団の人達に怪我とかは…。」
「いいえ、かすり傷を負った者もないとのことです。賊は速やかに捕縛されましたので。」
「そうですか。よかったぁ。」
やっと安堵の微笑を浮かべるあかねを女房は優しい笑顔で見守った。
この京で身分の高い、いわゆる貴族の御令嬢が警護の者に対してこんなふうに気遣いを見せることはまずない。
彼女達にとっては屋敷を警護している武士など人とも思わぬほど身分が違う存在だからだ。
ところがこの京を怨霊から救ったという神子はというと、こうして何かにつけて武士団の者のみならず、誰に対してでも心遣いを忘れなかった。
始めのうちはそんなあかねに不思議そうな視線を送っていた女房達も、今ではそれこそがあかねの優しさであり、あかねが尊いと言われる所以なのだと理解していた。
「屋敷の警護はしっかりしておりますので、神子様にはお心安く、お休みくださいませ。」
「あ、はい。えっと、武士団の皆さんに有り難うございます、お疲れ様ですって伝えて下さい。」
「確かに承りました。」
一礼する女房に微笑んで見せて、あかねは寝台へと戻った。
あかねの屋敷を警護しているのは頼久の部下に当たる武士達だ。
腕前はもちろん、人間としても優れた者が選抜されているはずで、あかねはこの屋敷の警護には何の不安も抱いていない。
どちらかといえば不安なのはその武士達が無理をして怪我などしないかということの方だった。
女房の話では今回は怪我人も出なかったということだから、あかねはほっと一安心して寝台に戻ることができた。
遠ざかっていく女房の足音を聞きながら、あかねは小さく深呼吸をするとすぐに眠りに入った。
誰も傷つかないですんだ。
その事実があかねを安らかな眠りへといざなった。
あかねの耳に大声が飛び込んできたのは賊が屋敷への侵入を果たせずに捕縛されたあの夜から五日後のことだった。
暑い夏の昼下がり。
暑さも今日が一番という時刻にその声は響いた。
あかねはちょうど頼久の着物を仕立てている途中で、この屋敷ではついぞ聞くことのない大声に驚き、針を持つ手を止めたのだった。
この屋敷へ忍び込もうとした賊が捕縛されたという記憶が新しかっただけに、あかねの体が一瞬緊張で固まった。
けれど、そんなふうに緊張したのは一瞬のこと。
あかねはすぐに何が起こっているのか確かめなくてはと立ち上がり御簾の外へ顔を出した。
すると…
「何かあった時に人数が足りませんでしたと若棟梁の前で言い訳をするつもりかっ!」
今度はその一言一句がはっきりとあかねの耳に届くほど大きな怒鳴り声が庭に響いた。
どうやら築地の向こうで警護の武士達が言い争っているらしい。
「暑さが言い訳になるわけないだろう!」
今度は違う武士の声だ。
「だいたい、万が一にも多勢で押し寄せられるようなことがあったらどうするつもりだ!」
どんどんヒートアップしていきそうな声に、あかねは慌てて出かけられる服に着替えると表へ飛び出した。
「ストーップ!」
表へ飛び出してみれば、そこには十人以上の若い武士が集まって今にも掴み掛らんばかりの喧嘩の最中だった。
だから、あかねの口から飛び出したのはこの京では全く通じない「ストップ」の一言。
何を言われたのかはわからずに一瞬きょとんとした武士達は、次の瞬間、ザッと音さえたててあかねの前に片膝をつくと頭を下げた。
「ああ、えっと、ストップっていうのはやめてって意味です。それから、みなさん立ってください。そんなふうにされると話ができません。」
自分の発した言葉に気付いて慌てて説明して、それからあかねは苦笑をこぼした。
武士達にとってみればあかねは京を救った神子であり、同時に左大臣家の養女でもあって、更に言うなら自分達の若棟梁である頼久の妻だ。
片膝つくくらいは当然のことなのだが、あかねとしてはそんなことをされて平気ではいられない。
「顔を上げてください!」
いつまでたっても微動だにしない武士達によーく聞こえるようにあかねが区切りながらそう叫ぶと、ようやく武士達は頭だけをそっと上げた。
「ほ、本当は立ってほしいんですけど……長くなりそうなので先に話を聞かせてください。どうして喧嘩してたんですか?」
「……。」
あかねが一番自分の近くにいる若い武士に視線を合わせて尋ねると、その武士ははっと何かに気付いたように目を見開き、それから顔を赤くして何故か深々と頭を下げてしまった。
そして当然のことながら問いへの答えはない。
何が起きているのかわからずにあかねが小首を傾げながら隣にいる武士に視線を移すと、この武士も同じような反応を見せた。
これはもしかして、自分には内緒という打ち合わせでもされているのだろうか?
そう考えたあかねは、若い武士達一同の中でも少しばかり年長者に見える一人に視線を定めると、きりりと表情を引き締めた。
「ちゃんと話してください。何があったんですか?一応、私は頼久さんのつ…つ、妻ですし!皆さんに守ってもらってるわけですから何かあったなら聞く権利があると思います!」
あかねが思い切ってそう宣言すると、その視線の先にいる若い武士が渋々といった様子で口を開いた。
「その…先日、賊を捕縛する際にその……少々手間取りましたので、警護の人数を増やすことになり……。」
「えっ、でも、速やかにつかまえてくれたんじゃ…。」
「速やかではありましたが、要領が悪かったと言いましょうか…その……今回は相手が一人でしたので何事もありませんでしたが、敵が複数であった場合に心もとないということになりまして、それで増員を…。」
「でもでも、頼久さんもいないし、増員って言っても大変なんじゃ……………もしかして今もめてたのって……。」
「ここ数日は暑さが激しく、倒れる者が出まして、人数がそろえ……。」
「ダメじゃないですか!そんな!倒れるまで無理しちゃ!」
「ですが!若棟梁の留守中に万が一のことがあっては我々一同、若棟梁に合わせる顔がありません!暑さで人手が足りなくなったなどと、言い訳にもなりません!」
「それでもダメです!そんな無理をしてみんなが倒れちゃったら……そんなことになったら……。」
「神子様…。」
きゅっと目をつむって苦しそうにしているあかねを若い武士達はすがるような目で見上げた。
貴族の身分でありながら惜しげもなくその姿を現し、細やかな気遣いをしてくれるこの女性は若い武士達にとってはそれこそ女神にも等しい存在だ。
その女神が苦悩しているとあっては、頼久よりも更に若い武士達はもう右往左往することしかできない。
若い武士達が片膝をついた姿勢のままでそわそわしていると、あかねの目がゆっくりと開いた。
「私、頼久さんのことを信じてます。だから、頼久さんが信じてる皆さんのことも信じてます。元のままの人数でちゃんと私を守ってくれるって信じてます。だから、元に戻してください。」
「ですが……。」
信用してもらえるのは嬉しい。
だが、その信用を裏切るようなことになるのは耐えられない。
そう若い武士はうったえようとして口を開いて、そして目の前のあかねが腰に手を当てて胸を張るのを見て目を見開いた。
「ダメです!そんな無理をしてみんな倒れちゃったらどうするんですか!私だって元は龍神の神子です!ちょっと賊が入ろうとしたくらいで恐がったりしません!」
「……。」
「ダメって言ったらダメです!戻してください!」
仁王立ちの状態でそう言い放つあかねは、頼久にとってはともかく、若い武士達にとっては神々しい女神に見えた。
しかも、その宣言が自分達の身を案じてのものとなれば感激はひとしおだ。
これはもう、この女神が何を言おうとも警護を強化しなくてはと若い武士達が心の中で決意したその時…
「警護の当番は元に戻せ、神子殿の仰せだ。」
低く流れる耳に涼しい声が響いて、この場の全員の視線が一斉に声のした方へ向いた。
午後の強い陽射しに照らされながらも汗一つ見せない頼久がそこに立っていた。
「頼久さん!」
「ただ今戻りました。」
「お帰りなさい。」
律儀に一礼する頼久にあかねがニコニコと微笑みながら駆け寄る。
武士達は片膝ついた姿勢のままぼーっと仲睦まじい二人を見上げていた。
「早かったんですね。」
「予定より移動が順調でしたので早く戻りましたが、よもやこのようなことになっていようとは。」
「このようなことって…頼久さん、どの辺から聞いてたんですか?」
「神子殿が出ておいでになった辺りからです。何やら話が込み入っていたようなので様子を見させて頂きました。賊が入ったのですか?」
「あ、はい、何日か前に。でも、ちゃんと皆さんがつかまえてくれましたよ?」
「当然です。」
「その時も私、賊の後ろ姿さえ見てないですし、全然大丈夫だったのに。」
頼久はあかねに微笑を浮かべて見せてから一つため息をついて、片膝ついたままの若い武士達を見渡した。
「詳しいことは後で聞く。警護の当番は元に戻せ。体調を崩した者の代わりは手配できるか?」
「はっ!おまかせください!」
「頼む。」
それだけ言うと、頼久はあかねの肩を抱いて歩き出した。
「…吉祥天だ………。」
仲睦まじい夫婦二人の後ろ姿を見送る武士達の間から、その声は自然とわき起こった。
頼久にとっては愛らしいばかりの仁王立ちのあかねは、どうやら若い武士達には本当に女神に見えたらしかった。
築地の向こう、更に庭の向こうに二人の姿が消えるまで、若い武士達は呆然とその神々しいほどの後姿を見つめていた。
「あの…皆さんあのままにしてきちゃってよかったんでしょうか?」
あかねは心配そうにそう言って隣を歩く頼久を見上げた。
頼久はと言えば、その顔に穏やかな笑みを浮かべてあかねの視線に応えながらもあかねの足元への注意を怠らない。
肩を抱く腕で歩きやすい道に誘導しながら頼久は口を開いた。
「大丈夫です。彼らはあれで、私がいない間は自分達できちんと仕事のできる連中ですから。まあ、今回は神子殿の御身のことでしたので、少々大げさになったようですが。」
「倒れるまで頑張ってもらっちゃって、なんだか申し訳ないです。」
「それは、彼らが勝手にやったことです。神子殿はお気になさらず。」
「最近、すごく暑かったし、大変だったと思うんです。それなのに頑張ってくれたんですよね。何かお礼においしいものでも作って……。」
「いえ、そのようなことをなさってはかえって彼らが恐縮してしまうでしょう。」
「あ、そっか、そうですよね。」
なるほどとあかねはうなずいたけれど、頼久のその言葉は真実が半分、牽制が半分だった。
あかねに差し入れなどされれば、あの若い武士達が恐縮することは間違いない。
けれど、頼久があかねを止めた理由はそれだけではない。
あかねの手料理をなるべく他人に食べさせたくはないというのが本当のところだ。
あかねはそんな頼久の胸の内には気付かない様子で、屋敷の中へと歩いていく。
その後を追うようにあかねと共に屋敷の奥へ移動して、二人並んで御簾の内に腰を落ち着けて、頼久はようやく一息ついた。
「頼久さんはずっとお仕事でやっと帰ってきたのに、なんだか大騒ぎしててすみません、驚きましたよね。」
「いえ、思いのほか、彼らがよくやってくれていたようで安堵しました。」
「それはもう!この前賊が入ったって騒いだ時だって、すぐにつかまえてくれて、私、騒ぎの後、安心してすぐ寝れたくらいです。」
「それは何よりでした。ですが、神子殿。」
「はい?」
「その……私が不在の時にあまりあのように皆の前に姿を見せるのは…。」
そう言って頼久はさきほど若い武士達に指示を出した若棟梁と同一人物とは思えないほど弱々しい苦笑を浮かべた。
あかねには全く自覚がないのだが、その愛らしい姿を目にすれば一方的にあかねに想いを寄せる男がいてもおかしくはないと頼久は思っている。
自分が隣で守れる場合ならまだしも、あかね一人であんなふうに若い男達の前に姿を見せるのは頼久としては避けたい事態だった。
「あ、そうですよね…すみませんでした…。」
「いえ、その、私がすぐそばでお守りできるような場合は構わないのですが…やはり私が不在の場合は心配ですので。」
「でも、武士団の皆さんがちゃんと守ってくれてるから大丈夫でしたよ?今回は。」
その武士団の皆さんが危ないのだとはとても言えなくて、頼久は苦笑を深くした。
頼久の苦笑の意味がわからないあかねは小首を傾げるばかりだ。
そんな様子も愛しくて、頼久は思わずあかねを抱き寄せた。
「よ、頼久さん?」
「お会いしていなかったのは数日でしたが、その間にも神子殿はお美しくなられました。」
「はい?……そんな急に変わってませんよ!」
「いえ…。」
そう低くつぶやいたきり、頼久はあかねを抱きしめて離そうとしない。
数日会っていなかったのはあかねも同じこと。
こうして抱きしめられてしまうと、それはそれでとても心地が良くて…
ゆっくり息を吸うと、頼久だとすぐにわかる梅花の香りに混じってお日様と草の香りがした。
そうだ、この人は長旅から帰ったところだったと香りで思い出して、あかねはすっと頼久の腕から逃れて立ち上がった。
「神子殿?」
「すみません、頼久さんは帰ってきたばかりで疲れてるのに…。」
「はぁ…。」
「夕餉になにかおいしいものを作ってもらってきます。あと、お酒も用意しますね。頼久さんはもう着替えてゆっくりしちゃってください。私色々手配して……。」
あかねがそこまで言ったところで、頼久はあかねの手を取るとそっと自分の方へ引き寄せた。
『きゃ』という小さな声と共にぽすんと小さなあかねの体が座っている頼久の膝の上へと降ってきた。
膝の上におさまったぬくもりをそっと両腕で抱きしめて、頼久は目を閉じた。
すると、目に浮かぶのは仁王立ちで若い武士達を相手に一歩も引かずに指示を出していたあかねの姿だった。
その姿が頼久の記憶の中、怨霊と戦っていた頃のあかねの姿に重なって見えた。
「頼久さん?」
「神子殿、お慕いしております。」
「へ……は、はい!私も大好きです!」
予想外の不意打ちにうろたえて、思わず大声を出すあかねにくすっと笑みを漏らして、頼久は目を開けた。
腕の中で自分を見上げる愛しい妻は、真っ赤な顔でそれでも優しく微笑んでくれていて…
あの頃もと頼久は思う。
怨霊と戦っていたあの頃も、あかねはこうして微笑んでいてくれたものだ。
髪が伸びて、着ているものもこちらの物になって、その顔も少し大人びた。
けれど、あの頃も今もあかねの強さ、優しさ、慈悲深さは少しも変わらない。
そのことに気付いて、艶を含んだ溜め息を漏らした頼久は、あかねを更にぐっと抱きしめて目を閉じた。
そしてもう一度、自分にこうして抱きしめる権利を与えてくれた愛しくてたまらないその人に、想いのたけを込めて頼久は囁いた。
「お慕いしております。」
管理人のひとりごと
まだ舞台が暑い日なのは、管理人の生息地が尋常じゃなく暑いからです!
吉祥天ってのは、ヒンズー教から仏教に輸入された女神様です。
容姿端麗な美しい女神様として知られてますね。
仁王立ちするあかねちゃんが若い武士にはそんなふうに見えたというお話。
頼久さんにとってはもうかわいくてかわいくてしかたないって感じに見えてます(^▽^)
だから本当は誰にも見せたくないのです(w
ブラウザを閉じてお戻りください