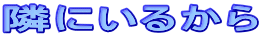
夏休みが終わったというのに暑い日は続いていた。
朝からの晴天、時折吹く風も生暖かい。
さすがに熱風とまでは言わないが、決して身に受けて気持ちのいい風でもなかった。
そんな夏の晴天の下をあかねはゆっくりと頼久の家へ向かって歩いていた。
夏休み中、ほぼ毎日のように通っていた道だが、今日はなんだかひどく長く感じる。
暑さのせいだとため息をついて額に浮かぶ汗をぬぐった。
いつもよりも少しだけ時間をかけて歩いて頼久の家へたどり着くと、すぐに扉が開いて中から頼久が笑顔で出迎えてくれた。
手に持っていた荷物は何も言わずに頼久に取り上げられて、あかねはにっこり微笑みながら中へ入る。
それはいつもの風景。
「今日は一段と暑いですね。」
「学校も空調設備あるはずなんですけど、どこへ行っても暑くて、みんな文句ばっかりでした。今日は昨日より暑いですよねぇ。あ、頼久さん、それ冷蔵庫で冷やして下さいね。昨日、一緒に食べようと思って作ってきたフルーツゼリーなんです。」
「承知しました。」
言われたとおりに頼久は冷蔵庫へゼリーをしまうと、代わりに麦茶を手にリビングへ戻ってきた。
テーブルの上には既に二つのグラスが並んでいて、頼久がかなり前からあかねの来訪を待ていたのがうかがえる。
それが嬉しくてあかねはソファに座るとにっこり微笑んだ。
「新学期はいかがですか?」
「秋になったらすぐ文化祭なんで、今から色々話し合いとかあって忙しいです。テスト勉強もしなくちゃいけないはずなのに、みんなもう今から文化祭の話で大盛り上がりなんです。」
「楽しそうですね。」
「みんな凄く一生懸命だからきっと楽しくなると思います。」
そう答えてあかねは麦茶を一口飲むと窓の外を眺めた。
青々とした草が綺麗に刈られて、花が咲きそろっているこの家の庭はいつ見ても気持ちがいい。
窓がきちんと閉まっているのはこの部屋のエアコンが効いているからなのだが、なんだか外の風を入れられないがもったいないくらい窓の向こうの世界は綺麗だった。
「もうちょっと涼しくなったら縁側で夕涼みとかできそうですよね。」
「はい。」
こんな他愛ない会話が嬉しくて。
二人でいる、ただそれだけの時間が幸せであかねはついつい多少疲れていてもここへ通ってしまうのだ。
今も、恋人と一緒にいることが嬉しくて少しばかりだるく感じる体のことなど忘れてしまうほど嬉しくて、あかねはソファにもたれて窓の外を眺め続けた。
「文化祭の準備が始まれば忙しくおなりでしょう、あまり無理はなさらず、お疲れでしたらここへはいらっしゃらなくとも…。」
「ダメ!ダメです!そりゃ、たまに来れないこともあるかもしれませんけど、でも、なるべくきますから!」
「ですが…。」
「頼久さんは私がここに毎日来ちゃ迷惑、ですか?」
「とんでもありませんっ!」
「なら、毎日来ます。」
楽しそうな笑顔でそう言われてしまっては頼久にはもう反論できるはずもない。
そもそも頼久の方こそが毎日あかねを家まで送っていくその時間が あかねと離れなくてはならないその瞬間が訪れるのが苦痛でならないのだから。
頼久が感謝の気持ちを述べようと口を開いた刹那、ソファにもたれたあかねから寝息が聞こえ始めて頼久は目を丸くした。
さっきまで楽しそうに微笑んでいたあかねはソファに崩れるようにもたれかかったまま、いつの間にか眠っていたのだ。
暑い日が続いたせいかすっかり疲れているらしいあかねの様子に、頼久は心配そうな表情を浮かべたまま、寝室から薄手の膝掛けを持ってくるとそれをあかねにそっとかけてやった。
エアコンの設定温度を上げてあかねの隣に座る。
確かに外は暑いが、エアコンが効いているこの部屋では夏風邪をひかせてしまうかもしれない。
あかねの安眠を守るため、頼久は細心の注意を払うのだった。
「何故、お前がここにいるのか?」
「答え、あかねに頼まれたから、だ。」
これは頼久の自宅、玄関にて、不機嫌な男二人によって交わされた会話。
あかねがフルーツゼリーを食べることができないほど爆睡して帰った翌週の金曜。
頼久のもとを訪れたのは愛しい恋人ではなく、その友人、天真だった。
当然あかねが訪ねてくるものと思っていた頼久は、不機嫌そのものの顔で天真を迎えてしまい、天真もまた、そうなることがわかっていたのだが不機嫌そのものの顔で訪ねてしまった。
結果、無愛想な男が二人、狭い玄関でたたずむことになってしまったのだった。
「神子殿に何かあったのか?」
「お前まだ神子殿かよ…って、そうじゃねー、そういう話をする前に俺を中に入れろよ。」
「神子殿に何があったのだ?」
どうやら一歩も引くつもりがないらしい頼久の様子に天真は深い溜め息をついた。
「『お願い、天真君。頼久さん絶対心配するから普通に用事があっていけないっていうことにしておいて』ってお願いされてる俺としてはあかねは用事があってこれねーとしか言えないんだが。」
「私が心配するようなこと…神子殿はお怪我でもなさったのかっ?!」
今にもつかみかからんばかりの勢いの頼久を手で制して、天真は再び溜め息をつく。
「用事があるでお前が納得するわけないしな。だからってわけを話したら最後、お前、何も考えずにすっとんでいきそうだしな…。」
「天真…神子殿に何があったのだ?」
完全に目が据わった状態でとうとう天真のシャツの襟に手をかけた頼久に、更に深い溜め息をついて天真は靴を脱ぐと頼久の手を払って勝手に中へ入り込んだ。
「おい、天真!」
「とにかく落ち着けよ。あかねは別に死にゃしないし、お前のことを嫌いになったって言ったわけでもねーから。」
「そ、そのようなことになれば、私は……。」
「あーーーーもう、脳内でそういう想定しただけで死ぬほど落ち込むのやめろ。鬱陶しい……。」
天真は勝手にソファに座り、頼久は必然的にテーブルを挟んで向かい側に座ったが、もう先ほどの天真の言葉がショックだったようでうなだれている。
そしてそんな頼久を見た天真も何故かうなだれた。
「お前なぁ……とにかく落ち着け。落ち着いて聞いてくれ。」
「うむ…。」
「さっき、あかねな、学校で倒れた。」
「なんだとっ!」
すっくと立ち上がる頼久の腕を間髪いれずにつかんだ天真は今日何度目になるかわからない溜め息をついた。
「だーかーら、ちょっと落ち着けって。」
「これが落ち着いていられるかっ!」
「話ができないだろうがっ!」
「神子殿がお倒れになったというのにお迎えにも上がらず…いや、しかし、連絡も下さらないとは…。」
「あかねが止めたんだよ。俺はお前にも知らせて車で迎えに来てもらえって言ったんだけどな。」
ここでようやく頼久は落ち着きを取り戻した。
あかねが自分の迎えを拒絶した。
その事実が頼久の理性をなんとか引き戻したらしい。
「何故、神子殿は…。」
「だから、心配かけるからだと。お前、必要以上に心配しそうだから連絡したくないってさ。まぁ、実際、ただの貧血だったから、蘭が送っていって今もそばについてるはずだから、とりあえず安心しろ。」
「…うむ……。」
やっとソファに座りなおした頼久はそれでも真っ青な顔でうつむいてしまった。
「で、俺としてはお前に話しておきたいことがある。」
「ん?」
「あいつ、あれでけっこう無理してんだ。中学と違って高校は意外と勉強しんどいしな、ここに毎日通うのも、そりゃ楽しいってのはあるのかもしんねーけど体力的にはけっこうきついはずなんだ。それでもここに通い続けるのには、あいつがお前に会いたいって以外にも理由があるらしい。」
「理由?」
「あぁ、今日、あと明日明後日、あいつたぶん安静にしてた方がいいから家でおとなしくしてろって言ったんだ。だもんだから、代わりに俺が派遣されたってわけだ。」
「それは…どういう話の流れだ…。」
「あかねがここに通う理由の一つはお前に会いたいから、もう一つの理由は、お前に寂しい思いをさせたくないから、らしい。」
「ん?」
「京からこっちの世界へ連れてきちまって、京にいた頃みたいに武士団の後輩や同僚に囲まれることもなくなっただろう?こっちの世界で生きてきた記憶があるって言ったって、そのこっちの世界で生きてたお前には親戚友人が皆無だろ?つまり、あかねはお前をこっちの世界へ連れてきちまったせいで京の仲間と引き離して一人にしちまったって思ってるらしい。だから、自分がなるべく一緒にいなくちゃならねーって気合いれてここに通ってたってわけだ。」
「その結果、過労で貧血…。」
「まぁ、そうだな。で、お前を一人にしないために派遣された俺ってことなんだが……結論として俺が一番哀れな気がしてきたぞ…。」
一人うなだれていく天真を放置して頼久は唇を噛んでうつむいた。
自分は己の意思で神子殿と共にこの世界へやってきた。
そのことを後悔したことは一度もないし、神子殿がこの世界にいらっしゃる限り寂しいだの心細いだとの思うことはこれから先も有り得ないだろう。
それなのに神子殿ときたらそんな自分のことを体調が崩れるほどに気遣ってくださるとはっ!
と、頼久は神子殿に大切に思われていることを幸せに感じることひとしお、同時に倒れてしまった神子殿に倒れるほどそばにいて下さらなくともいいのだということを説明申し上げなくてはっ、と焦る気持ち半分で考え込んでしまった。
どうすればあかねを安心させられるのか、自分がこの世界にいることを苦痛とは思っていないと伝えられるのかを真剣に考える。
眉間にシワを寄せて考えること数分、頼久はすっと視線を上げた。
「どうした?」
「神子殿のもとへお見舞いに行く。」
「いや、だから、あいつが気にするからやめとけって。」
「考えがある。」
「あん?」
「このままにしておいては一度は回復されても、また神子殿が過労で倒れられることになりかねん。今のうちに神子殿には御無理なさらぬように話をしておかなくてはなるまい。」
「……話、ねぇ。」
「……私が口下手なのは自分でも自覚している。だから、考えがあると言っている。」
天真はじっと頼久の顔を見つめた。
二人の真剣な視線がぶつかり合う。
京で相棒として共に戦っていた頃からこうして視線を交わすだけでお互いの真剣さは簡単に伝わっていた二人だ、今回も天真はふっと息を吐き出すと一つうなずいた。
「わかった。お前に任せるわ。三日間ここに通い詰めさせられるのもうんざりだしな。」
「私とてお前と二人でこの家に置かれても鬱陶しいことこの上ない……。」
今度は互いににらみ合ってから二人はすっくと立ち上がった。
何も言わずに荷物をまとめ、二人そろって家を出る。
その足は自然とあかねの家へ向かった。
「ヘタしたらあかねはもっと気にするからな。うまくやれよ。」
「わかっている。」
いつもならあかねと一緒に歩く道を天真と並んで歩きながら、頼久は自分がこれからなすべきことをじっくりと考えるのだった。
あかねはゆっくりと瞼を上げた。
目に入ったのは自分の部屋の天井だ。
まだ覚醒しきらない頭で思い起こしてみると、ぼんやりと覚えているのが蘭の心配そうな顔。
学校で倒れてそこからの記憶がはっきりしない。
確か天真と蘭に支えられて家まで帰ってきて、お母さんが買い物に出ていたから蘭がついていてくれて…
その後の記憶がなくなっていた。
どうやら蘭の看病に安心して眠ってしまったらしい。
部屋の中は薄暗くてもうすぐ夜になるらしいことがわかった。
ただ、ベッドサイドのランプがついているからあかねの周りは少し明るい。
そのランプの方へと目をやって……
「よよよよ、頼久さん?!」
椅子を持ってきてすぐ横に座っている人物に気付いてあかねは飛び起きた。
呼ばれた頼久はというと今まで読んでいたらしい本にしおりを挟んで閉じるとふっと優しく微笑みながら、あかねの肩をそっと押して再びベッドへと寝かせた。
「お目覚めですか?」
「は、はい…えっと……。」
「よくお休みでしたので、お目覚めを待たせて頂きました。」
「いえ、そういうことじゃなくて……どうして頼久さんがここに?」
「お倒れになったと聞きましたのでお見舞いに。」
「あぁもぅ、天真君、頼久さんには言わないでって言ったのに…。」
「私が天真から無理に聞きだしたのです。」
「天真君がどんなふうに話したか知りませんけど、ただの貧血で、ちょっと暑さに負けただけですから、あんまり心配しないで下さいね?」
「では、神子殿も、私がこちらの世界で孤独だなどという心配はなさらないで下さい。」
「えっ……もう、天真君でしょ、そんなこと言ったの……。」
布団を口元まで引き上げてあかねは真っ赤になってしまった。
頼久はそんなあかねさえも愛しくてくすっと微笑む。
「これからは、神子殿がお忙しい時は私がこちらへ参りますので。」
「はい?」
「ですから、神子殿がお忙しい時、お疲れの時は、私がこちらに伺うことに致しましたので。」
「致しましたのでって…でも、うち、お母さんがずっと家にいるし、来づらくありません?」
「いえ、特には。先ほど、御母上に許可も頂きましたので。」
「許可って……。」
そういえば頼久さんは寝てる私の部屋にあっさり通されてる?
と考えてあかねは深い溜め息をついた。
頼久がどれほど心を砕いて両親の信頼を得てくれているのかはよく知っているつもりだが、それにしても母の信頼はちょっといきすぎではないだろうか?
「とりあえず、今日のところはもう少しゆっくりお休みください。私は暗くなってまいりましたのでこれで失礼します。」
「あ、はい。わざわざ有難うございました。」
「いえ、明日、また参りますので。」
そう言って笑顔を見せて去っていく頼久の大きな背を見送ったあかねは、ふっと安堵の溜め息をついて布団をかぶり直した。
一人になってみるとやはりあっさりこの部屋に入る許可を出してしまった母のことが気になって。
あかねは一人眠るどころではなくて、しばらく頼久に予想以上に甘い母親のことを考え続けるのだった。
何故、あかねの母が頼久にあかねの部屋へ頻繁にやってくることをあっさり許可したのか?
この疑問の答えをあかねは翌日知ることになった。
翌日、前の日に倒れたとは思えないほど爽やかに目覚めたあかねは、リビングへ下りていってすぐテーブルの上に盛大に活けられている赤いバラの花を見つけて目を丸くした。
母に問いただせば昨日、頼久が見舞いにと持参した花だそうで…
次にあかねが気付いたのは花の横においてある大きな箱だ。
こちらも母に問いただすと、昨日、頼久が見舞いにと持参したお菓子だそうで…
最近話題の有名店のロゴが入った大きな菓子箱を見て、あかねは深い溜め息をついた。
(頼久さんがこんな、女性の好きなものを研究しつくしたみたいなお土産持ってくるはずない!いったい誰?頼久さんにこんな入れ知恵したのは誰?)
と心の中で叫びながらも、とってもご機嫌な母親を見てしまっては入れ知恵した人物に感謝さえしなくてはと思うあかねだった。
そして、この日、ドアチャイムが鳴ったのであかねが笑顔で玄関に迎えに出ると、そこには百合の花束と大きなケーキの箱を手にした頼久が立っていたのだった。
管理人のひとりごと
さて、頼久さんに入れ知恵したのは誰でしょう?
というのは小説部屋、その他にあります拍手御礼SSの「助言」を見て頂けばわかるようになっております(^^)
気になる方はそちらを御覧くださいね。
暑さと多忙さに負けてダウンしたあかねちゃん。
おかげで頼久さん、ちょくちょく家に来てくれるようになるようです(笑)
今回も天真君がいいやつですな(爆)
プラウザを閉じてお戻りください