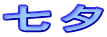
朝の気配を感じて頼久は静かに目を開けた。
庭でさえずる小鳥の声を聞きながらゆっくりと左腕の中にあるぬくもりを確かめる。
頼久がしっかりと左腕で抱きかかえているのは愛しい新妻だ。
心地よさそうな寝息をたてているあかねを見て、頼久は穏やかな微笑を浮かべた。
毎朝のことなのに、目覚めるたびに腕の中にある妻の姿を見ると必ず笑みがこぼれるのだ。
そしていつもならこの愛しい人の眠りを妨げないように静かに寝所を出るのだが、今日ばかりはそうはいかなかった。
何しろ昨夜、朝早くに起こしてほしいとその愛しい人に懇願されているから。
だから頼久はしばらく妻の寝顔を堪能してからゆっくりその肩を揺らしてみた。
「神子殿、朝ですが。」
「う〜ん…。」
頼久に肩をゆすられたあかねはというと、起きるどころかそろりと頼久の方へ身を寄せてそのまま頼久の胸にすりすりと頬ずりして寝息をたて始めてしまった。
一瞬驚きで目を見開いた頼久は、自分にすり寄ってきた妻を愛しそうに抱きしめてうっとりして…
そしてはっと我に返った。
そう、今日はなんとしても妻を早く起こさねばならないのだ。
「神子殿、起きてください。」
頼久が鉄の意志で自分の体からあかねを引き離すと、あかねはうっすらと目を開けて頼久を確認して、またその胸にすり寄ると寝息をたて始めた。
なんと愛らしいと頼久が感動しながら再び妻の小柄な体を優しく抱きしめてうっとりとする。
このように幸せな時を過ごせるのも皆この愛しい妻のおかげとしばし感動してから、頼久はまた我に返って激しく首を振った。
このままではあかねを寝坊させてしまう。
「神子殿、起きてください。早く起きたいとおおせではありませんでしたか?」
「ん〜…。」
「神子殿、何かやることがおありなのでは?」
「…頼久、さん?」
「はい、おはようございます。」
まだ寝ぼけているらしい妻ににこりと微笑んで見せて、頼久は上半身を起こした。
するとつられたようにあかねも上半身を起こしてねむたげに目をこする。
「お目覚めですか?」
「朝、ですか?」
「はい、朝です。」
ぱちくりと瞬きしたあかねが愛らしくて、思わず頼久がその体を抱き寄せる。
あかねの方は黙ってうっとり頼久に抱きしめられてから、はっと目を見開いて勢いよく立ち上がった。
「神子殿?」
「頼久さん!」
「はい?」
「今日のお仕事は?って、あ、おはようございます!」
「はい、おはようございます。その、落ち着いてください。まだそんなに遅くはございませんし、仕事は午後から警護が入ってるだけですが…。」
「よかったぁ、じゃぁ間に合うかも。」
「は?」
「頼久さんはこれから鍛錬ですよね?」
「はい、そうですが…。」
「よしっ!」
そう気合を入れてあかねは頼久の目の前で夜着をするすると脱ぎ始めた。
これは目に毒と慌てて頼久が目をそらすのにも気付かない様子だ。
「み、神子殿、何を…。」
「これでよしっと、じゃ、頼久さんは鍛錬、頑張ってくださいね!」
頼久があたふたとしている間にあかねは水干姿に着替えてさっさと寝所を出て行ってしまった。
後に残された頼久はというと、しばらく呆然としたまま動けずにいた。
あかねが何を焦っていたのか全く心当たりがない。
どうやら朝早くから起きて、頼久が仕事に出る前に何かしたいらしいのだが、こういう時、あかねはたいてい自分ひとりで突っ走るので頼久には何がなんだかわからないことが多い。
京に残って頼久の妻となってからのあかねは特に一人で何かと頑張っていることがあるらしい。
どうやらその頑張りをあまり頼久に知られたくない様子なので、頼久は黙って見守ることにしているのだが…
おかげで頼久はあかねが何を頑張っているのか探るのが大変だ。
女房や八葉の皆に話を聞いて回ることさえある。
今回も頼久はあかねが何をしようとしているのか全くわからない。
これはまた女房達にでも話を聞かなくてはと苦笑しながら頼久は立ち上がった。
あかねの去っていった方を見れば、朝陽が差し込んで縁が明るく照らされている。
鍛錬をするには心地良さそうな朝だった。
頼久は縁で深い溜め息をついた。
朝、愛しい妻の可愛らしい寝起きを見たまではよかった。
その後、妻は何やらいそいそと寝所を出て行ってしまい、そのまま朝餉にも姿を現さなかったのだ。
いつもなら朝早くから武士溜まりへ出かけていくところなのだが、今日は午後から左大臣の警護の仕事が入っているのでそれまであかねとゆっくりすごすつもりでいた。
そんな頼久の思惑は見事に外れていた。
あかねにはあかねの都合があるのだろう。
ひょっとしたら自分のためにまた何か懸命に努力してくれているのかもしれない。
そう思ってはいるのだが、それでもやはり愛しい妻と共に過ごせないというのは寂しいものだ。
頼久は真夏の庭を眺めながらまた溜め息をついた。
朝餉からここまで何度溜め息をついたことか。
遠巻きに心配そうな女房達が自分を見つめている視線さえもうどうでもよくなっていた。
あかねのいた世界の習慣に合わせて、この屋敷にいる時は昼も軽く食事をとる。
左大臣の警護に向かう前のその軽食だけはあかねと共にできるだろうかと、頼久の頭の中はそんなことばかりが巡っていた。
同じ屋敷の中にいるのだから、会いたければすぐ会いに行けばよさそうなものなのだが、そうなると何かを懸命に頑張っているあかねの邪魔になりそうな気がして。
あまり追いかけ回して鬱陶しいと思われるのもいけない。
などなど。
頼久の頭の中はそんな思考がぐるぐると回っているのだった。
「頼久さん!」
「はい?」
突然耳に入ってきた一番聞きたかった声に頼久は思わず微笑みながら振り返った。
見るとそこには何やら楽しそうな笑みを浮かべたあかねが大きな器を手に立っていた。
その姿を見て頼久が満面の笑みを浮かべる。
あかねが何を手に持っているのか気になりつつも、やっと会えた喜びでそれどころではないらしい。
あかねはというと、にっこり笑みを浮かべたまま頼久の隣へすとんと座って手にしていた器を頼久の方へ差し出した。
「はい、どうぞ。」
差し出された器の中には何やら菓子のようなものが入っている。
頼久は小首を傾げながらその一つを手に取ってみた。
「これは…。」
「索餅(さくべい)です。」
「これをお作りになるために今日は早く起きられたのですか?」
「はい。よかったです、頼久さんがお出かけする前にできて。」
あかねは心底嬉しそうなのだが、頼久には何故そんなにあかねが嬉しそうなのかがわからない。
このような菓子一つ作って食べさせるために何故あかねが朝早起きまでしたのかもだ。
「頼久さん、これ、嫌いですか?」
「いえ…嫌いではありませんが…何故…。」
「あれ、頼久さんひょっとして知らないんですか?京では夏、熱病にかからないようにって索餅を食べるって聞いて、それで作ってみたんです。頼久さんに熱病になってかかってほしくないし。」
「神子殿…。」
新妻の優しい心遣いに感動しながら頼久は幼い頃の記憶をたどっていた。
そういえば幼い頃は兄と共に夏、このような菓子を食べていたような気がする。
戦いの中に身を置くようになってすっかり忘れていたが。
「どうせ食べてもらうならやっぱり手作りしたくて、それで朝起こしてくださいってお願いしたんです。」
「神子殿…。」
自分の身を案じて心を込めて妻が手作りしてくれた索餅を頼久はじっと見つめた。
器の中にはまだたくさんあって、あかねがどれだけ張り切ったのかがよくわかる。
「食べて、もらえますか?」
「もちろんです、ただ…。」
「ただ?」
「神子殿も一緒に食べて頂けますか?」
「はい?私?」
「はい、神子殿にも熱病になどかかって頂きたくはありませんので。」
「あぁ、そっか。そうですよね、じゃ、一緒に食べましょう。」
そういうとあかねも器から一つ索餅を取り出して微笑んだ。
そして二人で笑みを交わして、二人同時にそれを口にする。
サクッと音がして二人は再び視線を交わした。
「口に合いました?」
「はい、とても。」
「よかったぁ。」
あかね本人が言うにはどうも料理にはそんなに自信がないらしいのだが、頼久はあかねの手料理が気に入ってる。
味ももちろんだが、あかねのような高貴な女性が手づから料理してくれるものなど頼久にとっては有り難くて畏れ多いほどなのだ。
「これで熱病にかからないですよね。」
「はい。元より鍛錬しておりますので簡単に病になどかかりませんが、このように神子殿に厄除けをして頂けば間違いありません。」
「私も頼久さんに元気をもらったからもう大丈夫ですよ。」
そう言って微笑むあかねが愛しくて頼久が抱き寄せようとしたその時…
「ほぅ、厄除けの索餅だね。神子殿の手作りかな?」
「あ、友雅さん。友雅さんも一つどうですか?」
ひょっこり現れた美丈夫は艶な笑みを浮かべながら頼久を一瞥するとあかねから索餅を一つ受け取って口にした。
「ほぅ、いいできだね。」
「そうだ!友雅さん!」
「ん?何かかな?」
「これ、藤姫にも届けてもらえませんか?」
「今からかい?」
「はい、今すぐ!」
「しかたないね、神子殿の仰せとあれば。」
あかねは綺麗な紙で索餅をいくつか包むと、苦笑している友雅に持たせた。
にっこり微笑んで「宜しくお願いします。」といわれてしまえば友雅にさからうことなどできるはずもなく、今でも忠実なる神子の八葉であると自負している友雅はすぐにあかねの屋敷を出て行くことになった。
「ふぅ。」
「神子殿?」
「友雅さんが来てくれると屋敷の中がぱっと明るくなった感じがして、おしゃれのこととか色々お話も聞けて嬉しいんですけど…。」
「はぁ。」
「今日は頼久さん、これからお仕事だし…その…今日くらいは二人きりでいたいかな、なんて…。」
「神子殿…。」
真っ赤な顔でうつむきかげんに語るあかね。
そんなあかねを見つめて頼久は心底嬉しそうな笑みを浮かべると、今度こそあかねの肩を抱き寄せた。
「よ、頼久さん!昼間です!」
「はい。」
「は、はいって…。」
首まで赤くなりながらもあかねが抵抗せずに頼久の腕の中でおとなしくしていると、再び庭の方で人の気配がした。
「お前らさぁ、昼間っからそれはねぇんじゃね?」
「夫婦なのだ、問題ない。」
聞こえた声にあかねがはっとして頼久から体を離せば、庭にはイノリと泰明の二人が並んで立っていた。
「へ、どうしたの?二人とも。」
歩み寄ってくる二人の八葉とあかねを苦笑しながら見比べて頼久は居住まいをただす。
どうやら誰にも心優しく人気の妻とはなかなか二人きりにしてもらえぬらしい。
「そろそろ暑くなってきたし、厄除けに索餅持ってきたんだけどな、そこで同じこと考えた泰明にばったりって…それ…。」
「珍しく神子も厄除けを考えていたのか。」
「め、珍しくって泰明さん…私だって学習するんです。」
「それってあかねの手作りか?」
「そうだよ。あ、そうだ、二人が持ってきてくれたのと交換しましょう、で、みんなで食べましょう!そうすればみんな無病息災!」
「お、いいな、そうしようぜ。」
あかねの提案に従ってたくさんの索餅が並べられ、縁はいつのまにか茶の間のようになってしまった。
楽しそうなイノリ。
いつもは無表情なのにどことなく微笑んでいるように見える泰明。
そして心の底から楽しんでいるふうのあかね。
三人の姿を優しく見守っていた頼久は、すっと立ち上がった。
「頼久さん?」
「申し訳ありません、私はそろそろ左大臣様の警護に参りますので。」
「あ、そっか。お仕事でしたよね…ごめんなさい、その…。」
せっかく二人きりでいたのにとあかねが落ち込むと、頼久はあかねの耳に唇を寄せた。
「昼は八葉と共にお楽しみ下さい。夜は私が神子殿を独り占めさせて頂きますので。」
「よよよよ、頼久さん!」
イノリと泰明には聞こえない声で囁いた頼久は余裕の笑みを浮かべている。
対して囁かれたあかねの方は真っ赤だ。
「では、行って参ります。」
「いいいい、行ってらっしゃい!」
真っ赤な顔でそういうあかねの唇にかすめるような口づけをして、頼久は颯爽と立ち去った。
残されたあかねの方はというと、お仕事にいく時は必ずキスをしてから行ってくださいと頼んだのは自分だというのに、イノリと泰明の二人がいる前でいつもと同じようにされて真っ赤になって固まっていた。
まさか人前でされるとは…
「なぁ、頼久って変わったなぁ。」
「そそそそ、そう?」
「神子、先程から言の葉がおかしいぞ。」
「そそそそ、そんなことないよ、うん。」
「ま、いいんじゃねーの、今の頼久、悪くないぜ。」
そういうイノリがニカッと笑って見せるのを見て、あかねはようやく落ち着いて微笑んだ。
「そうだ!永泉さんと鷹通さんも呼んじゃいましょう!今日はみんなで厄払い!」
「おお、みんなかなり会ってねーもんなぁ。頼久帰ってくるまで騒いでやろうぜ。」
「友雅はいいのか?」
「あ…えっと……もうちょっとしてから呼ぼうかなぁ、藤姫のところにお使いに行ってもらっちゃってて…。」
「ならば、藤姫と共にここへ呼べばよい。問題ない。」
「なるほど!」
あかねが賛成したと見るや否や、泰明は今名前の挙げられた者達の元へとすぐに式神を飛ばした。
夏の暑い午後。
夫が仕事に行って寂しいだろうと思っていたあかねの時間は、どうやら楽しい仲間達と共に過ごせることになるようだった。
管理人のひとりごと
平安の昔はこうして厄除けしていたそうです。
という知識は「平安時代儀式年中行事事典」より(’’)
いや、この資料便利です(爆)
頼久さん、二人きりにはしてもらえませんでしたが、夜は独り占めみたいです(w
夫婦なので、だいぶ頼久さんも余裕がでてきた感じが伝わると嬉しいです(^^)
あかねちゃんの人気者ぶりは相変わらずなので夫としては大変そうですね(’’)
プラウザを閉じてお戻りください