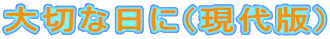
なんだかんだと騒いだ末に、結局、頼久の家であかねの誕生日パーティは開かれることになった。
集まったのは天真、蘭、詩紋といういつもの3人に、家主の頼久と主役のあかねの5人だ。
詩紋の手料理を堪能した一同はそのまま蘭が有名なケーキ屋で買ってきたというおいしいケーキをあかねのいれた紅茶で食べてほっと一息ついた。
朝からパーティの準備で盛り上がり、そのまま食事に突入して、頼久以外の4人はフル回転でここまできたのだ。
久々のイベントで盛り上がったのは言うまでもなく、昼食後のデザートにたどり着いてやっと落ち着いたのだった。
「あ、そうだ、あかねちゃん、はい、これ、プレゼント。」
「うわぁ、有難う。」
蘭から手渡された小さな包みを開けてみると中にはバラの香りの浴用剤が入っていた。
「夏ってなんとなく汗でベタベタするし、匂いも気になるじゃない?」
「そうだよねぇ。」
「バラの香りのお風呂に入れば頼久さんとくっついてても気にならないでしょ。」
「蘭!」
ぺろりと舌を出して見せるらんをあかねは顔を真っ赤にして睨みつけたが、頼久はというと苦笑しただけで紅茶を飲んでいる。
この手のからかいはいつものことなので、さすがの頼久も慣れてしまった。
「あかねちゃん、ボクからはこれ。」
「有難う!」
助け舟とばかりに詩紋がプレゼントを渡す。
蘭からのプレゼントよりは少し大きめだ。
早速それもあかねが開けてみると、中からかわいらしいエプロンが出てきた。
「うわぁ、かわいい、有難う詩紋君。」
「うん、あかねちゃん、最近お料理凄く頑張ってるから。」
小さな花の模様が可愛らしいエプロンはいかにもあかねに似合いそうで、詩紋も嬉しそうに微笑んだ。
「俺からはこれな。」
天真から渡されたのは封筒だ。
まさかラブレターではあるまいな?という頼久の鋭い視線を無視して、天真はあかねに封筒を押し付けた。
あかねがその封筒を開けてみると中に入っていたのは2枚のコンサートチケットだった。
「チケット?」
「おう、なんとかいうの行きたいって言ってたろ。」
「うわぁ、とってくれたんだ!有難う!」
「俺はその手の音楽はさっぱりだから頼久連れて行って来い。どうせ頼久はわかろうがわかるまいがお前と二人ならどんなコンサートでも読経でも喜んで行くだろ。」
「読経って…。」
あまりのたとえに苦笑しながらもあかねは喜んでプレゼントを受け取った。
そういうことかと安堵する頼久もあかねの手元を覗き込み、それがクラシックコンサートのチケットだと気付いて苦笑した。
確かに自分にはわからない音楽だが、あかねが誘ってくれれば喜んで行くだろう。
「これ、この前買ってきたCDの演奏してるチェリストなんです。たまたまコンサートをやるって聞いたから生で聞いてみたいなって思ってて…私もクラシックは詳しくないんですけど、この人のチェロだけはなんだか頼久さんの声みたいに聞こえて気持ちよくって…一緒に行ってもらえますか?」
「もちろんです。喜んでお供させて頂きます。」
「有難うございます。」
微笑み合う二人を見て残された3人は顔を見合わせて苦笑した。
「ま、頼久さんが断るわけないよね。」
「開演は夜7時ってなってるが、ま、頼久が一緒なら問題ないだろ。」
森村兄妹にそう言われてあかねは嬉しそうにうなずいた。
夜の外出にはうるさい両親も頼久が一緒となれば許可してくれること間違いない。
それくらい頼久はあかねの両親にも信用されているのだ。
そして、次は自分の番だとばかりに立ち上がろうとした頼久を天真が止めた。
訝しげに首を傾げる頼久。
「お前のは後にしとけ。俺達、今日は早めに引き上げるから。」
「何故だ?」
「何故って…せっかくあかねの誕生日だろうが、俺達も祝いたいから集まったが…。」
「別にお二人さんの邪魔をしたいわけじゃないのよ。」
「ということで、デザート食べて片付け終わったらボク達帰りますから、ごゆっくりどうぞ。」
「ちょっと!詩紋君まで!」
真っ赤になって抗議するあかねはだが、3人にはさらりと無視されて、頼久はそんな4人を苦笑しながら見守った。
何をたくらんでいるのか知らないが、この3人はいつだってあかねのことを、あるいは自分達二人のことを思ってやってくれているのだと頼久にはよくわかっているから。
「ほら、あかねちゃんが食べたがってたイチゴロールだよ。」
「うっ、あ、甘いものでごまかされたりなんかしないんだから……。」
最後の方は小さな声になりながら詩紋にすすめられたイチゴロールを受け取って、あかねはすぐに口元をほころばせた。
女性は甘いものに弱い。
これは頼久がこちらの世界へ来てから一番最初に詩紋と蘭と天真に教えられたことだ。
結局、あかねは甘いものでごまかされて、4人はいつものように楽しく笑いながらケーキを平らげた。
食事に使った食器をあかね、詩紋、蘭の3人が洗って、頼久と天真の二人が食器棚へと戻すとテーブルの上はすっかり綺麗に片付いた。
そしてまだ3時のお茶の時間にも遠いというのに天真、蘭、詩紋の3人はあかねが引き止めるのもきかずにさっさと帰ってしまった。
もちろん、あかねも頼久と二人きりでいられることが嬉しくないわけではないが、気心の知れた仲間といる時間も楽しいのだ。
「もう、3人ともそんなに急いで帰ることないのに…。」
3人を見送って台所で改めて紅茶をいれて、頼久と二人リビングのソファに落ち着くとあかねは少し拗ねたようにそう言ってうつむいた。
仲間を大切に思うあかねを愛しく想いながらも、なんだか二人気になったことが気に入らないようにも聞こえて複雑な心持の頼久は苦笑しながら一度奥の書斎に入った。
何事かとあかねが小首をかしげて待つこと数秒。
書斎から出てきた頼久は手に小さな箱を持っていた。
「私がこれをお渡しすることを知っていたので、皆、気を利かせたのでしょう。」
「はい?」
「神子殿、お誕生日、おめでとうございます。」
これ以上はないほどの優しい笑顔で差し出された小さな箱をあかねは目を丸くしながら受け取った。
頼久から何か誕生日のプレゼントがあるらしいことは食事の時の会話でわかっていたが、何を贈られるのか予想がつかなかった。
渡されたのがあまりに小さな箱でなおさらあかねは中身がわからずに小首を傾げる。
赤い包装紙で包まれたそれはかわいらしいピンクのリボンがかかっていた。
「開けてもいいですか?」
「どうぞ。」
そう答えながら頼久はすっとあかねの隣に座る。
箱を開けて中を見た時のあかねの表情を近くで見たかったから。
器用にリボンを外して包み紙も破らないように慎重に解いたあかねは、小さな箱の中から更に箱が出てきたのを見て目を丸くすると隣に座っている恋人を見上げた。
出てきたのは間違いなく指輪の入った箱だった。
嬉しさと驚きとが一緒になって目を大きく見開いたあかねに頼久はゆっくりうなずいて見せた。
あかねが再び箱へと視線を戻してゆっくり蓋を開けると、中には可愛らしい、小さなルビーのついた銀の指輪が入っていた。
ピンクではなくて深い赤のルビーはなんだか少し大人っぽく見える。
あかねはそれを箱から出すと、少し悩んでから左手の薬指にはめてみた。
ところが、どうやらサイズが合わないらしくて、かなり大きい。
石のついた指輪のサイズが大きいと目もあてられないことになる。
くるくると回るものだから石が綺麗に見える場所にとどまってくれないのだ。
あかねがどうしたものかと悩んでいると、頼久の大きな手があかねの左手薬指から優しく指輪を抜き取って、それを中指にはめた。
サイズはピッタリ。
せっかく恋人から贈られた指輪だから左手の薬指にはめたかったのに、何故かサイズは中指に合わせてあるらしい。
あかねは少しだけ悲しそうな顔で再び隣の恋人を見上げた。
「今のうちはこちらの指にしていて下さい。」
「でも……せっかく頼久さんにもらった指輪…やっぱり左手の薬指にしたいです……。」
サイズ、つめてもらってこようかな?とまであかねが考えたその時、指輪をはめた左手を頼久が大きな両手で包み込んだ。
「その指はとっておいて頂きたいのです。これはお誕生日の記念ですので。神子殿の誕生石はルビーと聞きましたのでその石にしてみました。薬指にする指輪はまた別の機会に改めて贈らせて頂きますから。」
「あぁ、そういうことですか…って、へ?」
薬指の指輪はまた別の機会に改めて?と心の中でもう一度その言葉をつぶやいて、恋人を見上げていたあかねは顔を真っ赤にして急にうつむいた。
すると視界に入ってきたのはたった今恥ずかしいことを言ってくれた恋人の両手に包まれている自分の左手で…
あかねは更に首まで真っ赤にしてうつむいたまま顔を上げられなくなってしまった。
左手の薬指にする指輪を改めて贈られるということは、おそらくそれはたぶんプロポーズということで…
それはつまり結婚を前提としている話であって…
それを違う機会に改めて贈ると約束してくれたということは、もう結婚は約束しているようなもので…
と、あかねが一人頭の中でぐるぐると考えてどんどん顔の赤みを深くしていると、頼久は両手で包み込んでいたあかねの左手をそっと持ち上げて、その指輪をしている手にそっと口づけた。
「よよよよっ、頼久さんっ!」
「サイズが…。」
「はい?」
「神子殿の指輪のサイズがわからないという話を天真にしたのですが、すると妹御とサイズが同じだということがわかったらしく、この指輪を選ぶのを手伝ってもらったのです。ですから、彼らは私が神子殿に指輪を贈ることを知っていまして。」
「はぁ…。」
「それで、おそらく気をまわして早々に帰ったのかと。」
頼久みたいな大人が恋人に指輪を贈る。
その行為の意味をあの3人が深読みしたとしてもそれはしかたのないことだろう。
かく言うあかねも左手の薬指にはめたいと思ってしまったのだから。
「そ、そっか、3人とも…。」
「はい、私が求婚するとでも思ったのでしょう。」
そう言って苦笑して頼久はあかねの左手をやっと解放した。
少しだけ名残惜しそうに。
「神子殿は…この指輪が薬指のサイズの方がよかたっと思って下さったのですか?」
「は、はいぃ?」
それはもちろんそうなのだが、もし「はい」と答えてしまったら、それはプロポーズされたかったということになってしまう。
そう思うと「はい」とは答えられなくて、あかねの返事はなんだかおかしなものになってしまった。
そして、慌てふためくあかねを見つめる頼久はというと、その顔にやわらかな微笑を浮かべて隣で真っ赤になっている恋人を見つめていた。
「私の気持ちが変わることはありませんので。」
「はい?」
「まだ神子殿はお若いですから、高校生活も大学生活も楽しんで頂きたいのです。いずれ、神子殿が成人された時に、また改めて求婚はさせて頂きますので、それまでは私のことはあまりお気になさらずに、普通の同年代の仲間と同じように生活なさって下さい。」
「頼久さん…。」
「…あと数年のことですので…私は今と同じく神子殿をお慕いしながら待ちます。もし、その数年で神子殿のお気持ちが変わるようなことがあろうとも、私の気持ちが変わることはありませんので。」
少しだけ寂しそうに微笑む頼久にあかねは泣きそうなようで怒ったような複雑な表情を見せた。
「頼久さんがそういうこと言うから…左手の薬指にしたいなって思っちゃうんです…。」
「は?」
「私の方が全然子供で、落ち着かないように見えるだろうし、だから頼久さんは私の気持ちが変わってもとかそういうこと言うんでしょうけど、私だって気持ちが変わったりしません。そう信じてほしいから、証を頼久さんに見ててもらいたいなって思っちゃうんです…。」
「神子殿…。」
思いもかけないあかねの言葉に驚いて、そしてその言葉が嬉しくて、頼久の顔には驚きの次に幸せそうな笑みが浮かんだ。
「有難うございます、私のような者にはもったいないお言葉です。」
「またそういうこと言う…もう頼久さんは私の従者でもなんでもなくて、恋人なんですからね?」
「はい、承知しております。」
かすれるような低い声でそう言った頼久はあかねの顎を持ち上げて、軽く口づけた。
「はぅぅ。」
テレてうつむいてしまったあかねの肩を抱いて、頼久は幸せに満ちた笑みを浮かべる。
「神子殿が成人なさるその日に、必ず薬指に合う指輪を贈らせて頂きます、お約束します。」
「…はい……。」
肩を抱き寄せられて、あかねは頼久の胸に頭をもたげて目を閉じた。
何よりも自分のことを一番に考えてくれる恋人の腕の中は温かくてとても安心で。
できることならいつまでもこうしていたい。
そう思ってしまうのだった。
後日、天真、蘭、詩紋の3人に頼久からのプロポーズの言葉はどんなだったのか?と聞かれて、あかねは真っ赤な顔で否定するはめになった。
蘭などは頼久さんのいくじなしとまで言ったのだが、天真は苦笑しただけだった。
真の友は相棒の想いを理解しているらしい。
そしてあかねはというと、それから毎日、アクセサリー禁止の学校へも指輪をペンダントのようにチェーンをつけて制服の下に肌身離さず身につけるようになった。
管理人のひとりごと
というわけで(笑)神子お誕生日もの現代版でした。
現代版で頼久さんがプレゼントするものといったら絶対コレ!と決めてかかったわけですが、よく考えたら婚約指輪も贈るじゃん(爆)
ということでその辺にこだわって書いてみました。
それとこれとは別ってことです(笑)
プロポーズもそのうち書けたらいいなぁ(^^)
プラウザを閉じてお戻りください