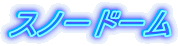
「だーかーらーよ、別にお前が気持ちをこめて贈るならあかねはなんだって喜ぶってーの。」
「それは、わかっているのだ。神子殿はお心優しきお方、どのような物でも嬉しいと言って下さるだろう。それがたとえ、欠片ほども神子殿がほしいと思っておいでではないものだったとしてもだ。」
そりゃそうだろう、と、天真は心の中で溜め息をつく。
あかねならどんな物だろうと頼久がプレゼントしてくれたものなら喜ぶに決まっている。
物じゃなくたっていいはずだ。
二人きりで楽しく過ごす時間を作ってもらえればそれだけで幸せだというだろう。
ということがわかっているだけに、天真は目の前で苦悩している頼久に溜め息をつくしかできなかった。
ところが…
「神子殿がそのようにお心広いお方だとわかっていればこそ、本心から喜んで頂けるものを贈りたいのだ。」
「そうかよ…。」
天真は再び深い溜め息をついた。
目の前にはいい年をして恋人のためのプレゼントを選ぶというだけで眉間にシワを寄せている男が一人。
そして二人の間のテーブルの上には雑誌だのカタログだのの山がある。
どうして天真がこんな状況に陥っているのかといえば…
事は珍しく頼久の方から天真を呼び出したことに始まる。
いつも酒を飲む相手ばかりさせているからと、呼び出しにも快く応じた天真は迎えに出てきた頼久の顔を見て一瞬で呼び出しに応じたことを後悔した。
頼久の顔には今まさに敵を切ろうとしているかのような殺気立った真剣な表情が浮かんでいたからだ。
もちろん、この平成の時代に頼久が人を切る必要があるわけもなく…
ということは人を切るか切らないかという瞬間と同じくらい真剣に何かを悩んでいるということになる。
源頼久という男は普段は実直で硬派で、天真にとっては良い友人だといっていい男だ。
ところが、こんなふうに真剣に悩み始めた頼久は天真にとっては厄介な存在以外の何者でもなくなってしまうのだった。
「神子殿は一年の行事の中でもクリスマスをことのほか楽しみにしておいでなのだ。来年は早々に受験も控えていることでもある。何か神子殿に気を晴らして頂けるような良い贈り物を選びたい。」
「気持ちはわかる。わかるがだ、俺にきかれてもなぁ。」
「お前は神子殿と同じく高校へ通っている分、私よりは神子殿の好みを心得ているだろう。」
「いねーよ。」
天真は再び深い溜め息をついた。
神子殿のお好みの塊自身に言われたくはないというのが本心だ。
「ま、蘭なら何かわかるかもしれない、か。」
天真としてはこのまま頼久を放置しておきたいところではあるのだが、それではあまりにもかわいそうになってきたので、ここは女同士仲のいい妹に助っ人を頼むことにした。
といってもこの場に呼んでしまうと色々と面倒なことになることは間違いないので、天真は携帯でピコピコとメールをうつとそれをすぐに送信した。
友人とよくメールのやり取りをしている蘭はメールの返信が早い。
これでそう時を待たずして何か参考になる意見をメールで送ってくるはずだった。
「天真?」
「ああ、今、蘭にあかねが欲しそうなものに心当たりないかメールで聞いてみた。10分くらいで返事来るだろ。」
「そうか、手数をかけてすまぬ。」
「まぁ、お前にはちょこちょこ世話になってるしな。しっかし、なんだってまた今年のクリスマスにかぎってそんな悩んでんだよ。適当にレストランで食事とか、指輪でも贈っとくとか、なんならここで二人っきりでべったべたのイブでもいいだろうよ。」
「外で食事は今までにも何度かしている。指輪も以前に贈ったことがあるのだ。次に贈る時には特別な指輪をとお約束してある。」
「そうかよ…。」
特別な指輪、ああ、ハイハイ婚約指輪ってやつな。
と、天真は一人心の中で悪態をつきながら頼久を上目遣いににらみつけた。
このまま惚気を聞かされたのではたまらない。
「今年は受験生ということで神子殿はそれは必死に努力なさっておいでだ。そのように努力しておいでの神子殿に少しでも心安くなるようなものをお贈りしたいのだ。いつまでも側に置いておけるようなものを。」
「まぁ、確かにあかねは頑張ってるな。絶対一年で一番近場の大学に合格するんだってかなり気合入ってるしな。」
「そうなのだ。ここで私が労って差し上げるのはもちろんだが、まだ受験までは間がある。その間、神子殿はお一人でこれからも努力なさることだろう。そんな神子殿のために私にできることをしたい。」
それがあかねが喜ぶクリスマスプレゼントを贈ることというわけだ。
天真は苦笑しながらソファにもたれた。
頼久の神子殿バカは今に始まったことではないが、最近になって加速したような気がする。
それでも、こうして頼久が努力してやればあかねは幸せになるのだろうから、その手伝いくらいはしてもいいかもしれない。
天真が一人心の中でそう思っていると、テーブルの上に置いておいた携帯が鳴った。
「うぉっ、もう来たか。」
天真が慌てて携帯を手に取ると、表示されていたのは案の定、蘭からのメールの着信だった。
すぐに天真がメールを開くと、そこには女子高生らしい絵文字いっぱいの文章があった。
最近ではすっかり慣れた妹からの派手なメールに一気に目を通して、天真は何度かうなずいた。
「なるほどな、さすがに女同士だとよくわかってるみたいだ。」
「何がいいかわかったのか?」
「おう、つまり、綺麗でかわいくておしゃれな小物がいいらしい。」
「……。」
綺麗でかわいくておしゃれ、しかも小物。
それは頼久にとって想像できないどころか未知の世界の未知の領域そのものだ。
「安心しろ、それだけじゃわかんねーだろうからって蘭からここで選べっていくつか店の紹介もついてきた。」
「店…。」
「はぁ、わかった、これから俺も一緒に行ってやるよ。」
綺麗でかわいくておしゃれな小物を置いている店を想像しただけで凍りついた頼久に、天真は深い溜め息をついた。
このまま放っておくとなんだかとんでもないことになりかねない気がする。
一方頼久はというと、天真の申し出にほっと安堵の溜め息をついていた。
「すまん、迷惑をかけるが頼む。」
「ま、俺の方が蘭につき合わされてる分、免疫あるだろうしな。行こうぜ。」
「うむ。」
こうして二人は思い立ったが吉日とばかりに連れ立って家を出た。
天真は隣に並んでやたらと気合の入っている頼久の背を眺めながら深い溜め息をついた。
今までに回った店は4件、ここが5件目だ。
そして蘭から紹介された最後の店でもある。
これまで頼久はあれでもないこれでもないと、周囲に大勢いる女性達に奇異の目を向けられながら真剣にあかねへのプレゼントを選んできた。
だが、どれもこれも今ひとつ気に入らないと頼久が渋い顔をするのでとうとう最後の店まで回りつくしたというわけだ。
ここで決まらないとなると大問題だ。
もうすっかり日が暮れてしまったから、家に帰ってまた蘭に相談しなくちゃならないだろう。
そんなことを一人考えている天真のことなど眼中にないといった様子で、頼久は真剣に品物の並ぶ棚を見回していた。
さすがに店内にはあまり人の気配はなくて、ゆっくり選ぶことができそうだ。
そうはいっても、これまで回ってきた店と品揃えが極端に違うのかといえばそうでもない。
天真はピンクや水色やハート型など、女の子が好きそうな色と柄のオンパレードに苦笑した。
この店でどれだけ自分が浮いているのかはよくわかっているつもりだが、それ以上に浮いてる男が真剣なのだからこれはもう最後まで付き合うしかない。
「頼久、なんか見つかったか?」
「神子殿は派手な色のものは好まれぬし、あまり幼すぎるものもお嫌いなのだ。」
それはお前につりあうように背伸びしてるからだろうとは言えずに、天真は苦笑しながらうなずいた。
頼久の顔はいたって真剣だ。
「しかし、あまり地味なものもせっかく愛らしい神子殿にお贈りするものとしてはふさわしくないような気がするのだ。」
「まぁ、そうだろうな。」
一応納得して見せながらも天真は溜め息をつくのをやめられない。
頼久の言うこともわかるのだが、このままだと本当にプレゼントを決めることは不可能だ。
そんな時は店員にでも相談にのってもらえばいいのだろうが、今の頼久にそんな余裕はない。
だいたい、あまりに頼久が真剣に殺気立った様子で選んでいるものだから、店員の方が恐れをなして遠巻きに眺めている状態だ。
天真はこれはもうだめかと半ばあきらめながら棚に並んでいる小物の群れを何とはなしに眺めていた。
「天真。」
「ん?」
「神子殿は雪は好きか?」
「雪が好きかって…そりゃまぁ、ホワイトクリスマスは綺麗だとか話してはいたが…好きかって聞かれるとな…。」
「神子殿は穏やかで美しいものがお好きなのだ。」
「わかってるなら俺に聞くなよ。」
あきれながら天真が頼久の方を振り返ると、そこには満面の笑みを浮かべている頼久が立っていた。
「これにしようかと思う。」
「あー、いいかもな、残るものだし、持って帰るのもそんなに大変じゃねーし。あかね、好きそうだしな。」
「そう思うか?」
「おう。」
「そうか、ではこれに決めよう。」
頼久はようやく手にした愛らしいスノードームを手にレジへと向かった。
派手ではなく、かわいらしく、穏やかに美しいもの。
スノードームは他の店にもあったが、この店にあったのはにシンプルなデザインで、ガラスの球体の中で本当に白い雪が深々と降るように見えていかにもあかねが好みそうだった。
見るからに浮かれている頼久の背を眺めながら、天真の顔にも微笑が浮かぶ。
これでどうやら頼久と二人きりの買い物から解放してもらえそうだ。
それに、たぶんあかねはこのクリスマス、きっと幸せな顔で過ごすことができるだろう。
そう思えば、天真もほっと一安心とばかりに笑みをこぼすのだった。
「お邪魔します。」
12月24日、つまりクリスマスイブ。
あかねはいつものように頼久の家を訪れた。
ただし、その顔色はあまりかんばしくない。
頼久はそんなあかねを迎え入れながら、楽しみにしていたはずのクリスマスだというのにどうしてあかねの顔色が優れないのかが気になってしかたがなかった。
リビングにあるソファに座ってあかねが小さく溜め息をつくのを横目で追いながら、頼久は手早く紅茶を入れてあかねの前にティーカップを置くと、あかねとはテーブルを挟んで向かい側に腰を落ち着けた。
夕食の用意はもうできているし、プレゼントも準備万端だ。
ただ、あかねの様子だけがおかしくて…
「神子殿、その…どうかなさいましたか?」
「はい?」
「いえ、先ほどから様子が…。」
「ああ……その…今年はとても忙しくて…冬期講習とか…それで……クリスマスプレゼントを手作りしようと思ってたんですけど、時間がなくて…。」
「そのようなこと、お気になさらず。」
「でも、今年はケーキも焼けなかったし、お料理だって頼久さんに全部任せちゃったのに…。」
「今年は特別ですからお気になさらず。受験が終わればなんでも神子殿の思い通りにできましょうから。」
「……でも…頼久さんには迷惑ばっかりかけてるし、クリスマスくらい喜ばせたかったのに…。」
「喜んでおりますが?」
間髪入れずにそう断言されて、あかねがハッと視線を上げれば、そこには満面の笑みを浮かべた頼久の顔があった。
「私はこうして神子殿のお側に置いて頂けるだけで嬉しく思っております。」
「そ、それはいつものことだし…。」
顔を赤くしてもごもごと言い淀むあかねの愛らしさに更に笑みを深くした頼久は、どうやら機嫌を直してくれたらしいあかねに渡すべく、小さな箱を取り出した。
「夕食の前ですが先にお渡ししておきます。どうぞ。」
「あ、有難うございます!」
あかねはぱっと明るい表情を浮かべて頼久から小さな箱を受け取った。
かわいらしいピンクの包み紙に綺麗な赤いリボンがかかっている。
どこからどう見ても女の子!という包装に、思わずあかねは包みと頼久の顔を見比べてしまった。
こんなふうに愛らしい包装のものを目の前の恋人が選んで買ってきたのかと思うとなんだかとても似合わない。
「開けてもいいですか?」
「どうぞ。」
一応ことわってからあかねは丁寧に包みを解いた。
すると中から出てきたのは小さな小屋と愛らしいトナカイ、そしてサンタが入っているスノードームだった。
「うわぁ、かわいい!」
軽く振ってみれば粉雪がドームの中に舞って、まるで本物の雪が降っているみたいに見える。
「気に入って頂けましたか?」
「はい!とっても!」
心の底から嬉しそうなあかねの返事に頼久もほっと安堵の溜め息をついた。
「でも、こんなかわいらしいもの、頼久さん、わざわざ選びに出かけてくれたんですよね…。」
「それについては天真にも協力してもらいました。私一人では手に余りましたので。」
苦笑しながら正直に告白すれば、あかねはクスッと笑みをこぼした。
頼久と天真、男らしい男二人が女性達に囲まれてスノードームを選んでいるところを想像したのだろう。
そう思えば頼久も気恥ずかしくて、照れ隠しに頭をかいた。
「頼久さんが一生懸命選んでくれたプレゼント、とっても嬉しいです。あ、そうだ、私からも。」
あかねはそういうとカバンの中から小さな箱を取り出して頼久に渡した。
それは手の平に乗るほどの小さな箱で、頼久は中身が予想できずに小首を傾げた。
「その…本当は手編みのセーターとか考えてたんですけど作ってる暇がなくて…それで、その…頼久さんは嫌かもしれないんですけど…。」
「開けても宜しいですか?」
「はい…。」
あかねから贈られる物で気に入らないものなどあるはずがないと思いながら、頼久はシンプルな包装のその小さな包みを開けた。
すると中から出てきたのはあかねにしては珍しく、シルバーでできているペンダントらしきものだった。
頼久がこの手のものを身につけないことを知っているだけに、さすがの頼久もこの贈り物には目を丸くしてしまった。
「使わないですよね…やっぱり…。」
「いえ、そういうわけではありませんが…。」
「えっとですね、実は…その…これ…。」
そういいながらあかねはセーターの下から自分の首にかけているペンダントを取り出して見せた。
それは今頼久が手にしているものと似たような形をしていて、なるほどペアになっているのかと頼久が納得しそうになったその時、あかねが頼久の隣へとその身を移した。
「私がしてる半分と、頼久さんのをこうして合わせると…。」
「これは…。」
隣に座ったあかねが頼久の手の上にあったペンダントと自分のペンダントを合わせると、それは綺麗な丸い形になって、どうやら満月を表しているように見えた。
二つあわせるとこうなるのかと頼久が妙に感心していると、あかねがペンダントをセーターの下へ戻してうつむいた。
「頼久さんはおそろいとか嫌かなって思ったんですけど…まだしばらく会えない日もたくさんありそうだし…こういうの欲しいなって思って…。」
頼久はしゅんとしているあかねの手から自分に贈られたペンダントを取り上げると、それを器用に自分の首にかけた。
剣の達人がペンダントなんておかしいだろうかと予想していたあかねだったけれど、シルバーでできているシンプルなそれは頼久によく似合って、思わず見とれてしまった。
「おかしくはありませんか?」
「全然!凄く似合ってます!」
「では、肌身離さずこうしておきます。」
「でも…。」
「神子殿もこれを首にかけておいでなのだと思えば、幸福なことこの上ない贈り物です。」
「頼久さん…。」
「大切に致します。」
「そ、そんなに大切にしなくてもいいんです。そんなに高価なものでもないし…。」
「いえ、神子殿から頂いたもの、しかも神子殿とそろいの物とあれば私にとっては何よりの宝ですので。」
相変わらずさらりとそう言って微笑む頼久にあかねは顔を真っ赤にした。
ついさっきまではこのプレゼントのことで落ち込んでいたというのに、今ではもう幸せな気持ちでいっぱいで…
この人の側にいるとどんな時だって必ず幸せになれると実感して、あかねはその赤い顔に幸せいっぱいの笑みを浮かべた。
「私も頼久さんからのプレゼント、大切にします。机の上に飾って、いつも頼久さんのことを思い出しながら見てますから。」
「はい。」
幸せいっぱいであかねが笑顔を浮かべていると、こちらも幸せな笑みを浮かべた頼久の顔が近づいて、優しく口づけを贈られた。
これが本当は一番のプレゼントかもしれない。
そんなことをあかねが思いながら赤い顔を更に赤くしていると、頼久はすたっと立ち上がり、腕まくりをしてキッチンへと向かった。
「頼久さん?」
「夕飯を召し上がって頂かなくては。すぐにできますので神子殿はそこでお待ちください。」
「て、手伝います!」
張り切る頼久の隣に慌てて駆けつけて、あかねも腕まくりをすると二人はニコリと笑みを交わした。
そして…
あかねが楽しみにしていたクリスマスの夜は、二人だけで過ごす静かで優しい夜になった。
管理人のひとりごと
頼久さんが女の子の大好きな小物を選ぶ店に入ったら…を想像した結果です(’’)(マテ
絶対注目されるんだろうなと。
で、そんな店、頼久さんが知ってるわけないので天真君が犠牲になります!
しかたないよね、真の友だし(’’)(コラ
ちなみに管理人は、頼久さんはあかねちゃんとおそろいなら花冠でもなんでも身につけちゃうと思います(’’)(オイ
ブラウザを閉じてお戻り下さい