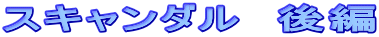
「ここって、伝説の木の下なんです。」
「伝説、ですか?」
コクコクとうなずくあかね。
「その…この木の下で告白すると想いが通じるって…この学校にある伝説なんです。」
「はぁ…告白、ですか。」
「そ、そうです。」
さて、この恋人は自分に何を告白するつもりなのかと頼久が首をかしげて考え込んでいるうちに、あかねは頼久の腕を離して正面に立つと、何やら意を決したように頼久をきりりと見つめた。
「頼久さん。」
「はい?」
「大好きです!これからもずっと一緒にいて下さいっ!」
キョトン。
何が起こったのか理解できずに目を大きく見開いて驚く頼久。
対するあかねは胸の辺りでまるで祈りでも捧げるかのように手を組み合わせて強く握っている。
あかねにしてみれば、京で想いを打ち明けてくれたのは頼久の方で、もちろん、男性と交際するのはこれが初めてなのだから自分から告白ということをしたことがない。
頼久からの告白が嬉しくはあったが、それに「はい」とだけ答えた自分が少し物足りなくもあった。
一生に一度くらい本気の告白をしてみたかったが、では誰にするかというと頼久しか相手はいないわけで。
もうすっかり恋人同士なのに告白なんておかしいかな?と思っても他の人に告白するなんて考えられないのだからしかたがない。
どうせするなら伝説の木の下でと頼久を連れてきて思い切って告白してみたのだが、どうやら頼久は面食らったらしくていつまでたっても返事が返ってこなかった。
いくら待っても答えが返ってこなくて、あかねが不安になったその時、頼久の顔にこれ以上はないというほどの幸せそうな笑みが浮かんだ。
「私も、心からお慕いしております。」
そう言いながら頼久はすっとあかねの小さな体を抱きしめる。
腕の中であかねは顔どころか耳まで真っ赤にして、それでもそのまま頼久に抱かれて目を閉じた。
力強い腕に抱きしめられて、伝説の木の下での告白は確かに想いが通じて嬉しくて、本当に幸せだと実感する。
しばらくそうしてあかねを抱きしめていた頼久は、元武士の鋭い感覚が人の気配を感じとったところであかねを解放した。
「頼久さん?」
「誰か来たようですので。」
「あ、ああ、文化祭ですからね、告白ラッシュかも。」
「は?」
「伝説の木の下で告白はみんな狙いますから。文化祭と修学旅行は告白ラッシュが起こることで有名なんです。」
「はぁ…。」
「お邪魔しちゃいけないから。」
そう言ってあかねは再び頼久の腕を抱いて歩き出す。
頼久はこの現役高校生達の行動がなかなか理解できず、目を白黒させながらあかねについて歩いた。
今まであまり深刻に考えたことはなかったが、こうしてあかねの学校を訪れて大勢のあかねと同じ世代の生徒達に囲まれてみると、やはり自分はあかねとずいぶんと年が離れているのだと自覚してしまう。
もちろん、元は武士という生い立ちもそこそこはあかねとの常識の距離を離しているかもしれないが、そこはこの世界で育った記憶を持っているのだから、やはりよくわからない話というのは世代の差のせいに違いなかった。
そう考えると、なんだかこうして人込みの中にあかねと二人でいるのが不釣合いな気さえしてきて、頼久の顔から笑みが消えた。
「うちのクラスに戻って少し休みましょう。たくさん歩いて疲れちゃった。」
「はい。」
念願の本気の告白ができて上機嫌のあかねは頼久の表情が翳ったことに気付かない。
その歩みは軽やかで、頼久はただ黙ってその後についていった。
周りには制服を着ている生徒、仮装している生徒、とにかく高校生ばかりがいる。
それも高校の文化祭なのだから当然のことだが、今の頼久にはやけに気になった。
同じ男性でも、こうも年が離れているとひどく子供っぽく無邪気で純粋に見えるものだ。
あかねの年頃ならばこういう男子生徒と付き合う可能性が一番高いのだろう。
そう思えば思うほど、自分はあかねにつりあっていないような気がしてくるというのに、校内へ入ると人の数は増して周囲の生徒達の視線をやたらとあびているのがわかって頼久を更に憂鬱にされた。
あかねがこんな年上の自分の腕を抱いて歩いているのがよほど珍しく見えるのだろう。
そう思って頼久が溜め息をついているうちに、最初に訪ねたあかねの教室へ戻ってきた。
あかねにいざなわれて奥の方の一番落ち着きそうな席についた頼久は、幸せそうな顔で隣に座るあかねに見つめられてなんとか微笑を浮かべた。
少し引きつっていたかもしれない。
自分でもそう思ったが一度暗く淀み始めた心の内は簡単にコントロールできなくて。
そんな頼久の異変に気付いたのかあかねが小首を傾げて何か言おうとしたその時、二人の前の席に天真と蘭が座った。
「どうだったよ、あかね。」
「ど、どうって…。」
「そりゃもちろんOKだったに決まってるじゃない。お兄ちゃんもそんな無駄な質問しないの。」
「それもそうか。」
「二人ともっ!」
顔を真っ赤にしてあかねが抗議しているところを見るとどうやらさきほどのあかねの愛の告白のことをこの二人は知っていたらしい。
「もう、今年の文化祭はあかねちゃんにとっては忘れられないものになるねぇ。何気に頼久さんとクレープ食べて間接キスして何気に頼久さんと腕組んで歩いて、何気に頼久さんに告白してOKもらって、だもんねぇ。」
「蘭!」
あのクレープにはそんな意味があったのか。
言って下されば口づけくらいいくらでも直接して差し上げるものを。
などと頼久が思っている間に天真が苦笑を浮かべて溜め息をついた。
「これで恋する乙女の目的は全て達成されたわけな。」
「そうそう、そういうこと。お兄ちゃんも彼女作ったらちゃんとこういうのに付き合ってあげるように。」
「俺は頼久みたいに女に入れ込んだりしねーから、お断りだ。」
「だからお兄ちゃんモテないのよ。」
「お前なぁ…。」
森村兄妹喧嘩勃発危機一髪のところで「まあまあ」といつものようにあかねが間に割って入った。
今日のあかねはどうやら全てが計画通りにいったらしくて上機嫌だ。
だが、頼久の方はというと、あかねが幸せそうにしているのはもちろん嬉しいのだが、校舎へ入ってからずっと自分に集中している視線が気になってしかたがなかった。
最初に天真と合流した時からやたらと自分に視線が集まることには気づいていたが、さきほどからその視線の数がやたらと多くなっているような気がする。
頼久が訝しげな顔をしながら辺りを見回すと、天真がすぐそんな頼久のそぶりに気付いた。
「頼久、あんま、キョロキョロすんな。ってか殺気を放つな。」
「ん?」
「別に、あいつらみんなお前の命狙ってるわけじゃねーから。」
「そうそう。頼久さんを狙ってるっていうか、あかねちゃん狙ってるだけだから。」
「蘭!」
慌てるあかねにぺろりと小さく下を出して見せる蘭。
頼久はなんの話かわからずにまたキョトンとするばかりだ。
「あぁ、やっぱ頼久さんはわかってないか。」
「そりゃお前、その手の話にはめっぽう疎いだろ、こいつは。」
「だよねぇ。」
「天真、なんの話だ?」
どうやら自分の文化祭訪問はただ単にあかねのウェイトレス&天女姿を眺めるためだけに企画されたものではないらしいことに気付いた頼久は、いつものように眉間にシワを寄せて天真を睨みつけた。
「ああ、頼久さん、さすがにお兄ちゃんかわいそうだからそんな目で睨まないであげて。あのね、あかねちゃんって実はけっこう人気なの。」
「は?」
蘭の説明に頼久は思わず間抜けな声をあげてしまった。
急に話が飛んで、何がなんだかわからない。
「蘭!そんな説明しなくていいから!」
「いや、あかねちゃん、さすがにここまで大注目されたら頼久さんには説明してあげなきゃかわいそうだって。頼久さんてば視線とか殺気とかそういうものには人一倍敏感だし。」
「そ、それはまぁそうだけど…。」
「でね、頼久さん、あかねちゃんはとっても人気者で、それはもうたくさんの男子に狙われてるのね。告白されることもここ半年で二桁に及びます。」
「……。」
「もちろんあかねちゃんは恋人がいるからってきちんと断ってるんだけど、その恋人が校内の生徒じゃないもんだからみんななかなか信じてくれなくて、告白ラッシュは続いてるのね。」
「……。」
「ただ、夏休み直前に風邪で倒れたあかねちゃんをお姫様抱っこで運んでいった男の人がいるって噂だけが一人歩きしてて、あかねちゃんはこのままだとその噂の男の人のことで猛烈に追及されかねない状態なのでした。」
「……。」
「そこで、もうこの際だから全校生徒お祭り騒ぎの文化祭であかねちゃんの噂の彼氏はこの人ですって公表しちゃおうって私とお兄ちゃんがあかねちゃんに勧めたの。ところが、あかねちゃんが頼久さんを呼ぶって話をしたらそれはもう一目見てみたいって男子生徒がわんさと現れて、こんな感じに遠目から頼久さんを観察するやつが増殖したってわけ。」
「ごめんなさい。こんな大騒ぎになるとは思わなくて…。」
本当に申し訳なさそうにあかねがうつむいて、やっとそういうことかと納得して落ち着いた頼久は再び慌てることになってしまった。
あかねがどうやら同世代の男の目をひいているらしいというのは頼久にとってあまり嬉しくない事態だが、そんな男達を牽制するために自分を紹介しようとしてくれていたことは嬉しかったわけで…
決して迷惑などではなかったとあかねに伝えなくてはと頼久が慌てて口を開こうとしたその時、4人の座るテーブルへと男子生徒が一人駆け寄ってきた。
「森村!喧嘩だ喧嘩!」
「あーあ、楽してバイト料稼げると思ったのによ。」
事情が全て飲み込めているらしい天真は溜め息をつきながら立ち上がり、ちらりと頼久の方を見た。
その様子に気付いて頼久が小首をかしげる。
「なんだ?」
「お兄ちゃん、まさか…。」
どうやら兄の企みに気付いたらしい蘭が上目遣いに天真を睨みつける。
「文化祭中に騒動が起きたらおさめてやるかわりに校内の売店での飲食無料にしろって生徒会と掛け合ったのって…ひょっとして……。」
蘭の視線にニヤリと笑って答えた天真はくいっと顎で頼久を呼んだ。
「手伝え、頼久。」
「ん?何をだ。」
「喧嘩はお前の得意分野だろうが。」
「…喧嘩が得意なわけではないぞ…。」
「斬り合いも喧嘩も似たようなもんだろ。とにかく、騒ぎが広がらないうちに止めちまうぞ。」
やる気満々で指を鳴らす天真が窓から外へ飛び出すと、頼久も深い溜め息をついてから立ち上がった。
報告にきた男子生徒も天真と共に窓から外に出ていて、このままではどうにも頼久も手伝わないわけにはいかない雰囲気だ。
「よ、頼久さん!」
「天真と二人ですから、すぐに片付けて参ります。危ないですから、み……あかねはここで待っていて下さい。」
「はい…でも………って、え?!」
頼久の身が心配で、それでも天真一人で行かせるのも心配でと一人困り果てたあかねは、ふと頼久に初めて名前で呼ばれた事に気付いて思わず声をあげていた。
頼久の方はというと一瞬「神子殿」と呼ぼうとしてはっと思い出して、なんとかあかねを名前で呼べたのでほっとした顔で窓から外へ飛び出した。
そこにはニヤニヤと笑っている天真の姿が。
「どこだ、騒ぎは。」
「上出来。」
「な、何がだ。」
「これからは人前では全部あかねで統一な。」
「なっ。」
「森村!こっちだ!」
「おう、そんな急かすな。行くぞ、頼久、背中、任せたからな。」
そういうが早いか、顔を赤くしている頼久を置いて天真が走り出す。
目指すは天真を呼びに来た生徒が指差している人込みの中だ。
人込みを掻き分けて二人が様子をうかがうと、喧嘩をしているのは二人だけでどうやら大事にはなっていないらしい。
天真と頼久は顔を見合わせて一つうなずくと、二手に分かれて喧嘩中の二人をあっという間に背後から羽交い絞めにして身動きできなくしてしまった。
「お前らなぁ、文化祭くらい楽しめって。」
そういう天真の言葉を聞かず、なおも暴れだそうとする男子生徒にあっという間に天真はキレた。
頼久が止めるのも聞かずに羽交い絞めにしていた男を同じくもう一人を羽交い絞めにしている頼久の方へと突き飛ばす。
解放されたのをいいことに自由になった男子生徒が頼久が羽交い絞めにしている生徒めがけて殴りかかってきた。
羽交い絞めにされている方は身動きできないのだからたまったものではない。
だが、頼久はあきれたような溜め息をついて羽交い絞めにしている生徒をそのままに、くるりと体をひねると拳を振り上げて襲ってくる生徒にさっと足払いをかけた。
頼久がやったのは自分の足で相手の足を払うことだけ。
それなのに襲ってきた生徒は地面にもんどりうってうずくまった。
勢いあまって勝手に地面と仲良くなったのだが、周囲からすると流れるような頼久がまるで魔法でも使ったかのように見えたらしく、周囲を取り巻いていたギャラリーから拍手が起こった。
「さっすが。」
「天真…。」
「怒るなって。これでお前がどんだけ腕っ節強いかこいつらにわかったわけだし。あ、そいつ離してやれよ、今ので震えてるぞ。」
天真に言われてようやく気付いて頼久は羽交い絞めにしていた生徒を解放した。
「お前も、くだらねーことでもう喧嘩なんかすんなよ。」
天真の声を背に受けながら、頼久に解放された生徒は何も言わずに駆け去った。
「さ、あいつらのところ、戻るぞ。」
「天真…。」
「ま、お前は外見だけでも十分かと思ったけどな、腕っ節も強いとこ見せておけば恐れをなしてあかねに手を出そうなんてヤツ、いなくなるだろ。」
人込みを掻き分けて天真と頼久は飛び出した窓から中へ戻った。
戻ってみると心配そうなあかねと不満そうな蘭の二人が出迎えた。
「よ、頼久さん、怪我とか大丈夫ですか?」
「はい、たいしたことはありませんでしたから。」
「あのなぁ、あかね、こいつの腕はお前が一番よくわかってるだろうが。高校生の喧嘩くらいで怪我なんかしねーって。」
「お兄ちゃんはそうやって頼久さんをうまーく利用して自分がおいしい思いしたんだよね?」
「そういう言い方すんな。まぁ、結果おいしい思いはしたけどな、頼久の腕っ節はギャラリーに見せ付けておいたから、これであかねにむやみやたらと手を出してくるバカはいなくなるだろ。」
「あ、そういうこと。」
「む、むやみやたらと手を出してくる人は今でもいないよ…。」
あかねは真っ赤になってうつむいた。
頼久はそんなあかねの隣に座って今日一日を振り返っていた。
いつもと違ってやたらとあかねが自分にくっついて歩いていたのも、天真達が自分をかまってきたのもどうやら全てあかねと自分の関係を周囲の者達から守るためらしい。
そんなにも心を砕いてもらっていることに感謝しながらも、それでも頼久はどうしても微笑むことができなかった。
あかねの相手がもし自分ではなくて天真のような同級生だったら、こんなことであかねに苦心させずに済んだのかと思うといたたまれない。
どうやらそんな頼久の想いは顔に出ていたようで…
「あかね、お前、当番全部終わったんだよな?」
「え、うん、終わったけど?」
「じゃ、お前、頼久と帰れ。」
「へ?」
「今日は帰りの点呼ねーだろ?」
「ないけど、でも…。」
「頼久、こいつ送ってってやってくれ。」
天真にそういわれてもあかね本人はそれでいいのかと頼久が隣の恋人を見れば、あかねはちょっと考えてから頼久に微笑みかけて立ち上がった。
「うん、今日は疲れたし、頼久さんももうこんなところでみんなに注目されているの嫌ですよね。帰りましょう。」
「よろしいのですか?」
「いいんです。さ、行きましょう。」
あかねは躊躇している頼久の腕を取って教室を出た。
見送る天真と蘭がしかたないなという顔をしていたのには二人とも気付かなかった。
それくらい、二人は自分達のことだけで精一杯だったから。
やはり大勢の生徒に注目されながら二人は廊下を足早に抜けて、玄関から外へ出た。
外はもう夕暮れ。
赤い夕焼けが校庭を綺麗に照らしていた。
「頼久さん車、駐車場ですよね?」
「はい。」
車に乗り込むまでに二人が交わした会話はそれだけ。
あかねに強く腕を引かれて、駐車場へやってきて、二人で車に乗り込むとドアを閉めて同時に深い溜め息をついた。
それがおかしくて、今度は二人で顔を見合わせて微笑み合う。
「なんだか凄く緊張しちゃいました。慣れないことたくさんしたし。」
「注目、されておりましたから。」
「そうですよねぇ。ごめんなさい、頼久さんはそういうの凄くよくわかる人なのに…無理やりこんなところに来てもらって、目立つことしてもらって……。」
「いえ…。」
急に頼久の声が沈んだので、よほどこの一日は迷惑だったのかとあかねは顔色を青くした。
運転席に座る頼久の横顔をまっすぐ見上げていると、自然と目に涙が浮かんだ。
ただ、この人とだけ一緒に、この人とだけ幸せでいたかっただけなのに、そのために頑張ってきたことはどうやらこの恋人には迷惑だったようで、それが悲しくて、申し訳なくて、あかねは涙が浮かぶのをとめることができなかった。
「み、神子殿?!」
そんなあかねに気付いて今度は頼久が慌てる。
頼久は頼久で、あかねに自分のようなものと付き合っているために苦労をかけてしまっていると自己嫌悪に陥っていたところなのだ。
そこへ恋人の涙を見せられては動揺せずにいられるはずがない。
「本当にごめんなさい…私みたいな子供と付き合わせて、そのせいで嫌な思いいっぱいさせちゃって……でも……嫌いにならないでほしいです……。」
「は?」
「一生懸命頑張って、なるべく早く頼久さんに迷惑かけないような大人になりますから、だから……待っててほしいんです…。」
こぼれそうになる涙をこらえて必死に訴えるあかねが美しくて、頼久は気圧されながらも一つ深呼吸をして、ここはあかねの誤解を解いておかねばと、頼久なりに覚悟を決めて口を開いた。
「神子殿は決して子供などではありませんし、私に迷惑をかけたことなど一度もございません。むしろ、私のような者とお付き合い頂いているために神子殿には多大なるご迷惑をおかけしているようで、申し訳なく思っております。」
「そ、そんなことないです!迷惑なんて全然ないです!」
「ですが、同じ年頃の同級生と付き合っていれば、このように文化祭で神子殿にお心を砕いて頂く必要もなく……。」
「そんなこと……私が勝手に頼久さんと恋人同士だってみんなに知っておいてもらいたいって思っちゃっただけです…だって………夏休みの前、私が倒れた時迎えに来てくれてたのはお兄ちゃん?とか聞かれるとけっこうショックで…。」
「は?」
「ちょと年の離れた兄妹に見えるみたいで……お兄ちゃん紹介してとか言われるともう……。」
話しながらも頼久の目の前であかねはどんどん落ち込んでいく。
兄妹に間違われたくらいのことをこんなにも気にしてくれる恋人が愛しくて、頼久はくすっと笑うとエンジンをかけた。
「頼久さん?」
「帰りましょう。お送りしますので。」
「………あの…。」
「はい?」
「もしよかったら……予定とか入ってるなら全然断ってもらっていいんですけど、もしよかったらこれから頼久さんのお家に……その…今日はずっとみんなに注目されてて全然落ち着かなかったし…その……。」
「承知しました。神子殿のお心のままに。」
そう言って頼久はアクセルを踏み込んだ。
これから二人きりになりたいといってもらえたことが嬉しくて、自然とその口元がほころぶ。
年齢が離れていることを気にしていたのは自分だけではなかった。
そう思うと、今までの憂鬱な想いもやわらいで、今はただ愛しい人の願いをかなえたいと思った。
「そういえば。」
「?」
「天真君と喧嘩を止めに行く時…その…頼久さん私のこと名前で呼んでくれましたよね?」
「あぁ、はぁ……。」
改めて指摘されると慣れないことをした自覚のある頼久はもちろん運転に気を配りながらもその顔を赤くする。
「どうして急に名前で呼んでくれたんですか?」
「それは……天真が、クラスメイトの前で神子殿などとお呼びすれば、神子殿が後で友人達にどのような追求を受けるかわからぬと言うので……お気にさわりましたか?」
「全然大丈夫です!これからもずっと名前で呼んでもらっても大丈夫なくらい大丈夫です!」
慌てたせいでなんだか変な物言いになって、あかねは急に口を閉ざすを顔を真っ赤にしてうつむいた。
これからもずっと名前で呼んでもらってもなどと言われてしまった頼久はというと、この状態で安全運転が可能なのか?というほど顔色を赤くして、それでも必死にハンドルを握っている。
これからずっとあかねを名前で呼び続けることが果たして可能かといわれれば、とても今すぐにできそうにはないのだ。
「その…これからもずっと御名をお呼びするのは…その……。」
「あ、えっと…別に絶対呼んで下さいってわけじゃなくて……じゃぁ、人前では名前で呼んで下さいね。それで、だんだん慣れてきたら普段も呼んでくれると嬉しいです…。」
「嬉しい、のですか?」
「あ、はい…嬉しいです。」
どうやらあかねが名前で呼ばれたがっているらしいことを察した頼久は、運転しながら眉間にシワを寄せた。
あかねが喜ぶことなら何でもしてやりたいところだが、急に名前で呼べと言われてもそうそうできるものではないからだ。
「ああ、また頼久さんそんな顔して。」
急に黙り込んだ頼久の様子に気付いて、あかねはクスクスと笑いを漏らした。
「そんなに難しく考えないでいいですから。いつか、名前で呼んでくれたら嬉しいなぁって、それくらいのことですから。」
「はぁ。」
「そうですよね、これからまだまだずっと一緒にいるんだし、時間はかかるかもしれないけどいつか必ず私も頼久さんにつりあう大人の女性になるように頑張りますから、頼久さんも時間がかかってもいいからいつか私のこと、名前で呼んで下さいね。」
「神子殿…。」
信号が赤になったので車を止めて、隣に座る恋人を見れば穏やかに微笑んでいて…
その笑顔はとても現役女子高生のものとは思えないほど落ち着いていて穏やかで、頼久の目には女神の微笑のように映った。
「承知致しました。ですが、神子殿はもう既に素晴らしい女性でいらっしゃいますので、私は急いで神子殿のことを御名でお呼びできるように努力せねばならないようです。」
「よ、頼久さんはまた!そんなこと言って!私はそんなに素晴らしくなんかないですよぅ…。」
つい先程まで落ち着いた笑みを浮かべていたあかねは急に顔を真っ赤にしてうつむいた。
そう、この恋人が平気な顔で恥ずかしい言葉を突如として口にできる人物であることを思い出したのだ。
頼久はアクセルを踏み込みながら楽しそうな笑顔を浮かべた。
「今日は頼久さんにも迷惑かけちゃいましたけど、もう大丈夫ですから。」
「はい?」
「あれだけたくさんの人に見られたんだからもう大丈夫です。ラブレターに断りの返事を書いたり、呼び出されて告白されて断ったり、部活の勧誘されて困ったりしなくて済みます。」
本当に心の底からほっとしているらしいあかねに対して頼久は、そんなにあかねは男性からの告白攻撃を受けていたのかと改めて驚いた。
ころころとよく変わる表情は愛らしいのに時折見せる女神のような優しさや穏やかさも魅力的なあかねだから、それは男達が放っておくわけはないと思ってはいても、実際にそんなに凄いことになっているとはさすがの頼久も想像していなかった。
「今日、頼久さんが一緒にいてくれたおかげでもう大丈夫です。有難うございました。」
「いえ、こちらこそ、楽しませて頂きました。」
そう答えながらこれはクレープで間接キスどころか本当に人前で口づけの一つでもしておいた方がよかったのではないか、などと考えてしまって、そんな自分に驚いて頼久は思わず苦笑した。
あかねにはいつも幸せであってほしい、嫌がることは何一つしたくはないと思っているのも本心なのに、あかねを誰にも渡したくないと思っている気持ちもまた本物で、頼久は生まれて初めての矛盾した想いに苦笑せずにはいられなかった。
「頼久さん?」
「また何か私が参加できるような行事がありましたらお誘いください。できるだけ参加させて頂きますので。」
「あぁ、一般の人が参加できるのって文化祭くらいなんですよねぇ。じゃぁ、また来年も来てくれますか?」
「御意。」
二人がそんな会話を交わしているうちに車は頼久の家に到着して、二人は車を下りると玄関で同時にほっと溜め息をついた。
玄関に入って扉を閉めればいつもの二人だけの空間で。
そこはとても幸せで落ち着いていて。
「やっぱりいいですね、頼久さんのお家。落ち着きます。」
「気に入って頂けて何よりです。」
そう言いながら頼久はそっとあかねを抱きしめた。
いつもは驚いて顔を赤くするのが常のあかねが、今日ばかりはそっと頼久の背に腕を回して抱き返す。
二人は夕陽が落ちて玄関が暗くなるまでそうして二人で静かに抱き合うのだった。
管理人のひとりごと
終わりましたぁ、文化祭後編でした!
あかねちゃんも頼久さんも何か理由がないと人前でベタベタはしないだろうなぁと思ったのでこんな流れになりました。
楽しんで頂けましたでしょうか?
結局、何やらいちゃいちゃして終わったとか思ったら負けです!←何が?
まぁ、今回の目標は頼久さんにあかねちゃんを名前で呼んでもらう、だったので達成されました(爆)
他サイト様ではあかねちゃんが凄く自分の呼ばれ方にこだわっているところが多かったので、うちはまたもやまったりめで(笑)
二人とも、そのうちもっと自然な感じになれるとは思いますが、時間がかかるとも思うんです、頼久さんですから(^▽^)
プラウザを閉じてお戻りください