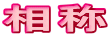
年が明けた直後のバタバタがおさまって、やっと日常に戻った頃。
あかねの周りはにわかにそわそわし始めた。
というのも、庭の花が咲く頃にあかねと頼久の婚儀が予定されているからだ。
待っている二人にしてみればまだまだずいぶんと待たされるという感覚なのだが、準備を整えようと腕まくりしている周囲の人間達にとっては準備の時間はいくらあっても足りないらしい。
藤姫は着物をどれだけ仕立てるか、調度品を総入れ替えしようかなどと毎日頭を悩ませているし、あかねの身の回りの世話をしている女房達もあかねに幸せな結婚をしてもらおうと躍起になっているのだ。
あかねは自分の周囲がなんだか落ち着かなくなっていることに気付いていたが、とりあえずは触れないことにしておいた。
何か言っても聞いてはもらえない様子だったし、それ以上にみんなが何やら楽しそうに見えたから。
ところが、毎日のようにやってくる許婚はというとどうやら屋敷が騒がしいのが気になるらしく、あかねの前で軽く溜め息をついた。
「頼久さん?どうかしたんですか?」
「いえ、その…どうもざわつく気配が気になりまして…。」
「あぁ、そうか。頼久さんはいつも辺りの気配に気を配ってますもんね。」
「警護の任がありますので…。」
そう言ってまた頼久は軽く溜め息をつく。
どうやら辺りが騒がしくて落ち着かないどころか、万が一にも賊が入ったときの事を考えると気配で察知することが困難になると心配しているらしい。
あかねはくすっと笑って空を見上げた。
空は綺麗に青く晴れ渡っている。
「ここには泰明さんが結界を二重に張ってくれましたし、そんなに警戒しなくても大丈夫ですよ。私も最初はそんなに浮かれなくてもって思ったんですけど、なんだかみんながとっても楽しそうだからそのままにしておくことにしました。」
「神子殿…。」
隣に座る許婚を見れば、空を見上げるその顔には幸せそうな微笑が浮かんでいて、頼久も自然とその口元をほころばせた。
愛しい許婚が幸せならそれでいい。
気配が探れないことで不都合があるのなら己を鍛錬すればいいだけのこと。
頼久は一人そう心で思ってあかねと二人、青空を見上げた。
こんなに穏やかに、幸せに空を見上げる日がこようとは。
想像もしていなかった幸せに頼久が酔いしれていると、そこへ一人の童がひょっこりやってきた。
庭の片隅からちょこんと顔を出して、しまったという顔をして姿を消す。
気付いた頼久が素早く追いかけて捕まえると、童はその衣装もきちんとしていて、どうやらそこそこの身分の家に仕えている子供らしい。
「頼久さん?」
普段なら気配でもっと早くに気付けたものをと胸の内で舌打ちをしながら、頼久は捕まえた子供を軽々と抱えてあかねの前へ戻ってきた。
抱えられた子供は抵抗するでもなく、だたひたすら目に涙を浮かべている。
「お、おろしてあげて下さい!泣いてるじゃないですかっ!」
慌てて階を駆け下りるあかねの勢いに驚いて頼久はすぐに子供を下ろしてやった。
声をあげることはないが、その目からぽろぽろと涙をこぼす童をあかねが優しい顔で覗き込む。
「どうしたの?どうしてあんなところにいたの?」
優しく問いかけても童はなくばかりで答えようとしない。
普段なら神子殿の問いかけに答えないとはなんと無礼なとしかりつけるところを頼久は、そんなことをしてはあかねの怒りをかうというのが最近ではよくわかっているのでとりあえずは黙って成り行きを見守ることにした。
「大丈夫、怒ったりしないから泣かないで。何か用事があってきたの?それとも迷子?」
あかねは何度か童の頭を優しくなでて、ゆっくりと答えを待った。
すると童の方もどうやら怒られることはないとわかったらしく、やっとその涙を止めてあかねを可愛らしく見上げた。
「龍神の神子様?」
「うん、そうだよ。私に何か用事?」
「これ…。」
童は懐から大事そうに紙を取り出してあかねに差し出した。
それは紅梅の紙に梅の花の枝がつけられた趣ある手紙のようだった。
「これを私に?」
童は恐る恐る紙をあかねに渡しながらちらりと頼久の方を盗み見た。
あかねがそれに気付いて小首を傾げる。
「頼久さんがどうかしたの?」
「警護の者には見つからないように神子様にお渡しするようにって……特に髪の長い長身の武士には見つかっちゃいけないって…。」
「言われてきたの?」
あかねの問いに童はこくりとうなずいた。
それを見て驚いたあかねがすっと頼久へ視線を向けると、頼久は激しく不機嫌そうな表情で眉間にシワを寄せて何か考え込んでいる。
そんな頼久の思考を邪魔してはいけないとあかねは一人で童の相手をすることにした。
「大丈夫、見つかっちゃったことは黙っててあげるから安心して。用事はこれだけ?」
「必ずお返事をもらってくるようにって…。」
「あぁ、そうなんだ。じゃ、ちょっと待ってね。」
童に優しく微笑みかけてからあかねはつけられた花をはずし、紅梅の紙を開いてみた。
するとそこには…
「うっ…。」
あかねが最も苦手とする流暢な文字の列が…
これはもうどうしようもないとすがるような目を頼久に向ける。
するとそれに気付いた頼久は苦笑しながらあかねに歩み寄った。
「どうかなさいましたか?」
「…読めないんです……。」
「私が読んでもよいのでしたら…。」
「全然いいですっ!お願いします!」
間髪いれずに答えたあかねはすぐに手紙を頼久に手渡した。
頼られたことが嬉しくて頼久が幸せそうな笑みでその手紙に目を通す。
頼久の紫紺の瞳が紙の上の文字をたどること数秒。
先程まで幸せそうだった頼久の顔が急に曇った。
「頼久さん?何か悪い知らせだったんですか?」
あまりの表情の急変にあかねの顔も曇る。
だが、頼久が口にした答えはあかねの想像だにしないものだった。
「申し訳ありません…私にはその…読めません。」
「はい?」
「申し訳ありません…。」
すっと手紙を返されて、あかねは目を丸くしながらもう一度手紙の文字を眺めた。
そこに並んでいるのは確かに容赦のない流暢な文字だが、源武士団棟梁の息子としてそれなりの教育を受けてきた頼久がまさか読めないとは思わなかったあかねは、しかたがないのでその手紙をたたみ直して懐へ入れた。
「えっと、ごめんなさい、今すぐお返事はできないの。そ、そうだなぁ、明日にでも取りに来てくれる?」
「……。」
童はまた今にも泣き出しそうな顔をしてあかねを見上げている。
あかねとしては今すぐにでも返事を書いて渡してあげたいところだが、頼久も読めないとなるともうお手上げだ。
内容がどんなものかわからないから女房の誰かに読んでもらうというわけにもいかない。
こうなってしまうともうあかねが手紙を読んでもらう相手は藤姫か他の八葉、たとえば友雅や鷹通、永泉辺りになるのだが、今すぐ会いに行って会えるものかどうかわからない。
「困ったなぁ……頼久さん、藤姫、今日は屋敷にいますよね?」
「はぁ、お出かけになるという話は聞いておりませんが…。」
「よしっ!決めた!」
あかねはそう言うが早いか童の手をとって歩き出した。
「神子殿?」
「藤姫に読んでもらってすぐに返事を書くことにします!」
すっかりやる気のあかねはすたすたと歩き出してしまい、そんなあかねを一人、いや、童と二人とはいえそのまま行かせるわけにもいかず、頼久は渋い顔で二人の後ろをついていくことになった。
土御門邸への道すがらあかねは色々と童に話しかけてみるが、この童、なかなかに口がかたくて自分の名前さえ明かさない。
どうやらよほど主人を慕っているようで、ただひたすらちゃんとお使いを済ませられるかどうかだけを気にしているようだった。
あかねの屋敷と土御門邸はそれほど離れていないから、三人はすぐに目的地へ到着した。
ところが、藤姫のいる局を目指そうとしたあかねに頼久が思いもかけないことを言い出した。
「神子殿、私はその…少々武士溜まりの方へ顔を出してまいります。」
「あ、はい。」
「お帰りの際にはお呼び下さい。」
頼久はそう言うと早々に立ち去ってしまった。
仕事がない時は常にあかねの側に寄り添って警護をしている頼久にしてはこれはかなり珍しいことだ。
少しばかり不安になりながら、あかねはそれでも童の手を引いて藤姫のもとへと向かった。
「まぁっ。神子様!」
縁に上がったところで御簾の内にいた藤姫があかねに気付いて声をあげた。
あかねが御簾を上げて中に入ろうとするとぱさっと音をたてて御簾を跳ね上げて、藤姫が嬉しそうに飛び出してきた。
「よくぞお越し下さいました。」
満面の笑みで出迎える藤姫。
あかねも思わず嬉しくなって藤姫と互いに手を握り合った。
「先触れをよこして下されば迎えを出しましたのに。」
「あ、いいのいいの、近いし、それに急いでたし。」
「急いでおいでなのですか?」
「あ、そうそう、あの子がもってきてくれた手紙を読んでもらいたくて来たの。」
あかねが童を見ながらそう言って藤姫に手紙を渡すと、藤姫は不思議そうに小首を傾げて童と手紙を見比べると、そっと紅梅の紙を開いて早速読んでみた。
その様子をあかねと童が興味深げに見守る。
手紙を読んでいた藤姫はみるみるうちに顔を赤くして、あっという間に読み終わるとその手紙を素早くたたんであかねの手に返してしまった。
「藤姫、どうしたの?」
「み、神子様、お聞きしたいことが少々…。」
「なぁに?」
「何故、この文をわたくしにお持ちになったのですか?」
「それはね、珍しく頼久さんが達筆すぎて読めないって言ったから、他に今すぐ読んでもらえそうな人って藤姫しか思いつかなくって。ほら、友雅さんも鷹通さんも永泉さんも忙しそうでしょう?泰明さんはつかまらないことが多いし、イノリ君は…読めそうにないし…。」
「頼久が読めないということはないと……あぁ…。」
「何?」
何か納得したらしい藤姫に小首を傾げるあかね。
対する藤姫は何か切なそうに溜め息をついた。
「頼久はおそらく文字が読めなかったわけではございませんわ。」
「やっぱり。頼久さんって武士団の棟梁の跡取りだもんね、ちゃんと勉強してるよねぇ。」
「神子様。」
控えめな声で呼ばれてあかねは再び小首を傾げた。
「今すぐということは、もしや、この文に返事をお書きになるおつもりですか?」
「うん、そうなの。あの子がどうしても返事を持って帰ってこいって言われてるんだって。手ぶらで帰したら怒られちゃいそうでしょう?」
無邪気なあかねを見て藤姫は深い溜め息をついた。
「神子様、友雅殿から教わっておいでと思いますけれど、たとえどのような内容にせよ、お返事なさるのはどうかと…。」
「えっと…それはひょっとして……。」
「はい、これは恋文ですわ。」
「…………。」
あかねは絶句して次に顔色を青くした。
自分宛の恋文をまさか許婚に解読せよと言っていたとは思いもしなかったからだ。
「頼久が読めなかったのは文字が達者だったからではなく、内容が内容なので口にできなかったのではないかと…。」
それはそうだ。
曲がりなりにも許婚の女性に宛てられた恋文を朗読などできるはずがない。
しかも意味を噛み砕いて説明など、友雅ならば面白がってやったかもしれないが、あの実直な武士ができるはずもないのだ。
だが、ここであかねはあることに気付いた。
恋文である以上、たとえ断りの返事であっても返事をしてしまうと気があることになってしまう。
つまり返事が書けないのだ。
ということはこの可愛らしい童は帰ってから叱られることになるかもしれない。
「ど、どうしよう…返事を持たせてあげないとこの子、怒られちゃうよね?」
「それだけではございません、この文、焚き染められている香といい、この紙の色合いの美しさといい、詠まれている歌の出来といい、とても高貴な身分のお方からの御文だと思いますわ。無下に無視してしまってよいものかどうか…」
「へ?だって私はもうすぐ頼久さんと…その…婚儀が控えてるわけだし……。」
いいながら真っ赤になるあかねに藤姫は困ったような泣きそうな顔を見せた。
気丈なこの幼姫にしては珍しい。
「それはそうなのですけれど……困りましたわ。」
藤姫が泣きそうな顔で文を見つめているとそこへふわりとやってきた何者かの長い指が藤姫の小さな手から文を取り上げた。
あかねと藤姫が視線を上げると、そこに立っていたのはいつものように着物を着崩して艶な装いの友雅だった。
「ほぅ、これはまた雅な文を……藤姫かな?受け取ったのは。」
「まさか、わたくしのような子供にそのような艶な文をよこす殿方などいらっしゃいませんわ。神子様に送られた文ですの。」
「ふーん。」
どこかほっとしたような顔で文を眺め回して、友雅はそれをあかねの手に返す。
「で、その童が使いできたと。」
「そうなんです。返事を持って帰らないと怒られるみたいなんですけど……。」
「返事をするわけにはいかなくて神子殿はお困りだというわけかな?」
「はい。」
「友雅殿、何かよい案はありませんか?お気づきと思いますが、この御文、とても高貴な身分のお方からのものではと…。」
「だねぇ。だが、まぁ、神子殿が返事をするわけにはいくまい。神子殿がこの文の主に乗り換えると仰せならいくらでもお手伝いできるがねぇ。」
「乗り換えたりしませんっ!」
「冗談だよ。」
顔を赤くして怒っているあかねにくすくすと笑って見せる友雅に藤姫は深い溜め息をついた。
「お心のお優しい神子様はこの童が叱られでもしてはいけないと悩んでおいでなのです、友雅殿も何か良い思案はございませんの?」
今度は幼姫にきりりと睨まれて友雅は楽しそうに微笑む。
この二人の姫君の相手をしていると飽きないというのが友雅の本音だ。
「返事はやめておきなさい。そこの童は帰っても少し皮肉を言われるくらいで叱られたりはしないだろう。」
「そうなんですか?」
「恋文の使いに童を使うのは常套手段だよ、神子殿。哀れをさそって返事を頂ける確率が上がるだろう?」
「そ、そうなんだ…。」
「まぁ、相手が高貴な身分で無下に断るのもと藤姫が心配するのもわかるが、この文字、香の薫り、文を出した相手に心当たりがあるから、私がとりなしておこう。だから、神子殿は何も心配せずに捨て置いてかまわないよ。」
「あ、有難うございます!助かりました。」
「いや、まぁ、私の得意分野だからね。さ、そこな童、もう帰って主にお返事はもらえませんでした。神子様のお心はお変わりなることはないでしょうとお伝えしてくれるかな?」
「でも…。」
「大丈夫、そう叱られることはないよ。」
友雅ににっこり微笑まれて少しだけ顔を赤くした童は何も言わずに駆け去った。
どうやら本当にたいしたことはないとわかったらしい。
「さて、神子殿。」
「はい。」
「これで用が済んだのなら、早々に武士溜まりへ行った方がいいと思うね。」
「はい?どうしてですか?」
「先程前を通ってきたんだが、物凄い音がして次々に若い武士が薙ぎ倒されていたよ。そうとう若棟梁の機嫌が悪いようでね。あのまま放っておくと怪我人が何人出るかわかったものではない。早いところ頼久の機嫌を直してやってほしいのだがね。」
「あああああ!」
童に気をとられていたあかねは友雅に言われてやっと頼久のことを思い出した。
そう、頼久はあかねに届けられた高貴な身分の男からの恋文を読まされた上にこんなところまで連れてこられて、今、一人武士団の方にいるのだ。
引きとめようとする藤姫にも気付かずにあかねは全速力で駆けていった。
「神子様…。」
「行かせてやりなさい、藤姫には私がいるからね。」
「今回の始末をつけて下さることは感謝いたしますけれど……もう少し神子様とお話がしたかったですわ。」
まだまだ男よりも神子様が大事らしい藤姫に苦笑しながら、友雅は次はこの姫君にどんな歌を送ったものかと思案し始めた。
どうやらいつも送っている歌が恋の歌だとこの幼い姫君はあまり気付いていないようだったから。
あかねが駆けつけた時にはもう頼久はほとんどの若い武士団の後輩を薙ぎ倒した後だった。
床に大の字になって転がる若者が十数名。
対して頼久は木刀片手に不動の姿勢で立っていた。
眉間にシワを寄せてこれでもかというほど機嫌が悪そうだ。
それでもその立ち姿のあまりの整った様子に、かけつけたあかねは状況が状況だというのに一瞬見惚れてしまった。
おかげで声をかけるのが少し遅くなり、自分から声をかける前に床の上でのびている若い武士達に見つかってしまい、ぼーっと見惚れる若者達の視線を追った頼久が視線の先のあかねにたどりついてはっと表情を変えた。
「神子殿!」
慌てて木刀をおさめて駆け寄る頼久にあかねは精一杯の微笑を浮かべて見せる。
「もうお帰りなのですか?呼んで頂ければ…。」
「うん、いいの、迎えに来たかったの。」
そう言ってあかねは頼久の手をとると、武士団の面々にぺこりと一礼して歩き出す。
このままここに頼久を置いておくと本当に怪我人が何人出るかわからない。
頼久は慌ててそのままあかねに手を引かれて歩き出した。
「神子殿…。」
「帰りましょう。屋敷に戻ったら何かおいしいお菓子食べましょうね。」
「はぁ……。」
なにやら楽しそうな様子のあかねとは逆に頼久はどんどん落ち込んで、あかねに手を引かれながらすっかりうなだれてしまった。
あかねが迎えに来てくれて嬉しかったのも束の間、先程見た恋文のことを思い出したのだ。
思い出してもその文をどうしたのかと頼久の方から尋ねるわけにはいかない。
そんな頼久に気付いてあかねは歩みを止めるとくるりと振り返って頼久の顔を見上げた。
紫紺の瞳が憂いでくすんでいて、あかねはそれを見ただけで胸が痛くなった。
「あの…さっきの手紙なんですけど…。」
「はい。」
「藤姫に読んでもらったんです。それで…あの…あれは恋文だったみたいで……返事を書くわけにはいかなかったから無視、しちゃいました。」
「……。」
あかねにしてみると頼久に安心してもらおうと思って話したのだが、どうも頼久の顔から苦悩の色が消えることはないようで、何が問題なのかわからなくて今度は逆にあかねの顔色が曇った。
「あの……。」
「あの文は…その…かなり高貴な身分のお方からのものと推察致しましたが……その…。」
「そうみたいでした。でも返事しなくていいって…その、誰からきたか友雅さんはわかるって、それでとりなしておいてくれるそうです。だから全然大丈夫ですから。」
「友雅殿が…。」
「えっと、友雅さんはたぶん、藤姫に会いに来たみたいで、たまたまばったり……。」
そこで途切れる会話。
久々に沈黙が痛い。
互いに黙り込んだまま思案することしばし、先に口を開いたのは頼久だった。
「あの香といい紙といい…おそらく主上に連なるお血筋の方が手紙の主かと…。」
「だから何だって言うんですか?」
いきなりあかねの怒ったような声が聞こえて頼久ははっと視線を上げた。
視線の先には瞳に涙を浮かべてそれでも怒った顔をしているあかね。
「相手が偉い人だから私が乗り換えるってそう思うんですか?」
「いえ、そういうことでは……。」
「友雅さんにも同じようなこと言われました、冗談だって言ってたけど。二人ともどうかしてます!そんなに簡単に、偉い人が言い寄ってきたからって好きな人を乗り換えたりできませんから!」
「……。」
「頼久さんだったら綺麗なお姫様から告白されたら乗り換えちゃうんですか?」
「滅相もありません!」
「私だって同じです。」
「同じでは…ありません……。」
「へ?」
頼久の声が一段と苦しそうに低くなったので、すっかり怒っていたあかねも目を丸くして驚いた。
何が同じではないんだろう?
「神子殿は主上に連なるお血筋の方からも望まれるほど清らかで高貴なお方なのです。一介の武士たる私とは全く違います。」
「また身分の話ですか……ずーっと頼久さんがそんなこと言ってたら本当に私、乗り換えちゃうんですから!」
とうとうあかねがキレた。
この許婚はことあるごとに身分が違うといって何もかもを遠慮しつくし、最近まで御簾の内にも入ってくれなかった。
それがやっと御簾の内で二人で話ができるようになったと思ったのにまたこれだ。
身分などない世界からやってきたあかねにとってはこの頼久の執拗なまでの遠慮がたまらない。
もうすぐ夫になるといっている人なのだから、誰かがちょっかいをかけてきたら「俺の女だ、手を出すな」くらいのことは言ってもらいたいのが乙女心というものだ。
だが、頼久が相手ではそんなことはとうてい望めそうもなくて、あかねはいつもどこか遠慮がちな頼久に寂しさを覚えていたのだった。
そんな普段の寂しさも重なって、あかねは涙を浮かべながら駆け出していた。
そこは元龍神の神子として戦っていたあかねだ、走り出すとそこそこ足は速い。
あっという間に自分の屋敷に戻ってくると、頼久には何も言わずに御簾を跳ね上げて自分の局へと駆け込んで、几帳まで立てて閉じこもってしまった。
「神子殿…。」
苦しげな頼久の呼びかけにも答えずに、あかねは袿を被って部屋の隅でうずくまっていた。
もし、本当にあの手紙に返事を書いてしまって、それで手紙の主と交際なんか始めちゃってもこの人は何も言ってくれないんじゃないだろうか?
そう思うと悲しくて、あかねの頬を涙が伝った。
「神子殿…その…先程のお言葉は……。」
その先が頼久の口からは出てこない。
自分が不甲斐ないばかりに乗り換えるといったさっきのあかねの言葉は本心なのかどうかを知りたいのに、どうしてもそれを強く問いただすことができないのだ。
答えが恐かったから。
「……頼久さんが…いつまでもそんなふうなら……私が身分の高い人に乗り換えてもいいって、しかたないなんて思ってるなら本当にそうしちゃいますからっ!そうしたら頼久さんはあきらめちゃうんでしょう?!」
涙声でそう言われて、頼久は階に立ち尽くした。
先程から自分が言っていたことの意味をここでやっとよく理解したのだ。
そう、あかねが身分高く清らかな女性だから身分の高い男に望まれてもしかたない。
ということは、己はこの許婚をあきらめるということなのだ。
そう考えて、頼久は急に表情を変えた。
今までの苦悩の表情が一変、武士らしい厳しいものへと変わる。
そして中のあかねの許可も得ずに御簾を跳ね上げて中へ入ると、さっさと几帳をどけて袿を頭からかぶっているあかねの手からその袿も剥ぎ取ってしまった。
「よ、頼久さん?」
あまり拗ねて見せたからとうとう頼久もキレて乱心か?と少しだけ恐ろしくなったあかねが見上げていると、頼久はひょいっとあかねを抱き上げてその場に座り、膝の上で顔を赤くする許婚をきつく抱きしめた。
「あきらめたりなどできません。」
「はい?」
「あなたをあきらめるなど不可能です。」
そう言って頼久はあかねの顎を持ち上げるといつもよりも長く、そして少しだけきつく口づけた。
さっきまで御簾の向こうですっかり遠慮していた許婚の変貌ぶりに驚きながらも、長い口づけの間にあかねもうっとりしてしまって、唇が離れた頃にはもうあかねの瞳から涙は消えていた。
「えと……あの……。」
一瞬で顔を真っ赤にしてうつむくあかねに気付いて、頼久は自分も顔を赤くした。
必死だったので気付かなかったが、許婚を自分の腕の中に閉じ込めてようやく一心地ついて自分が何をしたのかに気付いたのだ。
「その…ご無礼を致しました……。」
「全然ご無礼じゃないです!大丈夫ですから!」
「はぁ…。」
「いつもそういうふうにしてくれると嬉しい、かな、なんて。」
「はい?」
「だから、その…遠慮、しないで下さい。凄く身分の高い人が私に言い寄ってきても追い払っちゃって下さい。私、頼久さんにはそういうふうにしてもらいたいです…。」
「神子殿…。」
腕の中の許婚になんとも嬉しいことを言われて、頼久の顔にはようやく笑顔が戻った。
誰に対しても自分のものだと宣言してもいいのだとこの清らかな許婚は許しをくれたのだ。
しかもそれを望んでいるとまで言ってくれた。
頼久はあかねを抱く腕に力を込めて耳元に唇を寄せた。
「承知致しました。これから先はそのようにさせて頂きます。」
低い声でそう囁かれて、首まで真っ赤になったあかねは頼久の腕の中で小さくコクコクとうなずいた。
管理人のひとりごと
校正してみたらなんだか書いた自分が砂吐きそうでした(’’)
まだまだ修行がたりませんか?(マテ
ようやく婚儀が近づいてきたようですが、頼久さんはやっとこんな感じ。
結婚してもこの二人はあまり変わらなそうです(笑)
今回も藤姫と少将様にご登場願いました。
密かに管理人はこの二人も気に入ってます(爆)
プラウザを閉じてお戻りください