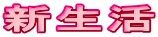
あかねに週末はあいていますか?と訪ねられたのはつい3日ほど前のことだった。
週末はもちろんあかねと二人で過ごすためにいつもあけてあるし、たとえふさがっていたとしても予定を変更してあかねのために時間を作る頼久は、すぐにあいていると返事をした。
するとあかねは、大学にも合格して新生活が始まるから新しく必要になるものを買いに行くので一緒に行って欲しいと、珍しくもはにかみながら頼久にお願いしてきたのだった。
あかねが頼久にこういったことをお願いすることは珍しくて、頼久は極上の笑みを浮かべて瞬時に快諾した。
それでなくてもあかねの望みなら何でもかなえたい頼久だ。
一緒に買い物をするくらいどうということはない。
どうということはないというよりもむしろ喜ばしいくらいだ。
あかねが合格した大学は自宅から通える距離にある。
だから、新しく居を構えるわけではない。
生活用品を買い込むというわけではないけれど、それでも大学生活を楽しむためにはけっこうなものが入り用になるようで、あかねは申し訳なさそうに頼久に荷物持ちの役目を依頼したのだった。
もちろん、荷物持ちだろうが、ただの送り迎えだろうが、頼久にとっては名誉ある役目に違いない。
日曜の朝、早くに起き出した頼久は軽く朝食をとると庭で少し素振りをしてから身なりを整えて家を出た。
あかねの家の前に車を乗りつけた頼久は、二階の自分の部屋の窓から顔を出しているあかねを見つけた。
愛らしく微笑んでいるあかねの顔はつい3日前に見たばかりだというのに、頼久にとっては久々に見たような気がした。
受験がすっかり終わってからは毎日のように会っていたからかもしれない。
すこしばかりおしゃれをして頼久に軽く手を振ったあかねはすぐに窓を閉めて玄関から姿を現した。
春らしい若草色のワンピースに白いバック。
「おはようございます。」
「おはようございます。よくお似合いです。」
「よかったぁ。ちょっと背伸びしちゃったかなって思ってたんです。」
うっすらと頬を赤く染めながらあかねはにっこり微笑んだ。
「どうぞ。」
「あ、はい、有難うございます。」
少しだけ大人びた様子のあかねを助手席に乗せて、頼久は運転席に落ち着いた。
「まずはどこへ参りましょうか?」
「ショッピングモールへ。だいたいそこで全部揃うと思うんです。」
「探しておいでのものは…。」
「大学って制服じゃなくなるんで、洋服と靴と、それからノートに大きめのバックです。大学に通うとなると資料とか教科書とか色々荷物も増えそうで。」
「なるほど。では、とりあえずショッピングモールへ参りましょう。」
「お願いします。」
頼久はいつもよりも慎重に車を発進させた。
助手席にあかねが乗っているとなれば間違っても事故など起こすわけにはいかない。
ゆっくりと辺りに注意を払って運転しながらも、頼久は横目で時折あかねの様子をうかがった。
あかねはというと助手席で機嫌良さそうに微笑みながら窓の風景を眺めたりしている。
受験が終わってすっかり気分もおちついたらしいあかねは、頼久と共にいる時はいつも上機嫌だ。
暖かくなり始めた春の陽射しの下を頼久も上機嫌で車を走らせた。
もうすぐあかねは入学式を迎えて大学生になる。
大学というところは高校よりはよほど時間が自由になるところだ。
となれば、頼久があかねと共に過ごすことができる時間もおそらくは増えることだろう。
大学生になったあかねとの時間。
それがどれほど楽しいかと想像しながら運転すれば、頼久にとって目的地までの運転はあっという間だった。
駐車場に車を止めて降りれば、あかねが自然と頼久の腕を取った。
驚いたのは頼久だ。
「えっと……高校も卒業しましたし、大学生になるし……その……。」
赤い顔でギュッと自分の左腕を握るあかねを見つめてキョトンとしていた頼久の顔に笑みが浮かんだ。
ちょっと恥ずかしいけれど、もう女子高生は卒業したのだから腕を組んで歩くくらいはしてみたい。
それがきっとあかねが頼久に伝えたい今の気持ち。
それを悟って、頼久はあかねに腕を預けたまま歩き出した。
「参りましょう。全てそろえるには時がかかりそうです。」
「あ…はい!」
頼久にうながされてショッピングモールへと足を踏み入れたあかねは、入り口に近い店からゆっくりと見て回る。
もちろん頼久はそのお供だから、何も言わずにただあかねの後をついて歩くのみだ。
最初に入ったのはかわいらしい洋服がたくさん置いてある店。
あかねはどの服にしたらいいか迷うと、頼久に意見を求める。
頼久にしてみれば何を着ていようとあかねは愛らしく神々しいと思うのだが、そんなことを正直に口にするとあかねがまた恥ずかしいと拗ねてしまうのでとりあえず本音は飲み込むことにした。
そして、あかねにはどれも似合うがと前置きをしてから自分の好きな色やデザインのものを選ぶと、あかねがそれにすると嬉しそうに決断を下すのだった。
最後に春らしい色のワンピースを買ってこれで洋服は全部揃いましたと言ったあかねはとても満足そうで、頼久はあかねが抱えている紙袋を全て引き受けながら上機嫌だ。
そんな頼久にあかねはそっと「頼久さんの好きな服も買えて凄く嬉しいです。」と顔を赤くして囁いた。
その一言が頼久をどれほど喜ばせるかも知らずに、あかねは頼久の手を引いて次の店へと入っていく。
洋服の後は文房具だ。
本来必要だったのはノートだったようだが、あかねはノートを手に取ってからも次々に文房具を眺めていた。
ボールペン、シャープペン、ラインマーカー、消しゴム、などなど…
頼久はあかねにボールペンはどれがいいだろうと相談されて、少し考えてから万年筆を勧めた。
せっかく大学生になるのだし、公式な文書を書くのではなく、ノートをとるのに使ったりするのなら万年筆の方が大学生らしくていいのではないかと提案したのだ。
あかねの中にその選択肢は全くなかったらしく、興味津々の顔になったあかねはすぐに万年筆が並ぶショーケースを食い入るように見つめた。
そして値段を眺めて苦笑して「とても高くて手が出ません」などと言うものだから、頼久はすぐ白地に薄紅の桜の花がちりばめられた美しい装飾の万年筆を一本購入すると、それをプレゼント用に包装してもらってあかねに渡した。
恐縮することしきりのあかねに自分が選んだ物を使ってもらいたいのだと懇願して受け取ってもらい、頼久は更に上機嫌になった。
これで大学では自分が選んだ筆記具をいつも持ち歩いてもらえるのだから頼久にとってはこれ以上嬉しいことはない。
他にも大量のノートや消しゴム、かわいらしい布製のペンケースなどを買ってあかねはニコニコと店を出た。
もちろん更に増えた荷物は全て頼久が引き受けている。
だいたいの買い物が終了したところでお茶にしようということになり、喫茶店であかねはケーキセット、頼久はコーヒーを注文して30分ほど休憩した。
ここまではよかった。
いつになく楽しい買い物ができたし、あかねは全ての目的を果たしたようだった。
頼久もあかねと二人のデート兼買い物を楽しんでいたのだ。
荷物は少しばかり多くなっていたけれど、それも体力自慢の頼久の手にかかればたいしたことはない。
二人は休憩を済ませると少し予定より早めではあるけれど、家へ帰ってゆっくりすることに決めた。
大量の荷物を軽々と持ち運ぶ頼久と、その隣を愛らしく歩くあかねの二人はショッピングモールをゆっくりと歩いていた。
二人ともその顔には満面の笑みが浮かんでいた。
ところが、あかねがある店の前で急に立ち止まった。
それと同時に今まであかねの顔に浮かんでいた笑みが消えて、慌てて足を止めた頼久に背を向けると目の前の店のショーウィンドウに張り付いてしまった。
頼久がよくよく見てみるとその店はどうやら化粧品を扱っている店のようで、店の外にまで鼻をつくような香料の薫りが漂っていた。
「み……あかね?」
あかねの隣に並んで頼久がそっと呼びかけてもあかねの視線は頼久の方へ向くことはない。
その視線はケースの中に並んでいる美しいガラスの小瓶をとらえていた。
「大学生になったらやっぱりちょっとはお化粧とかしようかなって思ってるんです…。」
「はぁ…。」
「私ってちょっと子供っぽいところがあるし…性格は…頑張って大人になるように努力しますけど、外見もと思って……。」
頼久は頼久であかねよりもかなり年が上であることを気にしているのだが、逆にあかねは自分が頼久からすれば子供に見えるだろうということをやたらと気にしている。
だからこうして何かにつけて大人っぽくなりたいというのだが…
頼久は今のままのあかねでじゅうぶん魅力的だと思うし、その魅力にすっかり参っているわけで、あかねがこれ以上何かを努力する必要など全くないと思っている。
逆に厚化粧などしてはせっかくのあかねの魅力がかき消されてしまうのではないかと思っているくらいだ。
だが、今そんなことを語って聞かせてもきっとあかねは納得しない。
何をどう言えばいいのか口下手な頼久はすぐに思いつかず、ただじっとあかねの言葉に耳を傾けた。
「でも、前にお化粧した時は頼久さん、あんまり好きじゃなさそうだったし…。」
「好きじゃないというよりはその…もったいないと申しましょうか…。」
「もったいないって、何が?」
「せっかくのみ……あかねの愛らしさが化粧で隠されてはと…。」
「よ、頼久さんはまたそういう恥ずかしいことを……。」
「申し訳ありません…。」
「私はそんな頼久さんが言うみたいにかわいくはないと思いますけど、でも、頼久さんがお化粧嫌いなのもわかってるんです。だから、香水っていう手もあるかなぁと思ったんですけど…。」
あかねの視線の先にあったガラスの小瓶達はどうやら香水のようだった。
カラフルなガラスに奇抜なデザインのその瓶をじっくり見つめて、それから隣にあるあかねの横顔を見つめて、頼久は小さく息を吐いた。
香水など使わなくてもあかねからはいつも何やらほのかに花の香りのようなかすかに甘い香りが漂っている気さえするのに、今更作り出された香料などどうして必要だろう。
だが、ここで頼久がそう力説してもやはりあかねは納得しないはずだ。
きっと努力できることが一つ減ってしまうことを悲しむに違いない。
頼久はこれはどうしたものかと真剣に考え始めた。
「頼久さん。」
「はい。」
「この青い瓶の香水のサンプル、ちょっと嗅いでみてください。」
「はぁ…。」
言われて頼久は自分の方へ近づけられたサンプルの香りを吸い込んだ。
やはりどこか鼻につくような刺激のある匂いに思わず顔をしかめる。
「あ、ダメなんですね…じゃ、こっちの方がいいかなぁ…これ、どうですか?」
次にあかねが手にしたのはオレンジ色の瓶のサンプル。
今度は柑橘系の香りがしたが、それもやはり人工的なわざとらしい匂いに頼久が顔をしかめる。
「これもダメかぁ…頼久さんの嫌いな香りなんてつけても意味ないし、どんな香りが好きか教えてもらえますか?」
すがるようなあかねの視線を受けて頼久は考え込んだ。
好きな香りといわれても、とうていこの香水の中にはありそうにない。
だいたい、あかねにこんなどぎつい香りが似合うはずもない。
けれど、ここは何か答えなければきっとあかねが悲しむ。
じっと考え込んで、あかねを見つめて……
そうしているうちに頼久の脳裏に京にいた頃のあかねの姿がよぎった。
物忌みで外出できない時など、局の中で愛らしく座っていた着物姿のあかねだ。
「頼久さん?」
いつの間にかその顔に穏やかな笑みを浮かべている頼久にあかねは小首を傾げた。
そんなあかねに頼久はやっと見つけた答えを口にする。
「神子殿は、もうご存知です。」
「頼久さん、神子殿になってますよ…って、はい?頼久さんの好きな香り、ですか?」
「はい、私の好きな香りはよくご存知のはずです。」
「ご存知のはずって……えっと…………まさか、梅香のこと言ってます?」
「はい。」
言い当てられて頼久が嬉しそうな笑みを浮かべる。
反対にあかねは困ったような顔で考え込んだ。
「梅香って…あんな上品で自然な香りの香水なんてあるのかなぁ…。」
「香水はないかと思いますが…。」
「ですよね…じゃ、香りもだめかぁ…。」
「いえ、香でしたら入手できるかと…。」
「へ?京にあったみたいなお香ってこっちでも手に入るんですか?もの凄く高価だったりしませんか?」
「そうでもないはずです。まぁ、京の梅香とは多少香りが違うかもしれませんが、香水よりは近いでしょう。線香などを扱っている店で扱っていると思いますが。」
「そ、そうなんだ…私、てっきりお香ってもの凄く高価なものかと思ってました。」
「高価なものもありますが、梅香の中には手頃なものもあったと思います。」
「じゃぁ、それを焚き染めたりしてみようかな…うん、その方が良さそうです。」
「では、次は香を扱っている店を探してみましょう。」
「はい。」
あかねの顔に輝かんばかりの笑みが戻ってきた。
そのことが嬉しくて頼久の顔にも笑みが浮かぶ。
二人は化粧品店の前を離れ、新たな目的地へ向かいながら何を語るでもなく京での日々を思い出していた。
つらい戦いの日々だったけれど、そんな中でも幸せを感じることもたくさんあった。
梅香の香りはその中でも優しい記憶と共に存在する幸せな記憶の断片だ。
その香りを求めて、二人は大量の荷物を車に乗せると街の中へとくりだした。
数日後。
頼久は隣に座って紅茶を楽しむあかねの体からほのかに薫る梅香の香りに目を細めていた。
それはやはり完璧に同じというわけではないけれど、京にいた頃の梅香に似た自然な香木の香りだ。
上品な香りはあかねによく似合っている気がして、頼久の顔には笑みが絶えない。
「頼久さん?」
隣に座っている恋人の様子に気付いてあかねが小首を傾げた。
二人でいると頼久が上機嫌なのはいつものことだが、今日はいつもよりもずっと機嫌が良いような気がする。
「やはり香にして頂いて正解でした。」
「そ、そんなに気に入ったんですか?」
「はい。」
低い声でそう答えて頼久はそっとあかねの肩を抱き寄せると、少しのびた髪に鼻を寄せた。
部屋の中で香を焚き染めているせいか、あかねの髪からも梅香はほのかに薫ってくる。
「よ、頼久さん…嗅いでません?」
「あまりに神子殿が魅力的ですのでつい…。」
「ついって、恥ずかしいですってば…。」
頼久から髪を引き剥がそうとあかねが視線を頼久の方へ向けてその顔を見上げれば、恋人の端整な顔はとろけんばかりの笑みを浮かべて目を細めていて…
思わずその表情に見惚れている間にあかねはいつの間にか口づけられていた。
唇が離れてからも頼久の幸せそうな笑顔は変わらなくて、突然口づけられたことに抗議もできなくて…
あかねが真っ赤な顔でしどろもどろになっていると、頼久はあかねを両腕でしっかり抱きしめてしまった。
「頼久さん?」
「しばし、このまま。」
「もぅ…。」
どうやらまた自分から薫る梅香にうっとりしているらしいと気付いて、あかねは頼久の胸にもたれると目を閉じた。
そんなに気に入ってもらえたのならとても嬉しい。
気に入ってもらいたくて選んだ香りなのだから。
それにこの香りのおかげでこんなふうに甘い一時を過ごせるのなら、それはあかねの望んだとおりになっているということでもある。
こんな幸せな時間にどんな不満があるだろう。
ただ一つ、とんでもなく恥ずかしいのだということを除けば、あかねに不満などあるはずもなくて…
新しく始まる生活のためにそろえたものは色々あったけれど、一番の幸せをもたらしてくれたのはこの香りだったとあかねは頼久の腕の中で微笑むのだった。
管理人のひとりごと
とうとう嗅いでるわ、頼久さん(’’)
ヘンタ…(っдT)(マテ
管理人は薫るものが大好きですが、香水はあまり好きじゃありません。
あの香り、きつすぎね?と思うわけです。
対してお香は大好き♪
ちなみに練香でよければ梅が香という名前のお香は市販のものがあります、お手ごろ価格で♪
そして管理人は常備してます(笑)
というわけでこちらの世界でも一応梅をイメージした香りは楽しめるのですね。
自分で調香すればたぶん平安時代に近い香りの梅香を作ることもできます。
管理人、レシピ持ってます(爆)
ですが、材料が揃わなくて作れない(^^;
ということであかねちゃんも市販品を使ってもらいました♪
そうしたら頼久さんに嗅がれたと(’’)
あかねちゃんが喜んでいるので問題はありません!←断言
ブラウザを閉じてお戻りください