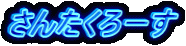
武士としての一日の仕事が終わり、これから左大臣の屋敷を警護する者の担当を確認して頼久の仕事はほぼ終了する。
目の前には若い者から古参の者まで、頼久の部下が一堂に会していた。
場の空気は神妙だが、決して暗くはない。
良い緊張の中で頼久は一つうなずいた。
「特に問題はないようだな。これで解散とする。」
特に問題はなく、連絡はつつがなく終了した。
ならば、休むべき者は休み、仕事に就くべき者は持ち場へ移動するべき時が来た。
そう判断した頼久が腰を浮かしかけたその時、最前列の若い武士が礼をしていた顔をはっと上げて頼久を見つめた。
「おそれながら!」
「どうした?連絡もれか?」
「いえ……その……お尋ねしたきことが…。」
もう一度腰を落ち着け直した頼久は首を傾げた。
頼久の部下達の中でも若者はどちらかといえばはっきりとした物言いをする者が多い。
それなのに今、目の前の若者は明らかに質問があるというのにその質問を口にすることを躊躇していた。
これは何か一大事が起こっているのか?と頼久が身構えたのも無理はない。
頼久は、何を言われても動揺は見せまいと居住まいを正してから若者を凝視した。
「お前も武士ならば歯切れの悪い物言いをするものではないぞ。」
「はい!申し訳ありません!では、その、簡潔にお尋ね致します!このたび、神子様におかれましては『くりすます』なる宴を御企画の最中という噂を耳に致しました。」
若者が思い切って語りだした話に頼久は思わずため息をついた。
あかねが『今年はクリスマスパーティをしたいと思います!』と元八葉の面々を集めて宣言したのはつい三日ほど前のことだ。
その話がもう、こんな若い武士にまで伝わっているとは思わなかった。
なにしろあかねはこの企画をなるべく秘密裏に進めたいと言って、こっそり準備をしていたのだから。
どこから情報が漏れたのかと頼久が眉間にシワを寄せて考え始めたその時、若者の口から予想だにしない言葉が飛び出した。
「その神子様主催の宴にて、最も尊いお役である『さんたくろーす』なるお役目を橘少将様がお引き受けになったというのはまことでございましょうか?」
必死の覚悟でこの質問を口にしたらしい若者は顔を赤く上気させて、今にも頼久につかみかからんばかりだ。
頼久は眉間にシワを寄せ、明らかに不愉快そうな表情をその顔に浮かべると、小さく溜め息をついた。
「まことだ。神子殿がお選びになった人選だ。我々がとやかく言うことではない。」
「それはそうですが、若棟梁こそが神子殿の夫でいらっしゃいます!であれば、尊いお役目は第一に若棟梁に…。」
「それ以上は言うな。それ以上言えば、私はお前を神子殿を罵った者として許せぬ。」
「……。」
低く響く真剣な声に若者は口を閉ざした。
もちろん、その顔には不満気な表情が浮かんでいるが、そんな若者を気遣ってやれるほど今の頼久には余裕がなかった。
若者の言う通り、その『さんたくろーす』という重要らしい役目はあかねの一声で友雅のものとなったのだ。
頼久は一番に立候補したし、イノリはもちろん、泰明や鷹通までもがその役目をぜひ自分にと立候補したのだ。
ところがあかねはそんな仲間達をいつものように艶やかな微笑で見守る友雅にこそふさわしいと、少し考えた末に宣言したのだった。
この三日、頼久の脳裏から「やっぱり友雅さんが一番似合うと思うんです。」と言ったあかねの声と顔を思わぬ日はなかった。
それはまるで、自分が大切に思う仕事を任せることができるのは友雅だけといわれている気がしたからだ。
もちろん、あかねがそんなことを言うはずはないと信じてはいる。
信じてはいても、うきうきと浮かれているあかねに指名されてこちらもまんざらではない様子の友雅の表情まで脳裏に焼き付いていては、愉快な心持にはなれなかった。
「全ては神子殿のお考えだ。これ以降、この話は持ち出すこと許さん。」
『はっ。』
さすがに頼久の威厳ある一言にこの場にいた全員が頭を下げた。
一番不本意なのは頼久本人だと察してもいるのだろう。
いつもと変わらぬ身のこなしで立ち上がり、そのまま自分達の前を去って行く若棟梁を武士達は気の毒そうな眼差しで見送った。
武士溜まりを後にした頼久は、月の下をゆっくり歩きながらも考え込んでいた。
ここ三日は屋敷へ帰ってもあかねは『くりすます』の宴の準備で頭が一杯だ。
つまりはいまのところ、頼久の気分を決してよくはしないその行事の話ばかりがあかねの口から流れ出てくるわけで…
いつもなら一刻も早く妻のもとへと急ぐ頼久の足は今、いつもよりもどうしてもその歩む速度を遅らせていた。
三日前、少し考え込んでから友雅を『さんたくろーす』にと宣言したあかねの楽しそうな笑顔。
その宣言を受けて「おやおや」とかなんとか言いながらそれでもすぐに引き受けようと答えた友雅の満足気な顔。
その二つが頼久の脳裏からはいつまでも消えなかった。
もちろん、何から何まであかねの望む全ての役を自分一人がこなせるなどと頼久は思っていない。
どちらかといえばどころか、どう考えても自分が不器用な人間だということは十分自覚している。
それでもやはり自分ではなく友雅が選ばれたことに自分ではどうしようもない嫉妬を抱いてしまうのだ。
『さんたくろーす』というお役目はあかねの話ではこの『くりすます』の宴において一番重要なお役目ということだった。
頼久の心に嫉妬が渦巻くのはそのせいもあるだろう。
そんな嫉妬心をむき出しにすることをあかねは決して喜ばない、そう思えばなお、頼久はあかねの前に座るこれからの自分を想像すると複雑な気分になった。
あかねの側にはいたい。
だが、あかねの前ではこのどうしようもないどす黒い感情を隠さねばならないのだ。
もともと愚直であると言われるほどまっすぐな頼久にとってそれはそれは非常に難しい仕事のように思えた。
「頼久さん!お帰りなさい!」
朗らかなあかねの声に頼久ははっと我に返った。
「神子殿、ただいま戻りました。」
「お疲れ様でした。」
ニコニコと微笑んで御簾を上げてくれるあかねの側へとその大きな体をすべり込ませながら、頼久は小さなため息をついた。
どうやらあまりに深く考え事をしていたために屋敷に到着していたことにさえ気づいていなかったらしい。
これではいけないと頼久が自分を律している間に、あかねは奥へと引っ込んでしまった。
これからすぐに疲れている頼久に夕餉を出そうと支度をしに行ったのだと気付いて、頼久は素早く着替えを終えた。
なんとかさっき自分を迎えて嬉しそうにしてくれたあかねの顔を思い浮かべて頼久がやっとの思いで心を落ち着かせたその時、あかねは食事を運んできた女房と共に頼久の前へ戻ってきた。
「さ、たくさん食べて下さいね。」
「はい、いただきます。」
あかねと二人、向い合せに座って頼久はすぐ箸を手に取った。
「今日はまた寒かったですね。24日は雪が降ったりして。」
「降った方がよいのでしょうか?」
「クリスマスですか?それはまぁ、雪が降った方がそれっぽいというか、ホワイトクリスマスって言いますしね。」
「はぁ…。」
「あ、ごめんなさい、頼久さんにはわからない言葉でしたね。白いクリスマスっていう意味なんです。向こうでは雪が降った方が情緒があるっていうか、そういうふうに言われてるんです。」
「さようですか。」
「色々準備したんですよ。女房さん達に手伝ってもらってお菓子もたくさん作ったし、あと衣装も完成しました。」
「それは、神子殿もお疲れ様でした。」
「少し疲れましたけど、でも楽しいから平気です。イノリ君が面倒見てる子供達、みんな喜んでくれるといいなぁ。」
「神子殿がお作りになったのです、喜ぶに決まっております。」
「そうだといいんですけど。」
あかねは当然だと言わんばかりの頼久に苦笑を浮かべて見せた。
そう、あかねがクリスマスパーティをすると言い出したのはイノリが面倒を見ている孤児達に冬の寒さの中でも何か楽しいことをプレゼントしたかったからなのだ。
あかねがクリスマスを企画した理由がこれでは頼久が反対するなどということは天地がひっくり返ってもありえない。
そうこうしているうちにクリスマスパーティはあっという間に助走を開始していたのだった。
「あの…。」
「何か?」
「ひょっとして頼久さん、怒ってます?」
「は?」
「怒ってるっていうか不機嫌っていうか…。」
「いえ、そのようなことは…。」
やはりかと頼久は心の中でつぶやいた。
自分が機嫌をうまく隠してこの世で最も大切な人の前に座ることなどできるはずもなかったのだ。
そういうことは友雅の専売特許と言っていい。
「でも……私がクリスマスのことばかり夢中になってたからですか?」
「違います。不機嫌というわけでは決して…。」
「……ごめんなさい、頼久さん、最初からあまり乗り気じゃなかったですもんね。」
「そういうわけでは…。」
目の前でどんどん落ち込んでいくあかねにかける言葉を見つけられずに、頼久は深いため息をつきながら箸を置いた。
食事などしている場合ではない。
せっかく『くりすます』を楽しんでいるあかねに不愉快な思いをさせるのは頼久の本意ではない。
では何をどう話せばあかねの心は軽くなるのかと考えてみてもしゃれた言葉など出てくるはずもなく…
頼久はいつものように正直に話すしかないと観念すると重い口を開いた。
「神子殿が『くりすます』なる宴を催されることに関しては何一つ問題はございません。ただ…。」
「ただ?」
「『さんたくろーす』のお役目を友雅殿にと指名なさったのはこの頼久が不甲斐ない故かと…。」
「へ………えーっ!そんなこと気にしてたんですか?!」
そんなこと、と言われて頼久は深いため息をついた。
そう、あかねにはそんなこと程度のことなのだ。
だから何の説明もなく友雅を指名したのだ。
わかってはいても頼久はうなだれていく自分をどうしようもなかった。
ところが、そんな頼久の耳に聞こえてきたあかねの声は予想外に明るいもので、頼久の顔をすぐに上向かせる力を持っていた。
「頼久さんは不甲斐なくなんかないです。そんなこと言わないでください。」
「ですが『さんたくろーす』のお役目は私には過ぎたお役目ということでは…。」
「違います!過ぎたとかお役目とかそんなたいしたことじゃなくて……その…みんなの中で一番年上が友雅さんだったから…。」
「は?年齢が指名して頂く理由だったのですか?」
「そうです。だってサンタクロースっておじいさんだから。」
「お、じいさん……。」
「そうなんです。白い髭のおじいさんなんです。もちろん友雅さんもおじいさんじゃないですけど、でも、一番年上の人にやってもらうのがいいかなと思って。」
「それだけのこと、なのですか?」
「それだけのことですよ。イノリ君なんて身長が足りないし、泰明さんに楽しそうにおじいさんをやってくださいって無理だと思うし、鷹通さんもおじいさんの演技とか無理だと思うし…永泉さんは論外というか…。」
苦笑しながら説明するあかねの言葉の一つ一つがあっという間に頼久の胸の内を晴れやかにしていった。
『さんたくろーす』は年長者がよかった。
それだけのことだったのかとあっという間に頼久はその顔に笑みを浮かべられるようになっていた。
「赤い服を着て白い髭をつけて、それで子供達に贈り物を配ってもらう予定なんです、友雅さんには。子供相手でも友雅さんはそういうこと得意そうな気がしませんか?」
「確かに。」
女性限定ではあるだろうが贈り物をすることにかけては友雅の右に出る者はいないだろう。
そう思えばなるほど『さんたくろーす』には友雅が適任と現金なもので頼久もすんなり納得できた。
「当日は子供達がたくさん集まってくれてるはずなので、頼久さんも贈り物を配るのは手伝ってくださいね。」
「承知致しました。おまかせください。」
「よろしくお願いします。」
すっかり胸の内のわだかまりが消えてみれば、あかねの笑顔は何よりも頼久の目には眩しく映った。
目の前の愛しい妻の一言、表情の一つでこんなにも気分が上下する自分に呆れながら、それでも頼久はこの後、幸福な一時を過ごすことができた。
「特別な報告はないようだな。今日はこれまでとする。」
頼久は部下の報告を聞いて指示を出し終わるとすぐにそう言って立ち上がった。
今夜は特に冷え込んでいるから早くあかねの屋敷へ帰って側にいなくてはと焦っていたからだ。
ところが、そんな頼久に先日『さんたくろーす』の一件で口を開いた若者が再び頼久を呼び止めた。
「若棟梁!」
「どうした?何か報告漏れがあったか?」
「いえ、その…先日の『さんたくろーす』なるお役目のことですが…。」
「それならば友雅殿が立派につとめられた。何か問題があるのか?」
「問題があるというわけでは……その…当日はたいそう珍しい出で立ちで、橘少将様は……翁のような姿であったと今、京中の話題になっているのですが…それはまことでしょうか?」
「ん?ああ、まあ、そうだな。翁といえば翁といえるだろう。」
クリスマス当日、あかねが用意した白い髭と赤い衣装を身に着けた友雅は何とも言えない顔で京の町を歩くことになった。
その顔を思い出すと思わず口元が綻びそうになるのを頼久は必死にこらえなければならないほど友雅の姿はいつもの艶やかな姿とは違いすぎた。
そのかっこうで京を歩き回ったのだから噂になるのは当然だろう。
「では、神子様はもしや、若棟梁にそのようなかっこうはさせられぬとお気遣い下さったのでは…。」
若者の目が希望で輝くのを見て頼久は苦笑した。
武士団の若い武士としては自分の尊敬する若棟梁が神に愛でられし神子に特別扱いされていると思いたいのだろう。
だが、あかねという女性はそんなふうに人を特別扱いするような女性ではない。
逆に友雅を貶めるために『さんたくろーす』に指名するような女性でもないことは頼久が一番良く知っている。
何しろ『さんたくろーす』に抜擢された理由は元八葉の中で最年長だったから、なのだ。
「神子殿はそのように人を贔屓なさったり蔑んだりなさる方ではない。」
「はぁ…。」
「翁の役故に神子殿がこのお役目を託せると思う人物の中で最年長の者を選ばれただけのことだ。」
「最年長、なるほど…。」
「お前も神子殿から『さんたくろーす』のお役目を賜りたいのなら早く年をとることだな。」
「はぁ…。」
照れたように苦笑する若者に微笑を浮かべて見せてから頼久は武士溜まりを後にした。
クリスマスの夜、あかねはとても楽しそうだった。
微妙な表情の友雅は気の毒だったが、それでもあかねが望むとおりの『さんたくろーす』を友雅は演じきったようだった。
子供達はあかねが用意した贈り物を喜んで受け取り、元八葉の面々も楽しそうな子供達とあかねの姿に満足だった。
もちろん、あかねが幸せそうなのだから頼久も幸せだった。
だが、頼久が今上機嫌なのは『くりすます』の宴がうまくいったからではない。
宴が終わって屋敷へ帰って来てから、あかねが頼久にだけ『くりすます』の贈り物を贈ってくれたからだ。
頬を赤くしながら「クリスマスは向こうの世界では大好きな人に贈り物をする日でもあるんです。」と言ってあかねが渡してくれた単衣は渡された瞬間から頼久の宝となった。
それをどうして着てくれないのかと悲しい顔であかねに詰め寄られるのはもう少し後のこと。
大切にしまってあるのだと真剣に答える頼久に怒ってあかねが大量の単衣を頼久のために仕立て始めるのは更に後の事だった。
管理人のひとりごと
メリークリスマス!(^^)
クリスマスは25日だから!
24日はイブだから!(ノД`)
ということで、すべり込みセーフなのかアウトなのか微妙なUPになってます○| ̄|_
すみません、さすがに師走は忙しいです…
でもね、せっかくのクリスマス1本くらいはどうしてもUPしたかったんで、急いで一本書きました。
誤字脱字はご容赦くださいm(_ _)m
ブラウザを閉じてお戻りください