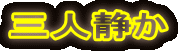
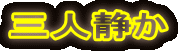
昼、ちらほらと降り始めた雪は夕方には本降りになった。
そしてその雪は陽の光が去りゆくのと共に止んで、今は冴えた冬の空に月が煌々と昇っている。
あかねは澄み切った月明かりに照らされている雪景色を御簾越しに眺めていた。
雪が積もった庭は今、月に照らされて幻想的な輝きを見せていた。
京の夜はあかねが育った世界のように明るくはない。
月がなければ本当の闇になる。
けれど、だからこそ、月明かりを反射する雪の庭は闇の中で美しくふわりと輝いて見えた。
「寒くはありませんか?」
そう言いながらやってきたのは頼久だった。
手にはあかねが返事をしなくても袿が一枚握られている。
「寒くはないです。今日は風もないですし。」
答えるあかねの肩にふわりと袿をかけて、頼久はあかねの隣に座ると共に庭へと視線を巡らせた。
「綺麗ですよね、夜のお庭も。」
「はい。」
楽しそうな声に頼久も即答して、その顔に笑みを浮かべた。
幼い頃から剣の修行ばかりして、しかも男ばかりの武士団で育った頼久は自他共に認める朴念仁だ。
風流を解するなどということは苦手中の苦手だ。
それでも、愛しい妻と二人並んで見る庭は無条件に美しいと感じた。
「それにしても…。」
頼久が妻と二人の夜を楽しんでいると、突然、あかねがその声を曇らせた。
辺りをきょろきょろと見回して小首を傾げる。
「どうか致しましたか?」
「ずいぶん静かですよね。お年越なのに。」
そう、本日は大晦日。
本来なら行事がたくさんあって、それ以外にも挨拶に来る客を出迎えたりと忙しいはずなのだ。
ところが、行事の気配どころか人の気配さえ感じられないことに気付いて、あかねはきょろきょろと落ち着きなく辺りを眺め始めた。
頼久はその口元に優しい笑みを浮かべると、きょろきょろしているあかねの体を抱き寄せた。
「頼久さん?」
「本日は誰もこの屋敷へは来ないようにと藤姫様が気を使ってくださいました。」
「へ…誰も来ないんですか?」
「はい。あかねは今年は一人の体ではありません。負担がかかってはいけないので、今年は二人きりで静かに新年を迎えるようにと藤姫様が。」
「そ、そんなことになってたんですか。」
「はい。」
「そんなに気を遣わなくても大丈夫なのに…。」
「せっかくの藤姫様のお心遣いです。今宵はゆっくりと静かに新たな年を迎えることと致しましょう。」
「そう、ですね。」
あかねはこの夏の終わりに頼久の子供を授かった。
つまり、今現在もお腹の中には子供がいるということだ。
あかね自身は病人ではないし、そんなに大げさにしなくてもいいと思っているのだけれど、こうして気遣ってもらうことは多い。
確かに今の体で多くの客の相手をしたり、行事に参加したりは少し辛かったかもしれない。
そんなことを考えて藤姫の心遣いと頼久の優しさに感謝していると、その頼久があかねを自分の膝の上に乗せて優しく抱きしめた。
「よ、頼久さん?」
「せっかく二人きりなのですから。」
耳元でそう囁かれて、あかねは顔を真っ赤に染めた。
抱きしめられることなど今までにも数えきれないほどあるけれど、今でもあかねはこうして頼久の艶っぽい声を耳元で聞くと顔を赤くせずにはいられない。
体全体で感じる優しい温かさはあかねをいつも安心させる。
すっかり顔を赤くしたその後で、あかねは頼久の体から感じる温もりに微笑んだ。
それはこれまでいつも自分を守ってくれた温かさだ。
そしてきっとこれからもずっと守ってくれると信じている温かさでもある。
あかねが冬の夜の寒さをすっかり忘れてうっとりしていると、再び耳元で頼久の声が聞こえた。
「お疲れでしたらこのまま眠って頂いても構いませんので。」
「そんな、せっかくのお年越なのに…。」
「あかねの体が一番大事です。それにここには二人きりですので誰に気兼ねすることもありません。」
「それはまぁ、気兼ねはしてませんけど…。」
「私はもう二人きりの夜を楽しませて頂いておりますのでお気になさらず。」
優しく低く響くその声に、あかねは思わず身を起こすと、きりっと頼久をまっすぐ見つめた。
突然のあかねの変化に頼久が小首を傾げる。
「何かお気に障りましたか?」
「こ、今年は二人きりじゃありませんから…。」
「は?」
「その……三人ですから、忘れないでくださいね?」
そう言ってあかねがそっと少し大きく見えるようになったお腹に手を置くのを見て、頼久はすぐに幸せそうな笑みを浮かべた。
「もちろん、忘れるはずなどありません。」
すぐにそう言葉を紡いだ頼久の大きな手が、あかねの手の上に置かれた。
膝の上に妻がいて、その妻のお腹に自分の子がいる。
こんな幸福を自分が味わう日が来ようとは、頼久はあかねに出会うまで想像もしていなかった。
親子三人きりで迎える初めての年はきっと思い出に残る一年になるだろう。
そう実感しながらも、頼久はあかねの上に乗せていた手をそっとあかねの髪へと伸ばした。
「このように幸せに新たな年を迎えるのは生まれて初めてです。」
「お、大げさですよ…。」
「いえ、決して大げさなどではありません。真実、心からこの幸福を与えてくださったあかねに感謝しています。」
「本当に大げさですから…その…私も幸せだからお互い様です。」
二人でそうして幸福を告げ合って、そのあとはもう言葉もなく微笑を交わすと、どちらからともなく身を寄せて庭を眺めた。
そうして黙って座っていると、やはりあかねは睡魔に襲われて…
髪をなでる大きな手の優しさに安心して…
あかねは年が明けないうちに頼久に寄りかかって静かに寝息をたて始めた。
しばらくはその愛らしい寝息を聞いていた頼久は、寝息が規則正しくなってきたところでそっとあかねを抱えて立ち上がる。
大事に大事に妻を抱えた頼久の足が向かうのは奥の寝所だ。
寒い夜に御簾の前で妻を寝かせるなどとんでもない。
奥の寝所にその小さな体を横たえて、頼久自身は幸せそうに眠るあかねの寝顔を見つめながら新しい年を迎えるつもりだ。
そしてそのまま、あかねの側で自分も眠りにつく。
そんな当たり前のようなことの一つ一つに幸せを感じながら、頼久の足は音も立てずに奥の間へとあかねを運んで行った。
翌日、新しい年を迎える前に眠ってしまったと不機嫌なあかねだったが、新年の挨拶に元八葉の面々がやってくるとその顔にはすぐに笑みが浮かんだ。
龍神の神子として京を救ったあかねの周りには、新たな年もまた、愛しい人と大切な仲間達があふれていた。