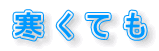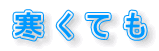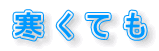
あかねは雪の中をゆっくりと歩いていた。
冬の寒さは確かにつらいけれど、たまに見る雪はとても綺麗で大好きだ。
たまには頼久さんと外をお散歩とかしてもらおうかな?
そんなことを考えながら歩くとどうしても自然と顔が微笑んでしまう。
京にいた頃は、全てが終わったらどうしようとか、そんなことも考えてしまってあまり余裕がなかった。
でも、今は違う。
源頼久という人がそばにいてくれるだけで、こんなにも自分の精神状態は違うものかとあかね自身、自分でも驚きだった。
京に行くまでの自分と今の自分を比較してみるととても同じ人間とは思えないほど変わったところがたくさんある。
京では色々な経験をしたから成長したといえばそうなのかもしれない。
でも、やっぱり頼久との出会いはその中でも一番大きな出来事だったと、あかねは最近改めて思うことが多かった。
同じ世界にいて、もう離れ離れになることなんてありえないのに、それでもあかねの心は頼久の言葉一つ、表情一つで揺れ動く。
何をするにも頼久と一緒にいること、頼久に喜んでもらえることが前提だ。
そうやってみれば源頼久という一人の人間があかねに及ぼす影響の大きさは計り知れない。
あかね自身、それをこの一年近い時間の中で再確認したのだった。
以前なら友達と遊びに出かけていた週末もこうして頼久の家へ向かって歩いている。
週末、頼久の顔を見ないことはほとんどなかった。
「神子殿、ようこそおいでくださいました、中へどうぞ。」
考え事をしながら歩いていたあかねが家の扉の前へ立っただけでいつものように頼久が顔を出す。
あかねは嬉しくてにっこり微笑んで中へと入った。
「今日も冷え込んでますよ〜。」
「明け方から雪も降っているようですね。」
「頼久さんはそんな時間から鍛錬してたんですか?」
「はい、まぁ…。」
リビングへと移動しながら返事をする頼久が珍しく歯切れが悪いのであかねはコートを脱ぎながら小首をかしげた。
「頼久さんが早起きなのは知ってますけど、明け方って、今日はいつもより早く鍛錬してたんですか?」
「…目が…覚めてしまいましたので…。」
「寒かったんですか?」
「いえ…その…神子殿にお会いできるかと思うとその…。」
嬉しさが先に立って目が覚めてしまったということらしい。
あかねはクスッと笑みをこぼして、それからすぐに小さくくしゃみをしてしまった。
どうやら外の寒さは思った以上にあかねの身に染みていたらしい。
すると、つつと歩み寄った頼久があかねの体を優しく抱きしめた。
「よ、頼久さん?」
「すっかり冷えておしまいですね。」
「そ、外寒かったから…。」
ギュッと抱きしめられてしばらく動けなくて。
最初はドキドキしていたあかねも頼久が静かに抱きしめてくれるとしだいにぬくもりが伝わって心地良くて、うっとりと目を閉じた。
手を握ってくれる頼久もこうして抱きしめてくれる頼久も、いつだって頼久は温かい。
「廊下でこうしていては寒いですね、中へどうぞ。」
苦笑しながら頼久がそう言ってあかねを解放する。
あかねは少しだけ残念な気がしながらも「はい」と返事をしてリビングへと足を踏み入れた。
するとそこには…
「頼久さん?」
「はい、なんでしょうか?」
「これはひょっとして…コタツ、ですか?」
「はい、神子殿が先日、冷え性で足が冷たいとおっしゃっておいででしたので購入してみました。」
「ええっ!わざわざ買ってくれたんですか?!」
「これで神子殿には冬も快適にお過ごし頂けるかと。」
「す、すみません、私、そんなつもりで言ったんじゃなかったんですけど…コタツってちょっと憧れるなぁと思っただけで…。」
「いえ、これがなかなか快適でして、私も普段は使うようになりましたのでお気になさらず。」
「で、でも、これ入れるためにテーブル動かしたりとか大変だったでしょう?」
「いえ、天真が手伝ってくれましたし、それに神子殿にお喜びいただけるならこれしきのこと。」
そう言って頼久は嬉しそうに微笑んだ。
満面の笑みで楽しそうにされてはあかねもこれ以上何を言うこともできない。
だから、あかねはコートとバックをソファの上に置くと、そろそろとコタツに足を入れてみた。
「うわぁ、あったか〜い。」
思わずそう言ってニコリと笑みを浮かべると、頼久は笑顔のまま黙って台所へ向かった。
「あ、頼久さん、お茶なら私が…。」
「いえ、神子殿はそのあままコタツに入っていてください。茶と茶菓子はすぐに私が。」
どうやらコタツに入って喜ぶあかねの姿がよほど嬉しいらしい頼久は、すぐに台所でお茶を入れると茶菓子とともにあかねの前に置いた。
「すみません。」
「お気になさらず。」
そう言って微笑みながら頼久はあかねの向かい側に座って足をコタツに入れた。
「いいですねぇ、コタツ、凄くあったかい。」
「はい。」
「はぁ、なんか幸せ〜。」
あかねは本当に幸せそうな笑顔でほっと小さく息を吐いた。
「コタツって鬼をも眠らせる力があるって聞いたことありますけど、本当かも。」
「鬼も眠らせる、ですか?」
「はい。それくらいきもちいいってことです。で、暖かいから眠くなるって。」
「あぁ、確かに、そうかもしれませんね。」
「今までは冬って寒くていやだなぁって思うことけっこうあったんですけど、コタツがあればそうでもないかも。」
そう言って本当に幸せそうにあかねはお茶を口にした。
可愛らしく両手で湯飲みを持つあかねが愛しくて頼久の顔からは笑みが絶えない。
「はぁ、お茶もなんかいつもよりおいしい気がします。幸せ〜。」
そう言ってニコニコと微笑んでいたあかねははっと何かに気付いたように目を見開いてじっと頼久を見つめた。
その顔があまりにも真剣で頼久が目を丸くする。
「神子殿?どうかなさいましたか?」
「えっと……頼久さん。」
「はい?」
「その…あの…。」
何かいいづらそうにしながらあかねの顔はどんどん赤くなっていく。
「コタツの温度が高いですか?」
「はい?あ、えっと…そうじゃなくて…。」
頼久はすっかりコタツが暑くてあかねの顔が赤くなったのかと思ったのだが、どうやらそうではないらしい。
「あのですね…せっかくのコタツだし…足を入れたりとかしてるわけだし…その……頼久さんと隣に並んでコタツに入りたいな、なんて…あの、頼久さんの隣へ行ってもいいですか?」
そう言ってうつむくあかねの顔はもう真っ赤だ。
頼久は嬉しそうに笑みを浮かべると何も言わずにあかねの隣に座り、コタツへ足を入れた。
そんなに大きくないコタツに二人並んで入れば、もちろん足や肩が触れ合うわけで…
自分から言い出したのだけれど、あかねはなんだか恥ずかしくなってしまって顔を上げられない。
「暖かいですね。」
「へ?あ、はい…。」
二人並んでコタツに入っていればそれはもう暖かさは二倍だ。
それだけではない。
いつも家に一人でいる頼久としては、こうしてあかねが隣にいてくれるだけで心の内が暖かくなった。
コタツの暖かさだけではなく、触れ合っている部分からあかねのぬくもりが伝わる。
そのことがあかねが今自分の側に、真実いてくれるのだと教えてくれるのが頼久にとっては何より嬉しい。
「ほ、本当にあったかいですね、コタツ。」
「はい。」
やっとの思いであかねが顔を上げて隣の恋人を見れば、そこにはこれ以上ないほど幸せそうにしている端整な顔があって…
あかねはまた顔を赤くしてうつむいてしまった。
普段はテレビを見ないという頼久の家のリビングはとても静かだ。
あかねがDVDを持ち込んだりテレビを見たいといわない限りほとんど音がしない。
そんな静かな部屋の中で二人きりでコタツに足を入れて並んで座っている。
それを意識すればするほどあかねはなんだか緊張してしまって…
「神子殿。」
「は、はい!」
呼ばれただけで思わず大きな声で返事をしてしまったあかねは、更に恥ずかしくて顔を上げられなくなってしまった。
「今日は何かお持ちではないのですか?」
「へ、あ、あぁ、えっと…今日は別に何も…お花見じゃなくて雪見とかどうかなって思ってたんですけど…。」
頼久が窓の方へ視線を向けると、確かに雪が降っている。
「確かに雪は降っていますが、雪見ですか?」
「風がない時の雪って凄く綺麗じゃないですか?桜の花が散っていくのに似てるなぁってこの前思って、それで…。」
「なるほど、では、もう少し温まったら雪見を致しましょうか。」
「はい!」
今度は張り切って返事をして、顔を上げたあかねは嬉しそうに微笑んだ。
「では、今しばらくコタツをお楽しみ下さい。」
「それはもう!とっても楽しんでます!」
「それは何よりです。」
そう言って頼久はそっと優しくあかねの肩を抱き寄せた。
少しだけ驚いたあかねはすぐに小さく吐息を漏らすと、ゆったりと頼久の胸に頭を預けて目を閉じた。
コタツは確かにぽかぽかと足を温めてくれるけれど、今のあかねには自分の全てを温めてくれる頼久のぬくもりの方が幸せで…
あかねはうっとりと頼久のぬくもりに甘えるうちに、いつの間にか意識を手放していた。
あかねはゆっくり目を開けて辺りを見回した。
部屋が薄暗いのはどうやら天気が悪いかららしい。
隣に座っていたはずの頼久の姿はなくて、あかねは足をコタツに入れたままその場に横になって眠っていた。
上半身にちゃんと毛布をかけてくれたのは頼久だろう。
その毛布をそっとよけて頼久の姿を捜すと、その背中は窓辺にあった。
見慣れた広い背中は微動だにせず窓辺に立っていた。
あかねはほっと安堵の溜め息をついて立ち上がった。
「神子殿。」
「すみません、私、コタツがあったかくて寝ちゃったみたいで…。」
「いえ、お気になさらず。それよりも、雪が。」
頼久がそう言ってあかねを窓辺へといざなう。
あかねは頼久の隣に立って窓から外を眺めた。
「うわぁ、きれい。」
「はい、本当に。」
「今日は風がないから静かにゆっくり降って来ますねぇ…でも…。」
「何か?」
「窓ガラスが反射して…。」
「あぁ。」
光が反射して外が見づらいことに気づいて、頼久はすぐに窓を開けた。
「うわぁ、すっごくきれいです!」
窓から上半身を出しそうな勢いであかねが飛びつくのを頼久はただ微笑んで見守った。
雪が降っている。
ただそれだけのことにこれほどまでに感動できる純粋な心の持ち主こそがあかねなのだ。
そのあかねの側にいることを許された自分の身が幸せだと実感する。
あかねは今でも頼久に京を捨てさせたことを気にすることがあるが、頼久自身はそのようなことを気にしたことは一度もない。
こうしてあかねの側で見守ることができることこそが幸せなのだ。
「凄くきれいなんですけど…。」
「どうかなさいましたか?」
今まではしゃいでいたあかねの声が急に低くなったので頼久は慌てた。
この少女の気分を害するような何があったのだろうか。
「えっと、当たり前のことなんですけど…寒い、ですね。」
そう言ってあかねは自分の肩を抱いて苦笑した。
「ずっと見ていたい気もするんですけど、そうすると風邪ひいちゃいそうだから閉めますね。」
「いえ、今しばらく。」
頼久は残念そうに窓に手を伸ばすあかねの背後に回ると、後ろからあかねをすっぽりと抱きかかえた。
「よ、頼久さん?」
「こうしていればもうしばらくは雪を眺めていられるかと。」
「そ、それは…まぁ…そうなんですけど…。」
「お嫌ですか?」
あかねは激しく首を横に振って否定した。
自分をやわらかく抱きしめてくれる頼久の腕はとても優しくて、背中に感じる頼久の体温はとても温かい。
心地いいと思いこそすれ、嫌だなどということは絶対にない。
絶対にないのだが、恥ずかしくて顔が赤くなるのも止められなくて…
「京では…。」
「はい?」
「雪が降ると何やら物悲しい心持がしたものですが、こうして神子殿と二人で見る雪は全く違うものであるかのようにいいものですね。」
「そ、そうですか?」
「はい。」
頼久が腕にそっと力をこめると、あかねはその腕に軽く手を乗せて微笑んだ。
雪も花も、二人で見ることがいいと言ってもらえる。
そのことが何より嬉しい。
「さぁ、冷えてしまいますね、そろそろ…。」
そう言ってあかねを解放しようとした頼久は自分の腕がしっかりとつかまれていることに気づいた。
「神子殿?」
「大丈夫ですよ、冷えたらコタツがあるし、頼久さんがこうしててくれればそんなに寒くないです。だから、もう少しだけ。」
「御意。」
小さな恋人の嬉しい申し出に頼久の顔にも自然と微笑が浮かんだ。
窓の外には静かにゆっくりと降り積もる雪。
腕の中には二度と離れぬと決めた愛しい人。
頼久は今の幸せを優しく抱きしめて、恋人がもういいと言うまでこうしていようと一人胸の中で誓うのだった。
管理人のひとりごと
我が家にはコタツがあるので(笑)
寒い時期はこれがいいよなぁやっぱりとふと思い立ちました。
まぁ、この二人にかぎって言うとコタツなんかなくても暖かそうですが(’’)
どうしてコタツの話になったのかの導入部分はいつか拍手御礼SSかなんかでやるかもしれません(w
気長にお待ちくださいませ♪
プラウザを閉じてお戻りください