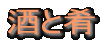
「お、お許しをっ!」
板の間に額を擦り付けんばかりにして若い武士がひれ伏すのを頼久は氷よりも尚冷たい視線で見下ろしていた。
左手は既に太刀を納めてある鞘にかかっている。
「許せると思うか?」
決して昂ぶってはいない、けれど、だからこそ腹の底から恐怖を引き出すような低い怒りに満ちた声に若い武士は「ひっ」と息を飲んだ。
「私がこの場にいないことをいいことに、神子殿の話を酒の肴に酒を飲むとは言語道断。そこへ直れ。」
「そ、そればかりは…。」
「情けをかけてやると言っているのだ。抜け。」
ひれ伏すばかりの若者は冷や汗を床に滴らせながらひたすら頭を下げるしかない。
情けをかけてやると言われても、今頼久によってかけられているのは情けというよりは拷問のように思える。
何故なら、彼は今、この若い武士に対して剣を抜けと言っているからだ。
無礼を許さん、討ち取ってくれると言われた方がどれほど若者にとって楽か知れない。
怒り狂った若棟梁と真剣で勝負など、拷問以外の何ものでもなかった。
しかし、怒りが頂点に達している頼久に、若者のそんな想いが理解できるわけもなく、実質的に武士団を束ねているといってもいい若棟梁の視線はゆるぎなく、ひれ伏す若者の背に注がれていた。
事の起こりは酒宴にある。
今ここは土御門の屋敷の武士溜まり。
床には酒と料理が並んでいて、武士団の武士達は酒宴の真っ最中だった。
左大臣を襲おうとしたらしい不逞の輩を軽く撃退し、左大臣から褒美を賜ったその祝いの宴だ。
酒が入ると男達は普段よりは饒舌になるし、話の内容が下世話になることもしばしばだ。
頼久は酒宴そのものも仲間達の楽しそうな姿も嫌いではないが、この下世話な話というのが苦手で酒宴を欠席することが多い。
特に、愛しい妻を屋敷で待たせている今となっては酒宴の席には最初の数分はその姿を見せたとしても、宴もたけなわという頃にはいなくなっているのが常だった。
すると、武士達の話題はそんな妻想いの若棟梁のことへと移っていき、話が転がるとあれほど剣の道に一筋だった男を籠絡した若妻のことも話題に上る。
京では珍しくこの若棟梁の新妻というのが武士団の面々の前にも颯爽と姿を現し、愛らしい姿を誰もが一度は見たことがあるものだから、話はいやが上にも盛り上がった。
そして、頼久の目の前にひれ伏す若者はどんなに酒が入っていたとしても話題にしてはいけないことを口にしてしまったのだ。
すなわち、頼久の命よりも大事な新妻の閨について。
小さく愛らしく、それでいて凛々しくもあるあの天女と添い伏すのはどれほど心地よいものなのだろうか。
などと口に出してしまったのだ。
いつもなら年長の者が若者をたしなめればすんでいたかもしれない。
ところが、この夜に限って頼久が酒宴に顔を出した。
普段は酒宴に出ない頼久が宴もたけなわになった頃に顔を出したのにはわけがある。
一度は屋敷へ帰って愛しい妻の顔を見た頼久、すぐにその妻に送り出されることになったのだ。
己の命どころか世界の何よりも大切な彼の妻曰く、武士団のみんなとも仲良くしてあげてください。
こう言われては頼久も妻の気遣いを無駄にすることはできない。
渋々屋敷を出て酒宴に顔を出した途端に若者の不埒な発言が耳に入ってしまったものだから、頼久の怒りは一気に頂点に達した。
怒れば怒るほど、怒鳴り散らすでもなく、暴れるでもなく、ただ静かに太刀に手を添えて低い声を漏らすこの武士の恐ろしさはちょっとやそっとのものではない。
若者がひれ伏したまま動けなくなったのもしかたのないことなのだが、それが頼久に理解できるわけもない。
「若棟梁、ここは、まだ未熟な若者のことですので、どうか…。」
「年若くとも、許されることと許されぬことがある。神子殿は我が妻である以上に、この京をお救い下さった尊きお方。そんなお方を酒の肴にするだけでも無礼だというものを、ましてや先程のような……。」
そこまで言って頼久はその先の言葉を飲み込んだ。
ここでもう一度同じ言葉を繰り返すことも忌まわしいといった様子だ。
間に入ろうとした年長者さえ頼久の全身から発せられる怒気に気圧されて、黙り込んでしまった。
「お前も武士ならば立って刃を手にするがいい。」
これはダメだ。
それがこの場にいる全員の一致した意見だった。
周囲を取り囲んで黙り込んでいる武士達は互いに顔を見合わせてため息をつく。
一見落ち着いて見えるが、実はかなり暴走してしまっているらしいこんな頼久をもし止めることができるとしたら、それは今話題の新妻の存在以外にありえない。
そのことを悟った年長のうちの一人が静かに立ち上がって武士溜りを後にした。
「神子殿、御在宅かな?」
御簾の内側で頼久の帰りを待ちながら頼久の衣を仕立てていたあかねは、聞き慣れた声に小首を傾げた。
先触れもなく仲間達がやってくることはままあることだけれど、こんな時間にいきなりやってくることは珍しい。
口調から察するに、差し迫った何かがあったというわけでもなさそうだ。
それでも、こんな時間にわざわざ訪ねてくるということは、きっと急ぎの用事があるのだろうとあかねは思い切って御簾をくぐった。
「こんばんわ、友雅さん。こんな時間に何かあったんですか?」
月明かりに照らされるあかねの姿に友雅は目を細めた。
頼久の妻となってしばし、最初に出会った頃よりはずいぶんと大人びたあかねは月明かりの下では驚くほど美しい。
「これは珍しい、神子殿が御自ら御簾の外へとお出まし下さるとは。」
「またそんなこと言ってからかわないで下さい。何か急ぎの用事があるんじゃないんですか?あ、頼久さんなら土御門の武士溜りで宴会ですけど。」
「ああ、それなら知っているよ、私は今、その土御門から来たのだからね。」
「藤姫のところにいたんですか?」
「そんなところだよ。陽も暮れたから屋敷に戻ろうとしたところでちょっと小耳に挟んだ話があってね、神子殿にお知らせに参上したというわけさ。」
「小耳に挟んだ話、ですか?」
「そう、私には面白いばかりの話だったが、神子殿には知らせておいた方がいいかと思ってね。」
「はぁ…あ、お酒とか飲みますか?」
「是非お願いしたいところだけどね、まあ、とりあえず話を終わらせてしまおうか。」
「あ、はい、どうぞ。」
すっかり御簾から濡れ縁へとその身を移したあかねは姿勢をただして友雅を正面から見つめた。
そんなあかねの隣に優雅に腰掛けると、友雅は扇を手にさも楽しげに語りだす。
「実は今日は良い薫りの香が手に入ったので、藤姫にいくらか献上しに行ったのだけれどね、その帰りになんだか武士溜りがとてもにぎやかでね。」
「あ、はい、今日は左大臣さんの警護でみんなが頑張って、左大臣さんからご褒美をもらったお祝いをしてるはずなので。」
「そうらしいね。武士溜りから出てきた武士に聞いたよ。」
「話って、そのことじゃないんですよね?」
「ああ、そうだね。武士溜りは確かに宴会場になっていたらしいのだけれどね、どうにも騒がしさが宴会という感じじゃなかった。それで捕まえた武士に聞いてみたんだよ、宴会中に何か問題でもあったのかい?とね。」
「えっ、何かあったんですか?」
一瞬であかねの顔に不安の色が広がった。
せっかくの楽しい宴会のはずなのに、そしてそこには大切な旦那様が出席しているはずなのに、何か大変な問題が持ち上がったのだろうか?
そんなことを考えて表情を曇らるあかねに友雅は艶やかに微笑んで見せた。
「ああいや、神子殿がそんなに心配するほどのことじゃないよ。私には面白いばかりの話だと先に断っただろう?」
「あ、そうでした…。」
「まあ、当事者達には笑い事ではないかもしれないけれどね。」
「はぁ……あの、何があったんですか?武士溜りで。」
「頼久がね。」
「頼久さんが?」
「暴走しているらしい。」
「はい?」
あかねが目をまん丸に見開いてきょとんとすると、友雅がクスッと笑みを漏らした。
「暴走って…はい?」
「若い武士を相手に自分と勝負せよと詰め寄っているらしい。」
「はいぃ?なんでそんなことに…頼久さんはそんなことする人じゃ…。」
「まあ、女神ともあがめる自分の妻が酒の肴にされていた上に、夜の生活がその話題の中心だったとなれば、頼久が怒り狂うのもわからなくはないけれどね。」
「………ええっっ!」
酒の肴だの夜の生活だのという友雅の歯に衣着せた物言いの部分をじっくり考えて理解して、あかねは慌てて飛ぶように立ち上がった。
それは、今の話は、総合すると自分のために頼久が仲間を相手に喧嘩を売っているということになると理解したからだ。
「そんなことになってるなら早く話してください!止めにいかないと!」
言うが早いかあかねは素早く御簾の向こうへ姿を消した。
友雅はクスクス笑いながらその背を見送って、優雅に月を見上げた。
水干を着込んだあかねがすぐに飛び出してくることは間違いない。
一人で行かせることなどもちろんできないから、友雅は異界からやってきた天女を無事夫のもとへ送り届ける役目を果たすつもりで、今は柱にもたれるのだった。
武士溜りには緊張が張り詰めていた。
床にひれ伏したまま動けずにいる若者のその頭上には鈍く光る剣先が揺れている。
痺れを切らせた頼久がついに抜刀した結果だ。
明らかに殺気を宿した頼久を止めようと、何人もの仲間達が間に割って入ろうとしたが、全て無駄だった。
ただし、時間を稼ぐことには成功した。
だから、頼久がとうとうひれ伏して謝るばかりの若者を無理にも立たせようとその足を一歩踏み出した刹那、声は聞えた。
「頼久さん!」
続いて聞えてくる愛らしい足音の後に、その小さな姿は現れた。
水干に身を包み、長くなった髪を後ろで束ねているあかねだ。
背後には面白くてしかたがないという様子がその表情からすっかり見て取れる友雅の姿もある。
この思いがけない二人の人物の登場に、頼久を取り巻いていた武士達は安堵の溜め息をつき、頼久は驚きで息を飲んだ。
「神子殿…。」
「よかった、間に合った。話は聞きました。もうその人、許してあげてください。」
「話…。」
頼久の刃を含んだ目があかねの背後に立つ友雅へと向けられる。
「私はここから抜け出してきた武士の話を聞いたとおりに神子殿にお伝えしただけだよ。」
賊であれば視線だけで背筋を凍らせるだろう頼久の視線を軽く受け流して、友雅は近くの柱にもたれるとクスッと笑みを漏らした。
どうにもこの状況がおかしくてしかたがないらしい。
友雅に何か一言言ってやりたくても、そもそも口下手な頼久にそれが可能なわけもなく、そうこうしているうちにあかねがいまだ床にひれ伏したままの若者と頼久の間に立った。
「お酒の席でのことじゃないですか、私、別に宴会で話題にされても嫌じゃないですから。みんな家族みたいなものなんだし。」
「いいえ、ただの噂話ではございません。神子殿を愚弄するような話をするような輩は断じて許せません。」
一瞬、年長の武士達もこれは神子殿でも無理なのか?と冷や汗をかいた。
それほど頼久の言葉には力があったし、言い放たれた言葉には一歩も譲らないという気概がこもっていた。
ところが…
「愚弄するようなお話だったんですか?」
あかねが周囲を見回しながらそう質問したものだから、頼久の表情が一変した。
目の前の妻の言葉が予想だにしないものだったからだ。
異界からやってきたこの天女は頼久はもとより、友雅や鷹通にも予想できない行動に出ることがある。
今がまさにその時だった。
「その…神子殿はいつも我らにまでお優しく、天女のようなお方ゆえ、おそらく褥の中でもしなやかでお美しく、その身を抱くことができれば天にも昇る心地であろうと…こいつはそのような話をしておりました。」
どうやら若者の隣で話を聞いていたらしい武士がそう報告すると、あかねは一瞬で顔を真っ赤にした。
「そ、そんな、天女とかそんなに凄くないですし…それにその…普通です!普通!天にも昇るとかそんな…っていうか、それ、愚弄なんてしてないじゃないですか。」
「いいえ、神子殿の褥での姿を想像するなど言語道断です。」
「想像くらい別に……されてると思うと恥ずかしいですけど、想像なんてされてるってわからなければわからないし……あれ、私、何言ってるんだろう…。」
「第一、神子殿は彼が想像している以上にお美しく、たおやかで、その身をこの腕に抱いただけで天に昇るどころの…。」
「ストップ!頼久さんストップ!」
このまま放っておくととんでもないことまで話し出しそうな頼久を必死で止めて、あかねは深い溜め息をついた。
確かにこれは暴走していると言えるかもしれない。
長くあかねと暮らしているおかげで「ストップ」の意味を把握していた頼久は、言葉を切ってあかねの顔をのぞきこんだ。
自分は何か失言をしたのだろうかと、その瞳に不安が揺れる。
「頼久さん、そのままだとこの人よりとんでもないこと話すことになっちゃいますから…。」
「……。」
あかねに指摘されてやっと我に返った頼久は、呻き声ににも似た声を飲み込んでうつむいた。
「とにかく、私は別に宴会の席で噂話されてもかまいませんから、頼久さんも刀しまってください。恐いです。」
「はっ。」
まるで主に命令されたかのように返事をした頼久は、流れるような所作で素早く刃を鞘へと収めた。
こうなればもう形勢は見えたも同然だ。
「さ、皆さん宴会を再開してください。」
「神子殿のお許しが出たからね、私も手土産を持ってきた。皆で飲み直してくれ。」
あかねが笑顔で宣言すると、背後で黙って見守っていた友雅が手を叩いた。
するといつの間に用意させたものか新しい酒と料理が次々に運び込まれた。
これにはこの場の武士達も大喜びで、あっという間に宴会は再開された。
「友雅さん、有り難うございます。」
「いやいや、実際に用意をしてくれたのは藤姫だからね。礼なら藤姫に。」
「はい、明日にでもおいしいもの持って会いに行きます。今日はもう遅いから。」
「そうだね。私は挨拶だけして帰るとするよ。」
「有り難うございました。」
ペコリと頭を下げるあかねに軽く手を上げて答えた友雅は、優雅な身のこなしで藤姫の暮らす局の方へと去っていった。
「友雅さんってほんと、よく気がつきますよね。」
「…………融通が利かず、気の利かぬ男でまことに申し訳なく……。」
「そ、そんなことないですから!」
今度は急速に落ち込み始めた頼久に驚いて、あかねは思わずその腕に抱きついた。
先ほどまでの勢いはどこへやら、今度は地面にめり込みそうなほどに落ち込み始めた頼久は、それでもあかねに腕を抱きしめられてあっという間にその目に光を宿した。
「神子殿…。」
「頼久さんが私のことを大事に思ってくれてるから怒ったんだってわかってますから。それは嬉しかったですから。だから、今日はもう帰りませんか?屋敷に帰って、ゆっくりしましょう?」
「ですが…。」
「私、頼久さんと二人でお月見したいです。」
上目遣いに見上げられてこんなふうにおねだりされて、頼久がうなずかないでいられるわけがない。
あっという間にその顔に嬉しそうな笑みを浮かべた頼久はすぐに表情を引き締めると、まだ床にひれ伏している若い武士へと視線を移した。
「神子殿の慈愛に溢れた御心に感謝するのだぞ。」
「はっ!」
「そ、そんな御心じゃないですから!」
「いえ、感謝致します!」
心の底からあかねに感謝している若者に何かを言い募ろうとするあかねの腕を引いて頼久は歩き出した。
その背に声をかける者は誰もいない。
幸せそうに寄り添う二人の背中を見送った武士団の武士達は、そのどの顔にも笑みが浮かんでいた。
そして見送られた二人は…
「頼久さんってひょっとしてああいう宴会、あまり好きじゃないんですか?」
「宴が好きではないというよりは、酒の席での下世話な話が苦手です。己が想いを寄せた女性を酒の肴にするなど、私にはできませぬゆえ。」
「ああ、頼久さんはそういう人ですよね。うん、頼久さんのそういうところ大好きです。」
「神子殿…。」
「今日は私が参加した方がいいって言ったから無理に出かけてくれたんですよね。これからは屋敷でゆっくりしててください。好きじゃないなら宴会なんて出なくてもいいですから。頼久さんが楽しいこと、してください。」
「それは、神子殿のお側に置いて頂くことこそ私の幸福ですが、しかし……やはりたまには宴に顔を出そうと思います。」
「あ、ちょっと楽しそうとか思ったんですか?」
「いえ、放っておくとどのような話をしているかわかったものではありませんので。」
「あはははは。」
あかねは思わず乾いた声で笑ってしまった。
どうやら頼久、今日の騒動を忘れてくれたわけではないらしい。
「でも、私だって本当は頼久さんと一緒にいる時間、長い方がいいんですよ?」
「そう、なのですか?」
「当たり前じゃないですか、大好きな旦那様と一緒にいたくない人なんていませんよ。ただ、独り占めしちゃいけないかなって思ってもいて、だから今日は宴会に出てくださいってお願いしただけで……。だから、出なくていいなら宴会に出ないで側にいてほしいです。」
「神子殿……承知致しました。神子殿のお望みのままに。」
「有り難うございます。まずは、お屋敷に帰って、二人でお酒飲みましょうね。」
「はい。」
二人は笑みを交わすと屋敷へ向かう足を速めた。
今はただ、二人きりの時間を過ごすことだけが楽しみで…
そして頼久は、たまに酒を口にした時の色っぽいあかねを想像してしまっている自分に苦笑した。
明日はあの若者を許してやらなくてはならないな。
頼久は心の中でそうつぶやいていた。
管理人のひとりごと
いや、頼久さんが喧嘩を売るところを書きたかっただけというか…(マテ
まあ、真剣勝負を常にやってる人だとは思うんですが、こういうシーンを書くことないなぁとか思いまして。
やあやあ我こそはっ!っていうのを書きたい時があるんです(’’)
あかねちゃんのこととなると我を忘れる頼久さん!をお楽しみいただけていれば幸いです(^^)
あ、少将様が出てきてるのは管理人の趣味です(’’)
ブラウザを閉じてお戻りください