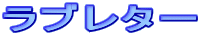
あかねは朝から張り切ってキッチンに立っていた。
料理に没頭すること2時間。
今は作り終わったおかずを重箱につめているところだ。
というのも、夏休みに入って頼久とゆっくり過ごそうとしていたところに、剣道部の合宿が入ってしまって、頼久は現在、学校の体育館に拘束されているからだ。
剣道部の顧問は引き受けた仕事なのだからしかたなく、頼久は毎日与えられた高校生の子守という仕事を忠実にこなしている。
なら、自分も少しは手伝おうと思い立ったあかねはこの日、手作り弁当を届けることになっていた。
重箱の中身は玉子焼きに、おひたし、煮物、焼き魚にアスパラのベーコン巻き、あとは漬物やフルーツなんかを入れてみた。
「よし、これならきっと二人ともおなか一杯になるよね。」
あかねは完成した重箱弁当を見てにっこり微笑むと、蓋をした。
昼まではまだじゅうぶんに時間がある。
重箱を風呂敷で包んで自分も身支度を整えると、あかねはニコニコと微笑みながら家を出た。
向かうはもちろん学校の体育館。
今頃、頼久と天真の二人は体育館の中で剣道部の部員達の練習を見ているはずだ。
頼久に会えると思えばいつもの通学路もなんだか楽しい。
照りつける夏の日差しの中を歩いて、あかねはあっという間に学校の体育館へとやってきた。
扉が開け放たれているのに中からは全くといっていいくらい音が聞こえなくて、あかねは小首を傾げながら中を覗いた。
すると…
「神子殿、どうぞ、中へ。」
すぐに気付いた頼久が歩み寄って、さりげなく重箱を取り上げてくれた。
見渡せば中には頼久の他には天真一人しかいない。
「おう、あかね、よくきたな。」
「二人ともお疲れ様。でも、誰もいないの?」
「ああ、あいつらな、暑さでバテて動けなくなったから早めに休憩してる。まったく、骨のないやつらだぜ。」
天真があきれたように答える中、頼久は体育館の一画に敷物を敷いてそこに重箱を置いた。
もちろん天真もその敷物の上に陣取る。
あかねの手料理が自分の分も用意されていることなどお見通しだ。
あかねは重箱と一緒に持ってきた水筒の中の麦茶を紙コップに注いで配ると、ほっと一息ついた。
「それにしてもみんな夏休みだって言うのに頑張るね。」
「あいつら、やる気だけは一人前だからな。」
「やる気があるのだ、そのうちものになるだろう。」
「それ、お前、マジで言ってるか?」
「うむ。」
頼久があかねから受け取った麦茶を幸せそうに飲みながらうなずいた。
天真を鍛えた頼久が言うのならきっと剣道部のみんなも強くなるのだろう、あかねはそう思う。
「で、あかねも張り切ったな、重箱って。」
「だって、男の人二人分のお昼ご飯って考えたらやっぱりたくさんあった方がいいかなって思って…それに頼久さんも天真君もよく食べるし。」
「まぁ、そうだけどな。」
「お気遣い頂き、申し訳ありません。」
「そんな、気にしないで下さい。私がやりたくてやってることなんですから。」
「そうそう、あかねとしちゃこういうところで女を見せておかねーと誰かに横恋慕されるんじゃねーかって心配なんだよな。」
「べ、別にそういうわけじゃ……。」
最後の方は聞こえないような小さな声になってうつむくあかねを見て、頼久が溜め息をついた。
そんな心配など欠片ほども必要ないというのに、天真がおかしなことを言い出すからだ。
胸の中で天真に悪態をついて、それから頼久ははっと思い出したように自分のカバンを引き寄せると中から封書の束を取り出した。
「頼久、なんだ?それ。」
「お前にだ。」
「はぁ?」
頼久が天真の方へ封書の束を差し出すと、天真は訝しげに首をかしげながらそれを受け取った。
頼久の隣ではあかねが不思議そうに天真を見つめている。
「おい、これ……。」
「どういう事情かはわからぬが、ここへ来るようになってからお前に渡してほしいと女生徒から何通も預けられていたのを忘れていた。」
「それってもしかして、天真君へのラブレターじゃない?」
真相に気付いたらしいあかねは目をまるまると見開いて興味津々の様子だ。
「……みたい、だな……。」
天真としてはそんなもの受け取ってもどうすればいいのかわからない。
だいたい自分に直接渡されるものは全て受け取りを拒否してきたのだ。
それをまさか頼久経由で渡されようとは……
「読まないの?天真君。」
「読んでもどうしようもないしな…。」
「返事書いてあげたらいいのに。」
「……それはねー、俺はそういうガラじゃねーよ。」
「まぁ、そうだけど……。」
筆まめな天真なんて想像もできない。
そう思ってあかねがクスッと笑っているうちに、不機嫌そうな顔で天真は自分のカバンを引き寄せた。
そしてさっき頼久がしたのと同じようにカバンの中から封書の束を取り出すと、キョトンとしている頼久にそれを押し付けた。
「天真、これはなんだ?」
「見りゃわかるだろ。渡してくれって押し付けられたのはお前だけじゃねーの。」
「っていうことは、これって頼久さん宛てのラブレター?」
「ま、そういうことだな。お前がいない時に渡すと後でごたつきそうだから、お前がいる時に目の前で渡そうと思ってたんだ。」
「ご、ごたついたりしないもん……。」
自信なさそうに声が小さくなっていくあかねを頼久は愛しそうに見つめる。
あかねは普通の女子高生よりはずいぶんと大人びていると思うが、それでもこうした純粋で愛らしいところは出会った頃のままだ。
頼久が渡されたラブレターのことなど忘れてあかねの愛らしさを堪能していると、あかねは上目遣いに頼久の顔を見つめた。
「頼久さん。」
「はい、なんでしょうか?」
「それ、読まないんですか?」
「は?」
「だから、それ、ラブレター……。」
「ああ。」
あかねに言われてやっとその存在を思い出して、頼久は手にしていたラブレターの束をじっくり眺めた。
ピンクだの水色だの、可愛らしいパステルカラーの封筒の束だ。
どれも女の子らしく可愛いデザインだが、どれをとっても頼久など持っているだけでも恥ずかしいような外見をしている。
これが、もしあかねだったら、こんな色やデザインのレターセットなど使わない。
きっと自分の好きな紫苑色のおとなしくも上品な封書をくれるのだろうと想像すると、頼久の顔には自然と幸せそうな笑みが浮かんだ。
「頼久さん?」
「どれもずいぶんと派手な封書だと思いまして。」
「それはまぁ、女の子が書くラブレターなんてそうですよ。」
「ですが、もし神子殿であれば、きっと違う装いの文を下さるでしょう。」
「それは、私は頼久さんが何色が好きか知ってますし、頼久さんがそういうキャピキャピしたの好きじゃないっていうのも知ってますから…。」
「はい、こういうものを見ると神子殿が京で物忌みのたびに下さった文を思い出します。」
「ああ、懐かしいですね。」
なるほどとあかねが微笑んで見せれば、向かい側で天真が苦笑した。
これではただ目の前で惚気られているようなものだ。
そう思って天真があきれていると、頼久がすっとラブレターの束をあかねの方へと差し出した。
「はい?」
「これは神子殿に。」
「どうして、ですか?」
「私には不要のものです。当然、返事を書く気もありませんし、処分は神子殿にお任せします。」
「任せられても…。」
「私が持っていても裂いて捨てるだけです。」
「でもやっぱり頼久さん宛ての手紙なんですから…。」
そう言ってあかねが苦笑したので、頼久は差し出した封書の束をあかねに渡すことはあきらめた。
だが、こんな物を持って帰って、ほんの少しでもあかねが心配したりするのは頼久の本意ではない。
頼久はしばらく眉間にシワを寄せて考え込むと、これしかないとばかりに封書の束を真っ二つに引き裂いた。
「頼久さんっ!何やってるんですかっ!」
「お前、やることが派手だなぁ。」
あかねと天真の反応は正反対。
あかねの方は顔色を青くして驚いているが、天真はやっぱりかという程度の苦笑を浮かべている。
頼久はというと二つに裂いた封書の束を重箱の横に置いて、これで一安心とばかりに微笑んだ。
「神子殿に欠片ほどの心配もして頂きたくないのです。これは本当に私には必要のないものですから。」
「でも、これを書いてくれた子達は頼久さんへの想いをこめて一生懸命書いたのに……。」
あかねとしては自分も頼久のことを深く想っているだけに、このラブレターを書いた女の子達の気持ちを考えると複雑だった。
どうしてもこのラブレターを書いたのがもし自分だったらと考えてしまうから。
ところが、頼久はそんなあかねの手をとって優しく微笑みかけた。
「私がほしいと願うのは神子殿の想いだけですので。」
「はうっ…。」
相変わらずさらりと言ってのけた頼久にあかねが顔を真っ赤に染め上げる。
頼久の満足そうな笑顔を見て、今度は天真が溜め息をついた。
「お前らなぁ、そういうことは頼久の家で二人きりの時にやってくれ。」
「ご、ごめんね。」
あかねは真っ赤な顔で慌てて頼久に握られていた手を引っ込めたのだが、頼久の方は天真のことなどおかまいなしに幸せ笑顔でたたずんでいる。
天真はそんな相棒にもう一度溜め息をついてから風呂敷包みへと視線を移した。
「そろそろ昼だな。あかね、それ……。」
「あ、そうそう、お弁当もう広げるね。」
あかねは赤い顔のまま慌てて重箱を広げた。
風呂敷包みの中から現れたのは豪華なおかずとおにぎりだ。
「おお、気合入ってんなぁ。」
「そうでもないよ。いつも作っているものを詰め込んだだけだし。天真君も遠慮しないで食べてね。」
「おう。」
もちろん最初から遠慮などするつもりのない天真はおにぎりを一つ手に取るとさっそく食事を始めた。
「はい、頼久さんもどうぞ。」
「有難うございます、頂きます。」
あかねに勧められて頼久もやっとおにぎりと箸を手にした。
「お、この玉子焼きは絶妙だな。」
「神子殿はまた料理の腕を上げられましたね。」
「二人がそう言ってくれるなら少しは上手になってるのかな。」
頼久はいつもなんでもおいしいと言って食べてくれるから、本当に料理の腕が上がっているのか疑わしいと思っていたあかねだが、天真までが本当においしそうに食べてくれるなら間違いない。
あかねは一緒に重箱のおかずをつつきながら、幸せそうな笑みを浮かべた。
ところが、今の今までおいしそうに料理を食べていた頼久が、突然箸を止めて眉間にシワを寄せ始めた。
あかねがすぐに気付いて顔色を青くする。
もしかして何かとってもおかしな味になっている料理があったのでは……
「おい、頼久、お前、人の作った料理食べながらなんて顔してんだよ。」
いち早くあかねの様子に気付いた天真が声をかけると、頼久がはっとあかねの方へと視線を向けた。
視線の先には青白い顔のあかねが…
「ち、違います!神子殿の料理に不満があるわけでは…。」
「何かおかしな味がするものがあったんなら正直に言ってください…。」
「違います!断じて違います!」
「お前がややこしい顔すっからだぞ…。」
そりゃもう、神子殿バカのことだから料理がまずいが顔に出るはずがないと内心は思っている天真だ。
「それはその…料理ではなく、違うことが気になりまして…。」
「料理じゃないこと、ですか?」
「はい……。」
どうやら頼久が気にしているのが料理の味ではないとわかって安堵の溜め息をついたあかねは、そのまま小首を傾げた。
料理じゃないというのならいったい何が気になっているのだろう?
「頼久、この際だ、はっきり言っちまえ。じゃないと、やっぱり料理がまずかったんじゃ?とかあかねが家に帰ってから悩みだすことになるぞ。」
「天真君!そんなことないから!たぶん……。」
また声が小さくなっていくあかねに天真は苦笑した。
あかねときたら、頼久のこととなると本当に繊細になるのだ。
それはまぁ、相棒の頼久も同じなのだが…
「私が気になったのはその……神子殿もこのような文をもしや受け取られているのかと……。」
「はい?」
あかねがキョトンとした顔で頼久の視線を追ってみるとその視線の先にはさきほど頼久の手によって二つに引き裂かれたラブレターの束が…
一瞬考えて、あかねはくすっと笑みを漏らした。
「私はもらってませんよ。昔は渡されそうになって断ることもけっこうありましたけど、今は全然ないです。」
「そう、なのですか。」
「はい。」
これは意外だという顔をした頼久に、天真は深い溜め息をついた。
「あのなぁ、頼久。お前、去年の文化祭でさんざん見られただろう?」
「うむ。」
「あれであかねに近づこうなんて男は皆無になったから安心しろ。」
頼久は事情がわからないとばかりに小首を傾げる。
その隣であかねはニコニコとただ微笑んでいた。
「お前、自覚ねーからな。」
「何がだ?」
「お前はその顔だろ?で、そのガタイのよさ、それでもってあの喧嘩の強さだ、で、しまいに社会人。もう立派な大人で、いつでも嫁さんもらえるわけだ。そんな男相手に誰が勝負しようと思うってよ。」
天真のあきれたような説明にあかねが嬉しそうな顔でコクコクとうなずく。
それを見て頼久は眉間のシワを消した。
「もしや神子殿に言い寄る男が後を絶たぬのではと案じておりましたが…。」
「そんなこと全然ないです。私なんかより頼久さんの方が全然モテるんだっていつも言ってるじゃないですか。」
「私にはよくわかりません。私がこうして側にいることを神子殿がお許し下さることさえ不思議にも有難くも思っておりますので。」
「頼久さんは自覚なさすぎです。」
あかねがそう言って苦笑すると天真が向かい側で激しく首を縦に振った。
頼久はあかねが自分に愛想を尽かしはしないかと常に心配している。
天真はそれをそばで見てよく知っているだけにうなずかずにはいられなかった。
「神子殿はそうおっしゃいますが、私には神子殿が全てです。ですから、神子殿も文のことなど気になさらないで下さい。」
「す、全てって……恥ずかしいですよ…。」
「私にとっては当然のことです、恥ずかしいでしょうか?」
「お前、相変わらずだなぁ。」
真っ赤な顔でうつむくあかねに代わって天真は苦笑した。
恥ずかしいことをさらっと言うのは今の頼久も京にいた頃と変わらない。
そして3人がそんなふうにゆっくりと昼食をとっていると、先に休憩に入っていた剣道部の生徒達が戻ってき始めた。
「お、やる気だな、やたら早く戻ってきやがった。」
「やる気があるのは良いことだ。我々も食事を済ませて稽古を始めよう。」
「おう。」
ラブレターの話をしていた二人はどこへやら。
頼久も天真も真剣な顔で料理をパクパクと平らげた。
「ごちそうさまでした、神子殿、申し訳ありませんが…。」
「あ、はい、どうぞ。稽古してきてください。クッキーたくさん焼いてきたから、よかったら後で休憩の時にでも食べて下さいね。」
そう言ってクッキーを置いて重箱を片付け始めたあかねの姿を頼久は寂しそうに見つめた。
もうこれであかねの姿が見られなくなるのかと思うと、それだけで自分の体が冷たく感じるようにさえ思う。
「な、あかね、お前、これから用事がねーんだったら見てったらどうだ?稽古。」
「え?どうして?」
「たまにはいいだろ、頼久が竹刀振るところを見るのも。今は夏休みで冷やかすようなヤツもいねーし。普段はお前、頼久の立場気にしてあんま見にこねーから、こういう時くらい、な。」
「ん〜。」
「どうぞ、神子殿さえ宜しければ。」
「それじゃ、今日は見学させてもらいますね。」
「はい。」
にっこり微笑むあかねに頼久は嬉しそうにうなずくと、天真と並んで歩き出す。
向かうは剣道部員達の待つ体育館の中央だ。
「天真。」
「ん?」
「気遣い、感謝する。」
「いや…せっかくの二人の夏休みを邪魔したのは俺だからな。」
天真は頭をぽりぽりとかくと竹刀をブンブンと振り回した。
そんな天真と共に頼久も竹刀を軽く振って調子を確かめて、それからちらりと自分達がもと座っていたところへと視線を走らせる。
するとそこにはニコニコと微笑んでいるあかねの姿が…
稽古を終えたら自宅までしっかりと送って差し上げよう。
頼久はその帰路を楽しみに剣道部員への稽古を始めるのだった。
管理人のひとりごと
季節は冬でも夏休みネタ!
出遅れてる(っдT)
でもどうしても部活顧問ネタ、一つやっておきたかったんです、ハイ。
あとはクリスマスとか正月とかはやろうかなと思うんですけどもねぇ。
もうちょっとで高校2年生もおわりだね、あかねちゃん♪
あとは3年生、大学受験と就職と、頼久さんとの結婚だね!(マテ
いや、そこにたどり着くまでは書き続けますよ!
頑張ります(><)
プラウザを閉じてお戻りください