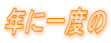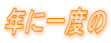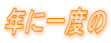
頼久はうっすらと口元に笑みさえ浮かべて濡れ縁に座っていた。
秋晴れの空から降り注ぐ光はとても穏やかで温かい。
焼けつくような暑さを感じた夏の陽射しがすっかりやわらいだのを感じながら、頼久は何するでもなく座っていた。
いつもならここで刀の手入れの一つもしているところだ。
だが、今日はいつもとは違う。
怨霊との戦いに勝利をおさめ、あかねが頼久の妻となってから毎年恒例の行事。
それが頼久の誕生祝いだ。
あかねと藤姫のはからいで頼久は毎年、誕生日には休暇を与えられることになっている。
今年も例外なくその休暇は与えられ、こうして頼久は何するというわけでもなく濡れ縁に座って秋の陽射しを楽しんでいるというわけだ。
武士溜まりに詰めている仲間達が忙しくしているのではないか?と少々心配なこともあるにはある。
なんといっても元は八葉として龍神に選ばれた身でもある頼久は今となっては左大臣にすっかり頼りにされている武士の一人なのだ。
もちろん、源氏の若棟梁という立場もある。
それでもこの休日だけは毎年ゆっくりと楽しむことに決めていた。
なんといってもこの休みは、大切な妻の気遣いが込められた休みなのだから。
「頼久さん、お酒でも持ってきましょうか?」
御簾の向こうからかけられた声に頼久の微笑が深くなった。
最近ではすっかり御簾の外へは出なくなったあかねが遠慮がちに自分の方を見つめている気配がする。
その気配さえ愛しくて、頼久の顔には笑みが消えることがない。
「いえ、昼間から酒というのは性に合いませんので。」
「あ、そっか。頼久さん、いつもはこの時間、お仕事してるんですもんね。」
御簾の向こうからは少しばかり後悔したような声が聞こえてきた。
あかねが御簾の内で何をしているのか頼久は知らない。
ただ、この休みの間、あかねはいつも頼久の側を離れないでいてくれるから、今日もこうしてずっと頼久と御簾一枚隔てただけの距離に座っているのだろう。
そんなあかねに気付いて、頼久はハッと目を見開いた。
そういえば、こうして三日の間、自分の側にいてくれるあかねは、もしや手持無沙汰なのではないだろうか?
ただそばにいるだけで幸せな自分とは違い、妻が闊達な性格なのを頼久は良く知っている。
「神子殿。」
「はい?」
慌てて頼久が呼びかけてみれば、帰ってきたのは愛らしいあかねの声。
その姿が見えないのがもどかしくて、頼久はすっと立ち上がると、御簾をくぐって中へと入った。
「どうかしたんですか?」
キョトンとした顔で頼久を見上げるあかねは、何かをしていた様子もない。
やはりかと頼久はため息をついた。
「頼久さん?」
「神子殿。」
「はい?」
「その…退屈なさっておいででは…。」
「へ?頼久さん、退屈でした?」
「いえ、私は神子殿のおそばに置いて頂けるだけで光栄ですが、神子殿は…。」
「こ、光栄ってそんな…。」
いつまでたっても初々しく顔を赤くするあかねを見つめて思わず微笑を浮かべた頼久は、はっと我に返るとこれではいけないと姿勢を正した。
「神子殿。」
「はい?」
「もしよろしければどこか、紅葉の美しいところへでもお出かけになっては?」
「でも、せっかく頼久さんがお休みで、お誕生日なのに私だけ出かけるのは……。」
「まさか、神子殿お一人でお出かけなどとんでもありません。私が警護させて頂きます。」
「頼久さんも一緒?」
「はい。」
柔らかく微笑む頼久につられてあかねもその顔に笑みを浮かべた。
二人でお出かけ、それはきっとデートのようで…
と想像していたあかねの耳に頼久の言葉がよみがえった。
警護させて頂きます。
頼久は確かにそう言ったのだ。
「頼久さん。」
「はい。」
「警護とかお供とかそういうんじゃなくて、一緒に出掛けてくれるなら行きます。」
「はぁ…。」
「頼久さんはもう私の旦那様なのに警護とかそういうこと、すぐ言うんですから。」
そう言ってあかねが拗ねて見せると頼久は困ったように苦笑した。
確かにあかねは今はもう主ではなく妻なのだが、頼久にとって敬うべき女性であることには変わりがない。
そう思えばこそ、どうしても言葉遣いや態度を改めることはできないでいた。
「では、その……私と共に紅葉狩りに出かけては頂けませんか?あかね。」
「…………………はいっ!よろこんでっ!」
名前を呼ばれたことに一瞬驚いて固まって、それからすぐに我に返ったあかねは大声で嬉しそうに返事をするとすぐに立ち上がった。
紅葉狩り、ということはそれなりの遠出をすることになる。
牛車を出して乗り込んで…がこの京の女性の普通の外出だけれど、あかねのことを良く知る頼久がそんな外出に誘うわけがない。
だから、あかねはさっさと奥へ引っ込むと、八葉のみんなと京のために戦っていた頃のように動きやすい姿へと着替え始めた。
見上げれば赤く染まった楓の葉とその葉の合間から秋の抜けるように高い青空が見えた。
久々に頼久と二人で馬に乗り、船岡山までやってきたあかねは馬から降りて細い山道を歩いていた。
普通、紅葉狩りといえば牛車に乗り、供を大勢連れて山のふもとで…ということになるのだが…
あかねの場合は頼久と二人、誰もいない美しい山道をゆっくりと歩いていた。
こういう山の中は猪などの獣が出ることもあるというが、頼久が一緒ならあかねにな何一つ心配はなかった。
頼久はというとあかねが上機嫌なのでこちらも言うことなしだ。
少し前を行くあかねの背にはだいぶ長く伸びた髪が一本に束ねられて揺れていた。
その髪の長さが自分と共に過ごしてきた時の長さだと思えば、髪そのものさえもいとおしい。
あかねを表へ連れ出した頼久の方は秋の景色を楽しむ間もなく、あかねに見惚れているのだった。
「ちょうどよかったですね、どの木もみんな綺麗に紅葉してて。」
「はい。」
あかねの言うとおり、景色は文句なかった。
赤や黄色の木々の葉がそよぐ風にちらほらと散る様は絵に描いたようだ。
「ついこの間まで暑い暑いって言ってた気がしましたけど、もうすっかり秋なんですねぇ。」
しみじみそう言いながら歩くあかねの背中を見つめながら頼久は真剣な顔で考え込んだ。
「神子殿。」
「はい?」
急に真剣な声で呼ばれてあかねは歩みを止めると、くるりと振り返った。
あかねの目に飛び込んできたのは美しい紅葉を背景に何やら真剣に考えている頼久の顔だった。
「神子殿はこの頼久の妻として色々と日頃からお気遣い下さっていますが、そのせいでつらい思いをなさっておいでなのではありませんか?」
「はい?別につらいと思ったことはないですけど…。」
「ですが、季節の移ろいを感じられぬほど屋敷にこもっておいでとは…。」
あかねはもともとこの京で育ったわけではないせいか、京の女性達とは比べ物にならないほど闊達だ。
一人で外出するのは普通のことだと思っているし、牛車に乗るよりは徒歩で移動することを好む。
あかねのそういう性質を心得ているだけに頼久にとってあかねが季節の移ろいを感じられずにいたことは衝撃だった。
もしこの京に残り、自分の妻になっていなければ、今頃自由に外を出歩き、季節の変化を楽しんだいたのではないか?
どうしてもそう考えてしまう。
「そんな、心配してもらうようなことじゃないですよ。最近は屋敷の中にいるのにも慣れましたし、それにけっこう屋敷の中でやらなきゃならないこともあるし。」
「やらなくてはならないこと、ですか?」
「はい。頼久さんの衣を仕立てたり、あと、お香を焚きしめたり、そのお香の手配をしたり、ご飯のことを色々考えたり、どれも屋敷の中で済むことですし、それにそういうのなんだか妻っていう感じがして楽しいんです。」
少しはにかんで言うあかねに頼久はほっと安堵のため息をついた。
あかねの笑顔は本物だった。
ということは、あかねは本当に今の生活を楽しんでいるということなのだろう。
「そんなことより、頼久さん。」
「は?」
びしっと指さえ突きつけそうな勢いであかねに呼ばれて、頼久は思わず目を丸くした。
ついさきほどまで微笑んでいたあかねが何故か厳しい表情で自分を見上げていたからだ。
この状況で何か説教でもされるのだろうか?と頼久は思わず姿勢を正した。
「せっかくのお誕生日なのにこれじゃぁ私ばっかり楽しんじゃってるじゃないですかっ!」
「はぁ…。」
「私、ちゃんと頼久さんのお誕生日お祝いしたいんですけど…。」
どうやら真剣にそう考えているらしいあかねにじっと見上げられて、頼久は苦笑した。
あかねはこうしていつも自分のために何かしたいと言ってくれる。
けれど、頼久にとってはあかねと共に過ごすことのできる時間が何よりも大切で、それ以上のものはこの世に存在しないのだ。
そんな想いをあかねに伝えたくても頼久の口は思うように動いてはくれない。
だから…
頼久はあかねをそっと抱きしめた。
「頼久さん?」
「祝って頂いております、毎年。」
「でも私なんにも…。」
耳元で想いのたけを込めて囁くように言えば、あかねは頼久の腕の中でうつむいた。
「神子殿が私のことを考えて下さる、そばに私を置いて下さる、それだけで十分です。」
「そんなの、いつものことじゃないですか…。」
自分のことを想い側にいる、それがいつものことだと言ってくれるあかねの髪に頼久は優しく口づけた。
「頼久さん?今、髪にしました?」
「はぁ、お気に召しませんか?」
急に視線を上げられて、頼久は面食らった。
確かにあかねは恥ずかしがりなところがあるが、人気のない山道で髪に口づけるくらいはよかろうと思ったのだが…
「そ、そういうわけじゃなくて…せっかくお誕生日なんですから…その……。」
「はぁ…。」
あかねが何を言いたいのかがわからずに頼久がキョトンとしていると、あかねが何かを思い切ったように一つうなずいた。
次の瞬間、あかねは思い切り背伸びをしたかと思うと頼久の首に腕を回し、ちゅっとその唇に一瞬の口づけを贈った。
まばたき一回分ほどの短い口づけに頼久が目を白黒させていると、あかねは真っ赤な顔で頼久を見上げてはにかんだ笑みを浮かべて見せた。
「頼久さん、お誕生日おめでとうございます。頼久さんが生まれてきてくれたこと、そして頼久さんに出会えたこと、私、感謝してます。」
「神子殿…有り難うございます。」
想いのこもった優しい言葉に、頼久は胸の内が温かくなるのを感じた。
もし、この女性に出会っていなかったらと思うと背筋が寒くなるほどだ。
それほど、頼久の中であかねの存在は大きく尊いものだった。
「さ、そろそろ帰りましょう。夕餉は色々御馳走を用意してもらってるんですから!一緒に食べましょうね。」
「はい。」
あかねはにっこり微笑むと頼久の手を取って先に歩き始めた。
小さな歩幅のあかねの歩みに合わせて、半歩後ろを手を引かれながら歩く頼久は小さな背中を微笑みながら見つめていた。
自分が迷った時はきっとこうしていつもこの女神が手を引いてくれる。
だからこそ、自分はこの小さな背中をいつまでも守り続けるのだと、己が生まれたその日に頼久は誓いを新たにするのだった。
管理人のひとりごと
頼久さんお誕生日おめでとうございます\(^O^)/
の、京版でした。
すべり込んでますが、祝う気持ちは毎年けっこう前からあるんですよ!
書くのが遅いだけ!
今年は二人で紅葉狩り。
一緒に過ごすことが大前提なら一緒に観光、一緒に温泉、一緒にダラダラ…
色々な過ごし方があるかなぁと。
今年は管理人の生息地の紅葉があまりきれいに染まらない気配がするので、二人に綺麗な紅葉を愛でてもらいました!
ブラウザを閉じてお戻りください