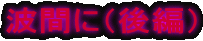
強い夏の日差し、きらめく海、さらさらとした砂浜。
海でのリゾートとしては申し分ない状況、ではあるのだが…
あかね達はとりあえず着替えて海へやってきて、そして凍りついた。
辺りは人人人、人の群れだ。
見渡す限りの人込みに一瞬凍りついて、次に同時に溜め息をついたあかね達は顔を見合わせて苦笑して空いている場所を探した。
とにかく座る場所を決めてしまわなくてははぐれて迷子になりそうだ。
背の高い頼久と天真が辺りを見回して場所を見つけて、敷物を敷くと5人はやっと一息ついた。
「それにしても凄い人だね。」
「予想はしてたけど予想以上だったね。」
あかねと蘭はそう言って苦笑を交わす。
夏休みで天気がよければ込んでるだろうとは思った。
思ってはいたが、ここまでとは…
「油断すると迷子になりそうだねぇ。」
「お前は油断するとさらわれそうだから気をつけろ。」
「せ、先輩…。」
天真の言葉に苦笑して詩紋は深い溜め息をついた。
「こう人が多くては物騒なこともありましょう、神子殿もお気をつけ下さい。」
「私は大丈夫ですよ、ずっと頼久さんの近くにいますから。」
「そのようにして頂ければ、必ずお守り致します。」
そう言ってあかねと頼久が笑みを交わせば、周囲で3人が深い溜め息をついた。
3人とも心の中でつぶやいたのは「ハイハイ」の一言。
「それにしてもあかね、お前、水着持ってこなかったのか?」
そう尋ねたのは天真だ。
何故かというと、あかねは可愛らしいミニのワンピースを着ているだけで下に水着を着ている気配がなかったから。
「うん、泳がないつもりだから。」
「ああ?海まできて泳がねーってか、またなんでだ?」
「えっとそれは……。」
「神子殿に水着は着ないで頂きたいと、私がお願いしたからだ。」
「はぁぁ?」
真面目な顔で答えた頼久に天真は心の底からあきれたような声をあげた。
「なんじゃ、そりゃ。」
「……ボク、わかった気がする…。」
「あのね、お兄ちゃん、わか〜い女子高生の彼女を持つ頼久さんとしては、水着なんて露出の高いものを着た可愛いあかねちゃんを他の男になんてチラッとでも見せたくないと、そういうわけよ。」
一緒に水着を買いに行って、自分は買わないとあかねに宣言された先日、何故水着を買わないのかの理由を聞いた蘭はそれこそ目が点になるほど驚いて、それからあきらめの溜め息をついたのだった。
「……頼久、お前、重症だな……。」
「何がだ?」
「いや、もういいわ……。」
「て、天真君もそんなにあきれないで、ほら、私だって納得して泳がないことにしてるんだし、ね。」
「……お前も重症だな……。」
「天真君っ!」
顔を真っ赤にしてあたふたするあかねを見て深いため息をついた天真は、突然両手に詩紋と蘭の手を引いて歩き出した。
「俺達は泳いでくるわ。お前らはそこでいちゃついてろ。」
「いちゃついたりしないからっ!」
バイバーイというように手を振る蘭と苦笑する詩紋の手を引いて、天真はあっという間に人込みの中へ入っていった。
その様子を見送って軽く溜め息をついて、あかねは辺りを見回した。
辺りは目の届くところ全てに人がいるといってもいいくらい大勢の人でごった返している。
夏休み中だから子供の姿ももちろん多いし、その保護者の姿もちらほら見えるが、一番多く目を引くのはやはり若い女性の水着姿だった。
夏真っ盛りで気温も高い、天気もいいとなれば水着を着て海で泳ぐのは当たり前だし、日焼けを楽しんでいる人もいる。
あかねは辺りを見回してそんな女の人を眺めて、それから軽く溜め息をついた。
自分と同じ女子高生だろうと思われる女性も、みんななんだかとっても色っぽい水着を着ていて、しかもスタイルがいい。
スタイルがいいからそんな水着を着ているのだろうけれど、自分のスタイルに自信がないあかねとしては複雑な心境だ。
頼久はあかねの水着姿を他の男に見せたくはないと言っていたが、これでは頼久は他の女性の水着姿を見放題なわけで…
外見も整っている頼久ならナンパなんかしようものならいくらでも女の子がついてくるのだろう。
そんなことまで考えてしまって、あかねがそっと隣に座っている頼久の方を見てみると…
そこにはニコニコと幸せそうに微笑んで自分を見つめているいる頼久の笑顔があった。
「よ、頼久さん?」
「はい、なんでしょうか?」
「なんでこっち見てるんですか?ほら、海とか空とか綺麗なのに…それにその……。」
「神子殿の方がずっとお綺麗です。」
「はぅっ……。」
綺麗な女の人もいっぱいいるのに、と言おうとしていたあかねは言葉を飲み込んだ。
どうやら隣の恋人には自分の姿しか見えていないらしいと悟ったから。
そしてそれはとても嬉しくもあり、恥ずかしいことでもあって…
あかねは顔を真っ赤にしてうつむいたまま、とうとう海を見ることさえできなくなってしまった。
「神子殿?どうかなさいましたか?」
「な、なんでもないです…。」
ひとしきりあかねが照れて下を向いていると、すっと視界に缶ジュースが差し出された。
それは、クーラーボックスに入れて持ってきたあかねのお気に入りのジュースだ。
「あ、有難うございます。」
「暑いですから、水分は取っておいたほうがよいかと。」
「あ、はい。」
上機嫌の恋人から缶ジュースを受け取って、あかねはまだ赤い顔のままジュースを口にした。
何故顔が赤いかといえば、いまだに頼久の視線が自分に注がれているから…
「あ、あのぉ、頼久さん。」
「はい、なんでしょうか?」
「そ、そんなに見つめられると恥ずかしいんですけど…。」
「申し訳ありません。今日の神子殿はいつにも増してお美しく、つい…。」
「う、美しくなんかないですってば…。」
「いえ、常日頃もお美しいですが今日もまたいちだんと…。」
「よ、頼久さん!」
「はい。」
「それくらいにしてください、恥ずかしくて溶けます…。」
「恥ずかしい、でしょうか…。」
相変わらず自分は真実しか口にしていないと言いたげな頼久は真剣な顔で小首を傾げた。
こちらの世界へやってきてこちらの世界の常識も手に入れた頼久だが、中身は同じ頼久のままなので、どうにもこの辺はなかなか変わらないらしい。
そんな頼久にクスッと笑みを漏らして、あかねは空を見上げた。
「夜は花火が上がるって言ってました。一緒に見ましょうね。」
「はい。」
自分は恥ずかしいことを口にしていたのかと苦悩していた頼久が一瞬にして立ち直ってその顔に笑みを浮かべた。
あかねと共に花火を見上げる。
それはなんとも魅力的な話だ。
「蘭が…。」
「はい?」
「部屋、頼久さんは一人部屋だから、私が遊びに行けば二人きりになれるって…蘭が……。」
「そう、ですね。」
「花火の時間になったら行きますね、頼久さんの部屋。」
「神子殿…はい、お待ちしております。」
二人は視線を交わして微笑み合って…
それからはずっと辺りを埋め尽くす人の流れも、綺麗に晴れ渡った空も、太陽に輝く海も全く目に入らないというように、二人はじっと互いを見詰め合って過ごした。
海で泳ぎ疲れて帰ってきた天真達があきれて溜め息をつくのに気付くまで。
夕食をみんなで楽しく済ませて、一度部屋へ戻って、あかねは蘭に追い出されるように自分の部屋を出た。
もうすぐ花火が上がるんだから、頼久さんと二人で見ないでどうするの!というのが蘭の言い分だ。
もっともなことなのであかねも部屋を出たのだが、いざ頼久一人きりの部屋へ行こうとするとなんだか緊張してしまってドアの前で立ち止まってしまった。
いつもは頼久が一人暮らししている一軒家に押しかけて行ってるのだから、どうして緊張するのかと言われるとそうなのだけれど…
いつもとは違うホテルの廊下の雰囲気がなんだか気になって、あかねは赤い顔でドアの前に立ち尽くしていた。
すると…
「ああ、やはり神子殿でしたか、どうぞ。」
急にあかねの目の前の扉が開いて、向こうからニコリと微笑んでいる頼久が顔を出した。
いつものようにあかねの気配を感じ取ってドアを開けたものらしい。
「えっと、お、お邪魔します…。」
頼久がいつものように体をずらしてあかねを招いてくれたので、あかねは真っ赤な顔で頼久の部屋へと足を踏み入れた。
そこは本当に人が一人眠るだけといったシンプルな部屋で、ダブルベッドが入っているあかね達の部屋よりもかなり狭い。
それでも窓からは海が見えて気持ちよさそうだった。
「何か飲みますか?」
「あ、私はいいです、さっき蘭とジュース飲んじゃったから、頼久さんはお酒どうぞ。」
「いえ、私は後で天真につき合わされそうですので。」
そう言って苦笑して頼久は窓辺にたった。
天真は何かにつけて頼久のもとへ酒を持ち込んで飲みまくっているから、こんな機会を逃すはずは確かにない。
「頼久さん、お酒強いんだから今から飲んでも大丈夫ですよ。今日は私を送っていかなくてもいいんだし。」
あかねがそう言って隣に並んで立って微笑んで見せても頼久は苦笑するばかりでどうやら酒を飲む気はないらしい。
あかねとしては、頼久はもう立派な大人なのだから好きな時に酒を飲めばいいと思っているのだが、意外と頼久はあまり酒を好まない。
京では仲間と飲むこともあったというから嫌いではなさそうなのにと考えてみれば、自分が未成年で一緒に飲めないからかと気付いてあかねは少しだけ落ち込んだ。
頼久は何かと色々気遣ってくれて、年齢差を感じることはあまりなくなってきたけれど、こういう時はやっぱり自分はまだまだ子供だと思わずにはいられない。
自分が子供だとあかねが一人落ち込みそうになったその時、きらりと窓の向こうが光ってすぐにドーンという音が聞こえた。
「始まったようです。」
「うわぁ、綺麗!」
窓の向こう、海の上にいくつもの大輪の花が咲き始めた。
毎年恒例らしい海の上の花火大会が始まったのだ。
頼久は瞳をキラキラと輝かせ始めたあかねを見て微笑んで、部屋の明かりを消した。
すると、花火だけが光って見えてとても綺麗だ。
「凄い、盛大ですね。」
「はい、これほどたくさん上がるとは思いませんでした。」
「これって、1時間くらいやるっていってましたよね?」
「はい。」
「楽しみ!」
次々に上がる大きな花火を見てあかねは満足気だ。
頼久の方はというと花火よりも花火に見惚れるあかねの方に視線が釘付けだったが…
「やっぱり海にしてよかったぁ。」
「他の予定もあったのですか?」
「海か山かで迷ったんです。ロッジを貸切で遊ぶっていうのも天真君が考えてたんですけど、ハイキングはもう行ったし、今度は海だって蘭が張り切って今年は海にってことになったんです。こんなに綺麗な花火が見られるなんて思ってなかったんですけど。」
「海は少し混雑していましたが、これならばゆっくり楽しめそうです。」
「そうですね。」
隣に立つ長身の恋人の顔を見上げて顔を赤くして、あかねは慌てて花火へと視線を戻した。
次々に上がる色とりどりの花火の光に照らされる恋人の顔があまりにも端整で綺麗で、しかも至近距離にあったものだから直視できなくて…
そんなことに気付いているのかいないのか、頼久はあかねの横顔を見つめたまま上機嫌だ。
「し、仕掛け花火も始まりましたよ!」
「はい。」
上空には大輪の花火、水面近くでは仕掛け花火が始まって、海は一面綺麗に輝きだす。
あかねはそんな花火を見るのに夢中になって、頼久はあかねを見るのに夢中だ。
天真達がいたらまたあきれたところだろうが、ここは二人きり。
次々に上がる花火に照らされて静かに楽しむ二人の時間はなんとも心地いい。
心地いいのだが…
「ん〜、さすがに1時間は長いかも…。」
「お疲れですか?」
「昼間はしゃいじゃったから…。」
そう言ってあかねは苦笑した。
朝は早くに起きたし、部屋割り騒動で騒いだし、海でも騒いで、さすがにずっと窓辺に立って花火を見続けるのは足がだるい。
そんなあかねを見て頼久は窓際に置いてあった大きな椅子を一つあかねの側に置いた。
「これにどうぞ。」
「私が座っちゃったら頼久さんが座れないじゃないですか。」
「いえ、私は鍛えておりますから、立っていてもどうということは…。」
「そ、そんなの申し訳ないですもん、だって、ここは頼久さんの部屋なわけだし…。」
こういう時、あかねは意外と律儀で頑固だ。
こちらの世界で共に過ごす時間が増えてそれをよく心得ている頼久は、無駄な抵抗はせずに持ってきた椅子にストンと座ってしまった。
いつもなら神子殿のことが一番と譲らないはずの頼久があっさり椅子に座ったのであかねは小首を傾げた。
これは、やっと神子殿が第一の姿勢を崩してくれたのだろうか?
「では、神子殿がこちらへ。」
「はい?」
にっこり微笑んでいる頼久は椅子に座った状態であかねに腕を広げて見せていて…
「そ、それは…。」
「これなら二人とも座れます。」
「それは、まぁ…そう、なんですけど……。」
「お嫌、でしょうか?」
急に悲しげな声でそんなふうに言われて、あかねが嫌ですといえるわけがない。
「い、嫌じゃないです!全然嫌じゃないです!」
「では、どうぞ。」
ニコッと微笑まれてしまってはもうあかねに抵抗する術はない。
だから、あかねは真っ赤な顔で嬉しそうに迎えてくれる頼久の膝の上に座った。
すると長い腕が優しくあかねの体を抱き寄せてくれた。
「どうぞ、楽にして花火をご堪能下さい。」
「あ、はい…。」
優しく抱き寄せられて、あかねは頼久の胸に体を預けるとうっとりと花火の上がる夜空を見上げた。
次々に明かり続ける花火はまだまだ終わりそうにない。
「なんだか…。」
「はい?」
「安心、しちゃいます。こんなふうに頼久さんにしてもらうと。」
「それは光栄です。」
「なんでかなぁ…ずっと京にいる間も頼久さんが守ってくれてたから、かなぁ…。」
頼久にとってそれは何よりも嬉しい言葉だ。
あかねが安心して心安らかにいてくれる。
それが自分の側だからこそと言ってくれる。
それほど嬉しいことはない。
だから、あかねの体を優しく抱きしめたまま、頼久はじっと幸せに浸っていた。
すると、あかねは何も話さなくなり…
「神子殿、花火は終わったようですが…。」
あっという間に1時間が過ぎて花火が終わってもあかねになんの反応もないので頼久がその顔をのぞきこんでみれば…
あかねは頼久の胸に体を預けたまま静かな寝息をたてていた。
頼久はそっとあかねの額に口づけるとしばらく恋人の小さくて暖かな体を抱きしめて、そのぬくもりを堪能してから横抱きに抱いて立ち上がった。
あかねを自分の部屋へ返してやらなくてはならないから。
ゆっくり優しく、愛しい人の眠りを決して妨げたりはしないように細心の注意を払って、頼久は歩き出した。
「だって、頼久さんが側にいると安心なんだもん…。」
「安心?安心って何!安心しないでしょ!普通!」
「へ?どうして?だって、頼久さん強いし。」
「そうじゃなくてね、あかねちゃん…。」
翌朝。
昨夜、お姫様抱っこで頼久に運ばれてきたあかねを見て愕然とした蘭は朝、あかねが目を覚ますとすぐに昨夜の所行を問い詰めた。
どうして夜、恋人と花火を見ていい雰囲気になっているのに寝てしまうのか?と。
しかも、ここはホテル、二人きりの夜の部屋で。
その答えが「安心したから」だったものだから蘭はもう理解不能といわんばかりだ。
「頼久さんは男!大人の男だからね!狼!そう!狼なの!」
「頼久さんが?まさか。」
「もう、なんていうか……ちょっと頼久さんに同情するわ、私……。」
「な、なんで?」
「それって頼久さんを男として意識してないってことになるよ?あかねちゃん。」
「そ、そんなことないよ!頼久さんはなんていうか、無責任にそんなことする人じゃないって信じてるだけ!それに一緒にいるとすごく安心する人なの!」
「だから、その安心ってのがね…。」
「それくらいにしとけ。頼久から話は聞いた。こいつらはそういう関係なの。もう、そうなっちまってんだからしかたねーの。」
「お兄ちゃん。」
「天真君。」
いきなり現れた天真に蘭は頭をグリグリと強めになでられた。
「頼久がこれ以上ないほど幸せだって顔で俺に語って聞かせたぞ、あかねが自分と一緒にいると安心だって言って寝てくれたってな。だから、もう、放っておいてやれや…。」
「そりゃ重症だね、二人とも。」
「だ、だから、何が!」
「神子殿、朝食の時間になりましたが…。」
「あ、はい、今行きます!」
ドアの向こうから頼久の声が聞こえて、あかねは他の事はどうでもいいとばかりに髪型がおかしくないかを鏡でチェックすると、すぐに部屋を飛び出して行った。
それを見送って互いに顔を見合わせて、森村兄妹は深い溜め息をついた。
「お兄ちゃん、私ちょっと心配。あの二人って結婚してちゃんとやっていけるのかなぁ。」
「俺はもう心配するのをやめた。あいつらはあれでいいいんだ、たぶんな。頼久も大人で男だ、そん時はなんとかすんだろ。」
「するかなぁ…。」
「詩紋が待ってんだろ、俺達もメシ行こうぜ。」
本当にもうすっかり二人の間を心配することをやめたらしい天真に続いて蘭も立ち上がった。
頼久もあかねも今はじゅうぶんに幸せそうなのは間違いない。
だから、今はいい。
でも、もし将来、あかねが結婚生活のせいで泣くようなことがあったら…
その時は私がなんとかしなくっちゃ!
蘭は心の中で一人密かにそう決意したのだった。
管理人のひとりごと
こんな季節ですが、ネタがある以上はやりますよ、海水浴(’’)(マテ
書き始めたのはもっと早かったんだけどなぁ…(、、)
4がフィーバーしちゃったのと頼久さんのお誕生日を祝ったりとかでこんな季節に…
しかも糖度低めでやたら長くてすみません(TT)
次に何か書くとしたらもう冬の話になるんじゃないの?って季節ですね…
修学旅行ネタあったのにな…
ぼちぼちゆっくりやっつけていきます(’’)
プラウザを閉じてお戻りください