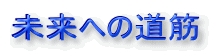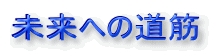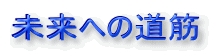
午前授業だったと言って頼久の元へやってきたあかねは、いったん家に帰って私服に着替えてきたにしては珍しく、大きな荷物を持ち込んでいた。
紅茶をいれようとする頼久を制して自ら二人分の紅茶を入れたあかねは、リビングのいつものソファのいつもの席に陣取ると大きな袋の中から紙の束をいくつも取り出してテーブルの上に広げた。
いつものことながらこうと決めたら行動力を発揮するのがあかねだ。
「神子殿?この書類はいったい…。」
「私、すっかり忘れてたんですけど、今週進路相談のための三者面談なんですよ。今日午前授業だったのもそのせいなんです。」
「進路相談、ですか。」
「そうなんです。私全然考えてなくてあせっちゃって、それで、色々資料集めて考えてみようと思って。」
テーブルの上に広げた様々な書類を手に取りながら真剣に読んでいくあかね。
自分の進路を真剣に考えているらしいあかねが可愛らしくて、向かい側に座っている頼久は思わず笑みを漏らした。
「…頼久さんは…私って何に向いてると思いますか?」
書類と一緒に持ち込んだ職業紹介の本に目を向けたまま何気ない風であかねがそう訪ねると、頼久は少し考えてから口を開いた。
「神子殿が就いてみたいと思う職業に就かれるのが一番かと。」
「……そう、ですよね…。」
考えがまとまらないのか、あかねは心なしか沈んだ様子でため息をついた。
数ヶ月前までは京を救うために必死で、こちらへ戻ってきてからは高校に慣れるのに必死だった。
更には頼久という恋人のことも気になっていたわけで、あかねとしては進路どころの騒ぎではなかったのだ。
受験までにはまだ間があるし、ゆっくり考えればいいと思っていた矢先の進路相談だった。
意外だったのが周囲の友達やクラスメイト達がけっこう真剣に将来のことを考えていたことだ。
もちろんまだまだ先のことと思っている友達もいないことはなかったが、あかねとしては自分があまりにも先のことを考えていなかったことに気付いて慌てたのだった。
「神子殿はどのような進路をお望みなのですか?」
そう頼久に問われてあかねはいっそう顔色を曇らせた。
これは何か言い方を間違えたかと頼久が慌ててその頭の中をフル回転させたが、その答えはあっさりとあかねの口からもたらされた。
「私は……本当はなりたいものがあるんですけど……。」
「なりたいものがおありですか?」
「はい……。」
返事をしながらうつむくあかね。
何か悩んでいるのか、あかねの表情は暗い。
それはよほど就くのが難しい職業なのだろうかと頼久が自分の表情も険しくし始めたその時、あかねの口から予想だにしない言葉が飛び出した。
「あの、私、できたら…その……高校卒業したらすぐ、頼久さんの…その…お嫁さんになりたいというか……。」
うつむいたまま真っ赤な顔でそう言うあかねの言葉はもう最後の方は声が小さくなって聞こえなかった。
だが、頼久にとってはこれで十分で「頼久さんのお嫁さん」という部分が耳に残り、きょとんとした顔のまま、しばらく呆然とあかねを見つめ続けた。
頼久の頭の中では、神子殿が自分の妻になりたいとおっしゃって下さったという喜びと、これは夢ではなかろうか?という恐れと、神子殿にプロポーズのような言葉を言わせてしまったという焦りとがごっちゃになってぐるぐると渦巻いていた。
あかねの気持ちを信じていなかったわけではないが、どう考えても自分の方が熱烈にあかねのことを望んでいるだろうと認識していた頼久は、まさかあかねの方からこんな話を切り出してくるとは思いもしなかったのだ。
どれを否定し、どれを肯定して、どうやって神子殿にお伝えしようか?と言葉を探しているうちに頼久の目の前であかねはいつの間にか涙を浮かべていた。
「……いや、ですか?」
「は?」
「だから……私がお嫁さんになるの、いやですか?」
「いえ!決してそのようなことはっ!」
「だって、頼久さん、なんにも言ってくれないから……。」
「いえ、その、何からお話すべきかと……まずその、神子殿にそのような話を先にさせてしまい、申し訳ありませんでした。いずれ私の方からゆっくりお話しようと思っておりましたが遅くなってしまい…。」
「えっ?」
「ですから、もとより私は神子殿に結婚を申し込むつもりでいたのですが、その…そのような話はもう少々先のことになるだろうと思っておりましたので…。」
ここであかねはまた顔を真っ赤にしてうつむいた。
自分が焦るあまりとんでもないことを頼久に話したのだということにここでようやく気付いたのだ。
あかねが恥ずかしさで真っ赤になっているのを見ているうちに今度は頼久の方が落ち着いてきたらしく、その顔にうっすらと微笑が浮かんだ。
「神子殿、私もいずれは神子殿が私の妻となって下されば、これほど幸福なことはないと思っておりますが、もう少々先に致しませんか?」
「はい?」
「高校卒業してすぐではなくてもいいのではないかと。」
どうして?という風にあかねが小首をかしげる。
その姿が愛らしくて、頼久は優しく微笑んだ。
「神子殿には大学に進学して頂きたいのです。」
「大学に?」
「はい。学問というものは修められる時に修めておいた方がよいものです。結婚は先でもできます。ですから、神子殿にはとりあえず大学進学を考えて頂きたいのです。その上で、何か就きたい職業に就かれるのもよろしいのではないかと。」
「頼久さん…。」
「この頼久のために神子殿の未来へ続く道が狭まるような選択はなさらないで頂きたいのです。今はやりたいことがなくともこれからできるかもしれません。結婚しても仕事をすることはできますし、神子殿は神子殿の道を自由に選べるように大学に進学なさって下さい。」
(その自分のなりたいものが頼久さんのお嫁さん、なんだけど…)
と心の中でつぶやきながらもあかねはゆっくりとうなずいた。
自分のことを一番に考えてくれている。
それがよくわかったから。
「わかりました。とりあえず大学に進学できるように勉強頑張ります。」
そうは答えたものの、あかねはどうしてもいつものように明るくは笑えなくて…
自分はこんなに頼久さんと一緒にいたいのに頼久さんは違うんだと思うとどうしてもあかねの顔には悲しげな表情が浮かんでしまう。 そんなあかねの想いに気付いたのか、うつむいていたそのあかねの頭を頼久の大きな手が優しく撫でた。
はっと驚いてあかねが視線を上げると、そこにはいつの間にか寄り添って座っている頼久の端整な顔があった。
その顔が優しく微笑んでいて綺麗で、あかねはぱっと顔を赤くする。
「それに、大学に進学してみてやはり早く結婚したいと思えば、学生結婚という手段もありますので。」
この一言にはっと顔を上げたあかねに頼久は微笑んで見せる。
あかねは何を言われたかを反芻して真っ赤になるとまた慌ててうつむいた。
「えっと…とりあえず、大学受験目指して勉強します…。」
「はい、そうなさってください。お手伝いできるところはお手伝い致しますので。」
「じゃぁ、まずは何になりたいか考えなきゃ…。」
やることが決まったあかねの行動は素早い。
もともとが闊達なあかねなので、資料を次々に手にとって真剣に進路について考え始めた。
「お花屋さん、小さい頃はなりたかったなぁ。あ、あと、お菓子屋さんもなりたかったんですよ、凄く小さい頃ですけど。でも詩紋君くらい上手にお菓子作れないと無理だろうなぁ。」
「今から練習すれば無理ということはないでしょう。」
「無理ですよ。詩紋君の方が絶対向いてます。あ、保母さん、楽しそうかも。小さい子供に囲まれて泣いたり笑ったり。子供ってかわいいですよね。」
「神子殿は子供がお好きですか?」
「はい、大好きです。無邪気でかわいいし、笑ってる子供って天使みたいって思いませんか?」
そんなふうに自分の将来について語りだすあかねが愛らしくて、頼久は微笑みっぱなしだ。
「神子殿には向いていらっしゃるかと。お優しい神子殿ならばきっと子供達もすぐになつくでしょう。」
「よ、頼久さんはまたそういうことを平気で……。」
「私も子供は嫌いではありません。神子殿はきっといい母親にもおなりでしょうね。」
「そ、そうですか?」
「はい、そう思います。ご自身の子供は何人ほしいですか?」
「は、はいぃ?」
あたふたと慌てるあかねに対して頼久は静かに微笑んでいる。
「えっと……えー…そ、そうですね…男の子もいいし女の子もかわいいし、最低でも二人はほしい、かな?」
顔を真っ赤にしてそう答えるあかねを優しく見守りながら頼久は静かにうなずく。
そんな頼久は心の中で神子殿に良く似た女の子はどれほど可愛らしいことだろうと想像して微笑んでいたのだが、次のあかねの言葉にはっと目を見開いた。
「よ、頼久さんは何人ほしいですか?」
「私、ですか?」
更に顔を赤くしてこくこくとうなずくあかね。
「そうですね…。」
とりあえずそう言って頼久は考え込んだ。
自分の子供のことなど今まで考えたこともなかった。
京にいた頃は兄の代理を勤め上げ、兄の子が成人した暁には源武士団の棟梁を譲ることこそが己の役目であり、自分が妻帯して子をもうけることなど考えてみもしなかったのだ。
だいたい、誰かを愛して妻としたり、人の親になったり、そんな人間としての幸福を手にすることなど兄を犠牲にした上にある自分の命に許されるはずがないと思っていた。
父に何度か妻帯を薦められたことがあったが、真剣に取り合ったことは一度もない。
もちろん、今は目の前にいるこの尊き神子のおかげで自分にも幸福に生きることが許されているのだと思い至ることができたのだが。
自分の子供が何人いたらいいかなど、今訊ねられても簡単に答えることはできなかったが、頼久は自分の子供とその子供の母親のことを考えて、目の前にいる愛しい恋人にたどりついてやっと笑顔を取り戻した。
どう考えても自分が子供を持つとしたらその母親はこの目の前の人しか有り得ない。
頼久にとってそれだけは動かしようのない事実だ。
「神子殿が生んで下さるのでしたら何人でも。」
「よよよ、頼久さんっ!」
あかねは真っ赤な顔でテーブルの上の資料の束をかき回し、見ているのかいないのかわからないスピードでそれらに目を通し始めた。
何が起こったのかよくわかっていないらしい頼久は小首をかしげる。
「神子殿?どうかなさいましたか?」
「頼久さんがあんまり恥ずかしいこと言うからですっ!」
「恥ずかしい、ですか?」
相変わらず自分の発した言葉の恥ずかしさがわからないらしい恋人が小首をかしげているのを見てあかねはとうとうため息をついた。
そしてこの人と一緒にいると心臓がいくつあっても足りないと心の中でつぶやくのだった。
管理人のひとりごと
他サイト様では急いで結婚というところがけっこう多かったので、うちはゆっくりめで(笑)
どちらかというと自分のことより相手のことを優先する頼久さんだから、きっとあかねちゃんの将来のことも真剣に考えてくれるだろうなぁと。
最後がこんな終わり方なのはただ単に甘いものが書きたかっただけです(’’)
プラウザを閉じてお戻りください