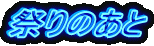
あかねは浴衣を着て可愛らしい巾着を手にうきうきと歩いていた。
紺が基調で白と赤で可愛らしい花と蝶の柄が染めてある浴衣はあかねのお気に入りだ。
下駄は鼻緒が赤で巾着も赤にしてみた。
色々悩んでこの日のために母と共に考えに考えて選んだ一式だった。
今日は夏祭り。
頼久の家で待ち合わせ、二人で出かけて途中、天真達三人と合流する予定でいた。
カラコロと可愛らしい音を立てて歩きながらあかねの顔は緩みっぱなしだ。
頼久はこの浴衣を褒めてくれるだろうか?
腕を組んで歩いてもいいだろうか?
一緒にりんご飴なんか食べてもらおうか?
などなど。
今からあかねの脳裏は楽しいお祭りの図でいっぱいだ。
夏休みに入って毎日のように朝から頼久のもとを訪れているあかねだが、外に出かけることはほとんどない。
今回もどうしてもお祭りだけは一緒に行きたいとあかねがわがままを言って、苦笑する頼久に無理やり「はい」と言わせたのだ。
どうせ回るなら夜店がいいと待ち合わせは夕方。
あかねは今、夕陽を背にして歩いている。
はき慣れない下駄をはいているからいつもより少しだけゆっくり歩いて、頼久の家の玄関の前に立つ。
いつものように玄関の扉を開けて出てきた頼久は、縦縞の入った紺の浴衣を着て微笑んでいた。
一瞬見惚れたあかねが、顔を赤くして慌てて視線をそらす。
「こ、こんばんわ。」
「ずいぶんと早いおつきですね。」
「そ、そうですか?」
うつむいたままのあかねに小首を傾げる頼久。
何かあかねはこのかっこうに不満があるのだろうか?と頼久が黙り込むと、あかねがそれに気付いて慌てて視線を上げた。
「あ、あのぉ、頼久さん?」
「神子殿のおっしゃったように着てみたつもりなのですが、どこかおかしいですか?」
「違います違います!凄く良く似合ってるからびっくりしただけです…。」
真っ赤になっているあかねの返答に頼久はほっと安堵の溜め息をついた。
あかねも一緒に選んだ少しシックな浴衣は長い髪を後ろで一本に束ねている頼久によく似合っていて、とても落ち着いた感じだ。
いつもその姿で過ごしているのではないかと思うほど自然で、どこかぎこちない自分とは大違いだとあかねはこっそり溜め息をついた。
何を着てもまだまだ子供な気がする自分と、何を着ても何をしていても大人に見える恋人との差に最近少しばかり危機感を持っているあかねだった。
「さあ、早めに出てゆっくり参りましょう。天真達を待たせてもなんですので。」
そう言って頼久がすっと左腕を差し出した。
「はい?」
「下駄は歩きにくいでしょうから、どうぞ。」
余裕の笑みを浮かべている頼久に対して、腕を差し出されただけで胸がドキドキするのを止められないあかね。
顔を真っ赤にしながらも腕を差し出されたことが嬉しくて、あかねはきゅっと頼久の左腕に抱きついた。
「では、参りましょうか。」
「はい…。」
この世界へ来てからしばらくはこうして外で腕を組んで歩くなどとてもではないが恥ずかしくてできそうにない様子だった頼久だが、今となってはすっかりいつもあかねをリードしてしまう。
リードされること自体は嬉しいあかねだが、それでもなんだかいつも余裕でいつも一歩先を歩かれているような気がするのはやはり自分があまりにも子供なせいな気がして少しだけ悲しくなってしまう。
頼久に会うまでの浮かれた気分はどこへやら、恋人の腕を抱きながらうつむいてしまう自分をあかねはどうすることもできなかった。
愛しい恋人の腕を抱きながらもついつい考えてしまう。
京にいた頃は頼久がよく身分が違うだの、自分は従者だのと言ってあかねを困らせた。
あかねはいつも身分なんて関係ない、みんな同じ仲間だと何度言って聞かせただろう。
対等な相手として見てもらいたくて、普通の女の子として自分を好きになってほしくて必死だった。
それなのに今は、9歳も年が違ってまだまだ子供の自分が大人の頼久には似合っていないような気がしてならない。
「神子殿?」
隣を歩く恋人の異変に気付いた頼久が心配そうに声をかけてきても、あかねには寂しそうに微笑むことしかできなかった。
そんなところも子供っぽくて嫌なのにどうすることもできなくて…
「私は何か…その…お気にさわるようなことを致しましたか?」
「ち、違います!全然そんなことないです!」
「ですが、先程から何やら神子殿は……。」
「なんでもないんです。本当に、全然なんでもないですから。」
そう言って苦笑するのが今のあかねには精一杯だ。
まだまだ心配だが、これ以上かける言葉も見つからなくて頼久もとうとう黙ってしまう。
重苦しい沈黙が二人の間を埋めて、夕陽が美しいのさえ今のあかねにはつらかった。
二人でいれば会話のない静かな時間も苦痛に思うことはなかったのに、今は沈黙が苦しくてしかたがない。
それでも口にする言葉は見つからなくてあかねはただ頼久の腕を抱く手に力をこめた。
「あのなぁ、お前ら、まだ明るいんだぜ。もう少し遠慮しろって〜の。」
そう声をかけられて二人ははっと視線を上げた。
いつの間にか待ち合わせ場所に到着していたらしく、二人の目の前には天真、蘭、詩紋の三人が微妙な表情で立っていた。
言われて初めて頼久とあかねが自分達の姿を見てみれば、あかねが頼久の左腕にぎゅうぎゅう抱きついている状態で……
自分が何をしていたのかに気付いたあかねはパッとその手を頼久の腕から離した。
「まったく、二人きりだといっつもそんなべたべたしてるんだねぇ。」
「し、してないしてない!」
ニヤニヤしている蘭の一言にあかねが慌てて首を横にブンブン振る。
そんなあかねをフォローしようとした頼久の肩をポンポンと叩いて天真は苦笑して見せた。
あれはじゃれてるだけだから放っておけ。
と相棒が言いたいらしいのを察して頼久も苦笑する。
「ま、ベタベタしてるかどうかは置いといて、どう?あかねちゃん、この浴衣。」
そう言って蘭はくるりと回ってあかねに浴衣を見せた。
「うん、よく似合ってるよ。浴衣っていつもよりちょっと大人っぽく見えるよね。」
「だねぇ。あかねちゃんも色っぽいよぉ。頼久さんもメロメロだね!」
「蘭っ!」
「だよね?頼久さん。」
と、自分の方を振り返る蘭に頼久はただ黙って微笑んで見せた。
メロメロかと言われればもちろんそうなのだが、それは別にあかねが浴衣を着ているからというわけではない。
「お、はっきりしないなぁ。」
「バカ、お前。今の質問は答えにくいだろうが。どうせこいつは浴衣着てようが何も着てなかろうがあかねには四六時中メロメロなんだろうよ。」
「おお、なるほど。さっすがお兄ちゃん。」
「天真君っ!そ、そんなことないもん……頼久さんは別にメロメロなんかじゃ…ないもん……。」
すっと天真の視線が頼久へと向いた。
何故かと言えば、何があったのかは知らないが、ここで頼久がうつむいたあかねを放っておくわけがないからだ。
案の定、頼久はすっかり顔色を変えて何か言おうと口を開こうとしている。
「頼久。」
「なんだ?」
さきほどとはうってかわった頼久の不機嫌な声。
「たぶんお前は今、もんのすごくこっぱずかしいことを言おうとしているんだろうが、そういうことは家に帰ってからにしてくれ。人通り増えてきてる。」
言われて辺りを見回してみれば、浴衣をきた人や子供連れの家族などの姿が目立ち始めた。
近くにある神社に向かって小さな人の流れができてきたようだ。
「さ、行くぞ。」
先頭きって天真が歩き出すと、蘭と詩紋がそれに続く。
何やらうつむいてしまっているあかねに言葉をかけることを禁じられてしまった頼久は、あかねの手を取ると、あかねが驚くのにもかまわずにその手をギュッと握って歩き出した。
頼久としては本当はどれほど自分があかねにメロメロなのかを伝えたいのだが、どうやら今それをしてはいけないようなのでとりあえずはあかねを離さないと態度で示してみたわけだ。
驚きながらもあかねが頼久の手を振り解こうとする気配はなくて、二人は仲良く手をつないで夜店の並ぶ道を歩き始めた。
まだ人の流れもそんなに多くはなかったから、五人はゆっくりと夜店を一軒一軒見て回る。
「うわぁ、射的、お兄ちゃん得意?」
「苦手じゃねーけど、もっと得意そうなヤツがいる。」
前を歩いていた蘭と天真が足を止めて振り返った。
二人の視線の先にいたのはもちろん頼久だ。
京では武士として弓の腕も確かだった頼久だ、おそらく射的もうまいだろうと予想したのだが、二人は頼久の顔から手の方へ視線を移して同時に溜め息をつくと無言のまま詩紋を引きずって射的を始めた。
頼久があかねと手をつないでいるのを見て、これは射的のために頼久があかねの手を離すわけがないと勝手に判断したのだ。
そうとはわからない頼久とあかねは顔を見合わせて互いに小首を傾げたが、射的で盛り上がっている三人がとりあえず楽しそうにしているのでそれを眺めることにした。
天真はなかなかの腕前で蘭と詩紋がほしがった小さな人形を打ち落とし、意気揚々と戻ってきた。
「あ、あかねちゃん、リンゴ飴食べたいって言ってなかった?あそこにお店あるよ。」
「あ、ほんとだ。ちょっと買ってきますね、頼久さんも食べます?」
やっと楽しそうに自分を見上げてきたあかねに微笑みながら「いえ私は」と答えようとして、頼久はあかねの向こうで蘭が渋い顔をして首を振って見せているのに気付いた。
これはひょっとして自分がこれから口にしようとしている応えは不正解なのか?と気付いた頼久はもう一度あかねの顔を見つめてから一つうなずいた。
「頂きます。」
「じゃぁ、二つ買ってきますね。」
ぱっと花が咲いたような笑顔を見せたあかねが詩紋と二人で店の方へ走っていくと、蘭が頼久の腕を軽くぽんぽんと叩いてうなずいた。
「よくできました。」
「なんだよお前、偉そうに。」
抗議したのは兄の天真だ。
だが、どうやら自分の予想が正しかったらしいということに気付いた頼久は、友達思いの少女に苦笑を浮かべただけだ。
「頼久さん、自分はいらないって答えそうだったから牽制したの。あのね、恋する乙女のあかねちゃんとしてはここは大好きな人とおそろいで同じもの食べて歩きたいの。だから、チョコバナナ食べません?とか焼きそば食べません?とか聞かれてもオールOKするようにね。」
「お前なぁ…。」
胸を張って自慢げに話す妹に天真はうんざいりしたが、頼久の方はというと愛しい人の友人のありがたい忠告として聞いておくことにした。
あかねが食べるものの量などたかが知れている。
今宵ばかりはあかねが食べるものとそっくり同じものを食べるのもいいかもしれない。
頼久がそう思ってあかねと同じものを食べる自分を想像して微笑んでいると、そこへあかね達が戻ってきた。
「はい、頼久さん。」
「有難うございます。」
楽しそうなあかねの手からリンゴ飴を受け取って、頼久はそれを食べながらあかねと二人並んで歩き出す。
天真、蘭、詩紋が前を歩いて夜店を一つ一つ見て回るのを頼久とあかねは二人並んで見守った。
二人にしてみればお祭りの雰囲気を二人で並んで味わうことができればいいわけで、祭りだからといって何か特別なことなどしなくてもいいのだ。
「お兄ちゃん、喉かわいた〜。」
急にそう言い出したのは蘭だ。
「お前…俺に買って来いってか?」
「うん、私とあかねちゃん、あそこで金魚すくいしてるからよろしく!行こうあかねちゃん。」
「え?」
キョトンとするあかねの手を引いて蘭が金魚すくいを始めてしまい、残された男性三人は顔を見合わせて苦笑した。
こういう状況で一番行動力を発揮するのはいつも蘭なのだ。
「詩紋、お前、あいつらと一緒にいろ、放っておくとはぐれそうだ。頼久、付き合えよ、どうせだから全員分買ってこようぜ。」
「うむ。」
「わかった、じゃぁ、ボクは一緒に金魚すくいしてるね。」
こうして詩紋はあかね達のもとへ走っていき、頼久と天真は飲み物の調達へ向かった。
陽がすっかり落ちてだんだん人が増えてきて、飲み物を売っている店へたどり着くだけでも一苦労だ。
全員分の飲み物を買って二人が人込みを外れたところまでやってきた時にはもうあかね達の姿は金魚すくいの店にはなくて、二人は同時に溜め息をついて辺りを見回した。
頼久と天真は背が高いから見つけるのは簡単なのだが、あかね、蘭、詩紋の三人は背が低いからなかなか見つからない。
「参ったな、携帯かけてみっか。」
天真が飲み物を近くの石の上に置いて携帯を取り出したその時、頼久の目にあかねの姿が飛び込んできた。
夜店の明かりに照らされた浴衣姿のあかねが美しくて、頼久はその姿に一瞬見惚れた。
そして次の瞬間、頼久の体は動いていた。
あかねは蘭と詩紋と一緒に金魚すくいを楽しんで、みんなで二匹ずつ金魚をすくって立ち上がった。
辺りを見回すと凄い人の流れでどこにも頼久と天真の姿が見当たらない。
「ボクちょっと天真先輩達探してくるね。」
「うん、お願い。」
にっこり微笑んで詩紋が去ると、あかねと蘭は溜め息をついた。
「凄い人の数だねぇ。」
「大丈夫、あかねちゃんは私が守ってあげるから。」
「守ってもらうようなことは起こらないと思うけど…。」
二人がそんな話をしながらくすくす笑っていると、そこへ男の二人組が近づいてきた。
あかねはあっけらかんとしたものだが、蘭は急にきりっと鋭い視線をその男達へ向けた。
「あかねちゃん、気をつけてね、あれ、ガラ悪そう。」
「へ?」
耳打ちする蘭の言葉に目を白黒させているうちに二人組が近づいてきて、蘭の予言通り決して品がいいとは言えない口調であかねと蘭を口説き始めた。
普段、常に頼久と一緒に歩いているあかねにとってはこういうナンパ自体が初めての経験で、ただ目を白黒させるばかりだ。
あかねが目を丸くしている間に蘭が撃退を開始したが、どうやら目の前の二人組が遠慮してくれる様子はない。
ようやくあかねが事態を把握して、龍神の神子として戦っていた時の凛々しい表情を取り戻し、二人の男をにらみつけて口を開こうとしたその時、目の前の男達が急に後ろを振り返った。
そこにあったのは…
「頼久さん。」
「お兄ちゃん。」
天地の青龍二人の殺気に満ちた視線。
京では命のやり取りをしていた二人だ、その視線たるや物凄い殺気に満ちていて今まであかね達を口説いていた男二人は一瞬で顔色を青くした。
「俺の妹に何か用か?」
天真がそう言って威圧している間に頼久は俊敏な身のこなしであかねの隣にその身を移すと、その肩をしっかりと抱いた。
そうしておきながら、二人組に殺気を放つことも忘れない。
すっかり気圧されて男二人は何も言わずに逃げて行き、天真と頼久はそれからしばらくしてほっと安堵の溜め息をついた。
「まったく、何ぼーっとナンパなんかされてんだ、お前は。」
「神子殿、大事ありませんか?」
心底心配そうな顔をしている頼久にこくこくとうなずいて見せるあかねに対して、蘭はぷっとむくれた顔で上目遣いに兄をにらみつけた。
「そもそもお兄ちゃんが戻ってくるのが遅いからいけないのっ!」
「あのなぁ…。」
「頼久さんも天真君も有難う。私、びっくりしちゃってなんにもできなくって。」
そう言って恥ずかしそうに微笑むあかねが愛しくて、頼久のその肩を抱く手に力が入る。
天真はというと、スキを見せるなくらいのことは言ってほしい頼久がそんな状態だから脱力の溜め息をもらすしかできなかった。
「あ、二人とももう戻ってたんだ。」
間の悪いことにそこへ現れた詩紋は、天真に首を抱かれてそのまま頭をグリグリされてしまう。
「お前がこいつらのそば離れてどうすんだよっ。」
「い、痛いよ、天真先輩。」
ひとしきり詩紋のあたまをグリグリして気が済んだ天真は、詩紋を解放すると蘭の腕を引いて歩き出した。
「まったく、お前らが危なっかしいから買い物にも行けやしねぇ。焼きそばでも食うぞ、腹減った。」
「お、お兄ちゃん痛い!」
天真に引きずられるように歩き出す蘭を追って、詩紋はまだ頭を撫でながら涙目で、あかねは頼久に肩を抱かれたまま歩き出した。
それからはもう焼きそばだたこ焼きだと一行は天真の自棄食いに付き合わされるハメになった。
蘭とあかねがこれ以上食べられないと贅沢な不満の声をあげる頃、やっと店を回りつくした五人は帰路につくことにした。
蘭などはまだまだ見たい店があるのにとごねていたが、結局天真に引きずられてしまうのだ。
他の三人はもう遅いからと帰宅するのになんの疑問もはさまなかった。
「やっぱあれだな、浴衣が悪い。」
「何よ急に、お兄ちゃんだって浴衣気に入ってたじゃない。」
「俺はいいんだ。お前らだよ。」
そう言って天真は蘭とあかねを見比べる。
「あぁ、さっきのナンパの話ね。浴衣なんてお祭りじゃみんな着てるじゃない。ああいう場所じゃナンパ野郎なんていっくらでもいるの。しいて言うなら買い物行く時のお兄ちゃんの人選が間違ってたんだよ。」
「はぁ?」
「頼久さん置いて詩紋君連れて行ってれば誰も絡んでこなかったって。あかねちゃんに声なんかかけようものなら殺されそうじゃない。頼久さんならあかねちゃんにはりついて離れることもなかっただろうし。」
「ちょっと、蘭!」
真っ赤になて抗議するあかねとは逆になるほどと思わず言いそうになって天真は溜め息をついた。
「ハイハイ、俺が悪かったよ。てことだから、頼久、あかねちゃんと家まで送ってけよ。」
「もちろんだ。」
「じゃ、またな。ほら、行くぞ。」
「お兄ちゃん、だから痛いって。」
「またね、あかねちゃん。」
後で合流した三人と合流したのと同じ場所で別れて、また二人きりになったあかねは頼久に肩を抱かれて歩き出す。
そういえば何かを食べている時以外はずっと肩を抱かれたままだったと気付いてあかねは隣の恋人の顔を見上げた。
いつもと表情や様子はあまり変わらないが、どうやら自分の肩を離してくれる気はないようだ。
「どうかなさいましたか?」
「えっと、ずっとこのままですか?」
「はい?」
「あの、肩……。」
「あぁ。浴衣姿の神子殿は男達の目を引きますので、こうしていないと…。」
「は、はい?」
「お気づきではなかったのですか?」
「そ、そんなに人目は引いてないと思うんですけど…。」
人目を引いているというなら浴衣姿で悠然と歩いている上に長身な頼久の方がよほど女性の目を引いているとあかねは思うのだが、どうやら頼久とは見解が違うようで…
「今日の神子殿はいつもより一段と大人っぽくていらっしゃいますから、人込みの中を歩いていてもよく不穏な男の視線が…。」
「ふ、不穏って……そんな…。」
急に頼久の目が鋭くなってあかねは慌てた。
一瞬、武士として自分を警護してくれていた時の頼久の姿がちらついたからだ。
「でも、その…このまま歩くのはちょっと恥ずかしいというか…もうちょっと違う感じの方が……。」
「では、お抱きしましょうか。」
そう言って悪戯っぽく微笑む頼久にあかねは思いっきり首を横に振って見せた。
「け、結構です……このままでいいです…。」
あかねは顔を真っ赤にしてうつむいて、結局肩を抱かれたまま歩き続けることになってしまった。
どうしたってやっぱり大好きな人にはかなわない。
そう思って更に赤くなるあかねの肩を頼久は家に帰り着くまでずっと優しく抱いていた。
管理人のひとりごと
頼久さんに浴衣を着せたかったんです(’’)
それだけです(マテ
もともとが平安武士なので着物を着てたとは思うんですが、武士ですからね、浴衣みたいなくつろいだかっこうはなかなかしなかったでしょう。
みんなで浴衣着て夏祭り、楽しそうだなぁと。
で、あかねちゃんと蘭はナンパされまくりだろうなぁと(爆)
もちろんシスコンお兄ちゃんと神子殿命な武士の二人が容赦しませんが(’’)
プラザを閉じてお戻りください