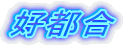
あかねは寒さを感じてゆっくり目を開けた。
まだ眠い目をこすって見えてきたのは明かりが漏れている蔀戸。
隣で眠っていたはずの夫の姿はもうそこにはない。
夫の頼久は必ず毎朝あかねより先の起きだして鍛錬をしているから、これはいつものこと。
あかねは寒さにふるっと震えて、体の上にかけてあった着物を抱き寄せながら身を起こした。
すると背中にも寒さが入り込んできて、本当に今朝は冷え込んでいるのがわかる。
一瞬、寒さに負けて着物にくるまって横になってしまいたい衝動を首を横に振って断ち切ったあかねは、着物を羽織って立ち上がった。
こんな寒い中でも朝から鍛錬を欠かさない夫のことを思えば、ここでひるんでいる場合ではない。
と、心の中で思っても寒いものは寒くて、あかねは苦笑しながら蔀戸の向こうへと歩き出した。
縁に立てばすぐそこの庭で黙々と木刀を振っている頼久の姿が。
あかねはにっこり微笑んでその場に静かに座った。
「神子殿、おはようございます。」
すぐさまあかねに気づいて頼久は木刀を振る手を止めた。
何より妻のことを優先するこの武士は鍛錬の最中であってももちろん妻を気遣うことを忘れない。
「おはようございます。私のことは気にしないで鍛錬続けてください。」
「ですが、寒くはありませんか?」
「大丈夫です、ちゃんと着物はおってきたし。それに、せっかく早く目が覚めたから、頼久さんの鍛錬するところ、見たいんです。」
「はぁ、神子殿にお見せするほどのものではありませんが…。」
「見られてるとやりづらいですか?」
「いえ、そういうわけでは。では、お言葉に甘えて続けさせていただきます。」
「はい、どうぞ。」
二人はにこりと微笑みあった。
そして頼久は笑みをおさめるとすぐに木刀を握り直し、鍛錬に戻る。
素早く己を切り替えて鍛錬に集中できるのは頼久が優秀な武士である証だ。
そう思えばあかねもなんだか嬉しくて、その顔には笑みが浮かんだ。
風を切る小気味いい音だけが早朝の庭に響き渡る。
綺麗な太刀筋の頼久をしばらく眺めてからあかねは急に立ち上がると屋敷の奥へと駆け出した。
その気配に気づきながらも頼久は一心に木刀を振り続けた。
屋敷の中へ入ったのなら危険はないから心配はない。
あかねのことだからまた何かを思いついてそれを即実行に移したのだろうとそう推測して、頼久は口元をかすかにほころばせた。
あかねのそういう闊達なところが変わらないことが嬉しいのだ。
異世界からやってきた自分を妻にした頼久に恥をかかせまいとあかねは今までとても努力してきた。
この京の女性に近づこうとすることであかねの本来の魅力が失われてしまうのではなかろうかと、頼久は心ひそかに心配していたのだが、どうやらそんな心配は無用らしいことが最近わかってきた。
この京を救った龍神の神子の魅力はどんなに時がたっても色あせることはないのだ。
そんなことを考えながら頼久が鍛錬を全て終えて汗をぬぐい始めたその時…
「きゃっ。」
常人の耳であればとらえることができたかどうかわからぬほど小さない、だが頼久の耳には届いたその悲鳴は、間違いなくあかねのもの。
そうと判断した刹那、頼久の体は疾風のごとく動き出していた。
木刀をその場へ放り出し、全力で声のした方へ走り出す。
屋敷の中を駆け抜けて頼久がたどりついたのは厨だった。
そこには何故か衣を水に濡らして床に座り込んでいるあかねの姿が…
「神子殿!どうなさったのです!」
顔色を青くして頼久が駆け寄ると、あかねは恥ずかしそうに苦笑した。
「だ、大丈夫です、ちょっと転んだだけ。」
「お怪我は…。」
「ないと思います、あちこち痛いけど。鍛錬が終わった頼久さんに冷たいお水を持っていってあげようと思って、それで器を持って歩いてつまずいいちゃって…ごめんなさい…。」
「私などのためにお気遣い頂いたばかりに…。」
「ああああ、私が勝手にそうしたかっただけですから!」
急に落ち込み始めた頼久にあかねは慌てた。
怪我をするようなおっちょこちょいを咎められるかと思いきや、この夫は妻にそんな気遣いをさせてしまった自分を責め始めたのだから。
「ほら、大丈夫ですか…痛っ。」
「神子殿!」
急いで立ち上がろうとして、あかねは急にふらつくと慌てて支えた頼久の胸に倒れ込んだ。
「いったぁ。」
「どこかお怪我を…。」
「右足がちょっと、痛い…です。」
申し訳なさそうにそういうあかねを座らせて頼久はあかねの右足の様子を見た。
すると明らかに熱を持って腫れ始めている。
「これは…ひねってしまわれたのですね…。」
「ああ、ごめんなさい…。」
「いえ、骨に異常はないようですから、腫れがひくまではゆっくり静養なさってください。」
「はい…。」
あかねが申し訳なさと情けなさでうつむいていると、急に体がふわりと浮き上がった。
不思議に思ってあかねが視線を上げれば自分の体はどうやら頼久に横抱きに抱き上げられて、さっさと屋敷の中へ運ばれているようだ。
「えっと、頼久さん、歩けないほどじゃ…。」
「いえ、無理をなさって悪化してはいけません。私のためにとお気遣い頂いたためにこのような怪我まで負ってしまわれたのですからこれしきのこと。」
「い、いえ、その、私が勝手にやって勝手に転んだんですけど…。」
と言ってみてももちろん頼久は下ろしてなどくれない。
あかねは頼久に抱き上げられたまま自分の局まで運ばれてしまった。
やっと頼久が下ろしてくれたのは局の一番奥だ。
「あ、有難うございました。」
「いえ、これしきのこと、お気になさらず。」
そういう頼久はあかねの向かい側に座って微笑んでいる。
と、ここであかねは小首を傾げた。
「頼久さん、お仕事ですよね?これから。」
「ああ、そうでした。」
そう言うが速いか頼久は奥から紙と筆を持ち出して何やらさらさらと書くとそれを使いに持たせて戻ってきた。
「頼久さん?」
「本日は一日ここにいることに致しました。」
「はい?だってお仕事…。」
「特に急ぐ仕事は入っておりませんし、雑務はこちらで済ませます。」
「でも…。」
「神子殿が怪我をなさっているというのに仕事どころではございません!」
珍しく大きな声で宣言されて思わずあかねもおののいてしまった。
普段はだいたいが神子殿のお望みのままにというスタイルでめったに声を荒げたりしない頼久なだけに、たまにこうして大声で何かを断言するととても迫力がある。
でも、新妻としてはここで引き下がるわけにはいかない。
「私のせいで頼久さんがお仕事をお休みするなんてダメですよ。ちょっと足をひねっただけなんだし…。」
「ですが、その状態では神子殿は満足に身動きがとれないでしょう。」
「大丈夫ですよ、どうしても動きたい時は誰か他の人に手伝って…。」
「他の者に手伝わせるくらいでしたら私がお運び致します!」
また大きな声で断言されてあかねは目を丸くした。
どうも今回は今までとは勝手が違うようだ。
「でも…。」
「いつもは私の仕事を優先してと神子殿には御不自由ばかりおかけしております。このような時くらいこの頼久に頼っては頂けませんか?」
「へ、私はいっつも頼久さんに頼りっぱなしですよ?」
「いえ、神子殿はいつもお一人で何から何までよく努力しておいでです。私などにお手伝いできることは少なく…怪我を負った時は誰しも心細いもの、このような時くらいはこの頼久にも何かさせて頂きたいのです。」
「頼久さん…。」
ここまで言われて訴えるような目で見つめられてはもうあかねに抗うことはできない。
「わかりました。頼久さんがそこまで言ってくれるなら、じゃぁ、お願いします。」
「はい、お任せを。」
嬉しそうにそう返事をして頼久はにっこり微笑んだ。
普段が無表情だのぶっきらぼうだのと言われる人なだけにたまに見せるこういう笑顔にあかねは弱い。
一瞬夫に見惚れて、それから我に返ってあかねは顔を赤くしてうつむいた。
「神子殿?お顔の色が赤いようですが、熱でも…。」
「ち、違います!」
ここで熱があるなどと勘違いされては更に物凄い看病をされてしまうとあかねは慌てて否定した。
「頼久さんとこんなふうにゆっくり一緒にいるの久しぶりだから…。」
「神子殿…申し訳ありません。」
「へ?」
「いつも神子殿には御不自由を…。」
「ふ、不自由はしてないです!全然してないです!」
「ですが、本日は誠心誠意、神子殿にお仕えさせて頂きますので。」
「つ、仕えてもらわなくてもいいんですけど…。」
と言ってみても、目の前の夫はどう見てもやる気満々で…
こうしてあかねは一日、夫のつきっきりの介護を受けることになった。
「静かですねぇ。」
日が暮れて辺りが薄暗くなって、局に明かりが灯される頃、あかねは何気なくそうつぶやいた。
珍しく二人きりで過ごす一日は思いのほか早く終わってしまって、少しだけ寂しい。
「皆もう休んだのでしょう。月も出ておりますし。」
「月が出てるんですか?」
「はい。」
あかねの目の前にいる頼久はそう答えるとにっこり微笑んですっとあかねの後ろへ回り込み、その小さな体を抱き上げた。
「よ、頼久さん、いいですってば。」
「いえ、神子殿も美しい月を御覧になりたいでしょう。」
「そ、それはまぁ、そうなんですけど…。」
と、あかねがもごもご言っている間に頼久はあかねを抱き上げたまま縁まで出てしまった。
外は身が引き締まるような寒さだが、あかねは寒さを感じない。
それはもちろん、妻を冷やしてはと抱きかかえたまま頼久が離さないからだ。
あかねが早朝、厨で捻挫してからというものこの一日、こうして頼久は何かというとあかねを抱き上げて運び、本人が宣言したとおり一日中あかねにはりついていたのだった。
「うわぁ、綺麗。冬の空って綺麗ですよね。」
「はい。お寒くはありませんか?」
「大丈夫です。」
腕に抱きかかえた妻が幸せそうに微笑んでいる。
それを目にするだけで頼久は嬉しそうだ。
「すみませんでした。」
「はい?」
つい先ほどまで月に見惚れていた妻が今度は自分の腕の中でなにやら落ち込んでいるらしいことに気づいて頼久は目を見開いた。
何を謝られているのか見当もつかない。
「私が朝、よけないなことしようとして転んだりしたから、頼久さんに一日迷惑かけちゃって…。」
「迷惑などではありません!」
「頼久さんは優しいからそういってくれますけど、一日中私をこんなふうに運んで歩くの、やっぱり迷惑ですよ…。」
「神子殿…。」
頼久は妻を抱く腕に優しく力を込めた。
どれほど自分がこの人を想っているか伝わるように。
「迷惑だなどということはありません。本心から申し上げているのです。」
「……。」
それほど説明してもあかねの視線は上がらない。
頼久はよくよく考えてから縁に腰を落ち着けた。
もちろん、妻は膝の上に乗せて抱きしめたままはなさずに。
そして落ち込み続ける妻を更に抱きしめて口を開いた。
「では、真実を申し上げますが…。」
「はい?」
「今日一日、私はとても幸福でした。」
「へ?」
「神子殿が怪我をなさっているというのに幸福というのは不謹慎かと思い、黙っておりましたが…。」
「どうして私が怪我をすると頼久さんが幸せなんですか?」
「いえ、神子殿が怪我をなさったからということではなく…神子殿が身動きできませんでしたので…。」
「だから頼久さんにいっぱい迷惑かけちゃったんじゃないですか…。」
「いえ、ですから…神子殿が身動きできませんでしたので、私は一日こうして何はばかることなくなく神子殿をお抱きすることができましたので…。」
「へ。」
更に優しくぎゅっと抱きしめられてあかねは顔を真っ赤にした。
「あの…別にそんな…こんな理由がなくても…頼久さんは私の旦那様なわけですし…抱き上げるくらい気にしないでやってもらっても…。」
「宜しいのですか?」
嬉しそうな声が頭上から降ってきて、あかねは思わず視線を上げた。
そこには期待に満ちた夫の顔が…
「え、えっと…。」
ここで「いいです」と言ってしまうと、この夫はそれこそ本当に毎日自分を抱き上げて歩くような気がして…
それくらいこの人の愛情が深いということをあかねはこの1年近い時間でよく理解しており…
そんなことになったら八葉のみんなが遊びに来たときとかもそうされてしまう予感がするわけで…
「た、たまになら…。」
「承知致しました。」
嬉しそうに答えた頼久は再びあかねをぎゅっと抱きしめた。
抱きしめられたあかねはというと、本当にたまにで済むのだろうかと少しだけ不安に思いながら、やっぱり暖かい夫の胸にうっとりともたれてしまうのだった。
管理人のひとりごと
さむーい冬のある日の源さんちを切り取ってみました(笑)
冬の寒さもあかねちゃんの怪我ももうこの家ではいちゃつく理由にしかなってません(’’)
頼久さんは意外とあかねちゃんを屋敷で一人にしていることを気にしています。
あかねちゃんはきっと他の八葉のみんなも遊びに来てくれるのでそんなに寂しくないです。
頼久さんが一人であかねちゃん欠乏症になっているものと思われます(’’)
プラウザを閉じてお戻りください