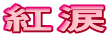
夏休みが明けてしばらくするとあかねは文化祭の準備があるとかで頼久に顔を見せに来る日が極端に減った。
つい先日、過労で倒れたばかりだというのにあかねの体は大丈夫だろうかと頼久が心配するほどあかねは忙しそうにしている。
だが、心配するのと同時に頼久は一抹の寂しさも感じていた。
夏休みの間中、毎日のようにあかねの顔を見ていたし、天真や蘭、詩紋といった友人達もちょくちょく遊びに来ていただけに、夏休みが終わってすぐの頼久はぽつんと取り残されたような感じになった。
4人は現役の学生なのだから学校へ行くのは当然のことだし、夏休みが終わればこうなることはわかりきっていたのだが、それでもやはり頼久の胸の内には寂寥感がぬぐえなかった。
朝の鍛錬、朝食を一人で終えて書斎へ入る頃にはあかねからいってきますのメールが入る。
昼食の頃にあかねからお昼休みのメールが届いて、夕方、あかねから今日は疲れたので帰って寝ますのメールがくる。
そんな日が何日か続くと、頼久自身も気付かぬうちにその顔には影が射した。
自分から会いに行こうかと考えたことも何度かある。
だが、年上の自分があかねの自宅へ頻繁に会いに行ったりなどしたら、あかねに迷惑をかけることになるのではなかろうか?
そう思うとやたらと会いに行くこともできなかった。
だから一日色々考えて、結局、頼久は自宅であかねとメールのやり取りをするだけで溜め息をつくことになる。
今日も昼休みの時間まではいつもと同じだった。
朝はおはようといってきますのメールが来て、昼休みに天真が弁当のことで蘭と喧嘩をしたというメールがきた。
そこまではいつものこと。
ところが、夕方になっていつもとは違った内容のメールが来た。
『これから行ってもいいですか?』
こんなメールが来たことは今まで一度もなかった。
今から訪ねてもいいかというメールは来るが、そういう時はたいてい他の話も楽しそうに綴られていたのだ。
だが、今回は違う。
訪ねてもいいかをきくだけのたった一行のメール。
頼久は嫌な予感がしてすぐに返信した。
『今すぐにでもどうぞ。お待ちしております。』
返したメールもそれだけ。
とにかく今は一刻も早くあかねの顔が見たかった。
もちろん、自分が寂しかったからというのもあるが、それ以上にいつもとは違う簡素なメールを送ってきたあかねの様子が気になった。
何か落ち込んでおいでなのではないか?
誰かに傷つくようなことを言われたのではないか?
いや、神子殿は誹謗中傷されるような方ではない。
などなど。
頼久が一人で悩むこと数分。
結局、話をしてみなければ何が起こったのかなどわからないという結論に達し、頼久はあかねを迎える準備を始めた。
あかねが何か落ち込んでいるようならできる限りのもてなしをしなくては。
そう考えた頼久はまずお湯を沸かした。
これであかねの好きなローズティをいれることができる。
あとは甘いもの。
これもあかねには欠かせない。
頼久は普段、甘い物はほとんど食べないが、それでもあかねが来たときのためにと多少は常備しているものがある。
それらを確認して準備万端とばかりに頼久は台所で一人うなずいた。
沸いた湯をポットへ移し、いつあかねが訪ねてきてもいいようにティーポットに茶葉も入れておく。
そうして待つこと数分。
いつものように恋人の気配を感じて頼久は玄関へ向かった。
ゆっくりとドアを開けるとそこには想像していた以上に衰弱しているように見えるあかねが立っていた。
「こんにちわ。」
そう言って微笑む笑顔も力なくはかなげだ。
「神子殿…。」
あかねのあまりの弱りぶりに驚いた頼久だったが、ここは玄関、とにかく中に入れなくてはとあかねを招き入れて、自分はすぐにキッチンへ向かった。
いつもなら自分が準備すると言ってくるあかねが今日はへなへなとソファに座ったまま動かない。
これはよほどのことかと頼久は顔色を青くしたが、とりあえずはローズティを入れて甘いお菓子と一緒にあかねの前に置いた。
「どうぞ。」
「有難うございます…ごめんなさい、みんなやってもらっちゃって……とっても疲れてて…。」
「わかっておりますのでお気になさらず。」
頼久はできるだけ優しく微笑んだつもりだったが、あかねは頼久の顔を見上げるとその綺麗な目に涙を浮かべた。
頼久がぎょっとして、慌ててあかねの隣に座る。
「学校で何かあったのですか?」
「ごめんなさい。久しぶりに会ったのに私…。」
それだけ言うとあかねはぽろぽろと涙をこぼし、声を殺して泣き始めてしまった。
一瞬顔色を青くして右往左往しそうになった頼久だが、すぐに肩を震わせて泣いているあかねの肩を抱き寄せた。
この状態では話を聞くのは不可能だし、言葉が苦手な自分では言葉で慰めることもできない。
となると、もうできることはそっとそばに寄り添っていることだけだ。
甘いローズティの香りが薫る部屋で、あかねは頼久に肩を抱かれたまましばらく泣き続けた。
京であれほど厳しい戦いの日を送っても決して泣き崩れたりはしなかったあかねが、何も話さずに泣き続けるとはよほどのことがあったのだろうと察して頼久もただあかねを見守った。
すると、しばらくしてあかねは手の甲で涙をぬぐいながら顔を上げた。
「ごめんなさい。急に。びっくりしましたよね。」
「いえ、何かおありなのだろうとは思っておりましたのでご心配なく。」
「へ?どうして何かあったって思ったんですか?」
「頂いたメールの様子がいつもと違っておりましたので。」
あかねが驚いて目を見開いた。
涙に濡れてはいても悲しげな表情とは別の顔を見ることができて頼久は内心、ほっと安堵した。
「その…何があったのかお聞きしても宜しいでしょうか?」
「えっと…。」
言おうか言うまいか一瞬だけ躊躇してうつむいたあかねは、何かを決意したように一つうなずいてから頼久をまっすぐ見つめた。
「あの…頼久さん。」
「はい。」
「私って八方美人で、いやな子だと思います?」
「は?」
「いやだから…その…誰にでもいい顔してきれいごとばっかり言ってかっこつけてるように見えます?」
今度は聞き返さず、頼久は問われた内容をよく脳内で吟味した。
目の前のこの恋人は何を知りたがっているのか?
そんなことを憶測してみてもとうてい自分にあかねが知りたがっていることが推測できるはずもない。
そう考えて一つ溜め息をついて、頼久はとにかく聞かれたことに正直に答えることにした。
「神子殿は誰にでもいい顔をなさってはおりません。嫌いなものは嫌いだとおっしゃるでしょう。」
「まぁ、そうですけど…。」
「おっしゃることもきれいごとなどではありません。神子殿はいつも前を向いていらっしゃるだけのことです。」
「前を向いてる?」
「はい。何が起こっても決してあきらめることなく、前へ進む。神子殿はそういう方です。そうやって我々を導いてくださいました。そして京をお救い下さった。」
「そ、そうでしょうか…。」
「京だけではありません。神子殿の前向きで純粋なお心が私をもお救い下さったのです。」
「頼久さん…。」
「そんな神子殿をきれいごとだけだなどと言う者がいるのなら、そのものの心根こそ曲がっているのです。」
「でも…みんなが仲良く、みんなが楽しくできるようにって…本当は不可能なことなのかもしれないって思って…そういうことを目指そうって言っちゃう私ってやっぱりきれいごとを言ってるんじゃないでしょうか…。」
「私はきれいごととは思いませんが…。」
「……。」
あかねは黙って考え込んでしまい、頼久の口はこれ以上うまくは動いてくれなかった。
京で過ごしていた時よりもずっとこちらの世界へ来てからの方が、頼久が己の口下手を呪うことが増えた。
今も、目の前で落ち込むあかねにどんな言葉をかけていいのかわからない。
頼久の中であかねが何にも代えがたい女神のような存在であることは間違いないのだが、それをうまく表現することができないのだ。
仕事で文章を書くことはできるのに、どうしてこうも口を使って言葉を紡ぐことは苦手なのかと頼久は己を責めるしかできない。
そしてそんな頼久に気付いたあかねはすっと視線を上げると力ない微笑を浮かべて見せた。
「ごめんなさい。私のせいで頼久さんまで嫌な気分になっちゃいましたね。」
「そ、そのようなことはありません!」
慌てて否定してみても眉間にシワをよせていただけに、頼久自身も説得力がないと自覚してしまう。
だが、たとえ自分には何もできないとしても、気のきいた言葉一つかけられなかったとしても、頼久にこのままあかねを放っておくことなどできようはずもない。
だから、頼久は思い切って思い通りには動いてくれない口を開いた。
「何が、神子殿をそのように傷つけたのですか?」
尋ねていいことなのかどうかもわからぬままそう口にした頼久に、だが、あかねはゆっくりと答えは始めた。
「文化祭の準備が迫ってて…。」
「は?」
「夏休み前から文化祭で出し物、何にするかって色々クラスで話し合ってたんです。」
「はぁ。」
「それで、やりたいことが二つに分かれちゃって。喫茶店をやりたいっていう人達と、劇をやりたいっていう人達にクラスが真っ二つに分かれちゃったんです。」
「神子殿はその双方が納得する道を探そうとなさったのですね?」
「はい。どちらかを選ばなきゃいけないとしてもなるべくならみんなが納得するように話し合いをって思ったんですけど…そんなのただのきれいごとだって言われちゃって…私はいつも八方美人で誰にでもいい顔をしたいだけなんだって……。」
頼久は深い溜め息をついた。
この清らかな心の持ち主をどうしたらそのように愚弄できるのか理解に苦しむが、今はそれどころではない。
なんとか愛しい人を元気付けたいと思っても、今の頼久に言葉でそれをなすのは至難の業だ。
だが、言葉以外でどうにかできるかといわれればそれも不可能で…
そう、このように迷った時はいつでもあかねが道を指し示してくれたのだ。
頼久は怨霊と戦っていた頃のことを思い起こしてふっと微笑んだ。
「頼久、さん?」
「神子殿の信じるようになさればよろしいかと。」
「信じるように、ですか?」
「はい。我々はいつも神子殿に導いて頂いてきたのです。その道はたとえ茨の道であっても、間違っていたことはありません。ですから、どうか神子殿の信じるままに。」
「…どうしたらいいかわからないんですよね…京にいた頃は私がやらなきゃ、私しか龍神の神子はいないんだからって頑張れたんですけど…この世界だと、私はただの女子高生で…私の意見なんて何十人もいるクラスメイトの意見の一つでしかないんですよね…。」
「神子殿…。」
落ち込み続けるあかねを前に頼久は必死で考えた。
今まで自分に全てを指し示してくれていた人が悩み、迷っている。
今こそ自分が力になって差し上げたいと思っても、頼久にはそれが難しいのだ。
あかねの望みをかなえるためにはどうしたらいいのか。
落ち込むあかねの隣で必死に考えて、頼久はようやく一つ選択肢を見つけた。
「両方、というわけにはいかないのでしょうか?」
「はい?両方って?」
「ですから、喫茶店と演劇、両方を行うことはできないのですか?」
頼久の意見にあかねは一瞬目を大きく見開いて驚いた。
「えっとそれは…予算とか限られてるし…時間も…。」
「双方が歩み寄って半分ずつ使えばできるのではないでしょうか?」
「予算も時間も半分ずつ、かぁ…でも場所が…。」
「それは、演劇を見ながら茶の飲める喫茶店、ではいけないのでしょうか?」
「へ?」
「喫茶店の中に舞台を作ってそこで寸劇のようなものを上演すればあるいは可能かと…。」
「なるほど!それいいかも!」
あかねはカバンの中から手帳を取り出すと、何やらせかせかとメモをとり始めた。
どうやら今の頼久の提案を詳しくメモしているようだ。
頼久はどうやら自分の存在など忘れてメモに熱中しているらしいあかねを優しく見守った。
「これでよしっと、あ、頼久さん、有難うございました。明日、提案してみますね。」
「お役に立てたのなら何よりです。」
「もし実現したら、その……えっと…頼久さん。」
「はい。」
「文化祭、見にきてくれますか?」
可愛らしく上目遣いにそう尋ねられて頼久に断れるはずがない。
「はい。ご迷惑でなければ是非。」
「迷惑だなんてことありません!絶対、来てくださいね。」
「はい、承知致しました。」
何があっても絶対に文化祭の日は空けようと心に決めて、頼久はあかねにティーカップを渡した。
その顔には今までの憂鬱そうな弱々しさはもうなくて、いつもの明るいあかねの笑顔が戻っていた。
「私、なんか、頼久さんには助けてもらってばっかりですね。」
「いえ、そのようなことは…。」
「ううん、助けてもらってばっかりです。こっちの世界へ来たら、頼久さん、きっとわからないことたくさんあるだろうから、私が助けてあげるんだって意気込んでたんですけど、全然大丈夫だし。私なんかよりずっとできること多いし、本当に助けてもらってばっかり。何かお返しできることありませんか?」
「は?」
「だから、いつも助けてもらってばっかりだから、私が何か頼久さんにしてあげられること……何かないですか?」
両手で包み込むようにティーカップを持ったあかねが頼久を見上げている。
そのしぐさも視線も、何もかもが頼久には愛しくて。
何かできることがあるか?などと可愛らしく聞かれては頼久も逆に何を頼んでいいかわからなくなってしまう。
表面には出さず、頭の中で右往左往した頼久は優しく微笑んであかねの手からティーカップを取り上げるとその肩を抱いた。
「よ、頼久さん?」
「何かできることはないかとお尋ねでしたので。」
「へ?」
「しばしこのままでいて頂けますか?」
「そんなことでいいんですか?」
「私にとってはとても重要なことです。」
「そ、そうですか…。」
「はい。」
肩を抱かれてそう言ってやわらかな笑みを浮かべられてはあかねも抵抗などできなくて。
顔を赤くしたまましばらくあかねは頼久に肩を抱かれていることになった。
これじゃぁいつもとかわらないじゃない。
と心の中でつぶやきながら。
「お前は…新学期が始まって文化祭の準備もあり、忙しいのではないのか?」
あかねが頼久に悩みを解決してもらった三日後、天真が夜半にいきなり頼久の家を訪ねてきた。
手にはもちろん酒瓶を持っている。
「あのなぁ、俺はお前に有益な情報を持ってきてやったんだ、もう少し歓迎しろ。」
「なんの話だ?」
そんな会話を交わしながら二人はリビングのソファに腰を下ろす。
なんだかんだ言っても頼久はこの真の友を追い返すようなことはめったにないのだ。
「お前、文化祭の日、絶対空けておけ。」
「お前に言われるまでもなくそのつもりだが?」
「これを見逃したらお前、一生後悔するぞ。」
「何の話だ?」
「あかねだよ。」
「ん?」
持参した缶ビールを開けて一気にごくごくと喉を鳴らして飲んでから、天真はギロリと頼久をにらみつけた。
「なんだ?」
「あいつのクラス、演劇喫茶とかいう企画通ったらしい。根っからの武士なお前には珍しく、あかねに入れ知恵したらしいじゃねーか。」
「入れ知恵というほどではないが…。」
「あかねが嬉しそうに話してた。でな、あかね、ウェイトレスやるぞ。」
「ほぅ、喫茶店の方に参加なさるのか。」
「違う。」
「ん?」
「あかねは午前の部はウェイトレス、午後の部は寸劇でちゃんとセリフのある役やるぞ。」
「掛け持ちなさったのか。」
「あぁ、だからこっちにはしばらく忙しくてこれねーだろうけどな、我慢しとけ。文化祭でいいもん見れる。」
「だから、何の話だ?」
「お前、あかねのウェイトレス姿が見れるんだぞ。」
「………。」
改めて天真に指摘されて頼久は頭の中であかねのウェイトレス姿を想像した。
可愛らしい…とてつもなく可愛らしい。
「頼久、お前、目がうつろになってんぞ。」
「…すまん……。」
「ウェイトレスだけで満足すんな。なんと、午後の部は演劇で天女の役だぞ、あかね。」
「て、天女?」
「羽衣伝説あるだろ、あれの天女役だ。つまり、文化祭に行けばあかねのウェイトレス姿と天女姿の両方が拝める。」
「それは…。」
なんという幸福かと頼久は天を見上げた。
天といっても見えたのは天井だが。
「感極まってんじゃねーよ…。」
「神子殿はもとより京では天から舞い降りた天女のようなお方であった。さぞかしお似合いだろう。」
「………。」
そうだった、こいつは神子殿バカだった。
と天真が心の中でつぶやいた時にはもう遅く、この夜、天真は一晩中、うっとりしている頼久に付き合わされるハメになるのだった。
管理人のひとりごと
あかねちゃん、文化祭に向けて始動です(笑)
ウェイトレスと天女て…なんかコスプレみたいだな(’’)
と自分でつっこみつつ。
あかねちゃんの両親を篭絡した頼久さんですが(爆)さすがに毎日のように通うことは控えるようです。
あかねちゃんに鬱陶しいなんて思われたら生きていけないので(笑)
最後は鼻血ふきそうな勢いの頼久さん妄想モードでしたが、大人だからきっとあかねちゃんの前ではまともに振舞うと思われます(爆)
プラウザを閉じてお戻りください