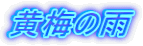
あかねは御簾の内側から外を眺めてため息をついた。
耳に届くのはかすかに聞こえる雨音のみ。
桜がすっかり散って、もうすぐ夏になると喜んでいたところにやってきたのが雨の続く鬱陶しい空だった。
そう、ここ京にも梅雨というものがあるのだ。
生まれ育った世界にはビニールのカッパもあれば便利な折り畳み傘もあった。
窓を閉め切っていても除湿機なんていう便利な物もあったし、長靴をはけば足を濡らさずに外出することもできた。
けれど、こちらの世界ではそんな便利なものは一つも存在しない。
あかねはじめじめとした鬱陶しさの中で雲の向こうで輝いているだろう太陽を想像するしかなかった。
べつに雨が降っているからと言ってあかねが困るようなことはあまりない。
外出はもともとあまりしないし、する時はどうせ牛車を使った方がいいと言われているのだから使えばいいのだ。
もともとこちらの世界の女性はあまり外出しないから、きっと雨でも困ることはないだろう。
乾かないだろうなぁと心配する洗濯物も、あかねが洗濯させてもらえるわけじゃない。
食べ物もカビちゃうなと心配して、それからカビるほど長期間保存がきく食べ物がこちらにはほとんどないことに気付いた。
つまり、雨だからと言ってあかねが困ることは今のところあまりないと言うわけだ。
唯一の心配といえば、外で仕事をすることの多い夫が雨に濡れて凍えてはいないか?ということくらい。
その夫、頼久も雨でぬれたくらいで体調を崩すなどという軟弱な男ではないから当の本人は雨だからといっておそらく困っていたりはしないだろう。
それでも、あかねは朝からしきりに雨粒を落とす曇天を見上げてため息をついた。
こんなふうに憂鬱になるのはやっぱり辺りが暗いからだろうか?
それとも昨夜は頼久が宿直で帰ってこなかったから?
原因がわからないまま、あかねは再びため息をついた。
晴れていればちょっと藤姫のところまで出かけて気晴らしということもできないわけじゃない。
もちろん、雨が降っていたからと言って出かけられないと言うわけでもない。
それはわかっていてもなんだか憂鬱で、あかねはため息をつくことしかできずにいた。
「気が淀んでいるな。」
「泰明さん?」
先に声だけが聞こえてきて、あかねは慌てて辺りを見回した。
すると、御簾を上げて声の主はいつもよりもほんの少しだけ不機嫌そうな顔で姿を現した。
もちろん、声の主は泰明だ。
常に表情を動かすことのないこの稀代の陰陽師は今、あかねの前にかすかに不機嫌そうな顔で座った。
「どうしたんですか?今日、約束とかしてなかったですよね?」
「約束はしていない。が、数日前、頼久から神子の様子が少し気にかかるから暇ができたら訪ねてほしいと依頼されていた。」
「よ、頼久さんが?」
「仕事が入っていて今日になった。確かに気が淀んでいる。」
「淀んでって…。」
相変わらず容赦のない物言いの泰明にあかねは苦笑を浮かべた。
どうやら大切な旦那様にすっかり憂鬱な気分を見抜かれていたことに驚いてはいるものの、それよりもはっきりと淀んでいると断言する泰明の物言いに圧倒されてしまった。
「それって、もしかして病気ってことですか?」
「いいや、気が淀んでいるだけだ。問題ない。」
「問題、ある、気がするんですけど…。」
「黄梅の雨が降る時期には良くあることだ。特に女人には。」
「黄梅の雨?」
「この時期に長く続く雨のことだ。」
聞き慣れない単語にあかねが小首を傾げれば、泰明から間髪入れぬ解答が飛び出した。
なるほど梅雨のことかとあかねが納得していると、泰明の顔がすっとあかねの方へ近づいた。
「泰明さん?」
「気鬱になっているだけだな。」
「確かにじめじめしてて嫌だなぁとは思ってました。でも、ちょっと憂鬱って言うだけですから、大丈夫ですよ。」
「いや、気鬱は放っておくと病になりかねん。」
「ああ、病は気からって言いますもんね。でも、そんなにひどくは…。」
「放ってはおけぬ。」
「ん〜、じゃあ、何か気晴らしでもした方がいいのかなぁ…泰明さんは何をすればいいと思いますか?」
「わからぬ。私は気鬱にはならぬ。」
あかねは「あはは」と力ない声をあげて苦笑した。
なるほど泰明は雨くらいで動じる精神など持ち合わせてはいないわけだ。
これはどうしたものかとあかねが考え込み始めたその時、耳慣れた足音が聞こえてあかねの顔がぱっと明るくなった。
その様子に泰明がうっすらと驚きの表情を浮かべるのと、御簾が上げられてあかねの見慣れた長身が中へ入ってくるのとは同時だった。
「お帰りなさい、頼久さん。」
「ただ今戻りました。泰明殿、来てくださっていたのですか。」
「ああ、ついさきほど。」
「にしては、濡れていらっしゃらないようですが…。」
「雨を避けた。」
「……。」
頼久とあかねは顔を見合わせて苦笑した。
今帰ってきたばかりの頼久は全身がしっとりとぬれているのだが、泰明は全く濡れていない。
どうやらこの稀代の陰陽師は雨粒を避けるということができるらしい。
そうとわかってもそうですかと納得できるわけもなく、けれどそこを追及しても泰明からわかりやすい返答が返ってくるとも考えにくく…
二人は顔を見合わせて苦笑しただけでこの話題には突っ込まないことにした。
「して、泰明殿、神子殿の御様子はいかがですか?」
「少々気鬱になっていたようだが。」
「やはりそうでしたか。ここのところ、雨が続いておりますゆえ。」
「だが、今はもう問題ない。」
「は?」
「お前が戻って、神子の気も安定した。」
「へ……。」
思わぬ泰明の断言にあかねが思わず声を漏らした。
思い返してみれば、確かに頼久が帰ってくると気分が良くなっている気がする。
そっと隣の頼久の様子をうかがってみれば、端整なその顔は優しそうな微笑を浮かべて自分を見つめていた。
「私がおそばにいることで神子殿の気が安らかになられるのでしたらいくらでもおそばに。」
「そうはいくまい。お前にも武士団の若棟梁としての責務がある。」
「いえ、雨がやむまでは…。」
「ダメです!そんなことでお仕事休むのは絶対ダメです!」
どうやら自分が側にいればあかねは気鬱にはならないらしいことが嬉しくてしかたがない頼久がとんでもないことを言いだしたので、あかねは慌てた。
あかねが幸福であるためなら今すぐ若棟梁を引退するとか言い出しかねないのが頼久だ。
そんなことになればあかねは幸せでも武士団の人間だけでなく、困る人が大勢出てくる。
頼久が一日休むというだけでも武士団は大騒ぎになるのだ。
「しかし、神子殿が病になどなられてはいけません。たかが気鬱と侮っては…。」
「侮ってはいませんけど、でも、頼久さんがお仕事を休むのはダメです。」
「では、どうすれば…。」
頼久は眉間にシワを寄せて考え込んだ。
このままでは雨が降っている間、頼久が仕事で屋敷を開ければあかねが気鬱になってしまう。
それが続いたならあかねはとうとう病になってしまうかもしれない。
それを避けるためにはいったいどうすればいいのか?
自分が仕事を休まずにあかねを気鬱から救う策、それを頼久は必死で考えた。
「要は気の滞りがなくなれば良いのだ。」
突然断言したのは泰明だった。
そう、この場には気のことなら誰よりも詳しい人物がいたではないか。
「泰明殿、何かよい策がおありなのですか?」
「神子の気が晴れることをすればよい。」
当たり前だろうと言わんばかりの泰明に頼久の視線は自然とあかねへ向いた。
あかねの気が晴れること。
それはあかね自身にしかわからない。
「神子殿。」
「気が晴れること、ですか…。」
泰明と頼久にじっと見つめられてあかねは考え込んだ。
頼久が側にいなくても雨のことなど忘れて楽しくなれるようなこと…
生まれ育った世界ならテレビを見る、映画を見る、ゲームをする、色々と思いつくこともあるけれど、こちらの世界となるとそうはいかない。
「えっと…琴の練習とか……お香の勉強とか……でも一人だとはかどらないんですよね…。」
「ならば師を呼べば良い。」
「師?あ、そうか、先生になってくれる人を探せば…。」
「探す必要はない。琴ならば友雅を呼び出せば良いだろう。香も友雅で良いが、それは永泉でも構わぬだろう。」
「あ、永泉さんに琴に合わせて笛を吹いてもらうのも楽しそう。」
「書を学びたいのであれば鷹通を呼べばよし、都の様子が知りたければイノリを呼べば良い。神子には八葉がついている。」
「そっか、なるほど。でも、みんな忙しいんじゃ…。」
「神子のためとあらば一日や二日の時間は誰でも作るだろう。」
ということは、一人に集中しなければいい、というわけだ。
あかねは仲間達の顔を次々に思い浮かべて、そしてその顔に笑みを浮かべた。
「わかりました。じゃあ、みんなに順番にお願いしてみます。」
いいことを思いついたとばかりに微笑むあかねに泰明は一つうなずいて見せた。
これで問題は解決、したはずなのだが…
この場で唯一人、頼久だけはその顔をうっすらと曇らせていた。
「昨日は永泉さんがお香をたくさん持ってきてくれて、色々合わせ方も習ったんです。それから、今日は友雅さんが琴を教えに来てくれるんです。みんな忙しいのに二つ返事で駆け付けてくれて、凄く楽しいです。」
「左様でございますか…。」
「鷹通さんも色々面白そうな物語を探してくれてるみたいなんです。面白い物語の方が文字を覚えるのも楽だろうって。」
「はぁ…。」
「泰明さんはお仕事忙しいみたいなんですけど、時々式神をよこしてくれます。」
「……。」
「雨だと外出できないだろうからってイノリ君は時々自分から話をしに来てくれて、お土産においしいものも持ってきてくれるんです。」
朝餉を前にあかねは頼久にここ数日の楽しさを語って聞かせていた。
梅雨が明ける気配はまだなくて、あかねの気晴らしのためにと元八葉の面々はあかねのお願いを快く聞きいれてくれているようだった。
けれど、そんな様子を語って聞かされている頼久はというと、適当にあいづちはうつものの心ここに在らずといった様子だった。
「頼久さん?聞いてます?」
「聞いては、おります…。」
さっそく夫の様子がおかしいことに気付いたあかねがその表情を覗き込めば、朝餉に手も付けずに頼久は眉間にシワを寄せていた。
「えっと……。」
あかねはじっと頼久の顔を覗き込んで考えて、はっと目を見開くと朝餉そっちのけで頼久の方へとにじり寄った。
「神子殿?」
「やだ、今度は頼久さんが気鬱ですか?」
「は?」
「だって、さっきから全然ごはん食べてないし、なんだか沈んでるみたいだし…。」
心配そうなあかねの顔を驚きの表情で見つめて、頼久は小さくため息をついた。
「神子殿のおそばに置いて頂いている身で気鬱などということは…。」
「でも…。」
「その…少々気になることがあるだけです。」
「気になること?なんですか?」
「ここ数日は仕事が詰まっておりましたゆえ、屋敷を留守にするほかなく…。」
「それはそうですけど、でも、その分はみんなが遊びに来てくれましたから、私は大丈夫ですよ?」
「いえ、大丈夫ではないのは私の方で…。」
「はい?」
あかねは小首を傾げた。
これはひょっとして仕事のしすぎで頼久が疲れてしまっているのだろうか?と考えて、あかねが表情を曇らせるのと同時に頼久は再びため息をついた。
「毎日、私が留守の間に皆がこの屋敷へやってきて神子殿と過ごしているのかと思うと…。」
「へ…。」
それはもしかしてやきもち?
苦々しい表情でうつむく頼久を眺めながら結論に行きついたあかねは、ほっと安堵のため息をついてから苦笑した。
「そんなこと気になるんなら、しばらくは私一人で過ごします。」
「いえ、それはいけません。それでは神子殿の気がまたふさいでしまわれます。」
「頼久さんが気にして仕事に身が入らないよりはましです。」
「ですので、本日は休みを取りたいと思います。」
「お休み、ですか?」
「神子殿はお怒りになるかもしれませんが、一日だけこの頼久をおそばに置いては頂けませんでしょうか?」
「そ、それは…一緒にいてもらった方が嬉しいのは嬉しいですけど…。」
正直なところ、あかねは迷った。
このまま頼久の言葉に甘えてしまっていいのだろうか?
こんなことで仕事を休んでもらってしまうのはいけないような気がする。
ところが、そんなあかねの胸の内を察してか、頼久が重い口を開いた。
「これより先ずっととは申しません、本日のみおそばに置いて頂きたいのです。さすれば、明日からはまた仕事に戻りますゆえ。」
「頼久さん…。」
つまり、今日一日一緒にいることができれば、明日からまた普段通りに仕事ができる、だから今日一日は一緒にいてほしい。
頼久がそう言っているのだと理解して、あかねはその顔に微笑を浮かべた。
「わかりました。じゃあ、今日は一日一緒にいて下さい。私も嬉しいです。それで明日からの仕事に身が入るなら、一日くらい休んでもいいですよね。」
「神子殿、有難うございます。」
頼久は微笑むあかねに律儀に両手をついて頭を下げた。
いまだに神子に仕えていた八葉時代の癖がぬけない頼久に苦笑して、あかねはすぐに頼久の顔を上げさせた。
「それじゃあ、友雅さんに今日のお稽古はできませんって手紙出さなきゃ。」
あかねは朝餉もそっちのけで慌てて奥の局へと姿を消した。
早くしないと友雅がやってきて頼久をからかったりしかねない。
そうなるとせっかくの休みが台無しだ。
そうとわかっていて急いでくれる妻の後ろ姿を見送って、頼久は御簾の向こう、音を立てて地面に落ちる雨を眺めた。
たまには続く雨もいいかもしれない。
ついさきほどまで恨んでいた雨の空さえ自分に幸福をもたらす使者のようにも思えてきて、頼久はそんな都合の良い自分の心境の変化に苦笑させられるのだった。
管理人のひとりごと
今年、梅雨入り早かったですよね?
管理人の生息地は梅雨ないんでよくわからないんですが(^^;
梅雨ってジメジメしてて憂鬱なんですよね?(マテ
平安時代は今よりずっと気温とか湿度とか高かったそうで…
ってことは梅雨は今より鬱陶しいんだろうなっていう想像で描いてみました。
もうね、ちょっと精神的に病気になりかけるくらいの鬱陶しさかなと。
まぁ、あかねちゃんと頼久さんの場合、根本的な理由は違うわけですが(’’)
八葉のみんなや頼久さんと過ごす一時を想像して、皆さんにも気晴らしをして頂けたなら幸いです(^^)
ブラウザを閉じてお戻りください