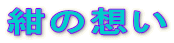
頼久はあかねに腕を引かれてゆっくりと街中を歩いている。
それというのもあかねが急に買い物に行きたいと言い出したからだ。
頼久としては真の友、天真にも外出を控えろといわれているし、人込みは得意ではないので外出はしたくない。
だが、先日、頼久があかねと共に買い物をしていた天真に嫉妬したことから、買い物には荷物持ちとして次からは自分を連れて行ってほしいと言ってしまっていたために誘われれば頼久に断るという選択肢はなかった。
結局、ほぼあかねに強制的に街中へ連れてこられてしまったのだ。
「えっと、まずはお洋服を見ます!」
「はぁ。」
楽しそうに断言して頼久を引き回すあかねの姿を見れば、頼久としても悪い気はしない。
だが、気になるのは周囲の視線だ。
京にいた頃にはなかったこの自分に集中する視線が気になってしかたがない。
何しろ、もともとが警護体質だから視線には敏感にできているのだ。
しかも、その視線を時折あかねが気にしているとなればなおさらのこと、頼久としては気分のいいものではなかった。
「えっと、これとかどうかなぁ。」
「は?」
頼久が周囲の視線を気にしている間にどうやらあかねのお目当ての店に到着したらしく、いつの間にか頼久はあかねにセーターを見立てられていた。
すっかりあかねの買い物に同行しているつもりだった頼久の目が驚きで大きくなる。
「み…。」
「ん〜、やっぱり紺とかグレーとか…グレーはちょっと地味ですねぇ。」
「あの…。」
「グリーン!モスグリーンとか!」
「いや、ですから…。」
あかねは次々と色々な色のセーターを頼久にあててみては似合うだの似合わないだのと一人で感想を口にして楽しげだ。
おかげで頼久が割って入る隙がない。
「やっぱり青系統かなぁ。うん!紺にします!」
「はぁ…。」
一人で何か決めたらしいあかねは決定した色のセーターを棚に戻すと、また頼久の腕を引いて次の店へ向かってすたすたと歩き始めた。
もう頼久には何がなんだかわからない。
「さて、あとはお料理何にするか考えないと。」
「は?」
「頼久さんは何が食べたいですか?パーティ。」
「パーティ、ですか?」
少しばかりうわずっている頼久の声を聞いてあかねがはっと何かに気付いたように足を止めて頼久の顔を見上げた。
そこには困惑顔の恋人が…
「ご、ごめんなさい、私一人で盛り上がっちゃって…。」
「いえ、その、パーティとは…。」
「頼久さん、お誕生日じゃないですか。」
「あぁ…。」
そうだった、こちらの世界では生まれた日を親しい人と祝うのだったと頼久が思い起こしているうちに、あかねは再び頼久の腕を引いて歩き出した。
「当日は私がたくさんお料理作ってパーティしようって思ってて…ごめんなさい、肝心の頼久さんに話すの忘れてました…。」
「いえ、そのようにお気遣い頂かなくとも…。」
「気遣いじゃないです、私が勝手にお祝いしたいだけ……ダメですか?」
悲しそうに上目遣いにそうきかれては頼久の思考回路はショート寸前だ。
だが、さすがの頼久もここですぐに返事をしなくてはいけないということは学習したのですぐに口を開いた。
「み…あかねが祝って下さるのならこんなに嬉しいことはありません。」
「よかったぁ。じゃぁ、9日は空けておいて下さいね。たくさんお料理作りますから。あ、天真君達も呼んでいいですか?せっかくだから盛大にやりましょう!」
小さくガッツポーズさえ決めたあかねに頼久が逆らえるわけもなく、頼久は苦笑しながらはりきって歩き出すあかねの後を追う。
ここで二人きりの方がいいなどとはとてもではないが頼久には言えない。
「たぶんその方が頼久さんも安心…。」
「安心、なのですか?」
「だってほら…天真君と一緒に詩紋君もくると料理が安全になるから…。」
うつむきかげんでそう言うあかねが愛らしくて頼久の頬は思わず緩んだ。
「私はいつもおいしい手料理を頂いておりますが?」
「そ、それはいつも作ってるものだから慣れてきたし…でもパーティでの料理っていつもは作らないものばかりだから…。」
「み…あかねなら大丈夫です。私は心配など致しません。」
「うっ…そういわれると…が、頑張ります。」
ニコニコと楽しそうに微笑んでいる頼久の顔を見てあかねはまた小さくガッツポーズをして気合を入れた。
それこそこの元武士はあかねが作ったものなら泥団子でもおいしいと言って食べそうなのだ。
とんでもなくまずいものを食べさせても満面の笑みでおいしいですと言うだろう。
別の意味であかねにとってそれは恐ろしい事態でもある。
これは絶対に料理の失敗は許されないとあかねは気合を入れ直さずにはいられなかった。
「私にとっては、こうして神子殿に誕生の日を祝って頂けるだけでも夢のようです。どうぞ、お気遣いなく。」
「頼久さんはまたそういうことを……って頼久さん。」
「はい?」
「また神子殿になってます…。」
「も、申し訳ありません…京にいた頃を思うとつい…。」
「もう半年過ぎたんですねぇ、京からこっちへきて。」
「はい。」
あかねは足を止めて空を見上げた。
もちろん頼久もあかねのとなりに立って同じく空を見上げる。
そこに広がる秋晴れの空はそんなに京とは変わらないというのに、この空が京に続いているわけではないと思うとなんだか不思議だ。
「京ではお正月にお祝いするんでしたっけ?お誕生。」
「誕生の祝いというよりは年が新しくなることを祝いますので、特に誕生を祝うということはありませんでした。」
「じゃぁ、今年のお誕生日はもう盛大にパーティしましょうね!こっちの世界にきてよかったって思うくらい。」
そう言って微笑むあかねを見つめて頼久は苦笑した。
あかねは意識していないのだろうが「こっちの世界にきてよかったと思うくらい」という言葉があかねの口をついて出るということは、頼久がこの世界へやってきたことをあかねが気にしているということだ。
当の頼久は京を恋しく思うことなど欠片ほどもないというのに。
「私は毎日、何度もこの世界にきてよかったと思っております。」
「はい?」
「朝起きて自分の部屋にいることを確認したとき、その後で神子殿からメールを頂いたとき、それに返信をするとき、いつもこの世界にきてよかったと思っております。」
「頼久さん……。」
一瞬驚きで目を見開いたあかねはすぐにその前にうっすらと涙を浮かべながら微笑んだ。
「また、神子殿になってます。」
「こ、これは…。」
慌てる頼久と涙を浮かべて微笑むあかねとの視線が交差する。
そうして静かに見つめ合うこと数秒。
あかねは再び頼久の腕を引いて歩き出す。
人込みの中を歩く二人の顔には幸せそうな笑みが浮かんでいた。
パーティは昼食をメインに開かれた。
夕食をメインに始めると、みんな帰る頃には暗くなってしまうからというのが理由だ。
あかねとしてはせっかくお誕生日パーティを開いても帰りに自宅まで頼久に送ってもらうようでは迷惑をかけてしまう、それが嫌だったのでパーティは昼間に開くことにした。
後片付けのことまで考えればなおさらだ。
それでもあかねと詩紋の二人は料理の準備があるのでずいぶんと早くから頼久の家を訪れた。
料理はあかね担当、ケーキが詩紋担当で、家主の頼久が話しかける隙もないほど忙しそうに動き回り、正午になって蘭と天真が姿を見せる頃にはテーブルが料理でいっぱいになっていた。
今日は主役だからといわれて料理を運ぶことさえ許されなかった頼久は、忙しそうな二人に代わって真の友とその妹を家の中へ招き入れるくらいしかすることがなく、苦笑しながら出迎えた頼久に天真も苦笑を返した。
リビングに入れば頼久がどんな状況に置かれていたのかは一目瞭然だ。
「お前、結局、誕生日祝ってもらうっていってるのに苦労してんのな。」
「苦労というほどではない。」
男二人がそんな会話を交わしながらソファに座る間に蘭はもうあかねを手伝い始め、パーティの準備はすぐに整った。
「お兄ちゃんはもう全然手伝わないんだから。」
「俺がやるようなことなんもなかったろうが。」
「あるある、みんなにジュースついで。」
「お前なぁ…。」
妹のあまりのしうちにあきれながらも渡されたジュースのペットボトルを受け取ってしまい、天真は渋々全員のコップにジュースを注ぐ。
「あ、俺と頼久はビー……。」
そこまで言って天真は周囲から殺気さえ感じて目を上げた。
目の前には並んで自分を睨みつけているあかね、蘭、詩紋の三人が…
「頼久さんはともかく、天真君はダメだからね!お酒なんて。」
天真を睨みつけてからすぐに頼久に愛らしい笑みを浮かべて見せるあかね。
そんなあかねとがっくりとうなだれる天真とを見比べて頼久も楽しそうに微笑んだ。
「ではでは、頼久さんのお誕生日をお祝いしてー、かんぱぁい!」
兄がうなだれている間に蘭が頼久と天真のグラスにジュースをついですぐに音頭をとると、賑やかにパーティは始まった。
この日のためにかなり練習してきたらしいあかねの料理はどれも好評で、テーブルを囲む面々には笑顔が耐えない。
最後に詩紋のケーキが切り分けられて、一同はやっと紅茶とケーキを前に落ち着いた。
「いやぁ、食べた食べた。」
「蘭、お前食いすぎ、太るぞ。」
「大丈夫、この日のためにダイエットしておきました。だいたい、太るなら私だけじゃないよ、あかねちゃんもでしょ。」
「お前、あかねの2倍は食ってたぞ。」
「うそっ!」
慌てて隣に座るあかねを覗き込んで、苦笑しているその顔を見て蘭は深い溜め息をついた。
「そうだよねぇ、恋人の前で力いっぱい食べる女の子はいないよねぇ。」
「そ、そういうわけじゃ…。」
赤くなるあかねを天真、蘭、詩紋の三人は暖かな目で見守った。
あかねが幸せそうにしていると自分達まで幸せになるのだとでも言いたげだ。
そして頼久はというと、そんな4人を見渡してやはり幸せそうに微笑んでいた。
「そうだ、あかねちゃん、頼久さんにプレゼント渡さないと。」
「あ!そうだった!」
料理に必死で蘭に言われるまですっかり忘れていたらしいあかねは自分のカバンの中から何やら包みを取り出した。
頼久の方もパーティを開いてもらうだけで十分だと思っていたので、あかねからプレゼントがあるなどとは思いもよらずに目を丸くした。
パーティに集まってもらうだけでも有り難いというのに、これ以上彼らに気を使わせてはと天真から特別にプレゼントなど用意しないように蘭や詩紋にも言っておいてもらったほどなのだ。
もちろん、あかねにもパーティだけで十分だという話はしてあったが、それであかねが納得するはずもない。
自分のカバンから包みを取り出したあかねは、恥ずかしそうにそれを頼久に手渡した。
「頼久さん、お誕生日、おめでとうございます。」
「これは…有難うございます…お気遣い頂き、申し訳なく…。」
「も、申し訳ないなんて、そんなたいしたものじゃないんで…。」
顔を真っ赤にしているあかねを見て幸せそうに頼久が微笑んでいると、隣に座っていた天真に肘で小突かれた。
これはどうやらここで開けてみろといわれているらしいと気付いた頼久は天真に苦笑を見せてからあかねへと視線を戻した。
「開けてみても宜しいでしょうか?」
「あ、はい、どうぞ。」
あかねの許可を得て頼久が綺麗な包装を丁寧に解いてみると、中から紺色のマフラーが現れた。
「これは…。」
「あかねちゃんの手編みだよぉ。あかねちゃんすっごく頑張ったんだから、ね、お兄ちゃん。」
「だな。」
「そ、そんなに頑張ってないよ…セーターにするつもりだったのに難しくてできなくてマフラーになっちゃって…ごめんなさい…。」
「いえ!とんでもありません!」
急にしゅんとうつむいてしまったあかねに頼久は慌てた。
あかねの手作りだというだけでそれこそ頭の中が真っ白になるほど嬉しかったというのに、あかねが何故落ち込むのかわからない。
「先日、色の話をなさっていたのはこのことだったのですね。」
「あ、はい、そうなんです。何色が似合うかなぁと思って。紺、嫌でした?」
「いえ、落ち着いていてとてもいい色です。神子殿が手づからお作り頂いたものとは、あまりにももったいなく…。」
「もったいなくなんかないです!来年はぜーーーったいセーター編みますから、今年はこれで我慢して下さい。」
「我慢などと!有り難く使わせて頂きます。」
そう言って頼久が嬉しそうに微笑むと、やっとあかねもその顔に笑みを浮かべた。
ただそれだけでそれ以上何を話すこともない。
ただ微笑んで見詰め合う二人を見比べて、残る3人が深い溜め息をついた。
「お兄ちゃん、片付けて帰ろう。これ以上ここにいるとむなしくなるだけだよ。」
「だな。」
「ボクも一緒に…。」
「ちょ、3人ともそんな急いで帰らなくっても…。」
『見てられないから。』
3人は声を合わせてそう言うとテーブルの上の食器をさっさと片付け始めた。
3人にしてみれば少しくらい二人きりでゆっくりさせてやろうという気遣いもあったのだが、結局あかねも片付けに加わって一緒に帰ることになってしまった。
「あかねちゃんはもう少しゆっくりしていけばいいのに。」
「もうすぐ日が暮れちゃうから。明るいうちに帰るってお母さんに言ってきたし。頼久さん、またゆっくり遊びにきますね。」
「はい、お待ちしております。」
明るいうちにあかねを手放すとなるとそれはそれで一抹の寂しさがあるのだが、さすがに頼久もそんな想いを顔に出すことはしない。
3人は玄関に立つ頼久に見送られて共に帰路についた。
夜。
天真は缶ビールを1ダース抱えて頼久の家の玄関前に立った。
ドアチャイムを鳴らしてしばらくすると頼久が物憂げにドアを開けた。
「お前さぁ、あかねならここに立つだけでチャイム鳴らさなくても出てくるっていうじゃねーかよ。気配なら俺が来たときだってわかるだろ、こっちは荷物持ってんだ、開けてくれても…。」
頼久に続いて中に入って、明るいリビングまでやってきて天真は息を呑んだ。
「お前も相変わらずだな、昼間あれだけ騒いだのにわざわざ酒を飲みにきたのか?」
そういいながら振り返って頼久が小首を傾げる。
何かに驚いているらしい天真があんぐりと口を開けて立ち尽くしていたからだ。
「どうした?」
「どうした?じゃねーよ、お前…冷静にどうした?とか聞くなよ…。」
「何故だ?」
「何故だ?って……なんてかっこうしてんだよ…。」
「ん?」
天真に言われて頼久は自分がどんなかっこうをしていただろうかと着ているものを確認する。
着ている服は昼間と同じだ。
着替えていないのだから当然だ。
「どこがおかしい?」
「……どこがって…決まってんだろ…お前、なんで家の中でマフラー巻いてんだよ…。」
「あぁ、これか。せっかく神子殿に頂いたからな。」
「……。」
天真は深い溜め息をついてソファに崩れるように座り込むと、持ち込んだ袋から缶ビールを一本取り出して口をつけた。
「お前の神子殿バカは病気の領域だな…。」
「そうだろうか…。」
「自覚がないところがなおさらな…。」
「…神子殿が、今日は早い時間に帰られたのでな……。」
「ん?」
頼久の声が急に沈んだので天真が様子をうかがえば、頼久は少しばかり寂しげな目でじっと缶ビールを見つめていた。
どうやら見つめているのは缶ビールではなく、記憶の中にあるあかねの姿らしいと気付いて、天真は苦笑を浮かべた。
「まぁ、あいつはあれでお前の誕生日を祝ったのに家までおくらせるとかはできねーって気を使ったんだろうし、今日は我慢してやれ。」
「わかっている…。」
「とりあえず、朝まで俺が付き合ってやるし、今日のところはそのままそのマフラー巻いてても我慢してやるから。」
「いや、これは…。」
そう言って頼久はマフラーを外すと大事そうに丁寧にたたんで近くにあるサイドボードの上に置いた。
「つけてなくていいのか?」
「ああ、お前と飲んでいると汚しそうだからな。」
「……。」
天真は再び深い溜め息をついで缶ビールをあおった。
この友人と一緒にいるとこんなふうに神子殿バカっぷりを見せ付けられるばかりだとわかっている。
わかっているが、それだけに頼久があかねが早く帰宅してしまって寂しがっているだろうこともわかる。
真の友と呼ばれる身としてはこんな夜くらい付き合って飲んでやろう。
そう決意してきたのだ。
そんな自分の決意を知ってか知らずかこの神子殿バカは目の前でその神子殿のことばかりを考えているのだが…
天真は再び深い溜め息をついて消えていたテレビをつけた。
これで少しは暇がつぶせるだろう。
「天真。」
「ん?」
「感謝する。」
「あぁ?」
驚いて天真が頼久を見ればその紫紺の瞳は京にいた頃のようにまっすぐに、だが、京にいた頃よりは遥かに幸せそうな笑みを含んで自分を映し出していた。
「けっ。」
自分の考えに気付かれていたことが少しばかり恥ずかしくて、それでも気づいてくれていることが嬉しくもあって天真は何も言わずにテレビへ視線を戻した。
頼久も何も言われなくとも缶ビールを開け、真の友とテレビを眺めた。
二人の男の間に言葉はない。
それでも頼久はあかねという愛しい女性と同じ世界にいられる幸せと、真の友と共に過ごすことのできる幸運とに感謝していた。
京という世界を失ってもなお、頼久は自分が誕生したその日を、この上ない幸福と共に過ごすのだった。
管理人のひとりごと
完成致しました、頼久さんお誕生日現代でお祝いバージョンでございます(^^)
こちらは現代組全員でお祝いでした♪
京があかねちゃん独り占めバージョンだったので(爆)
手編みはお約束ですな、管理人はやったことありませんが(’’)
現代にいるとあかねちゃんだけじゃなく真の友天真君の有り難さもしみじみ感じている頼久さんでした(^^)
何はともあれ、これにてお誕生記念短編2作完結でございます(^^)
頼久さん、お誕生日おめでとうございます♪
プラウザを閉じてお戻りください