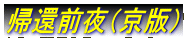
今、土御門邸ではささやかな宴が催されていた。
この場にいるのは八葉の八人と藤姫、それに龍神の神子だ。
京は怨霊の恐怖から解放され、龍神の神子によって救われた。
もちろん八葉の功績も大きい。
公にはされていないことだが、龍神の神子と八葉がこの京を救った事実は変わらないし、永泉の兄である帝からも内々にお褒めの言葉があった。
全てが片付き、京に平和が訪れた。
その祝いの宴は当然のことながら藤姫の父である左大臣によって盛大に催されたのだった。
「主上も是非出席したかったとおっしゃっておられました。」
と、残念そうにしているのは永泉だ。
さすがにこの世を統べる帝がこのような宴に出席することはかなわなかったらしく、それでも帝は龍神の神子への礼の言葉を永泉に託すことは忘れなかった。
「この世界のために命をかけてくださった神子殿に是非一言御礼申したかったと、わたくしに神子殿にくれぐれも宜しく伝えてほしいと言伝されております。」
「そ、そんな、私なんか、みんなに助けてもらってやっと色々できただけで…そんな永泉さんのお兄さんって偉い人じゃないですか、そんな凄い人にお礼言ってもらうようなこと全然してないですよ。」
すっかり慌てるあかねの姿も愛らしくて八葉は皆微笑を浮かべてしまう。
このまだあどけない少女は龍神の加護を得ているとはいえ京を救うために命がけで戦ったのだ。
その行為がどれほど貴重なものか、凡人になしえないことかをこの少女は全く自覚していない。
そこがまた清らかで尊いのだと八葉は皆、心の中で納得するのだが。
「何をおっしゃいます!神子様はこの京のため、本当にこれ以上ないほど御尽力頂きましたわ!このように今、平和にわたくし達が過ごせますのも神子様のおかげですのに…。」
「ふ、藤姫ちゃん!」
「父上まで宿直で出席なさらないなど…。」
宴が始まってからずっと浮かない顔をしていた幼姫はどうやらこのことが気にかかっていたらしい。
左大臣は密かに京を救った龍神の神子達に力を貸していたことが評価され、帝に重用されるようになったため、多忙すぎる毎日を送っているのだ。
それがわかっているだけにあかねも八葉も誰もこの場に左大臣がいないことを問題とは思っていないのだが、娘の藤姫としては何よりも大切な神子様を労うための宴に父がいないことが気になってしかたがないらしい。
「気にしないで、左大臣さんだって忙しいんでしょ?ちゃんとわかってるから。私は藤姫ちゃんがいてくれるだけで十分嬉しいよ?」
「神子様…。」
ぱっと微笑む藤姫がかわいらしくてあかねはその手をにぎにぎしてしまう。
藤姫も嬉しそうにあかねの手を握り返し、二人の少女はそれこそ本当の姉妹のように仲良さげだ。
「オレ達だけで楽しもうぜ。こんな宴会なかなかできねーんだし。」
そういいながら早速用意されたご馳走に手をつけているのはイノリだ。
「そうそう、せっかく全部終わってめでたしめでたしなんだ、かたいこと抜きにして楽しくやろうぜ。」
と、天真も乗り気だ。
イノリ、天真が料理に箸をつけるとそれが合図だったかのように宴は始まった。
酒を酌み交わす天地の白虎、笛を取り出して演奏する永泉、あかねと藤姫に料理を取り分ける詩紋、そしていつものように無表情なまま食事を口へ運ぶ泰明、それぞれがそれぞれらしく宴に参加する中、頼久だけはどことなく沈んだ様子で、だがいつもの無表情さも手伝って誰にも沈んでいることを気付かれることなく手酌で酒を飲んでいた。
「今宵ばかりは鷹通もかたいことは言わずに心行くまで飲んでくれるのだろうね?」
「友雅殿こそ、今宵はどこぞの姫君のところへ通わずに、我ら八葉と朝までお付き合いくださるのでしょうか?」
「これは…鷹通には一本とられたな。」
天地の白虎の会話に一同はくすくすと笑い声をたてる。
今まで、怨霊と戦っていた間も暗く沈みこむことの少なかった彼らだが、憂いの全てを打ち払った今、宴は喜びと安堵に満ちた安らかなものとなっていた。
あかねは隣に座る藤姫と何やら楽しそうに会話している。
八葉はそれぞれ皆楽しげに会話を交わしていたが、頼久だけは生来の不器用さと無口さを発揮して何も言わず黙々と酒と料理を口に運んでいた。
「おい、頼久、お前、宴の席だぜ?わかってるか?」
そう声をかけてきたのは相棒、地の青龍、天真だ。
頼久自身も真の友と思えるほど親しくなった天真はどうやら頼久の異変に気付いたらしい。
「わかっている。」
「わかっているってツラかよ。」
「では、私は今どのようなツラをしているというのだ?」
「ただいま神子殿警護中ってツラだな。」
そう言って口の中に料理を放り込む天真。
頼久はというとはっと一瞬驚いたような顔をしてからすぐにまたむっつりと不機嫌そうに黙り込んだ。
「お前は、怨霊もいなくなって京も平和になったってーのに何をそんなに不機嫌なんだ?」
「不機嫌では、ない……。」
「じゃぁなんでそんなツラしてんだよ。」
「このツラは生まれつきだ。」
そう言って頼久は杯の酒を一気にあおった。
どうやら話したくないらしいと気付いた天真はそのまま頼久を放置することに決め、酒瓶を手にイノリの隣へと席を移した。
そんな天真の気遣いを有難く思いながらも頼久は、曇る己の表情をどうすることもできないでいた。
「頼久、そんなところで一人で不貞腐れていないで、こちらで飲み比べでもしないか?」
天真の次にそう声をかけてきたのは友雅だ。
頼久がそちらへ視線を向けると、今をときめく橘少将は挑発するような視線を投げてきた。
だが、今の頼久はそんな友雅の挑発を受ける気にさえなれない。
「遠慮させて頂きます。友雅殿にはかないませんので。」
「謙遜だな。頼久はいつからそんなできた人間になったのだい?」
「事実を申し上げたまでです。」
「ふむ。」
こうまで言われてはもう友雅もこれ以上からむこともできない。
「で、では、わたくしが笛を奏でますので友雅殿、琵琶なり笛なりを合わせて頂けませんか?」
不穏な空気を察して懐から笛を取り出したのは永泉だ。
そんな永泉の心遣いに苦笑しながらも友雅は答えることにした。
「では、琵琶をあわさせて頂きましょう。」
友雅が女房を呼んで琵琶を用意させると、二人の合奏が始まった。
その音色は美しくも華やかで、この場にいる一同は妙なる調べに耳を傾けながら酒や料理を楽しんだ。
交わされるのは楽しげな会話ばかり。
聞こえてくるのはこの京でも右に出るものはないほど楽に通じた二人の貴公子の楽の音。
誰もがその音色に聞き惚れ、穏やかだが楽しげに会話を交わす中、いたたまれなくなった頼久は誰にも気付かれぬよう、静かに席を立った。
一人静かに席を外した頼久は、宴を楽しむ皆の声が小さく聞こえるくらいに離れた場所まで移動して、月の見える縁に座った。
酒は強い方で酔いを感じてはいなかったが、誰かに見つかったら酔いを醒ましていたといえばいいだろう、そんな言い訳さえ考えながら月夜の縁に座った頼久はふっと深いため息をついた。
宴が始まる前から頼久の胸の内にあったのはあかねへの強い想いと口走ってしまった己の言葉だ。
最後の戦いが終わった後、頼久はあかねにこの京へ残って自分の側にいてほしいと思わずその想いを口にしてしまった。
そしてあかねはというと、すぐそんな自分の想いに答えてこの京に残ると即答してくれたのだった。
それは頼久にとっては夢を見ているかのように幸せな出来事だったのだが、少しばかり時がたった今、頼久の中には複雑な想いが渦巻いていた。
元の世界へ戻るためにあかねは今まで努力してきたはずだ。
京を救いたいという想いは確かにあかねの中に存在していただろうが、同時に京を救えば元の世界に戻ることができるという想いもあったはずだ。
それなのに、あかねは頼久の望みを受け入れてこの京へ残ると言った。
それがあかねにとってどれほど苦しい決断だったかに思いを馳せた時、頼久は己の身勝手さとあかねの心痛に気付いていても立ってもいられなくなったのだった。
今、あの宴の席で楽しげにしているあかねさえもどこか無理をしているように見えて、頼久はいたたまれなかった。
この京に、己の側に残り、ずっと共に生きていってほしい。
それは頼久のわがままでしかない。
あかねは別の世界の人間で、本来この世界の人間ではないのだ。
そしてあかねは自分がいた世界を恋しく思っていたはずだ。
その想いを知っていてなお、自分の側にいてほしいなどと口にした己を頼久は責め始めていた。
もし明日までに心変わりをして、やはり元の世界へ帰りたい、そう言われても頼久にはもう引き止めるすべはない。
いや、引き止めるべきではない。
そう思うと胸の苦しさは増して息苦しくなる。
あかねのいないこの京。
あかねを失った自分。
想像しただけでも恐ろしい。
だが、あかねを引き止めることは罪、そんな気さえして。
頼久は頭を抱えた。
脳裏にちらつくのは宴の席で楽しげに微笑んで見せていたあかねの顔。
無理をしていらっしゃったのだろうか?
そんな想いが頼久の胸にわきあがる。
耳に残っているあかねの笑い声さえもなんだか痛々しかったような気さえして…
それでもあかねを失う恐怖を思うと、自分からあかねに元の世界へ帰るように言うことなどとうていできなくて…
頼久は頭を抱えたまま自分の中に渦巻く矛盾した想いに呻いた。
「頼久さん?」
投げかけられたその声は、たった今、頼久の耳の奥で聞こえていたものと同じ声だった。
この京を救い、己を救ってくれた女性、龍神の神子、あかね。
その優しく凛とした声を聞き間違えるはずなどない。
頼久ははっと勢いよく振り返った。
すぐ側にあかねは立っていた。
月光に照らされて、この世界を救った尊い少女は心配そうに頼久を見つめていた。
「神子殿…。」
「どうかしたんですか?」
すぐ隣に膝をつき、下から覗き込むように自分を見つめるあかねのその心細げな表情を目にして頼久は苦しそうに顔を歪めた。
宴の席では気付かぬふりをしていたあかねはとうに頼久の胸の内の異変に気付いていたのだ。
だから、頼久が席を立ったことにもすぐ気付いたし、こうしてすぐに追いかけてくることもできた。
だが、あかねがそんな風に自分を気遣い、宴が始まってからもずっと自分の方へと視線を送っていたことに頼久は全く気付いていなかった。
「頼久さん、宴が始まってからずっとなんだか元気がなかったし……何かあったんですか?」
今は自分のことを心の底から心配してくれているであろうあかねのその優しい瞳さえもが頼久にはつらく感じられた。
この優しい少女に自分が苦痛を与えている、そんな気さえしていたから。
「いえ……特に、神子殿に案じて頂くほどのことはございません…。」
今の頼久にはこれしか言うことができなかった。
あかねが京に残るといってしまったことをどう思っているのか聞くこともできなければ、残ると言ったその言葉をなかったことにしてあかねのいるべき本来の世界へ帰ってもいいのだとも今の頼久には言えない。
ただ矛盾した淀んだような想いだけがその胸のうちで激しく渦巻いていた。
「私………それは、私は頼久さんに比べたらまだ全然子供で…頼りなくて……私になんか話しても何も解決なんかしないかもしれないけど……でも、それでも……話してほしいです…頼久さんが何かに苦しんでるなら教えてほしいです…解決はできないかもしれないけど…側にいることくらいはできます…ううん、これからはずっと側にいたいって、そう決めたから…だから話してほしいです……。」
最後の方は悲しげでだんだんと小さくなっていく声でそれでもなんとか全てを話し終えたあかねは、必死に頼久を見つめながらもその瞳は涙にうるんでいて、頼久はそんなあかねを見ていることができずに思わず視線をそらした。
「神子殿はいつでも私を救って下さいます。頼りないなどということはございません。」
「でも、今は話してくれないの?」
小さな声でそうつぶやくように言うあかねの方へと視線を向ければ、その瞳からはもう涙が零れ落ちそうになっていて、頼久ははっと息を呑んだ。
その泣きそうな顔さえも清らかで美しかったから。
十六歳という年齢とは思えないほど大人びて美しく、静かな清らかさをまとっていて。
あかねが龍神に選ばれし神子なのだということをいやというほど思い知らされる。
「頼久さんがそんなにつらそうにしてるのに、私には何もできないの?」
あかねの瞳からとうとう涙が零れ落ちた。
その瞬間、心臓が止まるのではないかと思うほど頼久の胸が痛んだ。
もう、このままこの方を留め置いてはおけぬ。
そう心に決めて、頼久はあかねをまっすぐ見つめた。
「神子殿。」
いつもよりも低い掠れたようなその声にあかねはびくっと体をかたくすると、涙をぬぐって頼久の視線に応える。
「戦いの全てが終わったあの時、私は思わず咄嗟に己の想いを神子殿に押し付けてしまいました。この京へ残って頂きたいなどと、私が言うべきことではありませんでした。神子殿が私の望みをかなえて下さると、そうおっしゃって下さった時、私は天にも昇る心地でおりました。ですが、全ては私のわがまま。神子殿、どうか明日、元の世界へお戻り下さい。」
頼久は一気にそう言ってあかねに深々と頭を下げた。
搾り出すような掠れた声だが口にしなくてはと思っていた言葉は全て口にできた。
これで神子殿は何の憂いもなく元の世界へ帰っていけるはず。
己が言わねばならぬことは言えた、成すべきことは成した。
自分が神子殿にして差し上げられることはこれが最後。
そう思えば頼久の胸の内は晴れ晴れとさえしてきた。
だが、残された自分は……
そう考えて目を閉じる。
おそらく生きてはゆけぬだろう。
そうとまで思いつめた頼久だったが、いつまでたってもあかねの返事が聞こえないことに気付いて視線を上げた。
するとそこには声を殺して泣きじゃくるあかねがいた。
「み、神子殿!」
何がそんなにあかねを悲しませたのかわからない頼久はただただうろたえるしかできない。
やはり泣くほど帰りたいと思っておいでだったのだろうか、それともやっと帰ることができると安堵しての涙だろうかと頼久が考えあぐねているうちにあかねがきりっと視線を上げた。
まだ涙が零れ続けている瞳がしっかりと頼久をとらえる。
「頼久さんは私がいない方がいいんですか?」
「は?」
「さっきは残ってほしいって言ってくれたのに、今は帰れなんて……よく考えたらやっぱりこんな手のかかる子供なんて一緒にいない方がいいって、そう思ったんですか?」
「は?いったい何をおっしゃって…。」
「だって、そういうことじゃないですか…急に帰れなんて……私だってわかってます。自分がまだまだ子供で頼久さんのために何かしてあげることなんて全然できなくて…この京に残ったって邪魔なだけかもしれないって…わかってます。それでも残っていいって頼久さんが言ってくれたこと、凄く嬉しくて…本気にして……これからもずっと一緒にいられるって…そう思ってたのに……。」
そこから先はもう言葉にならなくて、あかねは再び声を殺して泣き始めてしまった。
「神子殿、それは…その……。」
「私、残りますから…。」
「……。」
あかねは着物の袖で涙をしっかりとぬぐうときりっと頼久を正面から見据えた。
翡翠色の瞳に浮かんでいる決意は何度となく戦いの最中に頼久が垣間見た強い意志の光を宿している。
「頼久さんが残ってほしくなくても残りますから。だって……頼久さんに二度と会えない世界に帰ることなんて、私、絶対できないから………でも、安心してください、頼久さんに迷惑はかけませんから。」
「い、いえ!迷惑だなどということは!」
「だって、帰れって…。」
「そ、それはそういう意味ではなく……その…神子殿はやはり元の世界を恋しいと思っておいでなのではないかと…私のわがままにお付き合い下さるために無理をなさっておいでなのではないかと思ったのです…。」
「無理って……頼久さんと離れて元の世界へ帰る方がずっと無理です…。」
「神子殿……。」
「それは、元の世界には家族も親しくしてた友達もたくさん思い出もあるけど、でも、元の世界のどんなものより頼久さんと一緒にいることの方が今の私には大切なの、だから、絶対帰らない……帰りたくないよ…。」
必死に涙をこらえていたらしいあかねの瞳から再び涙が零れ落ちた。
元の世界へ帰ることよりも自分の側にいることの方が大切だと言ってもらえたことが頼久にとっては信じられないようなできごとで、だが、目の前で泣いている尊い少女は確かに今、目の前にいて…
「帰りたくはない、そう、おっしゃって下さるのですね。」
「……でも、どうしても頼久さんが……いない方がいいって言うなら………。」
「言いません!そのようなことは決して!いいえ、元の世界へ帰ってもいいなどということはもう二度と、死んでも口には致しません。」
「じゃぁ、私、この京に、頼久さんの側にいてもいい?」
「もちろんです!」
おそるおそる視線を上げたその濡れた瞳に息を呑みながら、頼久はあかねの体を抱き寄せた。
もうすぐ失うとさえ思っていたぬくもりを腕の中に閉じ込めて、頼久は静かに目を閉じる。
この温かい幸せを、安らぎを、希望を、手放すことなどもう二度とできはなしない。
そう思えば思うほど、抱きしめる腕に力が入って…
「よ、頼久さん、苦しい…。」
あかねがそうつぶやくまで頼久は力いっぱいあかねを抱きしめようとしていた自分に気付かなかった。
毎朝鍛錬を欠かさない武士の頼久が力いっぱい抱きしめればあかねの華奢な体がもつはずもなく、頼久はあわててあかねを解放した。
夜目のきく頼久の目に月明かりに照らされてあかねの顔が真っ赤になっているのがはっきりと見えた。
「神子殿。」
「はい?」
「もう一度言わせてください。あなたをお慕い申し上げております、どうか、京に、この頼久の側にずっと…。」
「はい。」
あかねがふっと微笑むのを見て、頼久もまたその顔に微笑を浮かべた。
そして何を言うこともなく二人は歩き出す。
何の憂いもなく、今度こそ、全てを終えた宴を仲間達と共に楽しむために。
あかねのその手は頼久の大きな手にしっかりと握られて、その足取りもかろやかに、向かう宴会場からは楽しげな笑い声が聞こえていた。
管理人のひとりごと
2000Hit御礼でございます♪
京に残ると決めてしまったあかねちゃんはもう嬉しくてしかたない。
でも残ってもらっちゃう頼久さんは気になって気になって…
って普通ならなるんじゃないかな?という管理人の妄想からできたお話(笑)
ゲームだとあっさりその後のシーンが出てきちゃうので、実際にはもうちょっと葛藤があったでしょう?と思いまして。
現代版とあわせてお楽しみください♪
プラウザを閉じてお戻りください