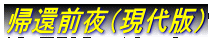
土御門邸ではささやかな宴が開かれていた。
あかねが龍神をその身に降ろし、京を滅亡の危機から救ったその夜。
あかねと八葉、藤姫が集まってささやかな宴会を開いたのだ。
ささやかになったのは龍神の神子や八葉の存在が公にされていなかったからだが、身分も家柄も関係なく八葉としての絆で結ばれた一同にしてみると、変に貴族達がぞろぞろ集まってくるような宴よりはこちらの方がよほど歓迎だった。
始めに永泉が帝から預かってきた言葉を皆に伝え、次は藤姫が父である左大臣からの感謝の言葉を伝えると、儀式っぽいことはそれで終わりで、あとはそれぞれご馳走と酒を前に普通の宴会へと突入した。
時折、永泉が笛を吹き、珍しく笛を持参していた友雅がそれに合わせて笛を奏でると、一曲が終わるまで一同は静かに二人の笛の音に聞き惚れたが、それ以外は皆勝手にしゃべりまくり、たいそうにぎやかな宴会となった。
「今宵ばかりは、皆様、思う存分お楽しみ下さいませね。」
そう言って藤姫もあかねの前にある杯に酒を注ぐ。
「ふ、藤姫ちゃん、私はお酒は無理!」
「少しでしたら大丈夫ですわ。わたくしも頂きますし。もし動けなくおなりでしたら、寝所までは頼久に運ばせますし。」
「そそそそ、それもどうかと……。」
「頼久が嫌だというのなら、私が運んで差し上げるよ?神子殿。」
そう言ってすっと優雅な身のこなしで何気なくあかねに身を寄せたのは友雅だ。
その手にはしっかり杯が握られていて、どうやらもうすっかり宴会を楽しんでいるらしい。
「友雅さんはもっと問題です…。」
「心外だねぇ、神子殿には誠心誠意お仕えしてきたつもりなのだが?」
「そういうことを言ってるんじゃないですよ。友雅さんに送ってもらったりしたら、友雅さんのことを好きな女房さん達に恨まれそうで…。」
「なるほど。」
自分で納得してしまった友雅はからからと楽しそうに笑いながらあかねの前を離れて、同じ白虎の相棒の隣へ座った。
「心配すんな、あかね。ここの酒はそんなに強くないから少しくらいなら大丈夫だぞ。」
「って、天真君!そんな勢いよく飲んじゃって!」
「大丈夫だって。お前が酔っ払ったら頼久に運ばせて、俺が監視しててやるから。」
「そ、それもどうかなぁ……。」
「では、私が監視役をおおせつかりましょう。神子殿、今宵ばかりは少々はめを外してもよいかと思います。神子殿は今日まで本当によく頑張ってこられたのですから。」
天真ばかりか鷹通にまでこういわれてはあかねも杯に口をつけないわけにはいかなくなってしまった。
すっかり酔っ払ったあかねを運ぶ役目を決定されてしまった頼久に視線を移してみれば、口元になにやら穏やかな笑みを浮かべてあかねを見つめている。
どうやらあかねを運ぶ役目を与えられることに不満はないようだ。
「わかりました、じゃぁ、ちょっとだけ。」
藤姫に注がれた酒の杯を手にとって、生まれて初めてあかねは酒を口に入れた。
「あ、おいしいかも。」
「まぁ、よろしゅうございましたわ。お気に召されたのでしたら、ささ、どんどんどうぞ。」
神子様のお世話ができるのも今宵が最後とばかりに、普通であれば藤姫ほどの身分の女性が決してしないはずの酌をこの幼姫は嬉しそうにやっている。
あかねは苦笑しながら酒で満たされる杯を見つめていた。
「そうだ、ボク、お菓子作っておいたんだけど、みんなまだ入ります?」
ごそごそと背後から荷物を取り出してこの場にいる全員に焼き菓子を配り始める詩紋。
男ばかりの八葉ではあるが、この京では甘いものはかなり貴重らしく、この場の全員が詩紋に礼を言って焼き菓子を受け取ると、全員がおいしそうに口にするのだった。
豪華な料理とうまい酒、それに詩紋の手によるデザートがそろったとなればますます座は盛り上がり…
「俺、なんかすっげー気持ちい。」
トップバッターでイノリがそんなことを言って歌い始めて、歌う者、踊る者、話す者、とそれぞれに宴会を楽しむこと数刻。
さすがにこの日まで命がけで戦ってきた面々は深夜にいたって疲れが見え、眠りこける者が出始めたところで解散と相成った。
「ほら、イノリ、行くぞ。詩紋、手伝え。」
「あーあ、イノリ君飲みすぎだよ…。」
最初に酔いつぶれたイノリを天真と詩紋が担ぎ出すと、クスクスと笑っていた友雅が席を立った。
「さて、では私も今宵はおとなしく家に戻って寝るとしようかな。」
「友雅殿がご自宅でお休みになるなんて、珍しすぎて明日は嵐にならねばいいのですけれど。」
「これは手厳しい。」
藤姫の舌鋒に友雅が苦笑していると、ドサッという音がして隣に座っていたはずの鷹通が何も言わぬまま床に倒れこんだ。
「鷹通…酔っていたのかい…。」
あきれたようにそうつぶやいて苦笑した友雅はすっかり酔って眠り込んでしまったらしい鷹通の右肩を担ぐと、一人では運びきれぬと悟って泰明へと視線を向けた。
「泰明殿、申し訳ないが手伝ってもらえぬだろうか?」
「問題ない。」
いつものように答えた泰明は友雅とは反対側から鷹通を担ぎ、別れの挨拶もそこそこに二人は鷹通を担いで去っていった。
「では、わたくしもそろそろ失礼致します。年頃の女性がいらっしゃる部屋にお邪魔するにはもうずいぶんと遅い時間になってしまいましたので。」
そう言って静かに席を立ったのは永泉だ。
「では神子様、わたくしも下がらせていただきますので、神子様も今日はもうゆっくりお休みください。頼久、神子様を頼みますね。」
「あ、私は一人で戻れますから、頼久さん、永泉さんを送ってあげて下さい。普通そうにしてましたけど、永泉さんもお酒飲んでたみたいだし。」
少し慌てた様子で藤姫の言葉をさえぎったあかねに違和感を感じながらも頼久は一礼してあかねの言葉に従った。
既に姿を消していた永泉の後を追ったのだ。
「神子様?」
「あぁ、本当に私は大丈夫だから。一人で戻れるから心配しないで。」
「ですが…。」
「大丈夫!じゃ、お休み藤姫ちゃん、また明日ね。」
いつものように明るい笑顔でそう言ったあかねは藤姫にヒラヒラと手を振って見せると、すぐ自分の局へ向かって駆け出した。
「神子様…。」
宴の間もいつものように振舞ってはいたが、どこか上の空だったあかねの様子にいち早く気付いていた藤姫は心配そうにあかねの後姿を見送るのだった。
あかねの予想通り、平気そうな顔をしてはいたもののしっかりと酔っ払っていたために牛車に乗るのも忘れて裸足で歩いて帰ろうとしていた永泉を見つけて頼久が、溜め息をつきながら無事に僧坊まで送り届けて武士団の棟の自分の部屋へ戻ってきたのはもうすっかり深夜になってからだった。
空には美しい月がのぼっていて静かな夜だった。
宴が賑やかだっただけに、屋敷中の人間が眠りに着いたこの時間はひどく静かに感じられた。
武士という職業柄、いつ何時賊の襲撃があるやもしれぬと酔うほどには酒を飲んでいなかった頼久は、先ほどまでの宴の様子を思い浮かべながら柱にもたれて月を見上げていた。
宴の高揚感が残っているのかまだ眠くはない。
いつものようにはしゃいでいた年少組や天真、いつもと同じように穏やかに、だが笑顔を絶やさず会話を交わしていた友雅と鷹通、そして時折永泉は笛を吹きながら、泰明と霊的な話や人の心について語り合っていた。
頼久の脳裏に浮かぶ仲間達は皆、今までにないほど穏やかで、そして幸せそうだった。
怨霊との戦いの間も、決して毎日悲観して必死になっていたばかりではなかったはずだが、それでもやはり、全てが解決した今宵の宴では、皆楽しげだった。
藤姫も、神子との別れを思って時折悲しげに表情を曇らせてはいたが、それでも楽しそうに最後とばかりに神子の世話を焼いていた。
いつも無口な頼久でさえ、時折天真と冗談を言い合ったりからかう友雅に切り替えして見せたりしたほどだ。
良い一時であった。
そう思って口元に微笑を浮かべて、そして頼久ははっとあることに思い至って微笑を曇らせた。
宴の最中のあかねの様子を思い出したのだ。
いつもと同じ笑顔、いつもと同じように八葉全員に屈託なく接していたあかね。
だが、どこか違和感があって…
自分ではなく永泉を送ってほしいと申し出たときのあかねも、どこか違和感があった。
それがなんなのかがわからず、頼久は月を見上げて考え込む。
明日、あかねは自分達の世界へ帰ることになっている。
龍神が力を取り戻した今、あかね、天真、詩紋、そしてこの京でみつかった天真の妹、蘭は元の世界へ戻るのだ。
まだ心の傷が癒えないからと宴を欠席した天真の妹のことが気になっておいでだったのだろうか?
そう考えて頼久は首を横に振った。
蘭は今、泰明の師である安倍晴明の庵で養生しているはずで、何も心配はいらなかった。
明日、自分達の世界へ帰ることができれば全てが解決するだろうと天真も言っていた。
ならば何故、あかねの笑顔には違和感があったのか?
考えれば考えるほどわからない。
最後の戦いが終わってすぐ、頼久はあかねが元いた世界へ帰るのならば自分も共に連れて行ってほしいと願い出た。
そしてあかねは即答でその願いを聞き入れてくれた。
だから、今の頼久にはなんの憂いもない。
明日以降も、たとえ生きる世界が変わっても、神子殿がお許しくださる限りお側で神子殿をお守りする。
そう心に決めた頼久は今までよりも胸の内は晴れ晴れとしているほどだ。
だが、もしや神子殿は違ったのでは?
そう思い始めると別れ際のあかねの様子が気になってしかたがなく、頼久は刀を手に立ち上がるとあかねの局へ向かって歩き出した。
あかねは一人、欄干にもたれて月を見上げていた。
宴が終わって一人になって、自分の褥に横になってはみたものの頭が冴えてしまって全く寝付けなくなったあかねは、眠れないのなら眠るのはあきらめようと縁に出てきてしまったのだ。
そうすると夜空には綺麗な月が出ていて、月を眺めながらあかねは宴の最中から浮かんで消えない考えに悩んでいた。
あかねが悩み続けていること、それは他ならぬ頼久のことだった。
戦いが終わってすぐに頼久はあかねが自分の世界へ帰るとき、共に連れて行ってほしいといってくれた。
あかねは頼久と別れずにすむことが嬉しくてつい即答で共に帰ることを承諾してしまった。
ところが、少し時間がたって冷静に考えてみると、それは実際にはとんでもない決断だったような気がしてきたのだ。
この京で生まれ育ち、源武士団の次期棟梁という確固たる地位を持っている頼久には家族や同僚や立場、全てを捨てて旅立つという決断だったはずだ。
そんな決断をそう易々と下してしまってよかったのだろうか?
頼久は何日も考え抜いた末に出した結論だったのかもしれない、だが、自分はどうだろう?
大好きな人と離れないですむ、ただそれだけの思いで即答してしまったのではないだろうか?
そんなことでいいのだろうか?
これから頼久が体験しなくてはならない苦労を考えるとあかねはどうしても明日、共に旅立つことを手放しでは喜べなくなっていた。
だいたい、頼久だってもしかしたら明日には心変わりするかもしれない。
一晩ゆっくり考えたら、やはり全てを捨てることはできないと思い直すかも。
もし、明日、共に行けないと言われてしまったら…
一人でいるとそんなことまで考えてしまって、あかねはいつの間にか一人、うっすらと涙さえ浮かべてしまっていた。
「神子、殿?」
「へ?頼久さん?」
今まさに思い浮かべていた人の声が聞こえてあかねは目を見開いて驚いた。
月明かりに照らされて庭先に立つ長身は確かに頼久のもので…
「神子殿?泣いていらっしゃるのですか?」
「へ?」
別に涙を流して泣いていたわけではないのに、夜目のきく頼久には涙に濡れたあかねの瞳が見えたようで、あかねは慌てて羽織っていた袿の袖で涙をぬぐった。
「泣いてたってほどじゃないですから…。」
「ですが、何か思い悩んでおいでだったのでは…。」
「えっと……そんなことより、頼久さん、どうしてこんなところにいるんですか?もうお部屋に帰って寝ないと。警護とか、今日は違う人に…。」
「いえ、警護にきたわけでは…。」
不意に二人の間におとずれた沈黙。
月明かりに照らされて、いつものあかねならロマンチックだな、くらいのことは思ったかもしれない静かな夜だというのに、今はその静けさが痛いほどだ。
「あの…頼久さんももう寝た方が……。」
「神子殿。」
「はい…。」
「何か悩みがおありでしたら、この頼久にご相談頂けませんか?」
階の途中まで上ってあかねに対して片膝をついた頼久は悲壮感さえ漂う真剣な顔をしていて、あかねは圧倒された。
そして、あかねは再びその二つの目に涙を浮かべながら観念して口を開いた。
黙っていても頼久に心配をかけるだけだと悟ったから。
「あの、ね、本当に明日、頼久さんに一緒に来てもらってもいいのかなぁって…。」
「は?」
「…あの時はほら、戦いが終わってちょっと普通の状態じゃなかったって言うか……冷静になって考えてみたらやっぱりこの世界を捨てられないとか、そういうふうに思ったりするんじゃないかなって思って……。」
あかねの中にはもっと色々な想いが複雑に入り乱れていたのだが、それを言葉にして表現することはとてもできなくて、やっとの思いでそれだけ言ったあかねを頼久は急に立ち上がってつつと歩み寄るとぎゅっと抱きしめてしまった。
「頼久さん?!」
「神子殿のいらっしゃらない世界になんの意味がありましょうか。私は神子殿がお許し下さる限り、二度とお側を離れぬと決めました。この想いが揺らぐことは絶対にございません。」
「ぜ、絶対って…。」
「それとも、神子殿はこの頼久がお供するのがお嫌なのでしょうか?」
「ま、まさかっ!それこそ、そんなこと絶対にありません!」
頼久の腕の中でそんなことを叫んでしまったものだから、あかねを抱きしめる頼久の腕にはより一層力が込められてしまった。
まるで今腕の中に閉じ込めている少女が愛しくて愛しくてしかたがないとでも言うように。
「よ、頼久さん、ちょっと苦しいです…。」
「も、申し訳ございませんっ!」
慌ててあかねからその身を離した頼久は片膝をついて深々と頭を下げた。
「そんなに気にしないで下さい、別に怒ったわけじゃないんですから。」
「はぁ。」
頼久が顔を上げると、しかたないなぁとでも言うようにあかねが苦笑しているのが目に入った。
それはいつものあかねの顔で、頼久はあかねから違和感がなくなったことに安堵した。
「明日…。」
「は?」
「明日、本当に連れて行っちゃいますからね?」
「はい。」
「本当に、本当に連れていっちゃいますからね?二度と戻って来られないんですからね?」
「はい、承知しております。」
はいと返事をしてくれたことよりも、返事をした時の頼久の顔が果てしなく幸せそうな笑顔だったのが嬉しくて、あかねは思わず安心して微笑と涙の両方を浮かべた。
「さあ、神子殿、明日は神子殿の世界へお帰りになる大切な日、今日はもうお休みください。」
「はい。」
おとなしくそう返事をしてあかねは御簾の向こうへと姿を消した。
そして、縁に控えていた頼久は、御簾の向こうから規則正しいあかねの寝息が聞こえてきたところで、微笑を浮かべて自室へと下がった。
翌日、晴れ晴れとしたあかね、頼久、天真、詩紋、蘭の5人は神泉苑からあかね達への世界へと帰っていった。
見送りにきた八葉の面々と藤姫に見せた5人の顔は、すべからく希望に満ちた笑みで彩られていたという。
管理人のひとりごと
2000Hit御礼でございます♪
現代へお供すると決めている頼久さんは晴れ晴れ。
でも、お持ち帰りしちゃうあかねちゃんの方は気にしちゃう。
現代へ帰還する場合はこうなるかなぁと。
そんなにあっさり全てが進んだわけではないだろうという管理人の妄想です(笑)
更に、全てが終わった夜くらいみんなで騒ぎましょうよとも思ったり(爆)
京版と合わせてお楽しみください♪
プラウザを閉じてお戻りください