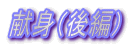
レストランを出た二人はまた腕を組んでゆっくりと歩いた。
映画上映の時間まではまだ少し余裕があるから、人込みを避けながらゆっくり歩く。
真昼の陽射しはだいぶ温かくなっていて、春の気配さえ感じる。
もう少ししたら桜も咲き始めるはずだ。
そんな春の予感さえ嬉しくて、あかねの顔からは笑みが絶えない。
「映画って何時に終わるんでしたっけ?」
「3時くらいでしょうか。」
「じゃぁ、それからまたどこかへ行くんですか?」
「そうですね、喫茶店などで少々休みをとってからもう一ヶ所行こうと思っている場所があります。」
「盛りだくさんですね。」
「映画が終わってお疲れでしたらやめますが…。」
「行きます!どんなに疲れてても行きます!頼久さんがどこに連れて行ってくれるのか楽しみだし。」
そう言ってあかねはギュッと頼久の腕を抱きしめた。
頼久としては疲れているあかねを連れまわすつもりは毛頭ないのだが、これではあかねの方が黙って家に帰ってくれそうにない。
もちろん、頼久もあかねを帰したいわけではないのだが、無理をさせたいわけでもない。
「頼久さん?」
どうやらあかねにどうやったら無理をさせずに澄むかを真剣に考え込んでしまっていたらしく、頼久は名前を呼ばれてはっと見上げてくるあかねへ視線を向けた。
「大丈夫ですか?」
「申し訳ありません、少々考え事をしておりました。」
「すっごく難しそうな顔してましたけど、何考えてたんですか?」
「いえ…み…あかねに無理をしていただきたくはないのでどうしたものかと…。」
「無理なんかしてませんよ?」
「いえ、あまり予定を詰め込みすぎて疲れさせてしまっては…。」
「疲れてないですよ、大丈夫です。こうしてれば歩くのも楽しいし。」
そう言ってあかねがギュッと頼久の腕を抱きしめて幸せそうに微笑む。
その様子が本当に幸せそうで、頼久はほっと安堵の溜め息をついた。
「でも、頼久さんがそんなに心配ならちゃんと疲れたら疲れたって言いますから。」
「はい。」
二人で微笑み合ってゆっくり歩いて…
そうこうしているうちに目的の映画館へ到着。
頼久がチケットを買っている間に何やらあかねはポスターを真剣に凝視していた。
「み…あかね?」
「ああ、これ、来月上映って面白そうかなぁって思って。」
あかねが凝視していたのはミステリー映画のポスターだった。
何やら綺麗な顔をした外国人俳優がポーズをとっているのが目に入る。
「この俳優さん、前の映画もよかったんですよねぇ。すっごくステキだったし。来月はこれ観に来ましょうか?」
「……。」
「頼久、さん?」
隣を見れば何やら不機嫌そうな顔をしている頼久。
あかねは小首を傾げてその顔を見上げた。
「どうかしたんですか?」
あかねには何故頼久が急に機嫌を悪くしたのか、その理由がわからない。
対して頼久はというと、あかねに「すっごくステキ」といわれた俳優が出ている映画は観たくないという自分のわがままと、あかねの望みはなんでも叶えたいという自分の希望との間で揺れ動いていた。
「頼久さ〜ん?」
「も、申し訳ありません、その…来月のこの映画ですが…。」
「頼久さんは観たくないですか?」
「いえ…そういうわけではないのですが…その…み…あかねがステキだという俳優を見るのは…その…。」
ほんの数秒、頼久の言葉にキョトンとしたあかねは、次の瞬間、あきれたような溜め息をついた。
「頼久さん、映画俳優に妬いてるんですか?」
「いえ…妬いている、わけでは…。」
と言い訳してみても、どこからどうみても妬いている自分に頼久は溜め息をつく。
「あのですね、頼久さんはこの俳優さんよりずーーーっとステキですから安心してください。さ、入りましょ。」
さらっとそんなことを言われて、頼久はその顔に輝かんばかりの笑みを浮かべた。
映画俳優よりステキだと愛しい人に言われて嬉しくないわけがない。
ニコニコと嬉しそうに微笑む頼久の腕を引いてあかねが映画館の中に入れば、今度は少しばかり人が込み合っていて前のほうの席は埋まってしまっていた。
「うわぁ、こっちはけっこう人がいますねぇ。」
「ここは思い切って後ろの席に致しませんか?」
「そうですね、映画って前の方の席だと首痛くなっちゃったりするし、一番後ろなら後ろの人のこと気にしないですみますもんね。」
そう言って二人で一番後ろの席に並んで座った。
スクリーンは少し遠いかもしれないが、それでも人が込み合っていないから二人でゆっくり映画を楽しめそうだ。
「何か飲み物でも買ってきましょう。何がよろしいですか?」
「ん〜、おなか一杯だから炭酸はちょっと…。」
「ではコーヒーでも。」
「そうですね、お願いします。」
そう言って頼久が席を立って場内から姿を消すと、もうそれだけであかねはなんだか寂しくなって、思わず頼久が姿を消した出口の方を見つめてしまう。
そこは人の出入りが激しくて、場内もどんどん人が増えているようだ。
映画館は一人で入ると物騒だと母に言われて、必ず映画は友達と観るようにしていた。
女の子が一人で映画館にいると痴漢にあったりするからと注意されていただけに一人きりになってしまうとなんだか不安になる。
でも、頼久さんが一緒だから安心安心、と自分に言い聞かせてあかねは苦笑した。
そう、”あの”頼久さんが一緒なのだからこれ以上安全な映画鑑賞はないはず。
痴漢なんかがあかねを触ろうものならそれこそ殴り殺す勢いで退治してくれるはずなのだ。
と、そこまで考えてそれはそれで頼久さんが警察に捕まっちゃいそうで困るかもとあかねが再び苦笑したところへ頼久が戻ってきた。
「み…あかね?何かありましたか?」
「あ、いえ、なんでもないです。頼久さんがいないとちょっと寂しいなって思ってただけです。」
「申し訳ありません。」
「あ、そうじゃなくて、その…私がわがままなだけだから、謝らないで下さい。」
顔を赤くしてうつむくあかねにコーヒーを渡して頼久がその隣へ腰を下ろすと照明が落とされて映画が始まった。
あかねはずっと観たいと思っていた恋愛映画なだけに、それまでの頼久とのやり取りも忘れて気合が入る。
そんなあかねの様子に気づいて頼久はほっと安堵の溜め息をつくと、後であかねに感想を聞かれたときに答えられるようにと映画に集中することにした。
あかねが好きなのは恋愛映画とミステリー映画で、今見ているのは面白いと評判の恋愛映画だ。
これもまた頼久は天真から教わった情報で選択した映画だったのだが、おそらく天真は食事をした店同様、妹の蘭から情報を聞いたのだろう。
映画自体は特に変わったところのない恋愛ものということだったのだが…
映画の中盤で頼久の隣からは嗚咽が聞こえ始めた。
明らかにあかねが声を殺して泣いている。
これは映画どころではないと頼久が隣の恋人を覗き見れば、あかねはハンカチを目にあてて懸命に涙をぬぐっていた。
今回ばかりはしっかり映画を見ていた頼久、あかねがどうして泣いているのかはわかっている。
そう、映画の内容が内容だったからだ。
普通に人気の恋愛映画だと思っていたのだが、物語の中盤、恋人同士が生き別れになるというシーンがあった。
京とこの世界、頼久と離れ離れになったかもしれなかったあかねはそういうシーンに弱い。
これはどうしたものかとしばらく考えて、頼久はあかねの肩に手をまわした。
自分は今ここに、あかねの隣にいるのだとわかって欲しくて。
そっと頼久があかねの肩を抱き寄せると、一瞬びくっとしたあかねが驚いたような顔で頼久を見上げてくる。
目が涙で潤んでキラキラとしているのが夜目のきく頼久にはしっかりわかった。
そんな恋人に頼久が見惚れていると、あかねはハンカチで涙をぬぐってスクリーンに視線を戻し、頼久の方へ身を寄せてほっと溜め息をついた。
どうやらあかねが安心したらしいとわかって頼久も安堵の溜め息をつく。
結局のところ映画はハッピーエンドで終了し、場内が明るくなる頃にはあかねの顔には楽しそうな笑みが戻っていた。
そんな恋人の様子を見て頼久が安堵の溜め息をついていると、あかねは慌てたように急に立ち上がった。
「み…あかね?」
「え、えっと…ちょっと近かったから…あ、明るくなってからはちょっと…。」
真っ赤な顔をしているあかねを見上げながら頼久は小首を傾げて考え込む。
そして数秒後、あかねがどうして立ち上がったのかに気づいて苦笑した。
そう、映画の最中に頼久はあかねの肩を抱き寄せていた。
明るくなればそれが周囲に見えるわけで…
「さ、頼久さん、次行きましょう!」
真っ赤な顔であかねが頼久の手を引く。
頼久はあかねにされるがままに立ち上がると、二人並んでゆっくり歩き出した。
映画館はとても込み合っていて、油断をするとはぐれてしまいそうだ。
あかねは頼久の左腕をギュッと抱きしめて歩く。
頼久はそんなあかねを人込みからかばいながら歩いて、やっとの思いで二人は外へ出て一息ついた。
「凄い人でしたねぇ。」
「本当に。」
「映画、よかったもんなぁ。」
「お楽しみ頂けたのなら何よりです。」
「すっごく良かったです。ハッピーエンドだったし。」
そう言って微笑むあかねは本当に幸せそうで愛らしくて、思わず頼久の顔にも笑みが浮かぶ。
「で、次はどこへ行くんですか?」
「お疲れでしたらどこかで休みますが…。」
「ん〜、別に疲れてはいないです。映画館ずっと座ってたからちょっと歩きたいくらい。」
「ではすぐ次に参りましょうか。」
「そうしましょう!どこへ行くのか楽しみです。」
そう言ってあかねはただ頼久についていく。
いつもとは違って腕を抱いて歩いていれば歩くことそのものがもう楽しい。
普段は頼久に向けられる視線の一つ一つまで気になるのに、今日はそれを気にしないですむ。
あかねはもう上機嫌だ。
「み…あかねは動物は好きですか?」
「はい?動物?」
「はい。」
「大好きです。犬とか凄く可愛いし。京では馬に乗せてもらって、あれも楽しかったです。一人で乗れるようになりたかったなぁ。」
「動物園はまだ少し肌寒いかと思いましたので。」
そう言って頼久が立ち止まったのは水族館の前だ。
「うわぁ、私、イルカとかも大好きです!」
あかねはそう言って嬉しそうに目を輝かせる。
二人そろって中へ入って最初に目にしたのは熱帯魚の大きな水槽だ。
大きな水槽を泳ぐ色とりどりの魚の間を通路が通っている。
そこをまるで海の中を歩くように歩いて奥へ。
「すごくキレイですね…。」
時々立ち止まって水槽に見惚れるあかね。
頼久はといえば水槽ではなくそんなあかねに見惚れてしまうのだ。
そしてゆっくり二人で水槽のトンネルを抜けて、奥へ入ると最初に二人を出迎えたのは上から手を入れることができる小さな水槽だった。
中を覗くとそこにはカニやヒトデがたくさん蠢いている。
「こ、これは…。」
「手で触れてもいいと書いてあります。」
「さ、触るんですか?これを?」
よくよく見れば水槽の中にはご丁寧にナマコまでいる。
どれも触ると気持ちが悪そうな生き物ばかりだ。
「ちょ、ちょっとこれは…。」
「無理に触らなくとも…。」
「ん〜、でもせっかくだし…。」
そこはそれ、好奇心旺盛な神子殿だ。
あかねはゆっくりと水槽に手を入れて、ヒトデを撫でてみた。
「あれ、意外と、硬い?」
「硬い、のですか?」
頼久の問いにコクコクとうなずくあかね。
頼久が触ってみればなるほど、外見よりは硬いかもしれない。
隣で恋人がヒトデの硬さに感心している間に、あかねは隣に蠢いていたナマコへと指をのばした。
恐る恐るプニっと触ってみると…
「きゃっ!」
「神子殿?!」
慌てて手を引っ込めて隣の頼久にとびついたあかね。
何事かと頼久の顔色が青くなる。
「き、気持ち悪い〜〜。」
「は?」
「ナマコはやっぱり気持ち悪いです…。」
そう言って涙目になっているあかねを一瞬キョトンとして見つめてから頼久は優しく微笑んだ。
「どうぞ。」
左腕であかねを優しく抱きとめながら頼久があいている右手でハンカチを差し出せば、あかねは素直にそれを受け取って手を拭いて、ハンカチを返しながら慌てて頼久から離れた。
キョロキョロと辺りを見回して誰もいないのを確認してほっと安堵の溜め息をつく。
どうやらあかねはよほど人目を気にしているらしい。
「そのように気になさらずとも。」
「ひ、人前は恥ずかしいです…から……。」
真っ赤になりながらも頼久に差し出された腕をとって、あかねは小さく深呼吸して歩き出した。
泳ぐ白熊やサメの水槽を見て感動しながら先へ進むと今度はイルカのショーをやっていて、二人並んで可愛らしいイルカのショーを堪能する。
その後に見たペンギンの行進はあまりの可愛さにあかねが身もだえしたほどだ。
全てを見終わって水族館を出る頃にはもうあかねはうっとりと満足げだった。
「ん〜、ペンギンすっごく可愛かったですね。」
「はい。」
頼久は心の中では「神子殿の方がお可愛らしいです」と思いながらも、そんなことを言うとまた恥ずかしいといわれそうなので黙っておく。
「おうちで飼えたらいいのに。」
「ペンギン、ですか?」
驚く頼久にコクコクとうなずくあかね。
さすがにペンギンの世話は大変だろうと頼久は思わず苦笑した。
「無理なのはわかってるんですけどね、あのよちよち歩くところがもうかわいくて。」
「では、またペンギンの行進を見に参りましょう。」
「あ、そうですよね!そうしましょう!」
頼久の提案に嬉しそうに微笑んで、あかねはまたギュッと頼久の腕を抱いた。
「そろそろお疲れなのではありませんか?」
そう頼久があかねに尋ねた時にはもう水族館を出てしばらく歩いて、辺りは夕暮れで赤く染まっている。
だが、あかねはというと寂しそうにうつむいて答えない。
「み…あかね?」
「…ちょっと疲れたかな…でも…その…まだ帰りたくないです……。」
なるほどそういうことかと納得して頼久は暖かく微笑む。
「はい、まだお帰しするつもりはございませんが。」
「はい?」
「これより我が家で夕食を共にして頂けませんか?」
「えっと、材料買って帰らないと…。」
「いえ、夕食は私が用意いたしますので。」
「へ?」
「普段はみ…あかねにおいしい手料理を作って頂いておりますから、今日は私が。」
「頼久さんが晩御飯作ってくれるんですか?」
「はい、お嫌ですか?」
「まさか!行きます!食べます!」
力いっぱい返事をするあかねに笑顔を見せて、頼久はあかねを誘って歩き出す。
頼久の顔にもあかねの顔にも笑顔は絶えない。
まだまだホワイトデーは残っている、二人ともそう胸の中で思いながら歩き続けた。
夕食は頼久の手料理の炊き込みご飯にお味噌汁、それに浅漬け。
和食にしたのは頼久が味を見るときにおいしいかどうかがわかりやすかったから。
それに昼食がイタリア料理になるのがわかっていたので、洋食よりは和食の方がいいだろうと頼久が判断したからだ。
あかねはもう全てを綺麗にたいらげて満足気で、食後にお茶を飲みながら幸せそうにしている。
ところが、そんなあかねが頼久が食器を下げて片付けるにいたって表情を曇らせた。
「神子殿?どうかなさいましたか?料理がお口に合いませんでしたか?」
「とんでもないです!すっごくおいしかったです!私もまだまだ料理の勉強しなきゃ。」
「いえ、神子殿は既にどの料理もとてもお上手です。」
そう言って頼久が褒めてもあかねはいつものように照れたりせずにやはり寂しげだ。
「やはり何か…。」
「ち、違います…その…あの…もうすぐ帰らないといけないなぁと思って…。」
「そう、ですね。」
ちゃんと門限までには自宅に送り届ける、頼久があかねをそうすることは約束されていることだ。
「少々お待ち下さい。」
「はい?」
急に頼久が書斎へと姿を消して、あかねは思わずキョトンとしてしまった。
この話の流れで頼久が自分の前から姿を消すのがとても不自然だったから。
いつもなら優しく抱きしめたりしてくれるのにとあかねが少し寂しく思っていると、そこへ頼久がとんでもないものを手にして戻ってきた。
「よ、頼久さん、それ…。」
頼久が手にしていたものとは、クッキーが山のように詰め込まれた小さなバスケットだった。
「神子殿の高校ではバレンタインデーにチョコレートをもらった相手の想いを受け入れる際にはクッキーを、義理チョコには飴を返すことになっていると天真に聞きましたので。お受け取り頂けますか?」
そうなのだ。
学校では昨日、ホワイトデー前日だというのにクッキーとキャンディが飛び交って、教師達が右往左往していたのだ。
バレンタインデーにチョコレートを渡しつつ告白した女の子と付き合うつもりなら男の子はクッキーでお返しをする。
それが付き合ってもいいという暗黙の了解。
確かにそんな暗黙の了解が学校にはある。
でも、それを頼久が実行してくれるとは思わなくて、あかねは呆然としたままクッキーのバスケットを受け取った。
「こ、こんなにたくさん…。」
「神子殿へ想いをお伝えするにはこれくらいはなければと。」
「う、嬉しいんですけど…全部食べたら太っちゃいそう…。」
と、あかねが心配するほどクッキーは大量だ。
「そう思いまして、砂糖は控えておきましたのでご安心を。」
「へ?………ひょっとしてこれ…頼久さんが…。」
「作りました。」
爽やかに微笑みながらそういわれて、あかねはさらにキョトン。
「作り方は詩紋に教わりましたのでご安心を。味は詩紋の保障付きです。」
「………あ、有難うございます!」
食事はともかく頼久がクッキーを、それも自分のために作ってくれたと思うとあかねは嬉しくて嬉しくて、思わずその目に涙を浮かべた。
「み、神子殿?!」
「あ、いえ、その、これは…う、嬉しくて…。」
そういわれて頼久は安堵の溜め息をつきながら、あかねを優しく抱きしめた。
「ではそろそろ、お送りしますので。」
「あ、はい、そうですよね…頼久さん。」
「はい?」
「今日は本当に有難うございました。さっきまで帰るの寂しいなって思ってたんですけど、こんなにたくさん頼久さんの想いがつまったクッキーもらったら、家に帰ってからも楽しみができて、少しだけ寂しいのが減りました。」
頼久の腕の中でそう言ってあかねが恋人の顔を見上げれば、頼久は優しく微笑んでいて…
そのまま頼久の顔が近づいて、あかねは優しい口づけにうっとりと目を閉じた。
唇が離れてからも幸せで、にっこり微笑んだあかねを頼久は玄関へと誘う。
二人離れ離れになる時は寂しいけれど、今日はきっと大丈夫。
あかねは家へ帰る道すがら、クッキーがたくさん詰まったバスケットを抱きしめてそう思うのだった。
管理人のひとりごと
ということで、頼久さんのホワイトデー大作戦終了です。
はりきっていっぱいつめこみましたね、頼久さん(’’)
おかげで長くなりましたよ(マテ
クッキーだ飴だって話は管理人が学生時代にはやった風習です。
もう遠い昔です(’’)
頼久さんとの楽しいデート、皆様にもお楽しみ頂けたでしょうか?
私も頼久さんとペンギンの行進、見に行きたいです(’’)
プラウザを閉じてお戻りください