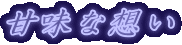
あかねはニコニコと微笑みながら小さな紙袋を片手に歩いている。
そう、今日は2月14日。
バレンタインデーだ。
最近はテストが多くてなかなか頼久と二人きりで会う時間もとれなくて寂しかったこともあって、あかねは朝早くから頼久の家へ向かって歩いていた。
ちょうど今日は土曜。
学校は休み。
この日だけは絶対に頼久と二人で過ごそうと、頼久の方でも時間をあけてくれているはずだった。
もうすぐ学年が変わって受験生になってしまえば、なかなか二人きりで楽しく過ごす時間なんて取れそうにないから…
もちろん、勉強を教えてもらいには来るつもりだけれど、勉強しながらではやっぱりゆっくりなんてできない。
だから、こんなイベントの日くらいは二人でゆっくり楽しく過ごしたい。
そんなことを思いながらあかねが頼久の家の扉の前に立つと、いつものようにすぐに扉は内側から開けられた。
もちろん、扉の向こうから現れたのは頼久だ。
「おはようございます。少し早かったですか?」
「いえ、お待ちしておりました、どうぞ。」
頼久に誘われていつものように中に入れば、部屋の暖かさにほっとした。
今ではあかねにとってこの家は自分の部屋よりも落ち着く空間だ。
「外は寒かったでしょう、コタツへどうぞ。」
「あ、でもお茶…。」
「私が。」
指先と頬を赤くしてやってきたあかねを早く温めたいのか、頼久は半ば強引にあかねをコタツへ入れると自分は台所へ立った。
バレンタインは一日、お互い仕事のことも勉強のことも忘れてゆっくり二人で過ごそうとかなり前から約束してあった。
だから、頼久は指折り数えてこの日を待っていたのだ。
本日も起床時刻は5時だ。
そんな頼久だから台所で紅茶をいれる後ろ姿もどこか軽やかだった。
あかねは既に暖かくなっているコタツへ入ってほっと一息つくと、頼久の背中をじっと見つめた。
広い背中は京でもこの世界でも全く変わらない。
この背中にどれだけ助けられたかわからないし、今だって守ってもらっていると思うと愛しさが増してあかねの顔には自然と笑みが浮かんだ。
「どうぞ。」
綺麗な低い声でそういいながら差し出されたティーカップを受け取って、あかねはにっこり微笑んだ。
本当にこうして二人でいられる時間はなんて幸せなんだろうと思う。
ところが、あかねが幸せをかみしめて微笑んでいると、すぐ隣に座るはずだと思っていた頼久がいつまでたっても座ろうとしない。
何があったのかとあかねが小首を傾げて頼久の顔を見上げると、頼久はブンブンと首を横に振った。
「頼久さん?」
「申し訳ありません、その……神子殿とこうして二人でいるのは久々ですので少々…。」
「少々?」
「見惚れてしまいました。」
今度はそう言って頼久が幸せそうに微笑みながらあかねの隣に座った。
そのままコタツに足を入れれば二人でぴったりとくっついて座ることになる。
あかねは顔を真っ赤にしてうつむいて、両手で包み込むようにティーカップを口へを運んだ。
「神子殿?」
「私も久しぶりに頼久さんの恥ずかしいセリフを聞いて照れてます。」
「恥ずかしい、でしょうか…。」
相変わらず無自覚の頼久は自分の言葉を思い出してみるのだけれど、いつもあかねがどうして恥ずかしがるのかが一向にわからない。
それでもこちらの世界へ来てからは乙女心を学習した頼久は、こんな時、話題を帰ることにしている。
「今年はバレンタインデーが土曜でしたから、学校は騒ぎにならずにすみましたね。」
「それがそうでもないんです。」
話題を変えた頼久の耳に届いたのは予想外の答えだった。
土曜といえば学校は休み。
なら、ギリチョコだ告白だと騒ぎにならないですんだはずだった。
ところが、あかねは頼久の隣で溜め息をついている。
「学校で何かあったのですか?」
「昨日なんですけど、やっぱり大騒ぎだったんです。」
「それはつまり、前倒しで結局のところは騒いだということでしょうか?」
「はい。気持ちはわからなくないんですけどね…。」
「気持ち、ですか?」
「せっかく年に一度のチャンスなんだから大好きな人に告白したいっていう気持ちです。私だって同じこと考えたかもしれないし。」
「……そう、なのですか?」
急に頼久の声に緊張が走って、あかねはあわてて隣を見た。
そこには捨てられた子犬のような顔をした頼久が…
「今、頼久さん、変な想像したでしょう?」
「変な想像では…。」
「私が言ってるのは、もしも私が頼久さんと出会うことなく普通の女子高生になって普通に生活していたら、やっぱりそういう気持ちになったかもしれないなっていうことです。私の場合は京で頼久さんに出会って、元の世界に戻るとか戻らないとか言う凄く大きな話になっちゃったから年に一度のチャンスどころが一生に一度になっちゃったから…なんというか……。」
「一生に一度の決断の時にこの頼久をお連れ頂いたこと、心から感謝しております。」
「お、大げさですよ、来てもらいたかったのは私も同じだったんだし…。」
そう言ってあかねが苦笑すると、頼久は優しい笑顔を返した。
あかねがどう思っていようと、やはりこの世界への同伴を許されたことは頼久にとって奇跡にも等しい幸福なのだ。
「あ、そうそう、それで学校では大騒ぎになったんです。校内中チョコレートのにおいでいっぱいになっちゃうし、先生は怒って女の子を追い掛け回すし、チョコをもらえない男の子はみんなうなだれてるしで大変でした。」
「それはなんとも賑やかそうです。」
「頼久さんも他人事じゃなかったんですよ?天真君の話だと、今日は剣道部の練習はないのかとか、頼久さんはどこにいるのかって聞いてくる女の子がけっこういたって……。」
「は?」
「頼久さんにチョコを渡したい女の子がけっこういたみたいなんですけど、昨日は剣道部お休みだったんですね。」
あかねは何気なくそう言って紅茶を飲んでいるが、頼久は一瞬頭の中が真っ白になった。
自分にはあかねという女性がいる。
学校ではそれは周知の事実になっているはずだ。
そのおかげであかねへの告白ラッシュは止まったのだと天真からも聞いた。
それなのにどうして自分にチョコを渡したい女生徒が発生するのか頼久には皆目わからない。
「神子殿…。」
「はい?」
「その、一つ不思議なのですが…。」
「はい、なんですか?」
「私にはその…神子殿という方がいてくださいます。学校ではそれが有名な話になっていると天真に聞きました…それで、その……。」
「どうして恋人のいる男性にチョコレートを渡したいのか?ですか?」
「はい。」
「ん〜、乙女心ですねぇ。」
「乙女心、ですか……。」
「恋人がいる人が相手でも好きなものは好きなんです。好きになっちゃったらしかたがないんですよ。」
「はぁ…。」
それはわからなくもない、と頼久は心の中でつぶやいた。
もしあかねが京で他の八葉なり、八葉ではなくても他の男を選んでいたとしたら。
それでもやはり自分はあかねを慕っていただろう。
だが、その想いを伝えようなどとは考えもしなかったはずだ。
もしそんなことをすれば心優しいあかねが苦しむことがわかっているのだから。
「略奪愛だってありますからね。私みたいな普通の女の子が相手なら頼久さんを奪えるかもって思っちゃってもしかたがないし。」
「そのようなご心配は無用です。」
「わかってます。」
慌てる頼久にあかねはクスッと笑って見せた。
他人から自分達がどう見えるのかはわからないが、頼久が簡単に他の女に乗り換えたりするような人ではないことだけはあかねも確信している。
「頼久さんが誠実な人だっていうことは私が一番よく知ってます。でも、他の人から見たらわからないじゃないですか。それに、本当に好きになっちゃったらもうどうしようもないものだから。私もそうだからそういうどうしようもない気持ちはわかるんですよね。」
「好きになったらどうしようもない、ですか。」
「女の子はそうなんです。私だってそういうふうにどうしようもないくらい頼久さんが好きじゃなきゃ、京を捨ててこっちの世界へきてくださいなんていいませんよ。」
サラリと何気なくそう言って紅茶を口にするあかねを見つめて、頼久は満面の笑みを浮かべた。
どうしようもないくらい頼久さんが好き。
そんなふうに言われたのはこれが初めてだ。
想いが通い合っているとわかってはいても、言葉にしてもらえるとそれこそ頼久などは天にも昇る心地だ。
「頼久さん?」
「神子殿にそのようにおっしゃって頂けるとは、この頼久、誰よりも果報者。」
「はい?」
やたらと嬉しそうな頼久の顔を正面から見つめて一瞬キョトンとしたあかねは、自分が口にした言葉を思い起こして突然顔を真っ赤にした。
「よ、頼久さんはそんなところばっかり気にして……そんなふうにでれっとしてたら本命チョコあげませんよ?」
「頂けないのですか?」
普段であればこんなふうに物をねだるような物言いをする頼久ではない。
でも、今日ばかりは最初からあかねがチョコを渡したいからあけておいてほしいと言っていただけにさすがの頼久も慌てた。
学校中のどの女生徒がチョコを渡してくれたとしてもそんなものとは比較にならないほどあかねからもらうチョコレートには意味がある。
一気に顔色を青くした頼久を見てクスッと笑うとあかねは傍らに置いてあった小さな紙袋を頼久に差し出した。
「冗談です。ちゃんと用意してきました。はい、頼久さん大好きです、これからも宜しくお願いします。」
「有難うございます、身に余る光栄です。」
そのセリフはなんだかやっぱり上司から褒美をもらっているように聞こえるのだけれど、あかねはとりあえず苦笑しただけで紙袋を頼久へ手渡した。
「開けてみても宜しいでしょうか?」
「はい、どうぞ。」
頼久が丁寧に袋から取り出したのは小さな平たい箱だ。
可愛らしく結ばれた紫苑のリボンを解いて蓋を開けると、中には手作りらしいトリュフチョコレートが入っていた。
「詩紋君に保障してもらったから、味は間違いありません!」
「神子殿がお作り下さるものはいつもおいしく頂いておりますが、これはまたいい香りです。」
「洋酒をきかせてみました。」
「では早速一ついただきます。」
小さな丸いそれを一つ口に入れると、頼久はゆっくりそれを味わった。
特に頼久は甘いものが苦手なわけではない。
京では甘い物は貴重品だったこともあって、今でも甘い物はなんだかありがたい気がするくらいだ。
それをあかねも知っているはずだが、このチョコレートは甘さが控えてあって洋酒の風味がきいていてとても食べやすい。
「どうですか?」
「とても食べやすい甘さで美味だと思います。」
「本当に?」
「はい。」
どうしてここで疑われるのだろう?
覗きこんでくるあかねの視線に頼久は小首を傾げて見せた。
「頼久さんは私が作るものはどんな味でもみんなおいしいって言うから…。」
そう言って眉根を寄せるあかね。
そんな表情も頼久にとっては愛らしいくてしかたがないのだが、今はそんなあかねに見惚れている場合ではない。
どうすれば本心からおいしいといっているのだとわかってもらえるのだろうか?
頼久はしばらく考え込んでから、すぐに行動に移した。
「へ?」
頼久のとった行動とは…
先ほど食べたばかりのチョコレートをもう一つ口に入れると、隣にいるあかねの肩を抱き、あかねが驚く間も与えずに口づけると少しだけ口の中で解けたチョコレートを口移しであかねに与えたのだ。
これにはさすがに慌てたあかねは唇を解放された後も、目を大きく見開いたまま凍りついてしまった。
「これで私が本意から美味だといっているとわかって頂けるかと……。」
これでどうだとばかりに喜んでいた頼久は、あかねが凍り付いているのに気付いて急に表情を変えた。
「み、神子殿?大丈夫ですか?どこかお具合でも?」
おろおろと頼久が慌てているうちに、コクリと口の中のチョコレートを飲み下したあかねは真っ赤な顔で頼久をにらみつけた。
「大丈夫じゃないです!きゅ、急にあんなこと……。」
「お嫌でしたか?」
「い、イヤじゃないですけど……びっくりするというか……。」
「私が味わっているチョコレートの味を同じように味わっていただければよいかと思ったのですが…神子殿には不愉快な思いを……。」
「ふ、不愉快ではないです!」
見る見るうちに落ち込んでいく頼久に今度はあかねが慌てる番だ。
あかねが懸命に否定してもどうやら恋人に嫌な思いをさせてしまったと後悔しているらしい頼久が立ち直る気配はない。
どんどん眉間にしわを寄せていく頼久を前にあかねは一つ大きく息を吸い込むと、何かを決意したように一つうなずいて今度はあかねの方から頼久に口づけた。
それは掠めるような一瞬のことだったけれど、あかねにとっては一大決心だ。
一方頼久はというと今まで落ち込んでいたのはどこへやら、一瞬驚きで目を見開いた後はその顔に幸せそうな笑みを浮かべた。
「こ、これでおあいこです!」
「はい。」
目の前にいる恋人の優しさも愛らしさも何もかもが愛しくて、頼久は優しくあかねを抱きしめた。
二人の間には甘いチョコレートの香り。
その香りにうっとりして、あかねは目を閉じた。
「甘いものって幸せになりますよねぇ。」
「私は甘いものよりも神子殿の方が…。」
「頼久さんはまたそんなこと言って……でも、私も甘いものより頼久さんと一緒の方が幸せです。」
「3月14日はお忙しいかもしれませんが、私のために時間を裂いていただけますか?」
「ホワイトデーですもんね。はい、喜んで一日あけておきます。」
そう答えてあかねはギュッと頼久の胸に抱きついた。
頼久のことだからきっと一生懸命考えて、再興のホワイトデーをプレゼントしてくれるはずだ。
またしばらく勉強やテストで会えない日が続くかもしれないけれど、3月14日だけは絶対にあけよう。
あかねは頼久の腕の中でそう心に誓うのだった。
管理人のひとりごと
つまりはただ甘いだけという…(マテ
この二人は現代ではもう特に事件ぽいことがなくてもいちゃついてるんですよねぇ(’’)
あかねちゃん、去年何を贈ったっけ?同じものだったような気がするなぁとかそういうことはいっさいチェックしない管理人なので気にしちゃだめです(コラ
忙しさにかまけてまた一気書きしてますので誤字脱字はご容赦くださいませ(TT)
というか、容赦してもらうことだらけだな、自分(TT)
何はともあれ、ハッピーバレンタイン!です!
プラウザを閉じてお戻りください