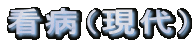
もうすぐ本格的な夏になる。
暑さと共にやってくるのは夏休み。
現役女子高生だから学校へ通わねばならないあかねにやっと大量の自由時間が発生する次期だ。
数日前からやけにうかれていたあかねだったが、前日は無理がたたったか少しばかり咳き込んでいた。
そのことが気になってしかたなくて、頼久は朝からずっと考え込んでいた。
自分に何ができるか?
あかねに体調を問えば大丈夫というだけで何も相談してはくれない。
だからと言って引きずって医者にいくわけにもいかないし、学校まで乗り込んでいくこともできない。
さて、どうしたものかと頼久がいつものように眉間にシワを寄せて考え込んでいると、テーブルの上の携帯が鳴った。
出る前に誰からの電話かを確認して大きく目を見開いた頼久は、あわてて携帯を耳に当てた。
あかねはとぼとぼと廊下を玄関へ向かって歩いている。
熱のせいで頭がぼーっとしてなんだか足下もふらふらする。
重たい辞典は置いてきたのにカバンさえもいつもより重たくて、ゆっくりと転ばないように注意して廊下を歩くのが精一杯だった。
昨日の朝から体調が少しおかしくて、頼久の家から帰宅する頃には咳まで出ていたけれど、それでも夏休みがくるのがうれしくてうかれてついつい頼久の家に長居をしてしまったのだ。
おかげで今日は朝から調子が更に悪かった。
ただ終業式に出席するだけだからと無理して登校してはみたものの、終業式が始まる前にすっかり体調が悪化してしまい、少しだけ保健室で休んだ後、帰宅を命じられてしまった。
運悪く、今日から両親は旅行に出かけることになっていて迎えを呼ぶこともできず、あかねは一人ふらふらと自宅への帰路についたのだった。
いつも見慣れているはずの学校の廊下がこんなにも長く玄関まで続いていたなんて。
そんなことをぼーっと考えながらふらふらと前へ進むあかね。
ようやく玄関にたどりついて靴を履き替えるのも体がだるく、あかねはいつもよりずっと時間をかけて靴を履き替えるとふらふらと外へ出た。
初夏の陽射しがまぶしくて一瞬目を閉じたあかねは、ふっと息を吐き出してから再び歩き出す。
今は一刻も早く家へ帰って薬を飲んで寝なくては。
そうは思ってもあかねの足は思うように動いてはくれない。
まっすぐ歩いているのかさえあやしい足取りでようやく校門までたどりつき、そしてとうとうそこであかねは自分の足につまずいてふらりと倒れそうになった。
が、地面にたたきつけられるはずのあかねの体はふわりと何かに受け止められて…
「大丈夫ですか?神子殿。」
「はい?……頼久、さん?」
優しく体を起こされて、あかねが朦朧とする思考で受け止めてくれた相手を見上げてみるとそこにはいるはずのない恋人が立っていた。
「あれ、どうして?ここに頼久さんが?」
「御母上から電話を頂きまして、御両親は旅行にお出かけだそうですね。」
「そうなんです、だから一人で帰ろうと思って…。」
そう言う間もまた倒れそうになるあかねを頼久はとうとう横抱きに抱え上げると、あかねが抗議する間も与えず、近くに停めてあった車の助手席に乗せてしまった。
あかねが取り落としたカバンを拾い、すぐに運転席へ座ると車を発進させる。
助手席に座らされたあかねはぐったりとシートにもたれて、隣で運転する頼久を見つめた。
「えっと、どうしてお母さん、頼久さんに電話を?」
「神子殿のお具合が悪いと学校からご自宅へ電話があったらしいのですが、ご両親がどうしても迎えに行けないのでと私に神子殿を託して下さったのです。」
「お母さんが…。」
「そんなに調子がお悪いのならメールなり電話なりして頂ければすぐに迎えに参ります。」
「いえ…でも…迷惑かけちゃうし……。」
「決して迷惑などではありませんので、どうか無理をなさらずにこの頼久をお呼び下さい。」
「…お呼び下さいって……そんな…頼久さん別に私の従者じゃないし……。」
「神子殿……。」
「それに、意外と大丈夫、な気がしたんですよねぇ…保健室にいる時は……。」
赤信号で車を止めた頼久が隣を見ると、あかねの顔は熱で少しばかり紅に染まっていて、その瞳は熱のせいか少し潤んでいるように見える。
いつもより浅くて早い呼吸はとてもつらそうだ。
「無理はなさらないで下さい…神子殿のために私は在るのですから、このような時くらいは頼って頂きたく…。」
「このような時って……私、いっつも頼ってばっかりですよ、頼久さんには。」
そう言って力なく微笑むあかねに一瞬見惚れた頼久は、信号が青に変わっているのに気付いて慌ててアクセルを踏んだ。
それでも病人の体にさわらないように、ゆっくり車を発進させる気遣いは忘れない。
「ご自宅までお送り致しますので、安心して今はお休み下さい。」
「あ、はい…。」
低い落ち着いた頼久の声はあかねをとても落ち着かせてくれて、熱からくるだるさも手伝ってあかねはすぐに助手席で眠りに落ちたのだった。
あかねの自宅へ到着してからの頼久の行動は迅速だった。
まずは横抱きにあかねを抱き上げるとそのままあかねの部屋のあかねのベッドまで運び、寝巻きに着替えて横になるようにと厳しく言いつけると台所で氷水を用意した。
電話であかねの母に必要な物のある場所は聞いてあったから迷うことなく氷水とタオル、そして体温計、薬、飲み水といった必需品を用意するとそれらをあかねの部屋へと運び込んだ。
あかねはやっと着替えを済ませて布団にもぐりこんだところで、頼久はすぐベッドサイドにあるテーブルに看病道具一式を置くと早速あかねの上半身を抱き起こして薬を手渡した。
「さあ、まずはこの風邪薬を飲んでください。御母上はおそらく夏風邪だろうとおっしゃってましたので。」
「あ、はい、有難うございます。」
こんな時まできちんと礼を口にしてあかねは恋人から渡された薬を水で一気に飲み込んだ。
そして頼久は薬を飲んだことを確認するとあかねを再び寝かせて、その額に冷たいタオルを乗せてやった。
先日、この世界であかねに再会した日に一度、頼久はこの部屋にあかねを運んで入っているのだが、その時は部屋の中が薄暗かったのと長居をするような状況ではなかったのとでよく見ていない。
つまり、頼久にしてみれば初めて足を踏み入れるに等しい恋人の部屋なのだが、そんなことを満喫している余裕はない。
「あの、頼久さん。」
「はい?」
「ちょっと不思議なことがあるんですけど…。」
「はい、なんでしょうか?」
「お母さんはどうして頼久さんに電話したんでしょう?」
「は?」
「私、頼久さんのこと、両親にちゃんと話はしてますけど、連絡先なんて知らないはずだし…。」
「あぁ、そのことですか。」
そう言って微笑む頼久にあかねは不思議そうな視線を送る。
京からこの世界へ戻ってきて頼久に再会したあの日、母は確かに頼久に会ってはいるはずだが、連絡先まで知っているはずはないとあかねはそこが不思議でならなかったのだ。
母は自分の携帯をのぞき見るようなことをする人でもない。
「御両親にはきちんとご挨拶させて頂きました。その際に私の連絡先、電話番号とメールアドレスと住所は書いてお渡ししましたので。」
「はい?挨拶?」
「はい。神子殿にこちらの世界で再びお会いできたあの日、神子殿がお休みになられた後で色々と話をさせて頂き、私が心の底から真剣に神子殿をお慕いしている旨を御両親にお伝えしました。」
「ご、御両親って、お父さんにも会ったんですか?」
「はい、ご帰宅を待たせて頂きましたので。」
と、にっこり微笑む頼久。
対するあかねはもう発熱どころではなく、目を丸々と見開いている。
「私と神子殿は年が九つほど離れておりますし、御両親にしてみれば私のような者と愛娘であられる神子殿がその…恋仲というのは不安になられるであろうと思いまして、私がどれだけ真剣に神子殿をお慕いし、神子殿を大切にしようと思っているのかを御両親にご理解頂いておりますので。」
そんなことを御両親にご理解頂けるまでってどれくらい両親を説得したんだろうと考えてあかねは気が遠くなった。
あかねの両親は決して過保護ではないが、それでもまっとうな人の親程度にあかねを心配してはいるはずで、そんな両親を説得してしかも病気の娘を預けてしまうほど信頼させるくらいの説得とはどれほどのものだろうか?
そう考えてあかねは涙が出そうになった。
いつかは自分からちゃんと両親を説得しなくてはと思っていたのに、そんなことは当の昔に頼久の心遣いが行き届いてしまっていて。
だからこそここ数ヶ月、あかねが頼久の家へ毎日のように通っていることにも両親は何も言わなかったに違いないと思うとあかねは嬉しいやら申し訳ないやらでとうとう泣き出してしまった。
「み、神子殿!どうなさいましたか!」
「…ごめんなさい…でも…頼久さんが一人でうちの両親を説得してくれてたなんて………私もちゃんと話さなきゃって思ってたのに、その前にちゃんと話をしててくれたなんて知らなくて……。」
「少しでも神子殿を傷つけるようなことはしたくはありませんので。」
「門限を守るようにってずっと言い続けてくれてたのもそのせいなんですね。お父さんやお母さんの信頼を裏切らないように…。」
「御両親に反対されるような付き合い方をしては神子殿のお優しいお心を傷つけてしまいますから。」
何ほどのことでもないというふうに微笑む頼久が本当に大きくて頼れる人に思えて、あかねは涙を流しながら瞼を閉じた。
この人の側なら大丈夫。
この人と一緒にいれば必ず幸せになれる。
そんな確信があかねの胸の内から自然と沸いて出た。
「有難う、ございます…。」
他にももっとたくさん伝えたい気持ちがあったけれど、熱に犯された体はこれ以上いうことをきいてくれなくて、あかねはなんとも言えない安心感と幸福感を抱いたまま心地良い眠りへと意識を手放したのだった。
あかねがようやく眠りについたらしい様子を見て頼久はやっと安堵のため息をついた。
寝息はさほど苦しそうではない。
熱は高くてもそうたいした病ではなさそうな様子に頼久は心底安堵した。
そして一息ついたところでやっと頼久にはこの部屋が恋人の部屋だということに気付く余裕ができて、ゆっくりを部屋の中を見回した。
きちんと片付けられた部屋にあるのは勉強のための机と本棚、クローゼット、小さなテレビ、テーブル、ベッドとその側には小さなサイドテーブルがあり、サイドテーブルの上には頼久の寝室にあるものと同じランプが置かれている。
それは先日、あかねが天真を荷物持ちに指名してわざわざ頼久とおそろいにするために買ってきたものだ。
窓にかかるカーテンはピンクでかわいらしい。
本棚にあるのはほとんどが勉強に関係するものばかりで、あかねがまだ現役の女子高生であることをいやというほど主張していた。
それでも綺麗に整えられている部屋はとてもあかねらしくて、頼久は一人ふっと微笑みながらあかねの額のタオルを氷水に浸して冷やすとかたく絞って再びあかねの額へ乗せる。
熱はあってもそう苦しそうには見えなくて、頼久はあかねの寝顔に見惚れた。
あかねは頼久の家でもよく眠ってしまうことがあるが、こうしてベッドに仰向けにきちんと寝ているところを見るのは初めてだ。
見れば見るほど赤みを帯びたあかねの顔はかわいらしくて、頼久の口元には不謹慎とは思いながらもつい微笑が浮かんだ。
静かな恋人の部屋、カーテンを閉めていても部屋の中を明るくする夏の陽射し、これであかねが元気だったら文句なしに幸せな世界だが…
頼久の目の前にいるあかねは額にタオルを乗せた病人だ。
おとなしく眠るあかねを見守ること一時間、頼久は思い立って階下へおりた。
あかねが目を覚ました時に食べさせる粥を作っておこうと思い立ったのだ。
喉越しがよくて栄養価の高いものを入れてみようと一人考えながら頼久は台所へ向かうのだった。
あかねは頼久が作ってくれた粥をゆっくりと口に運びながら始終微笑んでいた。
熱はまだ下がりきっていなくて体もどこかだるかったけれど、それでも頼久が側にいてくれて心を込めて作ってくれたお粥を食べられるなんてかなり幸せだった。
風邪で寝込んでしまったらしばらくは会えないとさえ思っていたから。
「おいしい。」
そう言って幸せそうに微笑むあかねを見ているだけで頼久も満足げだ。
ベッドの上に上半身だけ起こしてカーディガンを羽織ったあかねはこれまたいつもと違ってかなり愛らしい。
「お口に合いましたか?」
「さっきまで全然食欲なかったんですけど、これならたくさん食べられそうです。」
そう言ってまたぱくっと一口粥を口に運ぶあかね。
頼久はそんな姿を優しく見守る。
「食べたらもう少しお休み下さい。まだ熱があるようですから。」
「あ、はい……でも……。」
「何か?」
「頼久さんずっと迷惑じゃないですか?お仕事とか大丈夫ですか?」
粥を食べる手を止めて心配そうに見上げるあかねに頼久は軽く首を横に振って見せた。
「仕事はつまっておりませんし、迷惑だなどということは決して。こうして神子殿のお側にいられるだけで私はこの上なく幸せですので。」
「よ、頼久さん……。」
顔を真っ赤にするあかねに頼久は慌てた。
急に熱が上がったように見えたからだ。
「神子殿!熱をはかってください!」
「ち、違います!熱はたぶん上がってないです……。」
「ですが…。」
「頼久さんが恥ずかしいこと言うから…。」
「恥ずかしいこと、ですか?」
小首をかしげて先ほどから自分が発した言葉をたどってみるが、恥ずかしいことというのに思い当たらない。
頼久にしてみればどれも自分の本心を真剣に語ったつもりだ。
「えっと、もういいですから…恥ずかしいけど、嬉しかったからいいです…。」
「はぁ。」
頼久は納得いかない様子だがあかねは説明するつもりはないらしく、ぱくぱくと粥を口に入れ始めた。
あかねの食欲が旺盛なのはいいことなので、頼久もこれ以上追求することはやめた。
今はあかねの風邪を治すのが第一だ。
顔を赤くしながらあっという間に粥を食べ終えたあかねがおとなしく再び布団へ入ると、頼久は冷たくしたタオルをその額に置いて微笑んで見せた。
「ご両親は一週間ほどご旅行と伺いましたが。」
「えっと、正確には8日かな。沖縄で羽根のばしてくるそうです。」
「では、神子殿をお一人にするわけには参りませんので、熱が下がるまではこちらに泊り込ませて頂きます。」
「…………はいぃ?!」
あかねが驚いて飛び起きようとすると、頼久がやんわりと、だがしっかり肩を押さえて寝かしつける。
「どうか安静に。」
「だって、今、泊り込むって言いませんでした?」
「申しました。」
「………あの…。」
「はい?」
「…えっと…一応私、女の子なんですけど……。」
「存じております。」
「…頼久さんも男の人なんですけど……。」
「はい。」
「…………確認しますけど、頼久さん独身男性なんですけど?」
「無論です。」
「……………確認しますけど、それはまずいんじゃないかと…。」
掛け布団の端を口元まで引き上げて真っ赤になるあかねを不思議そうに眺める頼久。
病人の看病に泊り込んでいったい何がまずいのだろうか?
頼久の頭の中にはとにかくあかねに元気になってもらうことしかない。
「まずくはないかと…ご両親に許可も頂いておりますし。」
「……許可ぁ?!」
「はい。」
「お、お父さん、お母さん……。」
娘がかわいくないんですかとちょっとだけあかねは心の中で両親を疑ってしまった。
「神子殿は何も心配なさらず、ゆっくりとご養生下さい。」
そう言って満面の笑みを浮かべられてはもうあかねには何も言うことができない。
結局、あかねはこくりとうなずいて顔を真っ赤にしたまま布団を深くかぶるのだった。
こうしてあかねは三日三晩頼久の看病を受けて夏風邪を完治させた。
熱が高かった初日は頼久があかねのすぐ側で寝ずの看病をしたが、二日目からは客間で横になって眠った。
泊り込みという思いもかけない事態に一番動揺していたあかねだったが、二日目の夜からは頼久が側にいないことがなんだか寂しいと思ってしまうのだった。
管理人のひとりごと
先にUPした「看病(京)」の現代バージョンです。
こちらは看病する側とされる側が入れ替わってます。
今回のテーマは「あかねちゃんの両親を篭絡してる頼久さん」(爆)
一応、武士団の若棟梁なんかやってましたしね、そういう気配りできる人だと思います、頼久さんは(^^)
そしてお泊り許されちゃうほど信用されちゃうんです(笑)
プラウザを閉じてお戻りください