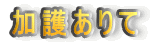
あかねはいつものように縁に座っていた。
秋の装いですっかり寂しくなってしまった庭を眺めているのだが、それは何故かといえば午前中は仕事があるらしい頼久がやってくるのを待っているというわけだ。
最近の頼久は左大臣や藤姫の警護の仕事が入ることが多くなった。
いつまでも神子殿の警護がお仕事ではなんだか特別扱いで嫌だとあかねが藤姫に話をして、頼久を普通の生活に戻してもらったからなのだが、それはそれであかねにとっては寂しい日が多くなった。
頼久が来ないとなると決まってこうして縁に出て頼久が来るのを待ってしまうあかねだ。
「神子殿、お待たせ致しました。」
「あ、早かったんですね。」
庭の向こうから姿を現した許婚にあかねは本当に嬉しそうな笑顔を浮かべて見せる。
昼過ぎには仕事が終わるだろうと聞いてはいたが、まだ陽は中天に昇りきる前で思ったよりずっと早い頼久の来訪だった。
階までやってきて一礼した頼久はあかねに促されて階に腰をかける。
それがいつもの頼久の席だ。
あかねは階の近くの縁に座っているから少しだけ頼久があかねを見上げる形になる。
主従関係にあった頼久にとってはその位置関係が今のところ一番過ごしやすいポジションらしい。
「お仕事どうでしたか?」
「はい、特に何事もなく。」
「よかったぁ。」
あかねがほっと胸を撫で下ろすのを柔らかな表情で見守る頼久。
頼久の腕が確かなことはこれまで四六時中といっていいほど守られてきたあかねのよく知るところではあるのだが、それでもやはり怪我の心配は尽きない。
「神子殿はお変わりありませんでしたか?」
「はい。私も特に何もなかったです。藤姫ちゃんから手紙が来たから返事を書いたくらいで。」
可愛らしく話すあかねを見て頼久は小さくうなずく。
そしてここでいつも二人の会話は途切れてしまうのだ。
もともとが口下手な頼久なだけに、あかねがどんなに頑張っておしゃべりをしてみても、こう毎日会っていては話題も尽きる。
だからいつしか二人並んで黙って座っていることが多くなったのだが、二人とも何を話すでもなく互いに視線を交わしてただやわらかく微笑んでいる。
最初は恥ずかしくて赤くなっていたあかねだが、今ではこうして二人で黙ってたたずむ時間がこれ以上なく幸せに感じられるようになった。
二人で一緒に座って同じ景色を眺める。
そしてたまに互いを見やって微笑み合う。
今のあかねにはそれで十分だった。
「神子。」
頼久とあかねがそうしてたたずんでいると、珍しい人物が姿を現した。
御室の皇子、永泉だ。
「永泉さん、お久しぶりです。」
「ご無沙汰しておりました。神子は健やかにお過ごしでしたか?」
「はい。永泉さんも元気そうですね。」
「はい。」
頼久は立ち上がって永泉に深々と一礼し、永泉はあかねから少し離れた縁に腰を下ろした。
「今日は神子にお願いがあって参りました。」
「お願い、ですか?永泉さんが私に?」
「はい。実は、近々、仏名会が行われるのですが。」
「ぶつみょうえ?」
「はい。今年一年の贖罪を懺悔し、善く生きることを祈願するためにあらゆる御仏の御名を唱える行事なのですが。」
「はぁ。」
「神子殿にも是非、仏名会に御出席頂きたいのです。」
「………はい?」
ほんの数秒考え込んできょとんとしたあかねに永泉は苦笑した。
天から降ってきたこの神子は京で行われる行事についての知識が全くといっていいほどない。
だが、そんな知識のなさを隠そうともせず、いつも無邪気に小首を傾げるのだ。
その無防備さが、少しだけ永泉には恨めしい。
「仏名会に御出席頂きたいのですが…お嫌でしょうか?」
「えっと…嫌とかいいとかいう以前に、私には何もできないと思うんですけど…仏様の名前なんて一つも知らないし。」
「その辺はご心配なく。神子に御仏の御名を唱えて頂くつもりはございませんので。」
「でも仏名会ってそういう会だって言いませんでしたっけ?」
「それはそうなのですが、神子殿はこの京をお救い下さった尊きお方、別段、御仏の御名を唱えて頂きたいとういわけではなく、ただその清らかな御身に同席して頂くだけでかまいません。」
「き、清らかな御身っていうことはないんですけど…。」
そう言ってあかねは赤くなってうつむいた。
京を救った尊き神子と呼ばれるのも嫌うあかねだが、清らかという言葉にも異常なほどに反応するところは今でも変わっていない。
「今年は怨霊が京を穢し、様々な災厄に見舞われました。神子が仏名会に同席して下されば、人々も安心して新年を迎えられることでしょう。是非、お願いしたいのですが、お嫌ですか?」
「えっと…嫌っていうわけじゃ…座ってるだけでいいんですか?」
「はい。」
優しく微笑む永泉。
あかねはその笑顔に一瞬見惚れてから階に座る許婚を見てみた。
いつものように座っている頼久はやはり穏やかに微笑んでいる。
もし何かあかねが出席しない方がいいことがあるなら、頼久の眉間にシワが寄っているはずだった。
これは出席した方がいいらしいとあかねは一つ小さく息を吐いた。
おとなしく座っているというのは得意じゃないけれど、他ならぬ八葉で仲間の永泉の頼みでもある。
無下に断ることなどあかねには不可能だった。
「わかりました。座っているだけでいいなら出席します。」
「有難うございます、神子。」
本当に嬉しそうに微笑む永泉にあかねは思わず見惚れてしまった。
そこら辺にいる女の子よりもよほどかわいらしい。
「神子?」
「な、なんでもありません。」
永泉さんが可愛らしくて見惚れてましたなどとはとてもいえないあかねは慌てて首をブンブン横に振った。
「あまり難しくお考えにならないで下さい。席も衣装もこちらでご用意致しますし、左大臣家の方にもこちらからお話ししておきますので。」
「はい。」
「快諾して頂けて安心致しました。では、わたくしはこれで。」
本当に嬉しそうに微笑んで、永泉は一礼するとあかねの前から去っていった。
再び二人きりになってあかねはほっと溜め息をつく。
仏名会。
どんなものだかさっぱりわからない行事に参加することになってしまった。
そのことがほんの少しだけ憂鬱だった。
「神子殿?」
「頼久さんは仏名会ってどんな行事だか詳しいですか?」
「いえ、私は警護につくだけで参加したことはありませんので…ただ、御仏の御名を三昼夜唱え続けるとうことです。」
「さ、三昼夜?!」
三昼夜って三日間?昼も夜も唱えっぱなし?
と、青くなるあかね。
それを見て頼久は思わず微笑んだ。
「ご安心下さい。神子殿はおそらくそのうちの数刻のみ同席されるだけかと。御仏の御名を唱える導師も入れ替わりますので。」
「それはそうですよね…一人で三昼夜って無理ですもんね。」
そう言ってあかねはほっと安堵の溜め息をついた。
「それにしても私がそんな大切な行事に招待されるなんて…龍神の神子っていったって、今はもう全然ただのおかざりだし、たいしたものじゃないのに…。」
「そのようなことはございません。神子殿は今も変わらず尊きお方、神聖なる儀式に参加なさるのは当然のことです。」
「そ、そんなことは…。」
「当日は私もできる限りお供致しますので。」
頼久にそう言われてあかねはやっと微笑みながらうなずいた。
おそらく頼久は武士という身分からして会場には入れないだろうが、それでも近くにいてくれると思えばあかねも心穏やかでいられるのだ。
「よろしくお願いします。」
「御意。」
二人はそう言葉を交わしたきり何も言わず、ただ微笑み合った。
ただただ二人で微笑み合う、そんな時間が愛しくて。
何を語ることもなく二人は縁でたたずむのだった。
頼久に伴われてあかねは内裏へとやってきた。
中までは入れない頼久とは笑顔で分かれて、迎えに来てくれた永泉と合流した。
頼久は心なしか心配そうに見えた。
あかねは自分も心細く思ったが、それでもなんとか無理に微笑んで見せて先を行く永泉に従った。
会場は清涼殿。
落ち着いている永泉の背中を見てもあかねの心細さは消えない。
目の前にある背中の大きさがいつもとは違って、逆に寂しくなってしまうのだ。
「神子?緊張しておいででしょうか?」
「あ、えっと、違うんです。緊張、してるわけじゃないです。」
そう言ってやはりあかねは力なく微笑んだ。
心配そうな永泉には申し訳ないけれど、今はこれがあかねの精一杯だった。
清涼殿へ到着するとつまらなそうに座っている友雅がすぐに見つかった。
友雅は永泉に連れられてきたあかねを見つけるとすぐに立ち上がって優雅な身のこなしで歩み寄ってきた。
あちこち几帳を立てて仕切られているから部屋中を見渡せるわけではないが、友雅が立ち上がっただけであちこちからざわめきが聞こえた。
それだけでも友雅の人気がどれほどのものかがよくわかる。
「よく来たね、神子殿。あちらに席を用意しておいたよ。」
「あ、有難うございます。」
友雅に連れられてあかねは几帳で仕切られた一角に腰を落ち着けた。
あかねに続いて永泉もその隣に腰を落ち着けると、友雅は二人を見比べてニヤリと笑った。
「たくさん人がいるみたいですね。几帳で見えないけど。」
「いるだろうね、年に一度の行事だしねぇ。」
「申し訳ありません。神子にこのような場所へ御出席頂いて…。」
あっという間に落ち込んでいく永泉に友雅が苦笑する。
「いやだなぁ、私、けっこう楽しみにしてたんですから。こういう大きな行事ってなかなか参加できないんでしょう?身分の高い人とかじゃないと。」
「それはまぁ、そうだね。」
「永泉さんが誘ってくれなかったら、こんな行事があること自体知らなかったんですから。誘ってもらってよかったですよ?」
「神子…。」
怨霊との戦いが終わり、京に平和が訪れて数ヶ月。
永泉があかねと毎日のように会っていたあの頃からずいぶんと時がたったというのに、あかねの優しさは変わらない。
それが嬉しくて、でも目の前にいる人が他人のものであることが悲しくて、永泉は弱々しい微笑を浮かべた。
そうこうしているうちにあちこちから低い声で仏の名を唱える声が聞こえ始めた。
一瞬会場内がしんと静まり返ったが、それも束の間、辺りにはざわめきが甦る。
あかねはそんなざわめき声に、なんだかとても嫌な雰囲気を感じて顔をしかめた。
「どうかしたかい?神子殿。」
「いえ…。」
言いよどむあかねに友雅も永泉も心配そうだ。
だが、あかねにはどう説明していいのかがわからなかった。
ただざわめき声を聞いて機嫌が悪くなっているなんて。
心配そうな友雅と永泉に見守られたまましばらく時は過ぎて、痺れを切らした友雅が同じくあかねのことが心配でならない永泉とうなずきあって立ち上がると、あかねは友雅と永泉の二人に強引に退出させられてしまった。
「えっと…あの…。」
「何も最後まで出席している必要はないからね。どうせ三日三晩続くのだし。」
「あぁ、それは頼久さんに聞きましたけど…。」
「そうなのです。ですから、どこかで少しだけ出席して頂ければそれでかまいませんので。」
戸惑うあかねにそう言って永泉は優しい笑顔を見せた。
「神子殿はどうも仏名会がお気に召さなかったようだしね。」
「別に仏名会が嫌だったわけじゃないんですけど…。」
「では、何が神子のお気にさわったのでしょうか?」
「お気にさわったって言うか……なんか凄く嫌な感じがして。」
友雅と永泉が顔を見合わせた。
龍神の神子が嫌な感じを感じたとはただごとではないのでは?と思ったからだ。
そんな二人の気配を察したあかねは苦笑しながら頭をかいた。
「怨霊とかそういうんじゃないですよ?そういうことじゃなくて、なんていうか……居心地が悪いって言うか…。」
やはりうまく説明できないあかね。
そんなあかねを見ていた友雅は少し何かを考えてからあかねの手を取ると歩く足の動きを早めた。
「友雅さん?」
「こういう時の神子殿には何を与えればいいのかよくわかっているのでね。」
友雅が何を言っているのかわからないあかねと永泉は顔を見合わせて小首を傾げながら、急ぎ足の友雅に合わせて歩みを速めた。
迷路のような内裏をするすると効率よく歩いてあっという間に友雅はあかねが入ってきた門の辺りまでやってきた。
すると…
「あ、頼久さん!終わりました!」
あかねのことが心配でずっと待っていたらしい頼久の姿が見えて、あかねはすぐに友雅の手を振り払うとその頼久の元へと駆けて行く。
友雅は隣を歩く永泉にウィンクして見せた。
「そういうことですか。」
「そういうものですよ。」
永泉と友雅、二人が苦笑しながら顔を見合わせている間に、頼久に駆け寄ったあかねの顔には満面の笑みが戻っていた。
「神子殿、お疲れ様でした。ずいぶんと早いお帰りですが、何か不都合でもございましたか?」
「不都合は別にないです。ただ、やっぱり三日三晩もやるから全部出てなくてもいいって友雅さんが連れ出してくれたんです。」
あかねがそう言って友雅を見ると自然と頼久の視線も友雅へ向いた。
二人の視線を受けた友雅はというと、もういつもの艶な笑みをその顔に戻してゆったりと二人に歩み寄る。
「まぁ、神子殿も何かお気に召さないようだったしね。義理は果たしたからいいだろう。さ、神子殿をお屋敷までお送りしようか。」
「せっかくですのでわたくしもお屋敷までお供致します。」
「じゃ、うちでお菓子でも食べてゆっくりしていって下さい。せっかく久しぶりに会えたんだし。」
あかねは嬉しそうに先頭をきって歩き出す。
三人の男は昔のように足取りも軽い龍神の神子に従った。
「その…神子殿。」
「はい?なんですか?」
「お気に召さないことがおありだったのですか?仏名会では。」
しばらく歩いて言い出しづらそうに切り出したのは頼久だった。
あかねの気分を害したものは何であっても排除したいのが頼久なのだ。
「ん〜、お気に召さないことってわけじゃないんですけど…なんていうか…凄く空気が悪かったんですよね。」
『空気?』
三人の男の声が重なった。
空気といわれてもよくわからない。
「友雅さんが私を席に案内してくれてからずっと、なんか噂されてるっていうか、こそこそ話してる声が聞こえて…仏名会が始まってからも、始まってすぐは静かだったのにだんだんまたこそこそ話してる声が聞こえてきたでしょう?あれ、凄くよくないことを話してるような、そんな気がしたんです。私の気のせいかもしれないけど…。」
「いや、気のせいではないだろうね。」
「そうなんですか?」
「あそこに集まっているのは公卿ばかりだからね。おおかた、出世のために何をするかという話をしていたのだろう。まぁ、私には興味がない話だけれどね。」
「友雅さんだって公卿じゃないですか。」
「私は武官だし、それに、出世には興味がなくてね。更に言わせてもらえば、出世の道具に女性を使おうなどというのは無粋の極みだよ。」
「出世の道具に女性を使う?」
あかねが立ち止まって友雅を見上げると、友雅の顔には苦笑が浮かんだ。
「話題の渦中の人はご自身の価値をご存じないからねぇ。」
「はい?私、ですか?」
友雅は困ったものだと言わんばかりに苦笑する。
「えっと、私と仲良くしても出世はできないと思うんですけど…。」
「これだからね、我らが神子殿は。頼久。」
「はっ。」
「我らが神子殿はご自身の価値をご存じないようだ。よくお守りしてくれ。」
「承知。」
「ええええ!なんでそうなるんですか?」
「神子殿の御身の安全はこの頼久、命に代えましても。」
「命に代えちゃダメですってば!もう、友雅さんがおかしなこと言うからです!」
可愛らしく男達をにらみ付けてからあかねはすたすたと歩き出した。
相変わらず自分が尊き神子だとは思っていないあかねに苦笑しながら後を追うのは友雅。
自分の尊さがわかっていない神子の身を案じて心配そうに落ち込みながら後を追うのが永泉。
そして許婚をどうやって守りきろうかと思案したせいで眉間にシワを寄せて後を追うのが頼久だ。
三人三様、大の男三人を引き連れたあかねの機嫌は屋敷に戻ってからもしばらくは直らなかった。
「では、神子殿、本日はこれにて…。」
「あ、はい。おやすみなさい。」
あかねの機嫌がやっと直って、友雅と永泉を送り出した頃にはもうすっかり夜も更けていて、頼久が退出する頃にはあかねはもう眠そうになっていた。
「今宵は冷えそうですので、暖かくなさってお休み下さい。」
「はーい。」
「では、失礼致します。」
いつものように一礼して頼久が立ち去ると、あかねは言われた通り褥の上に何枚もの着物を被って眠りについた。
仏名会に参加して疲れたせいか、あかねはあっという間に眠りに落ちた。
ところが、夜半、あかねはふと目が覚めた。
疲れてすぐに眠ってしまったはずなのに。
起き上がって辺りを見回して、真っ暗なことに気付いて。
どこか不安になってあかねは着物を何枚か羽織ると縁へ出てみた。
月明かりに照らされた冬の庭を見れば落ち着くだろうと思ったからなのだが、あかねは思いもかけない景色を見つけて目をこすった。
月明かりの下、階に座っている後姿が見えたのだ。
龍神の神子として戦っていた頃、警護してくれていたのと全く同じ頼久の背中がそこにはあった。
「頼久、さん?」
「神子殿…このような時間にどうかなさったのですか?」
「なっ、何言ってるんですか!頼久さんこそこんな時間にそんなところで何やってるんですか!」
「何とおっしゃいましても…警護、ですが…。」
「警護って…帰ったんじゃなかったんですか?」
「一度は戻りましたが…その…神子殿の御身に何かあってはと…。」
あかねは深い溜め息をついた。
昼間の友雅の話のせいでどうやらこの過保護に過ぎる許婚はいても立ってもいられなくなったらしい。
「大丈夫ですよ。友雅さんのあれはいつもの冗談ですから。」
「いえ…冗談ではございません。神子殿がこの京をお救い下さった尊きお方であることは間違いないのです。しかも愛らしくておいでです。出世を望むどこぞの公卿が狙っているやもしれません。」
「大丈夫ですよ。ちゃんと武士団の人達だって警護してくれてますし、私を狙うような人なんてそんなにいませんって。だから、頼久さんはちゃんと帰って休んでください。」
「……神子殿は…。」
「はい?」
「神子殿はこの頼久がここで警護することは迷惑にお思いですか?」
階に座っている頼久に悲しそうに見上げられてあかねは思わずブンブンと首を横に振っていた。
「迷惑なんてことないです!絶対ないです!そりゃ頼久さんに警護してもらえるならそんな安心なことはないんですけど…。」
「では、どのような不都合がおありなのでしょうか?」
「不都合というか…頼久さんにもちゃんと休んでもらいたいんです…。」
うつむいて語る許婚の言葉に安堵して頼久は小さく息を吐いた。
これで迷惑だと言われてしまってはどうしていいかわからなくなるところだった。
「ではやはりここで警護をさせて頂きたく。」
「でも、それじゃ頼久さん全然休めないじゃないですか。」
「自室に戻っても心配で眠れそうにありませんので。」
「じゃあ、せめて局の中に入って下さい。ここじゃ寒いし…。」
「それは…。」
やはりどうあっても頼久が局の中に入ってくれる気配はなくて、あかねは深い溜め息をついた。
「わかりました。それじゃあ、私も今晩はここにいます。」
「は?」
「頼久さん一人をここに座らせておくなんてできませんから、私も朝までここにいます。」
「それも…その……。」
頼久がやんわりと断ろうとあかねの様子をうかがってみると、どうあってもこれだけは譲らないとばかりにきりっとした顔がそこにはあって、今度は頼久が深い溜め息をついた。
この許婚が一度決めたことを貫く女性だということはよく知っている。
何しろ、この京を滅亡から救った女性なのだ。
ではどうしたものか?と考えて頼久はしかたないと苦笑を浮かべると、すっと立ち上がった。
「頼久さん?」
小首を傾げるあかねの背後にストンと座った頼久はそのまま着物を何枚も羽織っているあかねの体を膝の上に抱き上げて、ぎゅっと両腕の中に閉じ込めた。
「はい?」
「私も引けぬ、神子殿もお引きにならぬとあれば致し方ありません。朝まで二人で月でも愛でておりましょう。ですが、神子殿がお風邪をめしてはいけませんので。」
「えっと…。」
「まだ寒いですか?」
「さ、寒くはないです…。」
誰も見ている人間などいないとわかっていてもあかねは顔を真っ赤にしてうつむいた。
そんなあかねを更に自分の方へと抱き寄せて頼久は満足そうな笑みを浮かべている。
盗み見るようにあかねがその頼久の顔を見上げてみれば、幸せそうな笑顔にぶつかって、あかねはもう抵抗などできなかった。
何より、頼久の腕の中は温かかったし、これ以上あかねにとって安心できる場所はなかったから。
そしていつの間にか頼久の腕の中でうっとりと目を閉じたあかねは、そのまますやすやと寝息をたて始めるのだった。
管理人のひとりごと
京で行われる行事、仏名会のお話でした。
もちろん平安時代に実在した行事でございます。
資料は「平安時代儀式年中行事事典」(阿部猛 他/編)を参照致しました。
もちろん、資料は参照しましたが、風景なんかは管理人の想像で書かれていますので、正確な情報を知りたい方は管理人が参考にしました資料を御覧下さいm(_
_)m
宮中行事になっちゃったんで、頼久さんはマテさせられてます(笑)
こういう時のお供はやっぱり皇子と少将様でしょう。
二人ともせっかくあかねちゃんと頼久さんぬきで一緒にいられる機会だったのに、けっきょく頼久さんのところへ送り届けちゃってますな(笑)
頼久さんが心配性なところは相変わらずなのです(^^)
プラウザを閉じてお戻りください