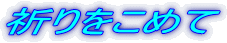
熱い鉄を打ち続ける毎日にイノリは没頭していた。
八葉として京を守るため、仲間と一緒に駆け回っていた日々は充実していたが、今も同じように充実している。
それでもたまにこの世界に留まってくれた龍神の神子に会いに行くと、かつての仲間達にも会えたりするのだが、最近は修行に忙しくてあまり訪ねていない。
あかねのもとを頻繁に訪れない理由は別に忙しいからというだけではない。
共に京のために毎日、怨霊を探して闊歩していた頃は龍神の神子に淡い想いを抱いていたイノリとしては他人のものになってしまったあかねに会うのがなんとなくつらい気もするのだ。
だが、今日、自分で打った小刀が完成して、その出来があまりにもよくて、イノリは久々にあかねの元を訪れることを決めた。
せっかく初めて上手くできた小刀はあかねに護身用に持っていてほしいと思ったからだ。
天の青龍の妻になったとはいえあかねは今でも龍神の神子だし、自分はその神子を守る八葉のままだ。
それより何より、共に京を救った仲間でもある。
だいたい、年齢なら頼久より自分の方があかねに近いじゃないか。
そんなことまで考えてイノリはすっくと立ち上がった。
あかねは確かに頼久のものになったが、あの優しい笑顔を向けてもらう権利くらいは自分にもあるはずだ。
そう心の中でつぶやいて、一つうなずいてイノリは歩きだした。
あかねはすっかり慣れた日常の朝を迎えていた。
最初の頃はどうしても夫よりも早く起きて色々準備してあげたいと頑張っていたけれど、朝の鍛錬をする頼久はどう頑張ってもあかねより先に起き出して、ひょっとするとあかねを起こしにきたりした。
妻たるものそれではいけないと当初はとても頑張って早起きしようとしていたけれど、今となってはもうあきらめた。
頼久が朝の鍛錬をしている間に起き出して、自分の身支度を整えて朝餉を一緒に食べて仕事に出る頼久を見送れればそれでいいと割り切ったのだ。
頼久もどうやらそれで十分満足らしく、というか、逆に自分より早く起きて頂くなどもったいないといいたそうなのであかねも譲歩することにした。
で、本日も、隣を見ると空の褥がきちんと整えられているのを確認してからあかねは着替えて庭の見える縁へ向かった。
庭では空を斬る小気味いい音をたてながら頼久が朝の鍛錬をしていた。
いつもの構え、いつもの鍛錬。
だが、何度見ても頼久の木刀を構える立ち姿が美しくてあかねは見惚れてしまう。
そして見惚れて声をかけ忘れていると必ず頼久の方が先にあかねに気付くのだ。
「神子殿、お目覚めですか。」
「はい、おはようございます。」
「おはようございます。」
何度か名前を呼んでもらえるように頼んでみたけれど、どうしてもいまだに自分を神子殿と呼ぶ頼久に苦笑しながらあかねは手ぬぐいを手渡した。
京には手ぬぐいというものは存在しないらしく、頼久が汗を拭くのになんだか普通の布を使っていたようなのであかねが手ごろな布を手ごろな大きさに切ったものを手ぬぐいとして渡すようになったのだ。
「有難うございます。」
いちいち丁寧に礼を述べてから頼久は嬉しそうに手ぬぐいを受け取って額の汗をぬぐってくれる。
これが毎朝の二人の日課になった。
「今日は武士団の方に顔を出すんですよね?」
「はい、少し若いものの稽古を見てやらねばなりません。」
まだ若いのは頼久も同じなのにとあかねはくすりと笑ってしまった。
武士団の次期棟梁は部下の面倒見がいい。
「申し訳ありません。」
「謝らないで下さいって何度も言ってるじゃないですか。私は今日の予定を確認してるだけで、別に頼久さんがお仕事に出かけることを嫌がってるわけじゃないんですから。」
「それはよくわかっておりますが…神子殿をお一人にしてしまうことに変わりはなく…。」
これも二人の毎朝の行事のようなものだ。
頼久は仕事があると必ず一言あかねに謝罪してしまうのだ。
休みの日となればそれはもう嬉しそうな笑顔で休みだと告げるのだが。
「もう、本当に謝らなくていいですからね。ってこんな言い合いしてたら武士団に行くの遅くなっちゃう。朝餉にしましょう、頼久さん。」
「はい。」
頼久が嬉しそうに返事をして階を上ろうとしたその時…
「お、あかね、頼久、久しぶりだな。」
庭へイノリが姿を現した。
最初に出会った頃よりは背も伸びて少しばかり大人びたイノリにあかねと頼久が笑顔を見せる。
「イノリ君、久しぶり!」
「元気そうだな。」
あかねと頼久にそう声をかけられればイノリの顔にも笑みが浮かんだ。
「まぁな、修行も充実しているし元気だぜ。頼久がまだいるってことはオレ、邪魔か?」
「そ、そんなことないよっ!これから朝餉なの、よかったらイノリ君も一緒に食べない?」
そう誘われてイノリは初めて自分が朝から何も食べずに飛び出してきていたことに気付いた。
あまりにも小刀が上手くできたことが嬉しくて、それをどうしてもあかねに贈りたくてどうやら空腹すら忘れていたらしい。
イノリは恥ずかしそうに苦笑しながら頭をかいた。
「そういやオレ、まだ何も食ってなかった。」
「じゃ、一緒に食べよう。」
「そうしろイノリ、遠慮はいらん。」
頼久にまでこう言われてイノリに断る理由はない。
結局、イノリは新婚家庭の朝食に同席することになった。
どれほどいちゃつく二人を見せられるのかと覚悟して食事の席についたイノリだったが、なんのことはない、頼久とあかねはもくもくと食事を始めて、たいした会話もないまま食事を終えてしまった。
「お前らさぁ…。」
「何?」
食事の後片付けをしようとしていたあかねはそれを女房達にまかせてイノリへ視線を移した。
いつも自分で食べた食器は自分で片付けたいあかねだが、女房達に止められてしまうのだ。
「老夫婦みたいだぞ。」
「何が?」
「もうちょっとこう、なんていうか…会話があってもよくね?」
「あぁ、だって頼久さんすぐ出かけなくちゃいけないし。」
「神子殿はこのまま。私は武士団の方へ参りますので。」
そう言って頼久が立ち上がるとあかねも慌てて立ち上がる。
「ダメです!朝はちゃんとお見送りするんですから!イノリ君、ちょっと待っててね。」
苦笑する頼久を先に歩かせてあかねはイノリの前から姿を消した。
変なところで変なことにこだわっているなと、イノリは溜め息をついて辺りを見回した。
この屋敷は頼久が移り住んでくる前からあかねが使っていた屋敷で、イノリも何度も訪ねているから見知らぬ場所ではない。
それでもやはりどこか雰囲気が違うような気がした。
屋敷全体が落ち着いて、穏やかな感じがする。
それが頼久が移り住んだことによる変化なのだろうとイノリは苦い思いと共に認めずにはいられなかった。
「ごめんね、お待たせ。イノリ君、何か用があってきたんだよね?」
一人で戻ってきたあかねはにっこり微笑んでイノリの前に座った。
あかねの笑顔は以前と何も変わらない。
だが、髪はずいぶんと伸びたし、着ているものも十二単ではないにしても小袿でもうすっかり京の人間のようだ。
あかねがこの京へ残ることを決めたと聞いた時、イノリは天真達と別れて自分の世界を捨てて大丈夫なのかと心配したものだったが、今ではすっかり京の人間のようになって楽しそうに微笑んでいる。
イノリは安堵するのと同時に少しばかり寂しかった。
「イノリ君?」
「お、おう、小刀、今まで打った中でも一番いいできに仕上がったんだ。だから、お前の護身用にと思って持ってきた。」
そう言ってイノリは懐から小刀を取り出すとそれをあかねに渡した。
あかねは鞘から抜いた小刀の刃を見てにっこり微笑む。
「本当、凄く綺麗だねぇ。」
「だろ。」
「でも私がもらっても使わないよ?たぶん。包丁ならたまに使わせてもらえるけど、小刀なんか抜いたら女房さん達が大騒ぎしちゃう。」
「護身用って言ったろ。」
「ん〜、護身で使うこともないと思うけど…。」
「あのなぁ、お前、自覚なさすぎ。京を救った龍神の神子で左大臣家の養女で、源武士団若棟梁の妻だろう?誰に狙われるかわかんねーじゃねーかよ。」
「あぁうん、それはわかってるんだけど、でもここは武士団の人達が守ってくれてるし、泰明さんの結界もあるし、それに頼久さんもずっと一緒にいてくれるし危ないことなんてないよ?」
そうだった。
イノリは心の中でつぶやいて深い溜め息をついた。
そう、神子殿大事の頼久が夫になったのだから、この屋敷に頼久がいる間はあかねに張り付いて離れないに決まっているのだ。
「だから、これはイノリ君が守ってあげたい人のために使って。」
そう言って優しく微笑んだあかねは小刀をイノリへと返した。
「でもよ、オレ、刀打つしか能がないし…何かお前のために作ってやりたいんだけどな…。」
頼久は夫として側にいればいくらでもあかねのためになんでもできるだろう。
友雅や鷹通は身分も家柄もある貴族だし教養もある、あかねのためにできることはいくらでもあるはずだ。
陰陽師である泰明は言うに及ばず、永泉だって帝の弟でしかも音楽ができる。
では自分は京に残ってくれたあかねのために何ができるかと考えれば、刀を作ることくらいしかない。
イノリはまだまだ頼りない自分に少しだけ腹が立った。
「そうだ!」
急にあかねがポンと手を叩いてにっこり微笑んだ。
何事かとイノリが目を丸くする。
「あのね、私、ほしいものがあるんだけど、この京じゃ絶対に手に入らないの。イノリ君作ってみてくれないかな?」
「オレが作れるものなのかよ。」
「鉄で作ってくれていいから、たぶんできるんじゃないかと思うんだけど…本当はプラチナとかで作るんだけど京にはないだろうし…。」
「ぷ、ぷら?」
「あぁいいのいいの、鉄で作ってくれていいの。あのね、この左手の薬指にはめる指輪がほしいの。」
「ゆびわ?」
「指にはめるわっかみたいなもの。私の世界では指輪っていうの。」
「指にはめるわっかって…そんな小さいもの…。」
「ダメ?できない?」
「作ったことねーからわかんねーよ、やってみないと。」
「そっか、じゃ、やるだけやってみてもらっていい?」
「まぁ、できるかどうかわかんねーけど…。」
「それでね、頼久さんの左手の薬指にも合うようにおそろいで作ってほしいの。」
「はぁ?」
「私のいた世界ではね、結婚指輪って言って婚儀をあげた二人はおそろいの指輪をするの。だから、もしできたら二人でおそろいにしたいの。私、結婚指輪に憧れてたんだけど京にはないから…。」
そう言ってあかねがうつむくとイノリは自分でも気づかぬうちに胸を叩いていた。
「任せておけ。オレがなんとかして作ってやる。」
「本当?」
「おう、時間かかるかもしれねーけど、待ってろよ。」
「うん、有難う。」
そう言って微笑むあかねの顔が自分だけに向けられていることが嬉しくて、イノリはすっと立ち上がった。
あかねがそんなにも喜んでくれるのなら、今すぐ作業にとりかからなくては。
「イノリ君?」
「早速帰ってやってみる。じゃな。」
「ちょっとイノリ君、そんなに急がなくっても!」
あかねが引き止めてももう遅い。
イノリはあっという間に屋敷を飛び出して姿を消してしまった。
イノリは木箱を手にのろのろと歩いていた。
あかねに結婚指輪なるものを作ってほしいと依頼されてから一ヶ月。
色々試行錯誤して作ろうと努力してはみたものの、結局あかねが望むようなものはできる気配がなかった。
それで不本意ながら少しばかり方向性を変えたものを作ってみたのだが、これであかねが喜んでくれるとは思えない。
それでも何も連絡しないではあかねが心配するだろうととりあえず持ってきたのだ。
あかねの屋敷の前で逡巡して、それからイノリは深呼吸をして門をくぐった。
「あ、イノリ君、久しぶり。」
庭へ回ると縁に座っているあかねがすぐに見つけて声をかけてくれた。
隣には微笑を浮かべた頼久がいる。
前回はまだ頼久が屋敷にいる間に訪ねて邪魔をしてしまったからと今日は昼めがけてやってきたのだが、どうやら頼久は休みで屋敷にいるらしい。
以前は武士らしくいつも厳しい顔をしていた頼久が、最近はやわらかく微笑むようになったのもあかねのおかげだ。
そう思うとイノリの心中は複雑だった。
「この前頼まれてたやつ…。」
「あ、できたんだ!」
「いや…それが……。」
「ダメだった?」
「わりぃ、小さすぎて俺には作れなかった。だからその…これ…かわりに。」
イノリに差し出された木箱をあかねは大事そうに受け取ると、すぐに蓋を開けてみた。
そこに入っていたのは鉄の輪が二つ。
「指は小さすぎて無理だったんだ、だから…。」
「これ、ブレスレット!」
「ぶれ?」
「ブレスレットっていうの、この大きさは。手首にはめるのにちょうどいい大きさに作ってくれたんでしょ?」
「ああ、指だと小さすぎたから手首ならと思ったんだ。」
「有難う!あ、ちゃんとおそろいで作ってくれたんだ!」
「まぁ、一応な…。」
「はい、頼久さん。」
「これは?」
急に鉄の輪を手渡されて頼久はきょととんとしたまま凍り付いてしまった。
「手首につけてもらえませんか?私もいつもつけておくことにしますから。」
「はぁ…。」
とりあえずあかねが楽しそうなので頼久は言われるがままに手首に鉄の輪をはめてみた。
少しひんやりとするだけで別に邪魔にはならないようだ。
「この前話しましたよね、結婚指輪のこと。」
「はぁ、夫婦がそろいで指にはめる鉄の輪のことでしたか?」
「そ、そういうふうに言われるとこうムードがないんですけど、まぁ正解です…で、それをイノリ君に作ってもらってたんですけど…。」
「小さすぎてできなかったから手首にはめる大きさになっちまったんだ。」
そう言ってイノリは頭をかいた。
「なるほど。」
「でも、これで憧れのペアルック。」
『ぺある?』
頼久とイノリが声をそろえて小首を傾げるのがおかしくてあかねはクスクスと笑い声をたてた。
「ペアルックです。おそろいって意味です。頼久さんとおそろいのものがほしかったんです。」
「神子殿…。」
あかねと頼久が視線を交わしてそれ以上言葉もなく微笑み合うのをイノリは苦笑しながら見守った。
そう、この二人は夫婦なのだ。
「有難う、イノリ君。」
「いや、約束のものと違うものになっちまって悪かったな。」
「そんなの気にしないで。イノリ君が丹精込めて作ってくれたんだもん、嬉しいよ。」
「そっか、ならオレも嬉しいぜ。」
「今度、何かおいしいもの作ってお返しするね。」
「そんなこと気にすんなよ。オレは………オレはお前が喜んでくれればそれでいいんだからな。じゃ、オレ行くわ。」
「ええー、もうちょっとゆっくりしていけばいいのに。」
「いや、修行あるし。またな。」
そういうが早いかイノリは駆け出していた。
あかねが頼久と二人で幸せになってくれればいい、そう祈りをこめてあの輪を作ったのは本当だ。
だが、それでも、目の前で幸せそうに言葉もなく二人で微笑を交わされては、やはりいい気持ちはしない。
駆け足で庭を抜けて少しだけ縁の方を振り返れば、そこには微笑んで手を振るあかねとやわらかな表情でそっとあかねに寄り添う頼久の姿があった。
二人の左手首でイノリが磨き上げた鉄の輪が光っている。
その輝きを見てイノリはにっと二人に笑って見せると、大きく手を振って再び駆け出した。
すぐ帰って修行に戻ろう。
そしていつか、頼久が唸るような名刀を打ってやる。
イノリはそう心に決めて走り続けた。
管理人のひとりごと
もう遅くなりすぎてなんだかなぁの感がありつつもどうしても書きたかったイノリ君お誕生日おめでとう短編です(^^;
ちょっと大人になったイノリ君と、あかねちゃんと頼久さんが何かおそろいのものを身につけるところを書きたかったので発生したお話です。
さすがにね、指輪は無理だと思うんですよ、小さいし。
ということで腕輪になりました(爆)
京だと本当は同じ香とか扇子のガラをそろえるかなぁと思いつつ。
何はともあれ、イノリ君、お誕生日おめでとうございます(^^)
プラウザを閉じてお戻りください