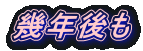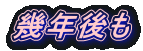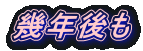
「では、わたくしは失礼致します。」
「うん、お休み。」
藤姫がニコニコと楽しそうに去っていくその背を見送って、あかねはほっと溜め息をついた。
まだ遠くの方ではにぎやかな人の笑い声が聞こえていて、今日が特別な日だと改めて気づかされた。
年末年始は京の貴族にとっては重要な行事が目白押しの季節だ。
あかねの養父でもあり藤姫の父であり、京の主たる帝に頼りにされている左大臣はそんな行事全てに顔を出さなくてはならない。
つまりは土御門邸から外へ出かけっぱなしというわけだ。
そして左大臣が出かけるとなれば動員されるのが警護を担当している武士達であり、その武士を指揮している頼久はここ数日ほとんどあかねの屋敷に帰れないという状況に陥っていた。
八葉に選ばれ、鬼と戦ったその功績も大きい頼久は左大臣には重宝がられていて、今回はどうしても警護から外れることができなかった。
藤姫が父に頼久を解放するように頼むと言い張るのを止めたのはあかねだ。
頼久の仕事が自分のせいで妨げられるのは嫌だというのがあかねの主張。
それでも一人で屋敷で年を越させるのはどうにも心配だと悩みぬいた頼久が選択したのが、土御門邸で藤姫と共に新年を迎えるようあかねを説得するという方法だった。
それなら藤姫も喜び、あかねも寂しい思いをしなくてすむし、頼久も心安く仕事に専念できるというわけだ。
この提案を喜んで受けたあかねは今こうして藤姫の隣の局で更けていく最後の夜を過ごしていた。
昼にこちらへやってきたあかねを藤姫は満面の笑みで迎えてくれた。
そこからは絵巻物や琴、碁、美しい扇子などなど…
藤姫が数日前からあかねを楽しませるためにと用意していた様々なものがあかねの前に並べられて、一日中とても楽しく過ごしたのだった。
おいしい食事をご馳走になって、それからしばらく藤姫と楽しくおしゃべりをして、夜が更けて眠くなった藤姫がついさっき退出したところだ。
土御門邸にはひっきりなしに客が訪れて、笑い声も響いている。
さすがに上級貴族となると正月はにぎやかになるらしい。
そんなことを思いながらあかねは褥に体を横たえた。
きっと今頃は藤姫も疲れ果てて眠っているだろう。
明日になれば一度頼久も顔を出すと言っていたし、ここは眠っておいた方がいい。
そうは思ってもなかなかあかねのまぶたは重くなってはくれなくて…
あかねは褥の中でぱちりと瞬きをしてから溜め息をついた。
今頃頼久さんはどうしてるだろう?
そんなことばかりを考えてしまって、ここ数日ゆっくり話もしていない夫の姿ばかりを思い出してしまって…
せっかくのお正月を一緒に迎えられないのは寂しいな。
そう思い始めるともう寂しさはつのるばかりだ。
やっぱり藤姫と一緒に寝てもらえばいいだろうか?
いいや、たとえば今藤姫が隣で眠っていたとしてもこの寂しさが消えるはずはない。
外へ出て月でも見上げようか?
そうすればきっと頼久と二人で見上げた月を思い出すに決まっている。
何をしてもどうやってもあかねの思いは愛しい夫へと向いてしまって…
今頃左大臣の警護で内裏の側にいるであろう頼久には到底会えるはずもない。
会えるはずがないと思えば思うほど寂しさは募るばかりだ。
こんなふうに寂しくなる時はどうすればいいのか友雅さんにでも聞いておけばよかった。
そう思ってもその友雅も今は帝の側近くにいるはずで、あかねにはどうすることもできない。
明日になれば会えるとわかっているのに、それでも寂しくて、あかねは目に浮かんだ涙をぬぐいながらとうとう身を起こした。
このまま眠るなんてとてもできるとは思えない。
やっぱり月でも眺めていようかとあかねがごしごしと涙をぬぐったその時、半蔀がカタリと音をたてた。
さきほど藤姫が出て行った後、掛け金を下ろしていなかったと気づいてももう遅い。
宴の夜は酒に酔った貴公子達が夜這いをかけてくるかもしれないから気をつけるようにと、前に友雅に注意されていたのをすっかり忘れていた。
あかねは慌てて辺りを見回した。
侵入者を撃退するための何か武器になりそうなものを探したのだ。
ところが、局の中にはそれらしいものは何一つ見当たらない。
あかねは一つ深呼吸をして半蔀をくぐる気配に思い切り近くにあった単を投げつけた。
「み、神子殿?」
「へ?」
「起きておいででしたか。」
「頼久、さん?」
「はい。」
あかねは近寄ってくる人影が小さな灯りに照らされるのを見てやっと安堵の溜め息をついた。
先ほど投げつけられた単を抱えているその姿は確かに頼久だ。
「すっかり寝ておいでのものと思っておりました。」
「あの…頼久さん、左大臣さんの警護だったんじゃ…。」
「はい、そうだったのですが…友雅殿にお気遣い頂きまして…。」
あからさまに不本意という顔をした頼久は、あかねの目の前に座ると小さく溜め息をついた。
「友雅さん?」
「はい、せっかく新しい年を迎えるというのに神子殿のお側にいないでは神子殿に寂しい思いをおさせするだろうとお気遣い頂きまして、左大臣様に私を帰すようにと進言してくださったのです。」
「もぅ、友雅さんったら、まだ私のこと子供扱いなんですね。」
「いえ、私も神子殿のお側にありたいと思っておりましたので…ですが、ご迷惑でしたら今すぐにでも…。」
「迷惑なはずないじゃないですか!」
思わず大きな声を出して、あかねは慌てて口を閉じた。
ここは自分の屋敷ではなく土御門邸。
大声を出すのははしたない。
「私だって会いたかったです…寂しくて眠れなかったんですから…。」
「左様でしたか。では、こちらへ出向いて正解でした。」
「そういえば…ごめんなさい。」
「は?」
「その…友雅さんにも気をつけるようにって言われてたんですけど、私、戸締り確認するの忘れてそれでそこが開いてて……。」
もし、入り込んだのが頼久ではなかったら、もしかしたらあかねは誰か見知らぬ男に言い寄られていたかもしれないのだ。
既成事実を作られていたかもしれない。
そう思えば、自分の迂闊さが申し訳なくて、あかねはしゅんとうつむいた。
「いえ、そのことにつきましては、藤姫様がお気遣い下さったようで。」
「藤姫が?」
「はい。私が来ないようでしたら戸締りをするよう女房殿に言いつけるつもりであったと先ほど庭先で…。」
「ふ、藤姫、気がついてたんだ、私が戸締り忘れてること…。」
「友雅殿に私を解放するよう進言せよと気配りくださったのが藤姫様でしたようで、それで、私が来るようなら戸締りはよかろうとお思いだったようです。」
「そうだったんだ…。」
「私は中に入ることができるとは思っておりませんでしたので、表で警護をと思っていたのですが…。」
「そんな!起こしてください!」
「ですが、開いておりましたので好都合でした。」
優しく微笑む頼久の笑顔に、思わずあかねは目に涙を浮かべてしまった。
自分の迂闊さを気にしているあかねを気遣う頼久の優しさが胸に温かい。
「神子殿さえ宜しければこのまま朝までお側に…。」
「もちろんです!一緒にいてください!」
「御意。」
間髪入れないあかねの返事に嬉しそうに微笑んで、頼久は腰から刀を外した。
上着も解いてくつろいだ姿になると、小さな灯りに照らされたその様子がなんだかとても艶やかで、あかねはほんのりと頬を赤くした。
「もうお休みになられますか?」
「あ、はい。」
「では、どうぞ。」
褥にあかねをいざなって、恥ずかしそうにしながらあかねが褥にもぐりこむのを見守った頼久は満足そうに微笑んで、褥の傍らに正座した。
思わずキョトンとしてしまったのはあかねだ。
当然いつものように同じ褥で寝てくれるものと思ったのに…
「あの…頼久さん?」
「はい。」
「なんで座ってるんですか?」
「私はお側近くにて神子殿の眠りをお守りすることさえできればそれで。」
「そんな…。」
「ここは左大臣様のお屋敷ですのであまりくつろぐわけには参りません。本来でしたら外で警護を…。」
「それは駄目です!」
「はい、ですからこのように…。」
そう言って頼久は動こうとはしない。
あかねは小さく溜め息をついて褥の中にもぐりこんだ。
いつもなら温かくて安心する旦那様の腕が抱きしめてくれているものだから、なんだか一人で眠るのは落ち着かない。
「あの…頼久さん。」
「はい。」
「寂しいんですけど…。」
「神子殿がお目覚めになるまでこうしてお側におりますゆえ。」
「……。」
やっと寂しいという一言を口にしたあかねはもう顔が真っ赤だ。
本当は隣で自分を抱きしめて一緒に眠って欲しいと言いたいけれど、そんなこと、まるで自分から誘っているようでとてもではないけれどあかねの口からは言えそうになかった。
それでもやっぱり一人寝は寂しくて…
あかねはくるりと頼久の方をむくと、上目遣いに端整な夫の顔を見上げた。
「さ、寒いんですけど…。」
「……。」
明らかに何を言われているのだろうと考えている顔であかねを見つめることしばし。
頼久は少しばかり長く感じる沈黙の後で、その口元をほころばせた。
「火桶をお持ち致しましょうか。」
「頼久さん……わかって言ってません?」
ぷっとむくれるあかねに微笑を深くして、頼久はむくれてとがっているその愛らしい唇に口づけを落とした。
「失礼致します。」
真っ赤な顔のあかねの隣に頼久が大きな体を滑り込ませると、嬉しそうに微笑んだあかねがすぐに頼久の胸に寄り添った。
あかねの頭の下に自分の腕を入れて、小さな体をしっかり抱きしめて、頼久はあかねの長い髪を優しく撫でた。
「これでお望み通りになりましたでしょうか。」
「はい、とっても温かいです。」
鈴の音のような愛らしい声が華やいでいることに気づいて、頼久は幸せそうな笑みを浮かべた。
新しい年を妻の側で迎えることはできないだろうと思っていただけに、今、腕の中にあるぬくもりが愛しくてたまらない。
「神子殿、もう少々…。」
話しかけようとして様子をうかがって、頼久はあかねが早くも静かに眠りについたことに気づいた。
小さな愛らしい寝息が聞こえてきたのだ。
そっと寝顔をのぞいてみれば、幸せそうな笑顔を浮かべていて、少しでも離れようとするとあかねは頼久の胸に擦り寄ってきた。
あまりに愛しい妻を抱きしめて、それでも起こすことはできなくて…
愛しくて愛しくてたまらない妻を抱きしめながら、頼久は一人苦笑を浮かべた。
これは、自分にとっては妻を求めることが許されないつらい一夜になりそうだと一人心の中でつぶやきながら。
管理人のひとりごと
どうしても京版もUPしたくて急いで書いた京版短編です(><)
ちと短めですが、やっぱり新しい年は京でも迎えたかったんだいっ!
もう書ききるのでいっぱいいっぱいってな状態ですので、誤字脱字はご勘弁を(TT)
頼久さんはあかねちゃんと甘く苦しい新年を迎えるようです(笑)が…
皆様には良い一年を迎えられますように(^^)
ブラウザを閉じてお戻りください