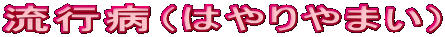
頼久は朝餉をあかねと二人、向かい合って取っていた。
こうして二人揃って朝餉をとるのはこの屋敷では毎日のことだ。
時にはあかねの手料理なども並ぶことがあって、忙しい毎日の中で頼久が幸せを感じることができる一時でもある。
「頼久さん、今日はお仕事ですよね?」
「はい。今日は早く戻れるかと。」
「じゃぁ、夕餉は私が作りますね。」
そう言ってニッコリ微笑むあかねを頼久は箸を止めてじっと見つめた。
何かいつもと様子が違う。
そのことに気付いたから。
何が違うのかと問われても何がと示すことはできないのだが、何かが違っている。
違和感のようなものにとらわれて、頼久は正面に座る妻を穴があくほど見つめた。
「頼久、さん?」
「申し訳ありません、ぶしつけなことを…。」
「いえ、それはいいんですけど、どうかしたんですか?」
小首を傾げられて、頼久は更にあかねをじっと見つめた。
愛らしい顔、つぶらな瞳、美しく流れる髪。
どれをとっても申し分のない美しさなのだが…
「その…少々お顔の色が赤いような……。」
「へ…。」
ようやくみつけた違和感の元を頼久が口にすると、あかねは慌てて両手で自分の頬を押さえた。
「あれ、今日はちょっと寒くて、さっき火桶に当たってたからそのせいかなぁ…。」
「寒かった、のですか?」
「はい。」
頼久は眉間にシワを寄せて考え込んだ。
あかねは今寒かったと言ったが、今日は冬の寒さもずいぶんとやわらいで頼久は暖かくなったものだと感じたのだ。
実際、庭の雪も溶けてきていて、春の足音が聞こえている。
しかも外はよく晴れていて、陽射しもほのかに暖かいくらいだ。
「神子殿、本日はずいぶんと暖かく感じられますが…。」
「へ?」
「もしや熱がおありなために寒気がしておいでなのでは…。」
「そう、かなぁ……。」
「そう体調が悪くなくとも万が一ということもございます。最近では流行病(はやりやまい)で姫君が何人がお倒れになったという話も耳に致しました。用心して本日は褥にてお休みください。」
「流行病……それはちょっと恐いかも…じゃぁ、今日は褥でおとなしくしていますね。その方が頼久さんも安心してお仕事できるだろうし。」
「そうなさってください。」
穏やかな頼久の声に一つうなずいてあかねが立ち上がったその時、小さなあかねの体がぐらりと揺れて次の瞬間、ふわりと前へ倒れこんだ。
声を発する間もなく、それでも常に鍛錬されている体が反射的に動いてくれて頼久が床に倒れこむ華奢な体を抱きとめる。
「神子殿!」
「あれ……頼久さん、私……。」
赤い顔でぼーっと頼久を見上げるあかねはやはりとても具合が悪そうだ。
頼久がその額に手を当てれば案の定、明らかに熱を持っていた。
「やはり熱が高いようです。すぐに泰明殿に来て頂きますゆえ、褥にてお休みください。」
もちろん、倒れたあかねを自分で褥まで歩かせるはずもなく、頼久は妻の小さな体を横抱きに抱くとそのまま寝室へと歩き出した。
慌てたのはあかねだ。
これから仕事に出るという夫に朝からこんな重労働をさせるわけにはいかない。
「頼久さん、自分で歩けますから。」
「いけません。またふらついて転んだりしては、病の上に怪我まで負われます。」
「だって頼久さんこれから仕事なのに……気をつけて歩きますから。」
「いけません。」
懇願するあかねにきっぱり言い放った頼久は、抱えている小さな体をギュッと抱き直して歩き続けた。
広い屋敷とはいえ、頼久にとってあかねを抱いて運ぶことくらいどうということではない。
抵抗する力もないまま運ばれたあかねはすぐに褥に寝かされた。
「ごめんなさい……。」
「お謝り頂く必要はございません。」
「でも、頼久さんお仕事なのに…。」
「そのようなことは考えず、神子殿はただ静かにお休みください。私は泰明殿に来て頂けるよう、手配して参りますので。」
「はい…。」
これ以上は何を言っても頼久の邪魔になると悟って、あかねはおとなしくうなずいた。
頼久はそれを見届けると、すっと立ち上がり、あかねに背を向けた。
具合の悪そうな妻を一人にするのは後ろ髪引かれる思いだが、ここは優秀な陰陽師である泰明に来てもらわなくてはならない。
そうすれば病魔など泰明がすぐに打ち払ってくれるはずだからだ。
頼久はあかねを救うためだと己に言い聞かせてあかねの局を後にした。
夜、頼久は濡れ縁のすぐ側、まだ雪が残っている庭に立っていた。
両手を力いっぱい握り締め、じっと濡れ縁を睨みつけている。
深夜であるにもかかわらず、頼久の立つ庭には僧侶が経を唱える声が響いていた。
朝、あかねが熱を出して倒れてから事態はあれよあれよと言う間に悪化した。
あかねの熱は上がり続け、慌てて頼久が呼んだ泰明の診断によると間違いなく流行病と断定された。
藤姫にもすぐにその知らせが届き、あっという間に僧侶が召喚され、加持祈祷が行われた。
それでもあかねの容態は悪化の一途をたどり、夕方には意識がなくなった。
加持祈祷の他、あかねの局の内では泰明が陰陽師として色々と処置をしてくれているはずだった。
友雅からは体を温めるようにと何枚もの着物が贈られてきたし、鷹通からは薬草の類が贈られた。
永泉からは主上からだと蜂蜜が届けられていた。
イノリは知らせた直後にすぐ見舞いに来てくれていたが、あかねが病をうつしてはいけないからと面会を断った。
八葉それぞれの心配と気遣いもあかねの体を回復させるには至らず、今もあかねは意識がない状態だ。
これで自分が流行病で倒れたら治ったあかねに心配されるからとイノリが日暮れと共に帰宅すると、頼久は一人で自分の無力さを呪うしかなくなった。
おそらく永泉なら加持祈祷を自ら行うことができただろうし、泰明は今も局の中でまじないの類を施してくれている。
だが、中にいてはまじないの邪魔だと泰明に宣言された頼久には、今あかねのためにできることが何一つなかった。
この病に効く薬を探したり、病で弱った体に栄養をつけるための食べ物を調達することもとっくの昔にやり終えた。
第一、そんなことは頼久がわざわざやらなくとも藤姫や友雅、鷹通達がすっかり手配してしまっている。
刀を振ることしか能のない自分にいったい何ができよう。
そう思えば己の力のなさが呪わしい。
頼久は眠ることもできず、当然のことながら武士団の仕事をすることなどできるわけもなく、こうしてただあかねの局の前で立ち尽くすしかなかった。
もし、この病であかねが亡くなるようなことになったら…
考えずにおこうと努力してもどうしてもそんな未来を想像してしまう。
そしてそのたびに頼久は胃の腑を握りつぶされるような感覚にとらわれ、次に全身に氷水のように冷たい汗をかいた。
あかねのいない未来。
あかねを死なせた自分。
あかねが苦しい時に何もできない自分。
到底受け入れられるものではない。
あかねがこの世からいなくなるのであれば自分も…
そう何度も心に決めて、それから龍神に愛でられし神子であるあかねが死ぬわけがないと必死になって否定する。
そんな葛藤が既に半日以上続いていた。
あの苦しい戦いを戦い抜いて、やっと幸せになろうという愛し子を龍神が死なせたりするものか。
頼久がそう心の中でつぶやいてひとしきり両手を強く握り締めた時、半蔀が開く音がして中から泰明が姿を現した。
反射的に頼久がすっと視線を上げる。
普段は見下ろす形になる泰明を見上げる頼久の顔は、月明かりに照らされて青白く、まるで死人のようだった。
「何をしている?」
「何も…。」
泰明の問いにただ一言、血を吐くようにそう答えて頼久は視線を足下へと戻した。
何をしているのか?
その問いは今の頼久には他のどんな問いよりもつらいものだった。
何もできない。
だからここで何もしないで、ただの愚か者として立っているのだから。
「することがないのなら休んでいるべきではないのか?」
「……。」
泰明の言うことはいちいちもっともだ。
彼が間違ったことを言うことはほとんど皆無といっていい。
今も泰明の言うとおり、できることがないのならちゃんと食べてちゃんと眠ってあかねのためにこそ体を大事にしておくべきだろう。
そうとはわかっていてもそれができない。
そんなことさえできない自分を頼久は呪うしかないのだ。
泰明はそんな頼久を見て小さく溜め息をついた。
「お前がその様子では病の神子の方が心配するぞ。」
「それは…ですが……。」
「病が快癒した時にお前が倒れていたのでは話にならぬ。」
「快癒、なさるのでしょうか……。」
「するに決まっている。あれだけの数の薬草、滋養のある食物に加持祈祷。何よりお師匠直伝のまじないを施した。早々に快癒するだろう。」
「それは……まこと、ですか?」
頼久の視線がゆっくりと上がった。
信じられないという顔で頼久を見上げる。
「お前は私をなんだと思っているのだ?龍神の神子を守る八葉の一人だぞ?できもしないことをできるとは言わぬ。」
「…よかった……。」
安堵のあまり崩れそうになる膝に思い切り力をこめて、頼久は深く息を吐き出した。
あかねは死なない。
稀代の陰陽師である泰明が言うのだから間違いない。
それはまるで自分が死なないと宣言されたような圧倒的な安堵感だった。
「ただし…。」
「た、ただし?」
あかねが助かることに条件がつくとは思っていなかった頼久は、その顔色をあっという間に青くした。
「神子の心持いかんでは病が長引くこともある。」
「心持……。」
「ここから先は私の仕事でも僧の仕事でもない、お前の仕事だ。」
「は?」
「神子の側について神子を安心させてやれ。神子がそれを望んでいる。」
「神子殿、が……。」
あかねが頼久が側にいることを望んでいる。
その泰明の言葉の意味をたっぷり10秒は噛み砕いて、そして頼久ははっと目を見開いた。
あかねが泰明に対して自分を望んだ。
それは意識不明だったあかねが意識を取り戻したということだ。
そうと気づいた頼久は、何も言わずに濡れ縁へと駆け上がり、そのままあかねの局へと転がり込んだ。
局の中は遠くから響く僧の声が聞こえるだけで意外と静かだった。
小さくおさえられた灯りに照らされて、褥に横になっているあかねが見える。
頼久は足音をたてぬように細心の注意を払いながらあかねのそばへと駆け寄って、その傍らに膝をついた。
「…頼久、さん?」
ゆっくりとあかねの目が開いて、薄い唇から自分の名がこぼれるのを頼久は奇跡が起きたような気持ちで聞いていた。
そして頼久は熱でほのかに赤くなっているあかねの顔をのぞきこむように身を乗り出して、全力の努力でもって笑みを浮かべた。
うまくできたかどうかはわからない。
もともと笑うのは得手ではない。
けれど、こんな時に目覚めたあかねに見せる自分の顔が情けない泣き顔であって欲しくはなかった。
「はい、ここに。」
発する声はかすれるかと思ったが、そうでもなかった。
頼久の声を聞いたあかねはその顔にうっすらと笑みを浮かべた。
「泰明さん、本当に呼んできてくれたんだ。」
「はい。苦しくはありませんか?」
「それが、そうでもなくて…泰明さん、色々してくれたから…。」
「さようですか。」
「今、夜ですか?」
「はい。」
「じゃあ、頼久さんはちゃんと休んでくださいね。」
「はい。」
自分が病の時まで夫の心配をする優しいあかねに頼久はただ肯定の言葉を紡いだだけだった。
もちろん、あかねの言いつけなのだからちゃんと休むつもりではある。
だが、どこで休むかまでは告げないでおく。
ここで、あかねの隣で休むといったらあかねは必ず反対するだろうし、あかねのそばを離れては頼久が眠れなくなることは間違いなかったから。
「…ごめんなさい……。」
「は?」
急にあかねの顔が悲しげに歪んで、その愛らしい唇が紡いだ予想外の言葉に頼久は動転した。
何故、あかねが謝る必要があるというのだろう?
「病気になんかなって…頼久さんに心配かけて……それに…こんなふうに夜、呼びつけたりして…。」
「何をおっしゃいます。神子殿が病に倒れてしまわれるほどのご苦労をかけ、病を治すために何一つお役に立つこともできず…。」
「そんな、頼久さんのせいじゃないし……側にいてくれるだけで私、凄く安心なのに…。」
「では、神子殿がお休みになるまでこうしてお側におりますので。疾くお休みください。」
「でも…私が寝たら、ちゃんと頼久さんも寝てくださいね?寝ずの看病とか絶対だめですから…。」
「承知しております。」
今すぐ休めと言わないのは、やはり心細いからだろうと察して頼久はあかねの髪をそっと撫でると笑みを浮かべて見せた。
するとあかねもようやくその顔に笑みを浮かべて目を閉じた。
病で疲れきっている体は自然と休息を欲していたようで、あかねはすぐに静かな寝息をたて始めた。
頼久が側にいると思えばこそ、安堵したのかもしれない。
熱で赤くなっているあかねの顔は、優しい微笑が浮かんだままだった。
「ほんとに頼久さんにうつったら大変だったじゃないですか…。」
病がすっかり癒えて、食事が普通にできるようになった朝。
あかねは久々に普通の朝餉を前にしてぷっとむくれていた。
何故かというと、病で寝込んでいた間中、頼久が実は夜も自分の隣で褥も使わずに寝ていたということが判明したからだ。
あかねは鷹通からの薬だの泰明のまじないだのが効いて夜はぐっすり眠っていたから気付かなかったのだが、頼久は昼も夜も決してあかねからは離れなかった。
その事実を今聞かされたところだ。
「うつりは致しません。普段から鍛えておりますので。」
「そういう問題じゃないですよ…それに、あの時、ちゃんと休んでくださいねってお願いした時ははいって返事してくれたじゃないですか。」
「どこで休むかはお約束いたしませんでしたので。」
「うっ……ずるい……。」
「神子殿を永久に失うかと思った瞬間もあったのです。神子殿のお側を離れるなど、到底私には無理でした。」
きっぱりとこう断言されてしまうとあかねももう抗議することができない。
心配かけたのは自分なのだからという思いもあって、あかねは何も言わずに溜め息をついた。
「神子殿の一大事にはお側に控えることくらいお許しください。」
「頼久さん…じゃぁ、病気の間はいっぱいお仕事も休んじゃったし、今日からは何も心配しないでお仕事してくださいね。私、病気で寝ていた分もいっぱい頼久さんのために色々頑張りますから。」
「いえ……。」
張り切るあかねから頼久は視線をそらした。
とたんにあかねの顔がいぶかしげな表情を浮かべる。
「いえって……。」
「藤姫様から、本日より3日は出てこなくともよいとさきほど使いが……。」
「えー!どうしてですか?」
「病が癒えたばかりの神子殿に心安くお過ごし頂くよう、細心の注意を払うようにと仰せつかりました。」
「そんな!」
「それに、病み上がりで私のために色々として頂くなどとんでもありません。」
「でも……。」
「藤姫様より厳命されておりますゆえ。」
この断言は、こればかりは絶対に譲らないと宣言されたようなものだった。
藤姫の命令ではあかねも抗いようがない。
もちろん、藤姫に頼んで頼久を仕事に駆り出してもらうことは可能だが、どうして大好きな旦那様に対してそんなことができるだろう。
あかねは正面で穏やかに微笑んでいる頼久を見てから深い溜め息をついた。
「もぅ、頼久さんも藤姫も過保護すぎ。」
「そのようなことは。本日は友雅殿、鷹通殿、それに永泉様とイノリも見舞いに来るとのことでした。久々ですので皆が顔をそろえるのもよいものかと。」
「皆って、泰明さんは?」
「もちろん、神子殿のお体を診るため……。」
頼久がそこまで言った時、泰明が御簾を跳ね上げて中へ入ってきた。
この元八葉は友雅と同様、先触れを使わずに黙って中へ入ってくる男性の一人だ。
「気の巡りが更によくなった。心安く過ごしているようだな。」
「泰明さん、はい、もうすっかり…。」
「油断は禁物だ。まじないを施す、朝餉が済んだら奥へ。」
それだけ言って泰明はさっさと奥へ引っ込んでしまい、あかねは頼久と苦笑を交わした。
どうやら過保護なのは頼久や藤姫だけではないらしい。
そう思いながらあかねは朝餉を急いで平らげるのだった。
管理人のひとりごと
京では風邪一つとっても病気は恐ろしいものでした。
今みたいに医療が発達してませんからね、薬もないし。
ないって言っても薬という概念はあったようで、薬草は主上の管理下で栽培されたりもしてたみたいです。
加持祈祷ももちろん行われましたが、ちゃんとお薬も飲んでたんですよ、平安の貴族達は(^^)
うちのあかねちゃんは一応貴族の部類に入るかなと思います。
頼久さんは右往左往してますが、友雅さんや鷹通さんは普通にお見舞いをくれてます(w
そして頼久さんには案の定うつりません!
頼久さんから体力を奪ったら何が残ると…(マテ
なので、頼久さんはあかねちゃんがどんな凶暴な病に倒れても寝ずの看病必至です!
ブラウザを閉じてお戻りください