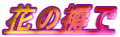
ぱたぱたたという足音が響くのはこの屋敷ではいつものことだった。
何故なら、この屋敷の女主はとにかく闊達でよく動く人物だったから。
京では考えられないほどよく動くその女主は、今日も朝から動き回り、自分はそうして動き回るくせに夫には動くことを禁じていた。
だから、頼久はじっと濡れ縁に座って耳に楽しく響く足音に耳を澄ませていた。
目の前に広がっているのは晴天の下に広がる美しい庭。
そしてその庭の中でも今は最も目立って見える桜の木は今が散り際で、ゆるやかな春の風がそよぐたびに薄紅の花弁を舞わせていた。
頼久はこの数日間、驚くほど詰め込まれた仕事に追われていた。
春ともなれば頼久のみならず源武士団の主筋にも当たる左大臣の外出が増え、そうなれば当然のように警護にあたる頼久達の仕事も増えた。
夜通しの警護ももちろんしなくてはならず、それが外出先でということになる日もあり、頼久はそれらの仕事に追われていたのだ。
今日、こうして濡れ縁にぼーっと一人で座っているのはそのためだった。
昨日まで忙しく仕事をしていた頼久は昨夜、ようやく解放されて本来ならば一瞬たりとも離れたくはない妻のもとへと帰ってきた。
このままでは妻であるあかねの愛する桜の花が散ってしまうのではないかと心配していたが、庭の桜はまだまだ見頃で、夜桜でもとあかねを誘ったのだが間髪入れずに断れてしまった。
というのも、あかねが花見よりも頼久の健康を優先したからだ。
結局、頼久はあかねに命じられるままに床につくことになり、ならばやっと与えられた休みの本日こそはあかねと花見をしようと決意していたのだが…
今度もそのあかねが、頼久が動くことを禁じたのだった。
もちろん、理由は仕事詰めだった頼久に休んでもらうためだ。
どうやらあかねも今日は花見をしようと思ってはいたようで、あかね本人は朝から大忙しのようなのだが、頼久はその手伝いを一切禁じられてしまった。
おかげで頼久は朝からこうして濡れ縁に座ったまま、散りゆく花を眺めつつあかねの足音に耳を澄ませることになっていた。
頼久にしてみれば、一晩や二晩は寝ずに仕事をしていてもどうということはない体力の持ち主だったから、あかねの側で何かと手伝わせたもらった方が気が休まるのだが、あかねがそれを許すわけもない。
自分が休むことであかねが心安らかになってくれるのならと、頼久は苦笑しながら一人で座り続けることになってしまった。
こうしておとなしく待っていればあかねが色々と心を尽くして二人の時間を楽しませてくれることは間違いない。
だから、屋敷のあちこちで聞こえる物音や足音、かすかに聞こえる愛しい人の声に耳を澄ませながら、頼久はじっとあかねとの幸福な時間が訪れるのを待っていた。
「頼久さん、お待たせしました。」
とたとたと愛らしい足音がして、その足音が自分の方へと近づいてくるのを感じただけで頼久の顔には笑みが浮かんだ。
視線を巡らせればあかねが女房達を従えてニコニコ微笑みながら頼久の方へと歩いてくるところだった。
女房達は料理と酒をあかねと頼久の周りに置くと、何も言わずに一礼して去って行く。
あかねは女房達に律儀に礼を言うと、頼久に満面の笑みを浮かべて見せた。
「えっと、お料理とお酒をとりあえず用意してみました。あ、でも、頼久さんは眠くなったら寝ちゃってもいいですからね。」
「いえ、それほど疲れてはおりません。昨夜はゆっくり休ませて頂きましたので。」
妻の優しい気遣いの一つ一つが幸せに思えてならない頼久は、あかねが差し出す杯を受け取ると、注がれる酒に少しだけ口をつけてすぐに料理を口にした。
今では一口食べただけですぐにわかる。
並べられている料理はどれもあかねの手作りだった。
「どれもこの上なく美味です。」
「それはほめすぎですけど…でも嬉しいです。」
顔を赤くしながら正直にそう言ったあかねは頼久と一緒に料理をつまみながら、花の舞う庭を眺めた。
春の陽射しの中を舞う桜の花びらは思っていたよりずっと綺麗で、あかねはその顔に幸せそうな笑みを浮かべながら頼久へと視線を移した。
以前は夜の間中、警護をしてもらっていたこともあるだけに、あかねも頼久が人とは比べ物にならないほどの体力の持ち主であることはよーく知っている。
それでも、心配になるのは目の前に座っておいしそうに料理を食べてくれるこの人が、心から大切な人だからこそだ。
「お仕事、大変でしたね。」
「いえ、大きな問題もありませんでしたので、さほどのことでは。」
「でも、連続だったし。」
「それは確かに……はい。」
頼久の箸が止まり、その眉間に軽くシワが寄った。
これはやはり連続の仕事で疲れているのかとあかねが表情を曇らせたその時、頼久はあかねが思ってもいなかったことを口にした。
「仕事自体は問題ではないのですが…花が開いてしまっていましたので。」
「はい?花がお仕事の邪魔になったんですか?」
「いえ、神子殿はこの季節をとても楽しみにしておいでですので、花見ができぬ間に花が散ってしまうのではと心配でした。」
「そ、そんなこと!花なんて来年も見れるじゃないですか…。」
「今年の花は今年限り、ですので。それに、花見ができるかどうかはもちろん気になっておりましたが、それ以上に神子殿と長く離れていることも我が身には辛く…。」
「それは……私もです…。」
もじもじしながら顔を赤くしてうつむくあかねを見つめて頼久はやわらかな微笑を浮かべながら再び箸を動かし始めた。
あかねが同じ想いでいたと言ってくれる、そのことが嬉しくてしかたがない。
もちろん、あかねが自分を待つその想いよりも自分の方があかねに会いたいと思うその想いは強いと頼久自身は内心で胸を張っているのだが…
「花が残っているうちに仕事を終えることができたので安堵致しました。」
「おかげで散り際の綺麗なところを一緒に眺められましたね。」
「はい。神子殿の手料理もこうして頂くことができました。望外の幸福です。」
「それは大げさですから!」
今度は首まで赤くなりながらわたわたと手を振るあかねも愛らしくて、頼久の顔からは笑みが絶えない。
そんな頼久に気付いたあかねは、赤い顔はそのままにやはり幸せそうに微笑むと、すぐに手で目をこすり始めた。
「神子殿?どうかなさいましたか?」
「いえ、ちょっと目が……。」
「埃でも入りましたか?」
「違うんです。ちょっと寝不足で…。」
「それはいけません!中でお休みに…。」
「なりません!せっかくお花見できるんですから、目いっぱい楽しんでから寝ます。」
赤くなりかけた目でキリリと睨まれて、頼久は小さく溜め息を吐いた。
あかねの言うことはもっともで、この花見を誰よりも楽しみにしていたのはおそらくあかねなのだ。
しかも青空の下、美しく散る花を見ずに寝るなどという選択肢があかねにあろうはずもない。
一度こうと決めたら愛らしい外見とは裏腹に決して決意を曲げないあかねを今すぐ寝かせるということは不可能だとすぐに結論にたどり着いて、頼久は根本的な問題に気付いた。
頼久は連続で仕事をこなしていたから寝不足になるのはとうぜんだが、何故あかねが自分の屋敷にこもりきりだったはずなのに寝不足になっているのか?
自分の留守中に何か不都合があったのかと気付き始めると不安材料は山のように引き出されそうで、そうなる前にと頼久はあかねを正面から見つめた。
そして、何事かときょとんとしているあかねに見惚れそうになる自分を心の中で叱咤して、箸をゆっくりと置くと、大きな体をあかねの方へ少しばかり寄せてじっとあかねの表情をうかがいながら口を開いた。
「何故、神子殿は寝不足になっておいでなのでしょうか?何か眠れぬようになるような不都合が…。」
「ないです!その、事件があったとか、病気になったとかそういうことはないです。」
「では何故。」
「頼久さんがいなくて寂しかったっていうのもちょっとはあるんですけど、それは昼間はみんなが遊びに来てくれたりしてけっこう大丈夫だったんです。」
「みんな、ですか…。」
「あ、はい、初日はイノリ君で、次の日が鷹通さん、永泉さんと泰明さんも来てくれたりしてけっこう賑やかだったんですよ。」
「それだけ、ですか?」
「はい?」
「その…友雅殿は…。」
「ああ、そういえば友雅さんは何か忙しかったみたいで、お手紙はもらいましたけどここへは来てないです。」
頼久は心の中で安堵のため息をつきながら、脳裏に主筋の少女の姿を思い浮かべていた。
年齢よりもずっとしっかりしているその少女、藤姫が気をきかせたことは間違いない。
元八葉の面々にあかねが寂しがらないようにと文を回して派遣したのだろう。
そして友雅には一人では訪ねないように釘を刺したに違いない。
それもあかねと頼久を気遣ってのことだ。
相変わらずの藤姫の気遣いに頼久は心の底から感謝した。
「昼間賑やかだったのなら夜はぐっすり眠れたのではございませんか?」
「それが、その…夜桜も綺麗だったりして、それを眺めてたら、頼久さんが帰ってきたら何を食べながらお花見しようかなとか色々考え出して、そうなるととまらなくなって、でも頼久さんがいないと寂しかったり色々で……。」
恥ずかしそうに苦笑しながらあかねはそう言ってまた目をこすった。
これはどうやらかなり眠いらしいと、周囲からは常に朴念仁と呼ばれている頼久にもはっきりとわかったが、それでも打つ手はない。
なにしろあかね本人がここで花見を続けると宣言しているのだ。
これはどうしたものかと頼久が考え込み始めるのと同時に、あかねはうっすら涙に潤んだ目を庭へ向けた。
折よく緩やかな風が吹いて薄紅の花弁が辺り一面に舞う。
視界が狭くなるほどの花の舞にあかねの目が遠くなった。
吹雪のように舞う花びらの向こうに何か違うものを見ているような、そんな目だ。
あかねの見ているそこは頼久の知らない桃源郷のような気がして、頼久ははっと目を見開いた。
あかねが花の向こうに見ているものは生まれ育った故郷なのではないだろうか?
龍神に愛でられてやってきたこの清らかな神子が望みさえすれば、この花は清らかな神子を二度と帰らぬはずの故郷へと帰してしまうのではないか?
そんな幻にとらわれそうになって、頼久は大きく一つ深呼吸をした。
あかねが元いた世界に帰ってしまうのではないか?
そんなことを考えていたともし口に出して言ったなら、あかねがムキになって否定した上、まだ信用してくれていないのかと拗ねられることは間違いない。
だから、微かにくゆる不安を口には出さず、頼久は代わりに手を伸ばした。
そっと手を伸ばしただけで届く場所にある小さな体は頼久の誘うまま、ことりと広い胸へと倒れ込んできた。
「頼久さん?お料理…。」
「今はこのまま…。」
「もしかしてお昼寝しろって言ってます?」
「いえ、ここ数日離れておりましたので、私がこうしていたいのです。」
それは本音のうちの半分だから嘘をついていることにはならない。
あかねに眠ってほしいというのも本心なら、あかねを抱きしめていたいというのも頼久のまぎれもない本心だ。
「頼久さんがこうしていて楽しいならいいですけど…。」
「何よりの幸福です。」
「そ、それは言い過ぎ……でも、私もとっても幸せです。」
あかねはその顔に幸せそうな笑みを浮かべて目を閉じると、そのまま頼久の胸に頬を寄せた。
聞こえる鼓動は穏やかで、広い胸はなんとも居心地がいい。
伝わる体温に安心して、あかねはあっという間に寝息をたて始めた。
「神子殿?」
そっと頼久が呼びかけてみてもあかねの目はもう開かない。
ただ規則正しい呼吸だけがあかねが今、なんの心配もなく幸せに眠っていることを頼久に知らせた。
小さなあかねの体をそっと抱きかかえ直して頼久が庭へと視線を移せば、そこには桜の花が始終待っていて、こここそが自分にとっては桃源郷と思われた。
風に乗ってあかねの髪に舞い落ちた花びらをそっと取り除いて、起こさないようにそっと抱きしめて、頼久は今の幸せに思いを馳せた。
こうして手をのばせばすぐに抱きしめることができて、それを幸せだと言ってもらえる、そのことのなんと幸せなことか。
どれくらいあかねが眠っているかはわからないが、きっと目を覚ましたらどうして起こしてくれなかったと怒られるに違いない。
そう予想することができても頼久にあかねを起こすつもりは毛頭なかった。
もしあかねの機嫌をたいそう損ねてしまったら、その時は月の下の夜桜を楽しもうと誘うとしよう。
昼間眠っていたのなら、夜は長く起きていられるはずだからと。
この提案を腕の中の大切な人が笑顔で承諾してくれると頼久には確信できた。
だから、今はただ、離れていた時間を取り戻すように、その間に空いていた二人の距離を埋めてしまうように、ただ優しくあかねを抱きしめ続けた。
管理人のひとりごと
久々にね、管理人が眠かったんです(ノД`)
ということであかねちゃんに花の下で頼久さんに抱かれて幸せにお昼寝してもらいました。
管理人は今年、ものすごく綺麗な花の散り際を見たわけで、ここで昼寝したい!と思いましたが、もちろんできるわけもなく…
だって、花見客満載だもの(^^;
それ以上に、この花の下で死にたい!とまで思いましたが、友人達にまだ早いから!と怒られました(’’)
綺麗な散り際の桜って何もかもを満足させてくれる、そんな気さえしてしまう、桜好きな管理人です!
ブラウザを閉じてお戻りください