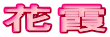
季節が巡るのは本当に早い。
あかねは最近そう思うことが多い。
向こうにいた頃と違って行事が多かったり、大切な人の身を心配したりと色々忙しくしているうちに時が経っているせいかも知れないけれど、それにしてもあまりにも早く季節は巡って、今年もまた桜が咲き始めた。
花が咲けば花見がしたいと思うのはまだうら若きあかねにはしかたのないことで、妻の闊達さを知っている頼久はそんなあかねに毎年花見の宴を催すことを許してくれている。
だから今年もとあかねは張り切ってお弁当の中身を考えたり、琴の練習をしたりと張り切っていた。
夕暮れ時ともなるとまだ少し寒くなるけれど、そんなことにめげるあかねではない。
紅の陽に照らされた庭の望める御簾の内で、あかねは黙々と琴の練習に余念がなかった。
友雅という優秀な師のおかげもあってあかねの琴の上達は早くて、少なくても文字を書くよりはまともにできるようになっている。
花の宴は最近忙しくなってなかなか会えない元八葉の面々に会うことのできる貴重な機会だから、この機に琴の腕前を披露しようとあかねの練習にも熱が入っていた。
「ずいぶんと熱心に練習しておいでなのですね。」
「頼久さん!」
御簾の向こうから声が聞こえて、あかねは慌てて琴から手を離すと御簾の向こうへと顔を出した。
するとそこには穏やかに微笑む頼久が立っていた。
「お帰りなさい、今日は早かったんですね。」
頼久は夜まで土御門邸で仕事だと思っていただけに、思いがけない夫の帰宅が嬉しくて思わずあかねの顔に笑みが浮かぶ。
「はい、明日と明後日は休みも頂きました。」
「よかったぁ。」
「それにしても熱心に練習しておいでですが…。」
「もちろんです。だって、久しぶりにみんなに会うし、また永泉さんとか友雅さんとかが一緒に弾いてくれるなんてことになったら大変だし。ちゃんと練習してみんなに上達したところを聞いてほしいし。」
「神子殿はもう十分お上手です。」
「そんなことないですよ、まだ全然。どうやったら友雅さんみたく弾けるようになるのか不思議で不思議で…。」
「友雅殿は……風流人として名の知られているお方ですので…。」
「まぁ、そうなんですけどねぇ、でも、私ももうちょっと上手になりたいなって思っちゃって…。」
そういいながら御簾をくぐってするすると縁に出てきたあかねは、庭がよく見える辺りにちょこんと座って苦笑した。
楽の音についてはよくわからない頼久でもあかねの琴の腕前が上達したことはよくわかる。
それほどあかねはよく琴を弾きこなすようになっているのだが、どうやら本人はまだ満足がいかないらしい。
「綺麗ですねぇ。」
うっとりとあかねがそういいながら見つめたのは庭にある一本の桜の木だ。
それは昨年、あかねがたいそう桜好きだからと藤姫から贈られた桜の木で、数日前から今が盛りとばかりに咲き誇っている。
藤姫のところには友雅から同じような桜の木が贈られたとかで、先日、庭までおそろいになったと二人で喜んだものだった。
頼久はうっとりと桜を見上げるあかねの隣に座って、その顔に穏やかな笑みを浮かべた。
「自分の家の庭に桜の木があるなんて、なんだか夢みたいです。しかもこんなに綺麗に咲いて。」
「藤姫様も本日は桜ばかり見ておいでであったと友雅殿がおっしゃっていました。」
「あれ、友雅さん、今日、藤姫のところにいたんだ?」
「はい、そのようです。花の宴のことでなにやらご相談があったとか…。」
「へー、なんだろう。今年は藤姫も連れて行こうとか、そういうことかな?」
「そこまでは…。」
いったい二人で何を画策しているのだろうとあかねが首をかしげて考え込み始めると、頼久はそんなあかねをじっと静かに見守った。
ああでもないこうでもないと小首を傾げて悩んでいるあかねはまだまだ幼げが残っていて愛らしい。
そんなあかねを黙って見ていることなどできない頼久は、すっと妻の細い肩を抱き寄せた。
「よ、頼久さん!」
「はい。」
「はい、じゃなくて、まだ明るいし、ここは外ですって…。」
「はい。」
あかねが何を言っても頭上から降ってくるのは幸せそうな「はい」ばかりだ。
視線を上げてみればそこにはやっぱり幸せそうに微笑んでいる端整な顔があって、あかねはそれだけで顔を赤くして何も言えなくなってしまう。
昔はいつも厳しくてつらそうな顔ばかりしていた人だから、そんな顔ばかりを見ていた日々があったから、あかねは幸せそうにしている頼久にはどうしても何も言えなくなってしまうのだ。
「陽が、落ちますね。」
頭上から聞こえたこの声で、あかねははっと視線を上げた。
するといつの間にか紅に染まっていた空はだんだんと藍色を帯びていて、桜の花も夜の帳に溶け込もうとしていた。
「あっという間ですね。」
「はい、まだ夏は遠い気が致します。」
「月が出たら、きっと夜桜が綺麗ですね。」
「今日は月が出るまでには少し間がありますから、ゆっくり待つと致しましょう。」
「そうですね。」
こんなふうにゆったりと過ごせることも嬉しくて、あかねは頼久に笑顔を見せた。
するとゆっくり頼久の端整な顔が降りてきて、あかねは静かに目を閉じた。
頼久はいつものようにぱちりと目を開けて、それからすぐに自分がかき抱いている華奢なぬくもりを確認した。
頼久の胸にすり寄って眠っているあかねはまだ心地良さげな寝息をたてていて、その顔を覗いてみればとても幸せそうだ。
頼久はその口元をほころばせてしばらく妻の寝顔を見つめてから、小さな体をぎゅっと抱きしめた。
毎朝のことだというのに、眠りから覚めて一番に目に入るこの小さな妻を抱きしめるたびに愛しさは増して、思わずそのままうっとりしてしまうこともしばしばだ。
だが、今日ばかりはそんなふうにはしていられない。
何しろ、今日はあかねが主催する花の宴の当日。
あかねをいつもよりも早く起こさなければならない。
朝から色々用意したいことがあるのだと、あかねは昨日眠る前にそう頼久に告げていたのだ。
だから、頼久はギュッときつく抱きしめてあかねのぬくもりを楽しんでから、半身を起こした。
それからあかねの細い肩を優しくゆする。
「神子殿、朝です。」
「うーん…。」
頼久が優しく揺り起こしても、たいていあかねは一度では目覚めない。
幸せそうな顔ですりすりと頼久にすり寄ったあかねは、すぐに寝息をたて始める。
何もなければ頼久もこのまま愛しい妻を抱きしめて眠らせてやるところなのだが、今日はそうはいかない。
頼久は意を決して再びあかねの肩をゆすった。
「神子殿、宴の準備があるのではありませんでしたか?起きてください。」
「頼久、さん?」
「はい、おはようございます。」
「もうちょっとだけ…。」
昨夜、夜遅くまで夜桜を楽しんだせいか、あかねは一度目を覚ましたのにまた眠り込もうとしているようだ。
頼久は苦笑しながらあかねの耳元に唇を寄せた。
「どうしても起きて頂けないのなら、少々無体をはたらくことになりますが…。」
低い声で頼久がそう囁くとあかねはぱちりと目を開けて、微笑む頼久を見上げた。
「よ、よよよ、頼久さんっ!」
「はい。」
叫びながら半身をがばっと起こしたあかねは顔を真っ赤にしてかぶっていた袿を抱きしめた。
「あ、朝から何言ってるんですかっ!」
「いえ、こういえば神子殿が起きてくださるかと。」
「……。」
ニコニコと機嫌よさそうに微笑む夫を上目遣いに睨みながら、あかねは真っ赤な顔で何も言えなくなってしまった。
確かに起きなかった自分が悪いのだし、頼久の思惑通り自分は起きてしまったわけで…
「頼久さんって…。」
「はい?」
「昔はあんなに神子殿の御心のままにばっかり言ってたのに…最近はそうやって私をからかったりとか、ひどいです…。」
「お嫌でしたら、何事も神子殿の…。」
「戻さなくってもいいですっ!」
慌ててそういうあかねに頼久はニコリと微笑んだ。
またやられた。
あかねがそう心の中でつぶやいた刹那、頼久がすっと立ち上がると几帳の向こうへとその身を滑らせた。
何事かとあかねが小首を傾げる。
几帳の向こうでは何か小さな声で会話が交わされて、少したってから頼久が戻ってきた。
「頼久さん?何かあったんですか?」
「はぁ…。」
さっきまで幸せそうに微笑んでいた頼久の眉間にはシワが寄っていて、あかねはそんな頼久の様子に驚いてすぐに駆け寄った。
すると、頼久は手にしていた紙をあかねの方へと差し出した。
「これは…文?」
「はい。」
頼久が手にしていたのは綺麗な紙に文字が書かれている文で、紙の上にはおそらくこの世界では上手であろう達筆な文字が連なっている。
あかねは「うーん」と唸り声をあげながらその文字と格闘して、それからこれは無理だと悟って頼久の顔をうかがった。
「それは友雅殿からの文です。」
「ああ、それでこんな凄い字なんだ…それで、なんて書いてあるんですか?」
「それが…。」
「何が悪い知らせですか?友雅さん病気とかじゃないですよね?」
「友雅殿が病というわけではないのですが…。」
「じゃぁ、なんて書いてあったんですか?」
「本日の宴には八葉全員、出席できぬと…。」
「えーーーーーーっ!」
お行儀が悪いとかはしたないとかそんなことはすっかり失念して、あかねは大声をあげていた。
どんなに忙しくてもこの日ばかりはいつもちゃんと出席してくれていた仲間達が、今回はそろいもそろって全員欠席とは…
「病ということではなく、皆、仕事の都合がそれぞれつかなかったようです。」
「そうなんだ……みんな最近凄く忙しそうだもんなぁ…。」
「神子殿…。」
がっくりとうなだれるあかねを見るのは頼久もつらい。
なんとかあかねを元気付けようと思ってみても、言葉の苦手な自分にはどんな言葉で妻を慰めていいのかもわからない。
頼久は更に深く眉間にシワを刻んで考え込んでしまった。
仲間達の仕事がどんどん忙しくなっていることは承知しているが、今からでも自分が訪ねて行って説得することはできないだろうか?
そう思いついた頼久は、さっと立ち上がると無駄のない流れるような所作でさっさと着替えを始めた。
「よ、頼久さん?」
「どうしても都合がつかぬものか、皆の元を訪ねて…。」
「い、いいですよ、そこまでしなくても、みんな忙しいんだろうし…。」
「いえ、年に一度、この日だけはと神子殿が楽しみにしていらっしゃるのですから。」
そう言うが早いか頼久は身支度を整えて外へと飛び出した。
それこそまだ寝巻き姿のあかねが止める間もない。
局から駆け出した頼久はそのまま廊下を駆け抜け、表へと飛び出した。
そして…
「まったく…。」
門を出てすぐにいきなり聞こえたその声に、頼久の足がぴたりと止まる。
声のした方を振り返ってみれば、そこには門柱にもたれて扇をひらつかせている友雅の姿があった。
頼久の目が鋭さを宿してその妖艶な姿を射抜く。
「友雅殿、本日は仕事で身動きが取れぬということではございませんでしたか?」
剣呑な眼差しでそう言う頼久に、友雅はあからさまな溜め息をついて見せた。
「大事な神子殿が催す宴に我ら八葉が全員欠席などということがあると思うのかい?」
「そのように文で知らせてくださったのは友雅殿ではありませんか。」
「だから、皆で結託しているのだよ。」
「は?」
ここで友雅は再び深い溜め息をつくと、パチリと音をたてて扇を閉じた。
「藤姫が言うには頼久は神子殿の言うことを全てハイハイと聞くばかりで、なかなか二人きりで神子殿を喜ばせるようなことをしないというではないか。」
「そ、それは…。」
「そこで我ら一同、今年ばかりは心優しい神子殿に夫と二人きり、幸せな花の宴を過ごして頂こうということになったのだよ。」
「……。」
それはそれ、毎日のように二人で庭の桜を眺めてはいるのだが、では、それであかねが幸せなのかと問われればそうだと断言することが頼久にはできない。
もしかするとあかねはもっと二人でと思っているのかもしれないから。
仕事で一人寂しい思いをさせていることも脳裏をかすめて、頼久はすっかり黙り込んでしまった。
「神子殿はなんといっても頼久の側にいたいがためにこの京へ残ったのだからね、もう少し神子殿のために頼久が心を砕くことだ。」
「それは……。」
「ん?」
なにやら不満げな様子を残す頼久に友雅が訝しげな表情を見せた。
頼久にしては歯切れが悪い。
「無骨者のこの身が至らぬのは重々承知しております。ですが、神子殿が八葉を仲間と呼び、いつも息災かと心を砕いておられるのも事実です。」
「ふむ、まぁ、そうかもしれないね。」
「ですので、本日は私が神子殿に尽くしたく思いますが、できましたら、明日にでも時は短くてかまいませんので、皆で集まれないものでしょうか?神子殿は二月も前から熱心に琴の練習をしておいででした。せめて、その琴の音だけでも…。」
そう言って苦しげにうつむく頼久を見て、友雅はニコリと微笑んだ。
「まぁ、そうだね、神子殿の琴の音には私も興味があるし、午後にでも皆で押しかけてみようか。」
「お願い致します!」
友雅の言葉に頼久は深々と頭を下げた。
これできっとあかねの顔には笑顔が戻るだろうと思えば見える世界の色まで変わった気がする。
「その代わり、頼久は今日一日神子殿のために尽くす、それが条件だ。」
「それはもちろん。」
「ではそのように藤姫に報告しよう。」
友雅はそういうと軽く手を振って歩み去った。
その後ろ姿を見送って、小さく一つ溜め息をついた頼久は決意も新たに屋敷の中へと踏み出した。
そう、友雅と約束したのだ。
今日一日は何があってもあかねの側で、あかねの幸せのためだけに過ごす。
その想いを胸に屋敷へ戻った頼久は、縁に出て心配そうな顔で迎えてくれてたあかねを有無を言わさず抱きしめると、そのまま深く口づけてから膝の上に乗せて腕の中に閉じ込めてしまった。
「よ、頼久さん?どうかしたんですか?何かありました?」
頼久の腕の中であかねは顔を赤くしたまま、それでも何が起こったのかわからない様子でキョトンとしている。
「八葉の皆は明日の午後であれば集まることができるそうですのでご安心を。」
「あ、そうなんだ、今日が都合悪かったんだね。」
「ですので、今日一日はこの頼久が誠心誠意、お仕えさせて頂きます。」
「はい?仕えるってそんな…。」
「いえ、庭の桜でも墨染めの桜でも、神子殿の見たいとおっしゃる桜を見せて差し上げます。どこへなりとこの頼久がお供致します。今日ばかりは神子殿のお側にて何事も神子殿のお望みのままに。」
耳元でそう囁かれてあかねは顔を真っ赤にしてうつむいてしまった。
この夫が恥ずかしくなるようなことを言うのはいつものことでだいぶ慣れたつもりだったけれど、こんなふうに耳元で囁かれることはあまりなくて…
あかねは赤い顔のまま上目遣いに夫の顔を盗み見た。
すると、自分を見つめる真剣な眼差しとぶつかってしまって、今度は視線を外せない。
「何かお望みのことがありましたか?」
「へ?えっと……その……じゃぁ…て、天気がいいのでこのままここで花を見ながら日向ぼっこ、とか?」
「御意。」
低い声でそれだけ言った頼久は幸せそうに微笑んであかねをギュッと抱きしめた。
腕の中には顔を赤くしながらも幸せそうにしている妻の小さな姿。
これで少しは友雅との約束を果たすことができただろうかと心の中で思いをめぐらせながら、頼久はこんな時間を与えてくれた中間達に感謝せずにはいられなかった。
管理人のひとりごと
毎年毎年仲間とじゃ頼久さんがかわいそうなので今年は二人きりのお花見です♪
まぁ、翌日にはみんなおしかけてきますが(’’)
藤姫は二人の仲がいいことは知っていますが、それでも頼久じゃきっと神子様を満足させられない!といつも心配しています(w
何しろあの朴念仁っぷりですから…
でも、まぁ、夫婦仲なんてもんは周囲がとやかく言うようなことではないわけで、この二人はたいていかってに仲良くします(’’)
うちのあかねちゃんは仲間も大切にし続けているので頼久さんがあかねちゃんをゲットするのが大変です。
ので、今回は仲間達の方が譲りましたというお話(^^)
プラウザを閉じてお戻りください