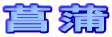
女性ならばすべらかく花が好きだということはこちらの世界では常識だ。
だから頼久は珍しく自分からあかねに外へ出ることを提案した。
桜の季節はよかった。
どこへ行っても桜が美しくて、あかねの機嫌もよかったから。
もちろん、頼久と一緒にいる間、あかねが不機嫌だということはそうそうないのだが、それでも桜が散ってしまうとあかねのあの花を見た時の華やかな笑顔が恋しくなった。
頼久が何か気の利いた言葉の一つも贈ればあかねはそれはもう嬉しそうに微笑んでくれるのだろうが、そういった芸当ができるはずもない自分であることは頼久自身が誰よりもよく知っている。
そうなると、あかねの笑顔を見るにはもう花を贈るしかないと頼久は決断した。
ところが、毎日毎日花束を贈るのもこれは天真に言われなくてもちょっとおかしな話だ。
それではどうすればあかねが喜ぶように自然に花を贈ることができるか。
頼久は一日いっぱい仕事そっちのけで考えて、そして思いついたことをあかねに提案してみた。
今が盛りの菖蒲を見に行きませんか?と。
するとあかねは頼久が見たかったあの輝くような笑顔を見せて嬉しそうに承諾してくれた。
そして今、頼久は少し離れたところから咲き誇る無数の菖蒲の中に立つあかねを見つめている。
今日は朝からあかねがあの輝くばかりの笑顔を浮かべたままだ。
頼久にしてみればただあかねを喜ばせたくて、その美しい笑顔を見たくてここへ連れて来たのだが、あかねは頼久が予想した以上にはしゃいでいて楽しそうだった。
そして頼久には予想外の贈り物もついてきた。
ただ華やかなあかねの笑顔が見れればよかったのだが、菖蒲の中に立つあかねは本当に清らかで美しい。
それを静かに独り占めにする時間を与えられたのだ。
頼久にとってこれほど幸福な時間はない。
「頼久さんもこっちに来てください。一緒に写真とってもらいましょう。」
「いえ、私はここでみ…あかねの姿を見ている方が…。」
「もう、またそんなこと言って。」
あかねは少しだけむくれたような顔をして見せてからすたすたと頼久の方へ歩み寄ると、その腕をとって花の中へと歩き出した。
「せっかく頼久さんが昼間の花畑に誘ってくれて嬉しかったのに、ずっと離れてたんじゃつまらないです。」
「ですが、花の中に立つみ…あかねはとても美しく、いつまででも眺めていたいのです。」
「ま、また頼久さんはそういう恥ずかしいことを…。」
「恥ずかしいでしょうか…。」
「私は恥ずかしいです!とにかく!写真、絶対撮ってもらいますから!」
あかねはさっさと写真をとってくれそうな人を探し出してくると、頼久の腕を抱いてにっこり微笑んだ。
菖蒲の中に立つあかねをただ一人で眺めていた頼久は、あかねと並んで写真におさまった。
管理人のひとりごと
管理人が菖蒲を見に行った際に妄想した風景をそのまま(’’)
花の中にたたずむあかねちゃんを見たら頼久さんもいちころです(マテ
花の中にたたずむ頼久さんに管理人はいちころです(’’)(オイ
プラウザを閉じてお戻りください