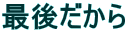
エアコンのきいた部屋の中で頼久は本を開いていた。
普段なら書斎で目を通す仕事の資料だが、今はリビングのソファにゆったりと座っている。
何故かというと、ステレオセットがリビングにしかないからで、そのステレオからはあかねが先日購入してきてくれたCDの美しいチェロの音色が流れていた。
そう、頼久はどうしてもこの音楽を聞きながら仕事をしたかったのだ。
というのも、最近のあかねは友人達との予定が入ったり、宿題に追われたり、家族旅行が入ったりで頼久のもとを訪れていないからだ。
会えないとなると恋しくなるのが人情というもので、頼久としては少しでもあかねを想っていたくて、こうして音楽を聞きながらローズティ片手に仕事をしているというわけだった。
そうしていれば、ほんの少しだけあかねの存在を感じていられるような気がするのだ。
それでもやはり会えない寂しさはつのって…
頼久は1時間ほどで資料に目を通すのをあきらめた。
脳裏にあかねの顔がちらついて集中できないからだ。
紅茶を一口飲んで、己がどれほどあかねを想っているかを再認識して苦笑する。
そしてとうとう玄関の扉の向こうにあかねの気配を感じたような気がして、苦笑しながらも頼久はゆっくりと玄関へ向かった。
とうとう幻の気配を感じたかと思った頼久だったが、頼久が開ける前に扉の鍵はカチャリと音をたて、次の瞬間、扉を開けてあかねが姿を現した。
「神子殿?」
「あ、頼久さん、いたんですね。留守かと思って開けちゃいました。」
そう言ってにっこり微笑むあかね。
頼久は目の前にいるあかねの姿に驚いて大きく目を見開いている。
「頼久、さん?」
「宿題が終わらずにお忙しいということではありませんでしたか?」
「あ、はい、えっと…その…今日で夏休み最後なんです。」
「はぁ。」
「宿題は残ってるんですけど…国語と古典だけで、他は昨日頑張って終わらせたんです。だから、その…せっかく夏休み最後の日だから頼久さんと一緒にいたいし……教えて、もらえませんか?」
赤い顔をして上目遣いにそんなお願いをされて頼久に断れるはずもない。
会いたくてしかたがなかった人に会えて、しかもこんなに可愛らしいお願いまでされて、頼久は思わず幸せそうに微笑みながらあかねを抱きしめていた。
「あの…。」
「はい?」
「お昼ご飯はちゃんと作りますから。」
そんなことを言うあかねが愛らしくて、頼久はぎゅっとあかねを抱く腕に力をこめた。
「御意。」
玄関で抱き合うことしばし、あかねが宿題を始められたのはそれから数分後のことだった。
管理人のひとりごと
せっかくの夏休みも宿題に追われるのはお約束(笑)
でも、頼久さんに会うためならあかねちゃんは頑張るのです(w
こうやってどうしても頑張らないといけない何かに追い詰められると成績って上がりそうだ(’’)
でもお昼ご飯は手作りのようです(笑)
プラウザを閉じてお戻りください