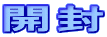
「すぐお茶いれますから。」
あかねはいつものように頼久の家にやってきて、ソファの上にバックを置くとすぐにキッチンへ立った。
出迎えてくれた頼久は「はい」とだけ嬉しそうに返事をして、いつものソファのいつもの席に座る。
そこからはキッチンに立って作業をしているあかねの後姿がよく見えるからだ。
あかねは手早くお湯をわかしながらティーポッとの準備を進めていた。
いつものローズティをポットに入れるまではいつもの動作。
ここからあかねはいつもとは違った行動に出た。
バックとは別にキッチンへ持ち込んだ手荷物の中から次々と何かを取り出したのだ。
あかねが持ち込んだのは自宅で焼いてきた手作りクッキーとジャム。
少し大きめの皿を取り出してその上にクッキーを並べたあかねは次にジャムの瓶と格闘を始めた。
まだ一度も開けたことのない真新しい瓶の蓋はなかなか開いてくれなくて、あかねの小さな手では蓋は大きすぎて…
うんうん唸りながら力いっぱいガラス瓶と格闘していたあかねはあまりに集中していたせいで、背後から近づく気配に気付かなかった。
気付いた時にはもう後ろから抱きすくめられるみたいに伸ばされた手があかねの手からガラス瓶を優しく取り上げていた。
「頼久さん?」
あかねが不思議に思っている間に瓶の蓋はあっさり頼久の大きな手によって開けられた。
「どうぞ。」
「あ、有難うございます。やっぱり男の人だとあっさり開くんですねぇ。」
「はい、簡単に開きますから、次からはお任せ下さい。それにしてもおいしそうな色をしていますね。」
瓶をあかねの手に戻しながら頼久はあかねの肩越しに瓶を中身を見つめた。
必然、頼久の顔はあかねの頬の辺りにくることになって、あかねが顔色を桜色に染めた。
「あ、あのぉ、近所においしい手作りジャムのお店ができて…クッキーにつけるとおいしいかなって…。」
「そのクッキーは神子殿が?」
「はい…その…詩紋君みたいに上手にはできなかったんですけど…。」
「いえ、とてもおいしそうです。」
あかねの手作りクッキーはどれも可愛らしい形をしていて、頼久は何より手作りであることが嬉しくてそのまま背後からあかねを抱きしめてしまった。
開封されたジャムの瓶を持っていたあかねは「きゃっ」と小さく悲鳴をあげてかおを真っ赤にしてうつむく。
「よ、頼久さん、お茶にしたいんですけど…。」
「今少し、このまま。」
艶のある低い声でそう囁かれてしまってはもうあかねには抵抗することなどできなくて…
二人は甘い香りのするキッチンでしばらくそのままたたずんでいた。
管理人のひとりごと
ジャムの瓶、これ、空かなくてイラっとすることがままあります、管理人…
そういう時、頼久さんみたいな人がパシッと開けてくれるといいなぁと…
つまり管理人の憧れ…
頼久さんなら空けられない瓶なさそうだし(’’)
後ろから腕を回してたって余裕なのです!
プラウザを閉じてお戻りください