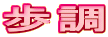
あかねは頼久と二人で歩いている。
市が立つというのでダイエットがてら散歩にきたのだが…
今、あかねはおそらく周囲の人から見れば一人で歩いているように見えるだろう。
何故かといえばそれは、頼久があかねの数歩後ろを歩いているからだ。
屋敷を出た直後はよかった。
ちゃんと隣を歩いてくれていたから、そっと隣を見上げると自分を見つめている優しい紫紺の瞳を容易に見ることができたのだ。
ところが、人通りが多くなるにつれて頼久は少しずつあかねの後ろへ下がり、市に到着した今はというともうすっかり従者の距離を保ってかなり後方にいるのだ。
追いついてほしくて歩く速度を落とせば頼久もそれに合わせてしまうから二人の距離はどうやってもちっとも縮まらない。
賑わう市の中であかねは一人、とても孤独で寂しい気がして。
何を見るどころでもなくて、まっすぐ市を抜けるとあまり人気のないところまで来てはたと立ち止まり、くるりと後ろを振り返った。
そこにはキョトンとしている頼久の姿が。
「頼久さん。」
「はい、なんでしょうか?」
「隣を歩いてほしいんですけど?」
「いえ、ですが……。」
「頼久さんっ!私は頼久さんの許婚になったはずなんですけど?」
「は、はぁ、はい、おっしゃる通りです…。」
どうやら怒っているらしいあかねとは逆で頼久はうっすらと頬を紅に染めている。
そんな頼久を見ても今日のあかねは容赦しなかった。
「来年の春には私、頼久さんの妻になるつもりでいるんですけど?」
「は、はい、おっしゃる通りです。」
「頼久さんは妻と歩く時も隣を歩かないで従者みたいに後ろをついてくるつもりなんですか?」
「それはその…人目もございますので…。」
更に頬を赤く染め上げて神子殿が自分の妻とご自身の口からおっしゃって下さった幸せにひたっていた頼久は、次にあかねの口から飛び出した言葉で顔色を一気に青くした。
「私が子供だからですか?だから頼久さんは私と並んで歩いているのを誰かに見られるのが恥ずかしいんですか?」
「は?」
どういう意味だ?と頭の中で考えて、頼久の顔色は更にどんどん青白さを増す。
あかねはどうやら頼久が自分のことを恥だと思っている、そう言っているようなのだ。
「め、滅相もありません!そのように思ったことなど一度もございませんっ!」
「だったら…並んで一緒に歩いて下さい…私、いつだってなるべく頼久さんの近くにいたいし、おしゃべりだってしたいです…。」
そういうあかねの目にはうっすら涙まで浮かんでいて、頼久の顔色はまるで病人のように青白くなった。
目の前で泣きそうになっているこの世で最も大切な人にどんな言葉をかけてよいかわからず、パニックに陥る頼久。
「どうしてもダメですか?」
「いえ、ダメでは…。」
「じゃぁ、お願いですから隣を歩いて下さい。」
涙に濡れた必死な瞳を見てしまってはもう頼久には抗うことなどできない。
愛しい人に歩み寄った頼久はそのまま細い体を抱きしめた。
「御意。」
やっと頼久の口をついて出た言葉はそれだけ。
だが、強く抱きしめるその腕の力で、あかねには頼久の想いが暖かく静かに伝わった。
管理人のひとりごと
身分があるとね、並んで歩くのも大変なんです、人前では(’’)
まだ婚約中だしね。
頼久さんのことですから、結婚してもあまり変わらない気もしますが…
でもやっぱりあかねちゃんにかわいくお願いされたらもちろん逆らえないのです♪
プラウザを閉じてお戻りください