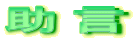
あかねは蘭、詩紋と一緒に喫茶店でケーキセットがやってくるのを待っていた。
そこは蘭が見つけた新しい店で、とてもおいしいと騒いだので、詩紋がケーキ作りの参考にしたいと言い出して、甘いものはパスだと言い張った天真を除いた三人で食べにやってきたのだ。
穏やかな夏休みの午後、三人は冷房のきいた店内で店の内装を眺めたりしながらくつろいでいた。
「感じのいいお店だね。」
「落ち着いてるよね。ボクでも入りやすい感じ。」
そんなことを言い合って詩紋とあかねが微笑む中、蘭だけはじーっとあかねを見つめている。
「蘭?どうかした?」
「楽しそうだなぁと思って。」
「楽しいよ?仲のいい友達とお茶を飲んでたら普通楽しくない?」
「そういうことじゃなくって。気にならないの?」
「何が?」
あかねは蘭が何を言いたいのか全くわからずにきょとんとしている。
一方詩紋は、蘭が何を言いたいのかはわからなくても何かとてつもなくいやーな予感がして黙り込んでいた。
「ほら、いつもなら一緒に買い物しててもお茶飲んでても、ずーーーーっと頼久さんのことが気になってて心ここにあらずって感じじゃない?」
「そ、そんなことないよ…。」
「そんなことあるある。でも、今日は違うんだなぁと思って。ひょっとして頼久さん今日、家にいないの?」
「う、うん…。」
「やっぱり。」
してやったりという顔で蘭がうなずいたのにあかねが抗議しようとしたその時、三人分のケーキセットが運び込まれて会話が一時中断してしまった。
あかねはイチゴショート、蘭はフルーツタルト、詩紋はモンブランを前にとりあえずは目的のケーキを口に運ぶ。
『おいしぃ。』
三人は同時にそうつぶやいて幸せそうな笑みを浮かべた。
暑いからと頼んだアイスティもケーキの甘みを流すにはちょうどいい。
「甘いもの食べてる時って幸せだよねぇ。」
「そうだよね…って、ケーキで思い出した!」
「何?あかねちゃん。」
今度は蘭が小首をかしげる。
「この前ね、頼久さんがうちのお母さんに凄くおいしいって有名なお店のお菓子とか、綺麗な花束をお土産に持ってきたの。でも、頼久さんが自分でそんなの選んだとは思えないし……。」
そう言いながらあかねは蘭と詩紋の顔を上目遣いに覗き見た。
すると詩紋は困ったような苦笑を浮かべ、蘭は自慢げに胸をはって見せた。
「もーーっちろん、私と詩紋君とで頼久さんにちゃーんと教えてあげましたとも!どう?お母さん喜んでたでしょ?」
あかねは「はぁ」と深い溜め息をつくと二人をきりっとにらみつけた。
「お母さんは喜んでたけど、あんな頼久さん、らしくない!お母さんは機嫌よすぎて気持ち悪いし、二人ともあんまり頼久さんに変な入れ知恵しないで!」
「何言ってるの!小学生みたいなお付き合いを脱出するためにはまず親から篭絡しないと!」
「ら、蘭!小学生みたいじゃないし、脱出する気もないから!」
「小学生みたいじゃない、いつも二人きりで一つ屋根の下にいるのに映画鑑賞しておしゃべりして門限までに帰るだけって。」
「うっ…映画鑑賞だけじゃないもん!」
「ふ〜ん、じゃ、他に何してるの?」
ニヤニヤと笑う蘭にあかねは顔を真っ赤にしてうつむいた。
そして更に煽ろうとする蘭を深い溜め息をついた詩紋が止めた。
「蘭さん、やめた方がいいよ。どうせまた、ボク達がすごーくむなしくなるだけだから…。」
「……そ、そうだね…。」
詩紋のおかげで我に返った蘭はアイスティを飲んで溜め息をつく。
そしてあかねは不機嫌そうに二人を見つめる。
「なんでむなしくなるのよ、二人とも。」
『惚気を聞くことになるから。』
間髪いれずに帰ってきた答えにあかねは再び顔を赤くしてうつむくのだった。
管理人のひとりごと
えー、このエピソード、実は前段階、頼久さんがお菓子をあかねちゃんのお母さんに持ってきたって話が短編の方で出てきます。
この話だけでも違和感がないとは思いますが、一応、関係しているお話ちゃんとありますのでお楽しみに(^^)
頼久さんはそんな女性のお気に入りの店とか知ってるはずないので、絶対人に聞くと思います。
絶対天真君に聞いて蘭と詩紋にまわされると思います(笑)
だって、天真君も知ってるはずないから(爆)
プラウザを閉じてお戻りください