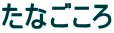
秋も深まり京を吹く風もさすがに冷たくなってきた。
それでももともと活発なあかねは黙って局にとどまってはいない。
大体は縁に出て、毎日訪ねてくる許婚と一日中といっていいほど長いこと話をしている。
今までは朴念仁だのなんだのと言われてきた頼久も、許婚のあかねの話を聞く時だけはとても楽しそうだった。
だが、さすがに秋も深くなると縁は冷える。
あかねが風邪をひかないようにと、縁に出るといってきかないあかねに頼久は厚着を懇願したくらいだ。
縁で話をするならば厚着だけは譲れないと珍しく頼久が断言して譲らなかった結果、あかねは着膨れた状態で縁に出ることになった。
「十二単ってどうしてあるのかわかった気がします、最近…。」
「はぁ…。」
「絶対防寒のためにあると思います、これ…。」
せっかく厚着をするのだからと女房達に手伝ってもらってあかねは十二単を着込んでいた。
前日は防寒のためだけにただ着膨れていたのだが、それだとより一層身動きはしづらいし見た目にも綺麗じゃなくて、どうせならと十二単を着ることにした。
これならすくなくても見た目だけは綺麗なはずだから。
あかねの大好きな人の前でおめかししていたいという乙女心は満たされたのだが、動きづらいことはこの上もなく、あかねは縁でうずくまったままため息をついた。
「あったかいのはあったかいんですけど…これじゃ何もできない…。」
そう言ってため息をつくあかねを困惑げな頼久が見守る。
頼久にしてみれば風邪さえひかないようにしてくれれば、あかねの手足となってどんなこともして差し上げるつもりなのだが、闊達なあかねがそういうことを嫌うことも知っていて…
「まだ雪も降ってないし、冬はこれからだっていうのに今からこんなんじゃ冬どうしよう…。」
あかねは欄干にもたれてため息をついた。
この方のもといた世界では冬は寒くはなかったのだろうか。
快適な世界だったと元の世界へ戻っていった頼久の真の友に聞いたことがある。
この世界へ残ったことで目の前の大切な人が悩んでいることが頼久にはつらくてならない。
だが、元の世界へ帰ればいいとはとても言えなくて、だからといって冬の寒さを相手に愛しい人を守る術などあるはずもなく、頼久はため息をつくあかねを前に考え込んでしまった。
「頼久、さん?」
愛しい人が自分の名を呼ぶ声で我に返った頼久は、ふとあかねの両手の指先が赤くなっていることに気付いた。
欄干に乗っているあかねの手はもともとが色白なのに加えて寒さで指先が赤くなってきて痛々しい。
頼久は思わず階を上ると、あかねの手を両手で包み込んでいた。
「ど、どうしたんですか?!」
急に顔を真っ赤にしながらそれでも手を自分の方へ引き戻すことはできなくて、あかねは身動きしづらい十二単も手伝って身動きさえできない。
一方の頼久はあかねの手をすっぽりと自分の両手で包みこんで黙っている。
しだいに冷たく凍えていたあかねの指先は頼久の手の温かさで温められて、恥ずかしさでただただ赤くなっていたあかねも時がたつにつれてその手の温かさにうっとりとし始めた。
「頼久さんの手って大きいですよねぇ。」
「そう、でしょうか…。」
「うん、大きくてあったかいです。」
そう言ってにっこり微笑むあかねの視線に出会って、頼久ははっとした。
元いた世界の全てを捨てても自分のもとへ残ってくれた愛しい許婚。
その誰よりも大切な人が今、温かいと言って微笑んでくれたことが頼久の胸を震わせた。
もといた世界を捨てさせてしまった自分にもできることがある。
こうして愛しい人を温めることくらいならできる。
頼久はふっと微笑を浮かべてあかねの後ろへ座ると、重たい十二単を着たその体をひょいと膝の上に抱きかかえてぎゅっと抱きしめた。
「よ、頼久さん?」
「どんなに厳しい冬がこようとも、寒い思いはさせませんので。」
「は、はい……。」
頭上から降る優しく低いその声に、あかねは顔を真っ赤にしてうつむく。
すっぽりと頼久の腕の中におさまって、後ろから回される頼久の大きな手で小さな両手を包み込まれて、あかねは今までにない幸せな暖かさに包まれていた。
寒い冬もいいかもしれない。
二人は同じ想いを抱いていた。
管理人のひとりごと
見てるこちは暑いよって話を書きたかったんです(爆)
冬寒くてもこれくらい暑ければ風邪ひきませんね、二人とも。
京は火桶しか熱源がありませんから、冬寒かったと思うんですよ。
でも、人肌あれば大丈夫♪
プラウザを閉じてお戻りください