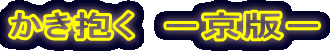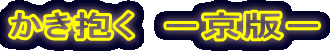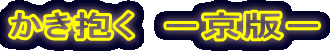
紙燭の灯りだけが頼りの暗い局の中。
頼久はその腕にしっかりとあかねの体を抱きしめていた。
寝る支度まではしたものの、どうしても眠る気にはなれなかったと言わんばかりの単姿のあかねは頼久の腕の中でおとなしく抱かれている。
紙燭が灯されているのは文机がその前にあるからで、文机の上には読みかけの書がのっていた。
それは先日、鷹通がよければと持ってきた歌集で、頼久がもしかしたら帰ってくるかもしれないと、それを何とはなく眺めながら待っていたのだろう。
そんなあかねの気持ちが嬉しくて、寝ているだろうあかねを起こさないように静かに帰ってきた頼久は、あかねが振り返って笑顔を見せると思わず抱きしめていた。
最近、頼久の仕事は増える傾向にある。
それは頼久が武士団の若棟梁として技量を認められいるという証でもあるから悪いことでは決してない。
八葉としての働きを認められたということでもある。
だから、頼久は決して仕事をおろそかにするようなことはしない。
しないが、そうなると今度は大切な妻の側にいる時間が削られていくことになるのだった。
ここ数日も、文のやり取りはしているものの、こうして顔を合わせることはなかなかできなくて…
今日も帰りが深夜に及んだので、おそらくあかねは寝ているだろう。
寝顔だけでも見られればとやってきた頼久をあかねが起きて待っていてくれたのだ。
頼久が喜ぶのは当然のことだった。
揺らめく紙燭の灯りに照らされながら、頼久は「ただ今戻りました。」の一言さえ言う間もなく、ただひたすらあかねを抱きしめた。
想像以上に苦痛だったあかねに会えないこの数日の時間を埋めるように。
そうしているとあかねもまた「お帰りなさい」の一言を言わせてもらえないことに苦情を述べるでもなく、その細い腕を頼久の背に回して愛らしく抱きしめた。
その細い腕のか弱い力には「大好きです」というあかねの声さえ聞こえてきそうな想いが込められていて…
あかねの想いを感じ取って、頼久はあっという間にあかねの体を軽く引き離すと、その小さな唇を自分の唇でふさいだ。
珍しくとどめることのできない想いに任せた頼久の口づけは、いつもよりも長く深いものになって、あかねが「ん」と苦しそうな声を出すまで続いた。
小さな声にやっと頼久が唇を解放すると、あかねは真っ赤な顔でにっこり微笑んでいた。
あかねがテレながら非難の言葉をつぶやくものと思っていた頼久の目は、あかねの赤く染まった艶っぽいその笑顔に目を見開いた。
紙燭に照らされるその笑顔は美しくも魅力的で、それでいて愛らしく…
熱病に犯されるようにふわりと伸ばされた頼久の手が、それでも優しくあかねをその場に押し倒すと、次の刹那、頼久の腰の辺りでかたりと音が鳴った。
「あの……頼久さん、刀…。」
頼久は刀の音にはっと我に返ると、就寝時以外は常に自分の腰に差されている刀へと目を向けた。
その刀はまるで、主を諌めているかのように頼久の目には映った。
大切な人を傷つけたりしないように、決して我を忘れて襲いかかったりしないように。
「失礼いたしました。着替えをしてまいります。」
「失礼なんかじゃないですけど、その刀は頼久さんの命を守ってくれる大切なものですから、大切にしてあげてください。」
「神子殿…。」
頼久は小さく息を吐くと、更に湧き上がる愛しさを必死で押さえながら、上半身を起こしたあかねを今度はただひたすら優しく抱きしめた。
確かに刀は賊と戦う時、頼久を守ってくれている。
だが、頼久の全てを守っているのは間違いなく、この腕の中にいる天女だった。
もう少しだけ…
この想いがもう少しおさまるまで…
頼久がそう心の中でつぶやきながらあかねを抱きしめると、あかねはうっとりと幸せそうに目を閉じた。
揺らめく紙燭の灯りに照らされたあかねのその顔は、頼久の脳裏に幸福という言葉の代名詞として焼き付いた。
管理人のひとりごと
はい、頼久さんにただひたすらあかねちゃんを情熱的に抱きしめてもらいたかった企画京バージョンです。
絵画っぽく書いたつもりなんですけど、見えましたかね?頼久さんがひしっとあかねちゃんを抱きしめている光景って(’’)
しばらくこの時代の衣装とか気にする話を書いてなかったんで、肌着って単でよかったんだよね?とか資料を確認してしまった…
平安時代の文化はそこそこ覚えたつもりだったのに…
ちょっとショックだったので勉強し直すかもしれません(’’)
ブラウザを閉じてお戻りください