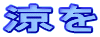
頼久は仕事を終えて足早に屋敷へ帰ってきた。
春の花が終わって初夏になって、陽も長くなった。
早く帰れば妻と夕暮れの美しい庭を共に眺めることができるかもしれない。
そう思えば妻の暮す屋敷へと向かう足は自然と速くなった。
息があがっている自分を微笑みながら迎えてくれた妻と夕餉を共にして、頼久は望み通り妻と二人、縁に並んで庭を眺める時間を得た。
「すっかり暑くなってきましたねぇ。」
「はい。私がいる間でしたら薄物を…。」
「絶対着ないって言いましたよねっ?!」
「はい…。」
あかねにギロリと睨まれて頼久は言葉に詰まった。
この愛らしい妻は夏の暑さをしのぐために仕立てた着物をいっさい着ようとしない。
頼久としては暑さで妻が病にならないかと心配でしかたがないのだが…
「そうだ!」
頼久が妻の身を案じている間にあかねはひょいっと局の奥に入ると扇を手にして戻ってきた。
「神子殿?」
驚く頼久をあかねはひらりと広げた扇でパタパタとあおぎ始めた。
「み、神子殿?何を…。」
「暑いでしょう?だから、こうしたら頼久さんは涼しいかなって。」
にっこり微笑むあかねに頼久は顔色を青くする。
自分はどんなに暑くても寒くても頑丈にできている自信がある。
だが、この妻は違うのだ。
頼久は慌ててあかねの手から扇を取り上げるとそれであかねをゆっくりとあおぎ始めた。
「頼久さん、それじゃぁ逆ですよ。」
「逆ではありません。私は頑丈にできておりますので少々のことで体を壊したりは致しませんが、神子殿は違います。この京では神子殿に涼んで頂くことも武士の身である私にはできかねますので、どうか今しばらく私にこのようにさせて頂きたく…。」
「もぅ、せっかく疲れてる頼久さんに涼んでもらおうと思ったのに。」
そう言って不機嫌そうに溜め息をつくあかねに苦笑しながら、それでも頼久は譲らない。
自分の身がどうなろうとこの妻さえ健やかであってくれればそれでいいのだ。
「これじゃぁ、私、頼久さんのために何もさせてもらえないじゃないですか…。」
「……では…。」
むくれるあかねの言葉に少し考えて、頼久は小さな妻の体をひょいと自分の膝の上に乗せてしまうと、正面から妻を扇であおぎ始めた。
「よ、頼久さん?」
「こうしていれば風が二人共に当たりますので。」
「そ、それはまぁ…。」
「それに私も神子殿に幸福にして頂いておりますので。」
「はい?」
片手をあかねの腰に回してキュッと抱きしめて幸せそうに微笑む頼久の顔を見て、あかねは真赤になってうつむいた。
初夏の夕暮れの中、二人は幸せそうに涼をとる。
管理人のひとりごと
京は暑いですからねぇ(’’)
涼をとるのは大変なわけですよ。
でもね、膝に抱っこしてたら風送っても意味なし(’’)(コラ
いいんです、二人がそれで幸せなら♪
プラウザを閉じてお戻りください