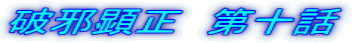
一行は晴れ渡った青空の下、ゆっくりと馬を進めていた。
敵の正体がなかなかつかめず、長期戦覚悟とさえ思っていた矢先、敵は正体を現した。
村人を襲った手口が違っていたり、状況が理解しがたかったりしたのは敵が二人いたから。
片方はあかねに頭突きを食らわせてくれた小さな子供、もう片方は見たこともないほど大きな熊だった。
あかね達はその熊を退治し、もう森で人が襲われたり村の家が襲われたりすることはないと村人達に熊の死体を見せて説明した。
驚きながらも村人達はあかね達一行に感謝し、そして村は平和を取り戻した。
鬼と呼ばれたものの正体である巨大熊を倒したことであかね達の仕事は終わった。
村を立て直し、畑を耕すのは村人達の仕事。
だから、あかね達はこれから前向きな作業に追われるであろう村人達にこれ以上世話になるのもどうかという結論に達し、早々に村を後にした。
事件は解決、任務完了。
誰の顔にも満足気な笑みが浮かんでいていい状況だった。
けれど、ただ一人、あかねの顔には笑みがない。
そんなあかねを見てしまえば、元八葉の面々が朗らかに笑っていられるはずもなく、結局、一行は微妙な空気のまま、移動を続けていた。
全てが終わったというのにあかねの表情が晴れないのにはもちろん理由がある。
あかねを襲った小さな男の子がその原因だ。
あかねを襲い、頼久に峰打ちされて気絶し、気付いてからはすっかりあかねに懐いたその子供は何故か全てが終わるとあかねの側を離れて行った。
その理由があかねにはわからない。
あかねとしては懐かれている以上、京へ連れて帰って屋敷で一緒に暮らそうか?とまで考えていたので、男の子が離れていったのは少しばかりショックだった。
一緒に行かないかとあかねが優しく誘っても子供は黙ったまま村に残る意思表示をした。
だから、今、あかねは頼久と共に馬に乗っているのだけれど…
すっかり沈んでしまっているあかねに元八葉の面々はなんとなく声をかけることも躊躇われて、全ての仕事を終えたというのに一行はしんと静まり返っていた。
そんな状況に耐えられなくなった友雅は、仲間達を代表して頼久に視線を送った。
友雅の視線に気づいた頼久は、小さく溜め息をついてからあかねを抱く腕に力を込めると耳元に唇を寄せた。
「神子殿、大丈夫ですか?」
「へ?何が、ですか?」
「落ち込んでおいでのようにお見受けします。」
「あ、えっと…ごめんなさい。」
「お謝り頂く必要はございません。あの童のことですか?」
「……はい…どうして一緒に来てくれなかったのかなって…私、何か嫌われるようなことをしたと思います?」
「いいえ。」
頼久の返事は即答だ。
何故なら、頼久にはあの子供があかねの側を去ったその理由に思い当たることがあった。
熊を倒し、全てを終えてあかねのもとへ戻った頼久に、あかねの隣に立つあの子供は強い視線を向けてきたのだ。
言葉を話すことができない子供のその視線は言葉よりもよほど雄弁で、頼久はほんの小さな子供の視線に圧倒された。
そしてその視線が自分に何を語りかけているのかを悟っていた。
「もともと村の子供だったわけだし、残る方が幸せなんじゃないかって、それはわかってるんですけど…なんだか嫌われちゃった気がして寂しくて…。」
「それは違います。」
「そう、ですか?」
「はい、もし、私がいなければあの童はおそらく神子殿と共に京へとやってきたと思います。」
「はい?頼久さんと何が関係あるんですか?」
「私はあの童に言ってしまいましたので、神子殿をお守りする役目を譲るつもりはない、と。」
あかねが振り向くと、そこには頼久の苦笑があった。
「でも、あの子は…。」
「あの子は神子殿を母親代わりとして慕っていたのではなく、おそらくは恋していたのであろうと思います。」
「そ、そんなことは…。」
ぱぁっと顔を赤くして、あかねは慌てて前を向くと視線を下げた。
なんだか恥ずかしくて顔を上げていられない。
「あの童は森で立派に一人で生き延びてきたのです、既に一人の男としての自負があってもおかしくはありません。だからといって私は神子殿をあの童に渡すつもりは毛頭ありませんので。」
「当然です!」
「ですから、彼が去ったのは当然のことです。神子殿が気になさることではありません。」
「頼久さん…。」
背後から自分の腰を抱いている頼久の腕に優しい力がこもるのを感じて、あかねはにっこり微笑んだ。
頼久の言うことが本当なら、やっぱり村にあの子を置いてきてよかったのだと思えたから。
たとえあの子がどんなに自分を想ってくれようと、あかねがあの子を頼久以上に想うことは絶対にない。
きっとあの子もそれがわかって離れて行ったんだ。
そう思うとあかねはやっと自分の生まれ故郷である村に残った子供の幸せを素直に祈る気持ちになれた。
「我らの天女殿はようやくご機嫌を直して下さったのかな?」
あかねの表情が変わったのを素早く見つけたのはやはり友雅だった。
馬を隣に寄せて艶やかに微笑んだ友雅にあかねも笑みを返した。
「心配させちゃってごめんなさい。」
「いやいや、心配などしていないさ。神子殿には優秀な夫がついておいでだからね。」
「はい!」
「友雅殿…。」
あきれる頼久の代わりにあかねが元気よく返事をすると、鷹通、泰明、イノリ、永泉の顔にも笑みが広がった。
「では、湯治場へ急ごうか。あんな化け物の相手をしたのだから、少しは羽根をのばさないとね。」
そう言いながら友雅があかねにウィンクをして見せれば、あかねはその顔に苦笑を浮かべた。
「あの熊もかわいそうでしたね。」
「獣は一度人の肉を喰らうとその味を覚えて人ばかり襲うようになるという。他に方法はなかった。神子が思い悩む必要はない。」
「はい。」
親を失った哀れな子供のことのみならず、敵であった獣のことにまで心を痛める優しい神子に泰明は整然とした口調で断言した。
そして泰明が何故そんなふうに断言してくれたのかがわかるからこそ、あかねは明るく笑ってうなずいた。
あかねが笑顔を取り戻しさえすれば一行の足取りは軽くなる。
友雅に所望され、泰明に促されて永泉が馬上で笛を吹き始めれば、もう一行の歩みは楽しい温泉への旅へと変わっていた。
ちゃぷんと水の音がして、頼久はびくりと肩を震わせた。
間違いなく愛しい妻の気配が音のした方から感じられて、頼久の額に汗がにじんだ。
「頼久さん、そこにいます、よね?」
「はい。」
そう答えるのが精一杯だ。
あかねはどうやらほっと安堵のため息をついたようで、揺れていた水面が静かにおさまった。
今、頼久は妻と二人きり、露天風呂につかっていた。
妻と二人で湯につかってどうしてそんなに焦っているのかと言われれば確かにそうで。
二人で一緒に暮らしている上に毎晩一緒に眠っているのだから、もちろんあかねの裸体を見たことがない、わけではない。
だが、頼久にとってこんな明るい、しかも温泉の中で色っぽく湯につかるあかねというのは目の毒以外の何物でもなかった。
幸いなことに、陽が傾いてくると気温が下がり、湯の温度が高かったせいか激しく上がる湯煙のおかげであかねの姿ははっきりとは見えない。
そのことに頼久は胸の中で感謝しつつ、脳裏に友雅の姿を思い浮かべて顔をしかめた。
どうしてこんなことになっているのかと言えば、そもそもの原因は友雅だった。
せっかく湯治にきたのだからあかねにはゆっくり湯につかってもらおうというのは全員の一致した意見だった。
あかねに安心して湯につかってもらうため、頼久は出入り口付近で警護をすると心に決めていた。
ところが、友雅は言い出したのだ、それでは入口を使わずに進入してきた賊はどうするつもりなのか?と。
泰明が式神を使って警護という意見も出たが、泰明は式神が見ている物を見ることができる。
つまり、湯船付近を式神が警護すればあかねの裸体が泰明の目に触れるかもしれないということで却下された。
かなりの勢いで却下したのはあかねだった。
そして議論は転がりに転がって、簡単じゃないかという結論に達した。
夫である頼久が一緒に入れば問題はない、というわけだ。
一行の中で一番腕が立つのも頼久だし、あかねが一緒に風呂に入ることを拒否しない唯一の男も頼久だ。
これで解決とばかり全員が納得した友雅の意見だったのだが…
夕陽に染まる温泉でそれでなくても愛しくてならない妻と裸の付き合いなど、頼久にとってはとんでもない災難でしかなかった。
これで、ここが自宅、もしくは二人きりでの旅先だったなら問題はなかったかもしれない。
が、ここは他の仲間と共にやってきた旅先で、あかねの愛らしさに理性を焼き切られた頼久が妻を襲っていい状況では決してない。
「気持ちいいですねぇ。」
湯気の向こうに見え隠れするあかねが心から楽しそうな声でそう言うと、頼久は小さく溜め息をついた。
先日まで気を張り詰めて戦っていたこともあって、温かい湯は確かに気持ちがいい。
気持ちはいいが…
正直、頼久はそれどころじゃない。
「頼久さん?気持ちよくないですか?ひょっとして私と一緒に入るの嫌でした?」
「滅相もない!」
悲しそうな声に慌てた頼久は思わず身を乗り出してしまい、その勢いで湯気が揺れ…
湯気の切れ間にお湯に使つかって上気するあかねの顔が見えてしまい…
「でもなんか、頼久さん、居心地悪そうっていうか…。」
「居心地が悪いわけでは決して…。」
慌てて目を反らせてなんとか呼吸を整えて、頼久は大きく溜め息をついた。
居心地が悪いなどということが愛しい妻の側にいる以上、あるわけがない。
けれど、今の自分の状態をあかねに説明するのはかなり難しい。
だいたい、今の自分の状態を詳しく説明してしまえば、あかねに軽蔑される、ということも考えられなくはない。
「でも、やっぱり頼久さんもみんなと一緒に男同士で和気藹々とっていう方がよかったですよね。ごめんなさい。お風呂の中でまで守ってもらっちゃって…。」
あかねはなにやらどんどん落ち込んでいく。
自他共に認める口下手の頼久、うまく口先ではぐらかすなどという友雅のような芸当ができるわけもなく、これはもう何もかもを正直に白状するしかないと覚悟を決めた。
「あの…私、先にあがってみんなに…。」
「神子殿。」
「はい?」
もう湯船からあがって早くみんなを呼んでこようと思っていたあかねは、突然呼び止められて慌てて姿勢を元に戻した。
頼久の声はあまりにも真剣で重々しくて、あかねにそれを受け流して立ち去ることを許さなかった。
「神子殿のお側にあって居心地が悪いなどということは私に限ってはありえないことです。」
「頼久さん…。」
「ただその…。」
「ただ?」
「…湯につかっておいでの神子殿は……その……いつもよりもお美しく……艶やかと申しましょうか…。」
「そ、そんなことないですよ!」
「いえ、正直に申し上げますが。」
「はい!どうぞ!」
「湯の中にある神子殿のお体を想像しないでいることはできません。」
「はい?」
「……そうなれば、その……私も男ですので、神子殿を欲しいと…。」
「ああああああーーー!」
「神子殿?」
「そ、それ以上はいいです!わかりました!」
慌てて大声を出したあかねは顎の辺りまでお湯につかって顔を赤くした。
どうやら意図が伝わったらしいと安心した反面、頼久は緊張もしていた。
次に聞えてくるあかねの言葉が恐ろしい。
湯船につかってそんなことを考えているとはと軽蔑されるのではないか?
もしくは、過度に自分を警戒するために、せっかく温泉につかっているというのにあかねは少しもくつろげないのではないか?
沈黙の中で頼久の緊張はどんどんエスカレートし…
「えっと、その…一応、ここは外出先ですし、みんなも近くにいるわけで恥ずかしいですし…。」
「承知しておりますので、私のことはどうかおかまいなく。」
「あ、でも、嫌っていうわけじゃなくてですね…常識的にダメっていうかなんていうか…。」
「はい。」
嫌というわけではない。
頼久にはこの一言で十分だった。
どんな非難の言葉を受けねばならないかと覚悟していた頼久に、この言葉は救いの囁きだった。
「それで、その…ちょっと嬉しかったです。」
「は?」
「頼久さん、ちゃんと私のことそういうふうに見てくれてるんだなと思って。私、ちょっと子供っぽいところがあるし、あんまり色気がないっていうか、そういうの気にしてたので。」
色気がない?
なんの話だと一瞬頭の中を真っ白にした頼久は、ブンブンと首を横に振って小さく溜め息をついた。
あかねのことを以前から慕っている男がどれほどいるかあかね自身はいまだにわかっていない。
武士団の若者達にとってどれほど憧れの的になっているのかもだ。
自分の魅力を自覚してないというのはそれはそれであかねの美点でもあるけれど、ここまで来ると頼久は激しく否定しないではいられなかった。
「神子殿は立派な、そして大変魅力的な女性です。私はもとより、他の男達をも惹きつけてやまぬ魅力をお持ちです。もちろん、色気もお持ちです。ですので、どうか他の男の目には触れぬよう、お気をつけいただきたく…。」
最後の方は嫉妬の言葉のようになってしまって、頼久は声を小さくした。
ところが、あかねはというとクスッと笑みを漏らしただけで頼久を非難したりはしなかった。
「そんなことないと思いますけど、でも、頼久さんがそういうなら気をつけます。」
京では貴族の女性は屋敷の奥に引きこもって滅多に他人に姿を見せることがないというのはあかねも良く知っていること。
だから頼久がこんなことを言うのだろうくらいに理解したあかねは、これはもう家に帰ったらしっかり引きこもって頼久を安心させようと心に決めたようだった。
そして頼久はというと…
結局のところ湯につかって妙に色っぽいあかねの魅力というものからは逃れられず、あかねがすっかり満足したと言って湯からあがるまで、己を律することに全ての集中力を注ぎ込まなくてはならなかった。
京は夏の盛り。
暑さは日に日に増して、屋敷の中は風が通らなければ蒸し風呂のようだ。
それでもあかねは屋敷の奥に引きこもり、決して外へ出ようとはしなかった。
そんなあかねの様子を知っていて、訪ねてきたのは元八葉の中でも気遣い上手の友雅だ。
あかねは友雅とはしっかり御簾を隔てて対峙した。
それはこの京での常識。
なのだけれど…
「神子殿も冷たいね。昔は共に手を取り合って怨霊と戦った仲間の私にまでそんな他人行儀な。」
「これが普通だって教えてくれたの友雅さんじゃないですか。それに、こうしてないと頼久さんに心配かけちゃいますから。」
「なるほどね、妙なところで頑固で自制心が強くて、そのくせ心配性で嫉妬深く、独占欲の強い夫を持つと大変だね。」
「頼久さんはそんな人じゃありません。」
静かに断言するあかねに友雅はクスッと笑みを漏らした。
相変わらず、元龍神の神子と元八葉の夫婦は仲が良いらしい。
そうなると、からかいたくなるが友雅だ。
「いくら旅先だからと言って、夫婦が二人、湯につかっていてあの会話は、童ではないのだから。」
「き、聞いてたんですかっ!」
「まぁ、ね。頼久が我慢ならなくて事に及んだ場合は他の仲間達を上手く牽制してやろう、くらいは思っていたさ。私は大人だからね。」
「盗み聞きするような人を大人とは言いません!」
「まったくです。」
むきになって怒るあかねの声に続いたのは話題の主、頼久の声だった。
どうやら武士溜りから戻ってきたらしい頼久は、友雅の背後から御簾へと歩み寄ると、その前に片膝をついて御簾の向こうにいるであろう妻に頭を下げた。
「頼久、ただいま戻りました。」
「お帰りなさい、頼久さん。」
機嫌の良さそうなあかねの声に友雅が苦笑していると、とりあえずの挨拶を終えた頼久がギロリと友雅を睨んだ。
「藤姫様より、すぐに土御門の屋敷へ来て欲しいと伝言を承って参りました。」
「私かい?」
「はい。どうせ神子殿の所においでだろうと。」
「藤姫にはかなわないねぇ。」
「何やらご機嫌斜めでしたのでお急ぎになった方がよろしいかと。」
「それはそれは…確かに急いだ方が良さそうだね。では、神子殿、またね。」
「あ、はい、気をつけて。」
さっきまで友雅の行動を怒っていたのに、別れ際は仲間をいたわるそのあかねの優しさに友雅は穏やかな笑みを浮かべると、優雅な身のこなしで歩み去った。
その背を見送って頼久が小さな溜め息をつく。
「頼久さん?」
友雅がいなくなったので御簾から顔を出したあかねに、頼久は笑みを浮かべて見せた。
きっちり友雅との間に御簾を隔てていてくれたあかね。
そしてそのあかねの顔を自分は好きな時に好きなだけ見ることが許されている。
それだけでも頼久にとっては望外の幸せに思えた。
「あの、お仕事、終わったんですか?」
「はい。」
覗き込んでくる翡翠の瞳の魅力には抗えなくて、頼久はその手を伸ばすとあかねを自分の方へと引き寄せた。
ふわりと腕の中に小さな体を閉じ込めて、嫌がってはいないかと様子をうかがえば、あかねは頼久に満面の笑みを見せた。
「それじゃあ、これからずっと明日まで一緒にいられますね。」
「はい。」
嬉しそうなあかねの声、言葉。
それをもっと聞きたいと思いながらも、頼久はあかねの唇を自分の唇でふさいだ。
ここは京。
あかねの屋敷。
頼久の帰る場所。
だから…
頼久は長い口づけの後、ゆっくりと御簾の向こうへあかねをいざなった。
管理人のひとりごと
こんな終わり方をするはずじゃなかった(マテ
とはいえ、終了いたしました\(^o^)/
いや、当初の予定では温泉の帰り道、みんなでワイワイ頼久さんをいたぶりながら歩く、みたいな終わり方を予定してたんですが…
なんか、盗み聞きまでされて頼久さんかわいそう(TT)と頼久さん贔屓の管理人が思ってしまったため、ラスト変更でございます!
頼久さん、幸せそうでしょ?(笑)
いやぁ、温泉のシーンを書きたいがために連載を始めたので、最後は書いてて楽しかったです!(>▽<)
途中、更新が滞ったりなど致しましたが、ここまで長きに渡りお付き合いいただいた皆様、有り難うございましたm(_ _)m
少しでもお楽しみ頂けていれば幸いです(^^)
ブラウザを閉じてお戻りください