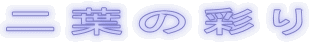それはきっと彼らにとっては日常なのだろうし、ごく普通のことなのだろう。
そうわかってはいてもどうしても頼久は冷静ではいられなかった。
ここ数日、いつもなら学校から帰るとすぐにやってくるか学校帰りに寄るかしてくれていたあかねが自宅へ直行で会えなかった。
しかも、やっとゴールデンウィークに入ったというのにその前半はあかねからの連絡が皆無で、多少のメールのやりとりだけだった。
そして今日、ゴールデンウィークのちょうど中間になってやっとあかねが大量の荷物を持って訪ねてきたのだ。
久々に会えた嬉しさで思わず玄関であかねを抱きしめた頼久だったが、あかねはというとさっさとその腕から逃れて何故か台所へ駆け込んだ。
「今日は凄くおいしいご飯作りますからね!詩紋君にしっかり習ってきましたからっ!」
力いっぱい元気にそういったあかねはエプロンをかけて台所にこもってしまった。
大量に持ち込んだ荷物はどうやら全て食材だったらしく、それらを次々に袋から出しては調理を始めたのだ。
頼久はというと置いてけぼりをくったかのようにリビングのソファに座ったままで台所に立つあかねの背中を見つめていた。
「今日はね、鍋なんです!」
「鍋、ですか。」
「そうです!鍋なんです!鍋は出汁です!出汁が勝負なんです!」
「はぁ…。」
「この一週間、みっちり詩紋君に習いましたから、絶対おいしいですから!」
「……。」
ということは、自分があかねに会えなくてイライラしていた間、詩紋があかねを独り占めにしていた?
と、心の中でとっさに想像してしまい、頼久はあわてて首を横に振った。
あかねにしてみれば頼久においしい鍋を食べさせたかっただけだろうし、詩紋にしてもあかねに料理を教えてくれと頼まれれば断れるはずもない。
そうとわかっていても頼久はどうしても料理してくれているあかねの背中を冷静に見つめることはできなかった。
「えっと、昆布は水からで…かつおは他の鍋で…あれ、水からだっけお湯だっけ、メモメモっと…。」
あかねは次から次へと食材を取り出し、鍋を用意し、カバンからメモを取り出しと忙しく動き回る。
「確か詩紋君はここで…。」
ぶつぶつとつぶやきながら料理するあかねの口からは何度となく詩紋の名前が出てきて…
それを耳にするたびに頼久の顔は不機嫌そうに歪んでいく。
そんなことには全く気付かないあかねはというと食材を次々に一口大に切り、出汁をとり、着々と料理を進めている。
鼻歌まで飛び出して、それでもわからないことがあるといつの間にか詩紋の名前を口にしながらあかねが料理をすること一時間、だいたいの調理が終わって今まで使った道具を洗うというところまでたどり着いて、あかねの動きはやっとおだやかになった。
「これで下準備は万端ですからね。あとは晩御飯までこうして余熱で置いて、食べる直前に葉野菜を入れて一煮立ちでできあがりですからねぇ。」
「はぁ。」
「あ、おひたしか何か作りましょうか、お鍋って色々入ってて栄養バランスはいいんですけど箸休めはほしいですよねぇ。」
あかねは上機嫌で次々に料理に使った道具を洗い、冷蔵庫からほうれん草をとりだして水で洗い始めたところでほうれん草をその手からぽとりと落とした。
「えっと、頼久、さん?」
あわてて振り向こうとしてもその体は後ろから頼久にしっかり抱きしめられていて全く動かせない。
あかねは料理をしようにも両腕が自由にならず、不自由なのと恥ずかしいのとでどうしていいかわからずに顔を真っ赤にしてうつむいた。
「頼久さん、あのですね、そうしてるとお料理ができないんですけど…。」
「…料理は後で私が致しますので……。」
いつもとは違う掠れた声に驚いてあかねは目を丸くする。
「あの…おひたしの作り方もちゃんと詩紋君に習ってきたから大丈夫、なんです、けど…。」
詩紋の名前が出たところでぎゅっと更に強く抱きしめられてあかねはまたうつむいた。
どうもいつもの頼久とは様子が違うことにやっと気付いて、まだかすかに濡れている手を自分の体に回されている頼久の腕の上にそっと置いた。
「何か、あったんですか?」
「……いえ、何も…ただ……今少し、こうしていて下さい…。」
どこか悲しげな、そしてつらそうな掠れる声は今まで聞いたことがないほど切なくて、あかねは言われるまでもなく動くことなどできなかった。
ほうれん草を洗うために流れている水道の水の音だけが聞こえる静かな台所で、後ろから恋人に抱きしめられているこのシチュエーションはあかねにはかなり恥ずかしいもので、あかねはひたすら顔を赤くしてうつむいていた。
背中には優しい恋人のぬくもりが感じられて、なんだか少し幸せな気分だ。
ただ、自分を抱きしめるその腕にこもった力がいつもより少しだけ強い気がして、それだけがあかねには気になった。
「すみませんでした、料理、お手伝い致します。」
そう言って頼久があかねを解放したのはたっぷり五分以上たってからだった。
やっと解放されて振り向いたあかねの目に映ったのはいつものように優しく微笑む頼久で、あかねは満面に幸せそうな笑顔を浮かべると手伝うといった頼久を台所から追い出してさっさと料理を再開した。
そうやって料理をして、その後はいつものようにゆっくりおしゃべりをして、そしておいしい鍋を晩御飯に食べて帰ったあかねには、家まであかねを送り届けた頼久が帰り道、どんな顔をしていたかなど想像もつかなかった。
これは気晴らしの一つもしなくてはならない。
翌日、頼久は未明から真剣にそう考えた。
あかねを自宅へ送り届けてとんでもなく不機嫌そうな顔で帰ってきた頼久は、結局
、その夜、一睡もせずに朝を迎えた。
それでなくても昨日、あかねに不審がられているのにこのまままたあかねに会えば昨日以上に不審な行動に出かねない自分を頼久自信が持て余していた。
とはいえ、気晴らしといっても特にどんな趣味も持たない頼久だ。
結局、まだ暗いうちから寝室を出た頼久は庭で木刀を振ること二時間。
予想通り全く気が晴れることがなかった頼久は、ざっとシャワーを浴びて着替えると食事もとらずにそのまま外へと出かけた。
仕事柄、家の中にこもっていることが多い頼久は気晴らしにと外へ出ても行き場所に困ってしまい、とりあえずはぶらぶらと商店街を歩くことにする。
だいたい、書店か文房具店、あとは食料品店に行くくらいで他の店はほとんど知らない。
この機に少し色々な店を見て回ろうかと考えて、頼久はふっと息を吐いた。
何を考えても頭の片隅にあかねの顔が浮かぶ。
楽しそうに料理をしながら詩紋の名を呼んだあかねの笑顔だ。
これでは気晴らしになっているのかいないのかと自分で苦笑しながら頼久はゆっくり歩く。
何をやってもこの調子では気晴らしになどならないかもしれない。
そう考えると自然と苦笑が浮かんだ。
今日はあかねは午後からやってくることになっている、だから、それまでにはなんとかして自分の精神状態を戻しておきたい。
いつもどおりに戻すのが無理でも何とかおさめなくては。
頼久がそう考え込みながら歩いていると、ふと武士として研ぎ澄まされた感覚が何かに気付いて自然とそちらへ視線が向いた。
おそらく、頼久が京で武士などやっていなければ気付かないだろうほどの距離にいる二人の人影に、常人とは違う感覚を持った頼久は気付いてしまった。
それは楽しげに天真の腕を引いて歩くあかねの姿。
頼久はぴたりと歩みを止めるとまるで吸い寄せられるかのように二人の姿から目を離せなくなった。
若々しく輝くあかねの笑顔。
手を引かれて迷惑そうな表情を浮かべてはいるが、どこか浮かれているような天真。
二人は当然のことながら同じ現役高校生で、はしゃいで歩く姿は自然に町の中に溶け込んでいる。
雑貨屋に入っていく楽しげな二人を見送った頼久はしばらくその場に立ち尽くした。
天真は頼久にとっても親しい友人だ。
京では頼もしい相棒でもあった。
こちらの世界にきてからもよき友人だし、色々とアドバイスをくれたりもしている。
あかねと天真は頼久があかねと出会う前からの友人でもある。
二人で商店街を歩いていても、共に買い物をしていても何の不思議もない。
疑うことなど欠片もないはずなのだ。
それなのに、頼久は全身から血の気が引くのを感じていた。
数分の間そうして呆然と立ち尽くし、そしてやっと働き始めた頼久の思考は二人にみつかってはならないという答えをはじき出し、足早にその場を立ち去った。
「お邪魔しま〜す。」
午後になって顔を見せたあかねはいつもと全く変わらない様子で、顔には何か楽しいことがあったのか満面の笑み。
その笑顔さえもが胸に突き刺さって、いつものようにドアを開けてあかねを迎え入れた頼久はすぐにそんな異変をあかねに気付かれてしまった。
「頼久さん、なんか顔色悪いですよ?体調悪いんですか?」
「いえ、そのようなことは…。」
「でも、いつも健康優良児の頼久さんがそんな青白い顔してるなんて…熱とかないで
すか?」
リビングへ入ってすぐテーブルの上に荷物を置いたあかねは長身の頼久につつと歩み寄ると、思い切り腕を伸ばして頼久の額に手を当てた。
「ん〜、熱はないですね。食欲とかありますか?晩御飯、何か消化のいいものにしましょうか?」
「…体調は悪くありませんので、お気遣いなく…。」
「ん〜、そう言われても…頼久さん、昨日からなんか調子悪そうだし…。」
ん〜、と再びうめき声を上げながら考え込むあかねを見下ろしながら頼久は自分の眉間にシワが寄るのを押さえられなかった。
耳にこびりついているのは昨日の詩紋の名を口にするあかねの声。
目の奥に焼きついているのは天真と楽しげに歩くあかねの笑顔。
「頼久、さん?なんか怒ってます?」
「いえ、別に…。」
「でも…なんだか苦しそう…。」
心底心配そうに見上げるあかねはどうしようもなく愛しいのに、目の奥にちらつくあかねの笑顔は胸に刺さって、頼久はどうしても微笑むことができない。
「私に何かできることありますか?」
何を聞いても答えてはもらえないと思ったのかあかねが必至の瞳で見上げてくる。
その表情があまりにも必至で、うったえかけてくるようで、頼久は思わずあかねを抱きしめていた。
「やっぱりおかしいですよ、頼久さん…。」
「できることはないかとおっしゃったので…。」
「こ、これが私にできること、ですか?」
「はい。」
頼久の腕の中に閉じ込められた状態であかねは顔を真っ赤にしていたが、そんなあかねに頼久が気付くわけもなく、その抱きしめる腕の力はだんだんと強くなる。
「あ、あの、頼久さん、他に何かできることって…。」
このまま黙っていたらどれくらい抱きしめられるのだろうか?と考えてちょっとだけ恐くなったあかねがおずおずとそう聞いてみると、案の定腕にこめられる力は少しだけ弱まって、その代わりに頭上から掠れたような声が降ってきた。
「質問に答えて頂けますか?」
「質問?はい、別にいいですけど…私に答えられる質問なら。」
「今日、午前中、天真と何をしていらっしゃったのですか?」
「はい?午前中って、あれ、見てたんですか?!」
驚きのあまり頼久の顔を見上げようとしても、頼久の大きな手のひらでそっと頭を抱えられてしまって、あかねはどうしても身じろぎさえできなくてただその腕の中でひたすら赤くなる。
頼久はというと今の自分の顔を、おそらくは怒ったようないらだっているような醜く歪んでいるだろう顔をあかねに見られたくなくてしっかりとあかねを抱え込む。
「その質問に答えると、頼久さんの調子は良くなるんですか?」
「答えによります。」
「ん〜、ちょ、ちょっと恥ずかしいんですけど…。」
恥ずかしい?
その一言で頼久の腕には再び力が込められる。
「実は昨日、食料の買い出しをしてる途中で見つけちゃったんです。」
「何を、でしょうか?」
「えっと、頼久さんの寝室のベッドの横にランプが置いてあるじゃないですか?」
「はぁ。」
「あれと同じものを見つけたんです。」
「はぁ。」
「それで、実はうちのベッドサイドのランプが壊れかけてて…ちょうどいいから、その…おそろいのランプにしちゃおうかなって…でもちょっと大きくて一人で持って帰るの大変そうだったんで、天真君に荷物持ち頼んだんです…。」
「……。」
頼久が無言でたたずむこと数十秒。
やっとその腕からは力が抜けて、あかねはゆっくり頼久からその身を離して恋人の顔を見上げた。
そこには何故か果てしなく安堵したようなほっとした表情があって、あかねは小首をかしげる。
「…私に言って頂ければ荷物持ちくらいいくらでも致しました…。」
「えっ、だって恥ずかしいじゃないですか…。」
「何がでしょうか?」
「…おそろいのランプ買いたい、なんて…頼久さん本人に話すの恥ずかしくて……。」
「恥ずかしいなどと……これからは荷物持ち程度、この頼久にお言いつけ下さい。」
「お言いつけ下さいって、そんな……。」
いつもながらの物言いに抗議しようとしたあかねは、ここでふとある事実に気付いて目を丸くした。
何故そんなことを聞かれたのか最初はあかねには全く意味がわからなかった質問の答えを聞いて、頼久はどうやら心底安心したようで…
質問の内容と言えば午前中は何をしていたか?で、答えは天真と買い物をしていた。
買っていたのは頼久が使っているものとおそろいのランプ。
この答えを聞いて頼久は安心し、そして、先ほどの頼久の発言、荷物持ちなら自分に。
これら全てから導かれる答えは…
「あの…もしかして頼久さん、やきもち、やいてました?」
「……。」
顔が赤い。
一瞬のうちに真っ赤になった。
ということは、この質問は図星。
そう判断してあかねはにっこり微笑んだ。
「頼久さんが妬いてくれるなんて思いませんでした。」
いつもは自分よりずっと大人だなぁとか、京にいた頃よりずっと余裕があってなんだか自分ばかりが右往左往してて悔しいなぁなどと思っていたあかねにとってはこれは少しばかり嬉しい事実で、思わずにっこり微笑んだのだが、頼久はというと顔を赤くしたまま凍りついている。
「えっと、頼久、さん?大丈夫ですか?」
「……普段はその…このように嫉妬したりはしない…と、思います…おそらく…。」
「はい?」
「その、最近は…ここ一週間ほどは神子殿にほとんどお会いできませんでしたし、その…私がお会いできない間は詩紋とご一緒だったようですし…。」
「あぁ…そんなことで妬いてくれたんですか。」
かわいいと言わんばかりに嬉しそうに微笑むあかねの前で頼久はこれ以上ないほど赤くなる。
「そんなこと、では……。」
「あぁ、ごめんなさい、頼久さんにとっては妬いちゃうくらい大変なことでした。でも、私にとってはなんていうか、天真君と詩紋君は前から仲のいい友達だし…。」
「承知しております。ですから、今回は特別です。」
「でも、気をつけますね。頼久さんも私が気にしないように女の子がいるところで色々教えたりするのやめてくれたんだし。私も頼久さんが気にするようなことしないように気をつけます。荷物持ちはこれから頼久さんにお願いしますし、詩紋君にお料理教わる前にお母さんに教わることにします。どうしても詩紋君に教えてもらいたい時は、今度からここで、頼久さんの目の前で教えてもらうことにしますね。」
「神子殿…。」
その心遣いが嬉しくて、頼久はふっと優しく微笑むとあかねの唇に軽く口づけた。
今度はあかねがみるみるうちに真っ赤になってうつむくのを、余裕の笑顔で頼久は優しく抱きしめた。
「今ので嫉妬は消えましたので、あまりお気になさらず。天真は我が真の友、詩紋も同じ八葉、仲間と思っておりますから。」
「は、はい…えと…今日の晩御飯は生姜焼きを予定してるから、今からお肉をタレに漬けますからっ!」
慌ててそう言ったあかねは顔を真っ赤にしたまま台所へ駆け込んだ。
あかねを優しく見守りながらソファに座る頼久。
背中にそんな頼久の暖かな視線を感じながらあかねは食材を冷蔵庫から取り出し、心の中でつぶやいていた。
(やきもちやかせたら、またキスしてもらえるのかな?)
なんて考えて、あかねは一人台所で更に顔を赤くするのだった。
管理人のひとりごと
五分水道出しっぱなしってどうよ!とか
あかねちゃん、たぶん頼久さんの前で詩紋君に料理習ったらそれはそれで違う感じに妬くと思いますΣ( ̄ロ ̄lll)
と自分でつっこみつつ(笑)
今回は現代版八葉に嫉妬する頼久さんでした。
こっちは八葉が二人しかいないのでちょっと短め。
友雅さんがいないから煽りも少なめ(爆)
書きたかったのはお料理中に後ろから抱かれるあかねちゃん、それだけでした(マテ
プラウザを閉じてお戻りください