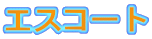
あかねはもう習慣になっていると言ってもいいほど自然に、週末、頼久の家へ向かっていた。
最初のうちはこんなに頻繁に通ったりして迷惑じゃないだろうかと心配さえしていたのに、今となっては毎週、週末は頼久の家で二人で過ごすのが常だ。
平日も無理をすれば会えないことはなかったが、学校があるあかねには毎日頼久の家によってから帰宅するのはかなりつらい。
だから、どうしても会うのは週末に限られた。
どうしても寂しくなったり、会いたくなったりした時は、メール一つで頼久の方から会いに来てくれるのだが、そういつもいつも頼久を呼び出すわけにもいかない。
だから、週末はあかねにとって大切で、そして幸せな一時だ。
手土産に手作りのオレンジゼリーを持ってあかねがドアの前に立つと、いつものようにドアはすっと開いて微笑を浮かべた頼久が姿を見せた。
「こんにちわ。」
「ようこそ、どうぞ中へ。」
頼久が体をずらして道を開けると、あかねは慣れた足取りで中へ入る。
もう頼久がいざなうまでもなく、あかねは勝手知ったる家なのですぐに台所へ行って冷蔵庫の扉を開けた。
「ゼリー作ってきたんです、冷やしておかないとおいしくないから冷蔵庫に入れておきますね。お昼ごはんの後に食べましょう。」
「いつも申し訳ありません。」
「私がやりたくてやってるんですから、頼久さんは気にしないで下さいってば。さて、お昼ご飯までにはまだちょっと時間があるし…紅茶、いれますね。」
「お手伝い致しましょうか?」
「すぐだからいいですよ。頼久さんは座っててください。」
「はい。」
最初の頃はどうしても手伝うと言ってよくあかねと共に台所に立っていた頼久だが、最近では自分の体の大きさで一緒に台所に立つと邪魔になることもあると気付いて、簡単な作業の時はあかねを見守ることにした。
リビングのソファに座っていると台所で作業をしているあかねの後姿が目に入る。
楽しそうに紅茶をいれるあかねの後姿を静かに眺めている一時は頼久にとっても幸せな時間だ。
もっとも、こうしてこの家の中にあかねがいてくれれば、どんな時間も幸せなのだが。
あかねは手早く紅茶をいれると二人分の紅茶をリビングへ運んで、頼久の向かい側に座った。
「神子殿。」
「はい?」
「少々お話したいことがあるのですが…。」
あかねはティーカップを片手に小首を傾げた。
頼久がこんなふうに改まって話を始めることは珍しい。
表情もどことなく緊張しているように見える。
これは何かよくない話なのかとあかねは表情を引き締めた。
「なんでしょう?」
「はぁ…その…次の土曜なのですが…。」
「あ、お仕事がつまって会えないとか、そういうことは遠慮しないで言って下さい。私、気にしませんから。」
慌ててそういうあかねの顔は一生懸命微笑んでいるのだがそれでもどこか悲しそうで。
気にしないと言われて少しだけ落ち込んだ頼久は、そのあかねの表情を見て微笑んだ。
「いえ、そういうことではなく…実は、新しく創刊される雑誌の創刊記念パーティに招待されてしまいまして。」
「なんだ、やっぱりお仕事じゃないですか。それってお仕事の関係のパーティなんでしょう?」
「はい。その…もし神子殿さえよろしければ、一緒に出席して頂きたいのですが…。」
「はい?」
一瞬、あかねの頭の中が真っ白になった。
雑誌の創刊記念パーティなんてそんな正式で盛大なもの、どんなパーティになるのか想像もつかない。
少なくてもクラスメイトの誕生日パーティよりは盛大なはずだ。
「えっと、私が、そのパーティにですか?」
「はい。できれば女性同伴が好ましいと担当に言われまして。」
「あぁ、海外だとパーティって奥様同伴とかが普通だって言いますよね。」
「私が同伴できる女性となると神子殿しかいらっしゃいませんので、もし都合がよければ共に出席して頂きたいのですが…無理でしょうか?」
「へ、無理、じゃないんですけど…。」
土曜はもちろん頼久に会うために予定をいっさいいれずに空けてあるのだから不都合なはずがない。
だが…
「私、そんなちゃんとしたところに出席したことないし…テーブルマナーとか全然わからないし…一緒に行ったら頼久さんに恥かかせちゃいます、きっと…。」
そう言ってあかねはうつむいてしまった。
頼久なら立っているだけで様になるし問題はないだろうが、では自分はと考えるとまだまだ子供でそんな席に似合うとは思えない。
あかねはうつむいたまま深い溜め息をついた。
「立食パーティらしいのでテーブルマナーは特に必要ないかと…衣装もこちらで用意しますが…無理でしょうか?」
久々に聞く頼久の悲しげな声にはっとあかねが顔を上げれば、そこには元武士とは思えないほど情けない顔をした頼久がいて、あかねはぎょっと息をのんで思わず首を横に振っていた。
「そ、そんなことないです。もともと土曜は空けてありましたし。」
「有難うございます。では、土曜の6時にお迎えにあがります。」
満面の笑みでこういわれてはもうあかねにはどうすることもできない。
頼久の笑顔にこたえるように引きつった笑みを浮かべながら、あかねはこれからみっちり勉強しようと心に決めていた。
結局、たいしたことができないまま一週間はすぎた。
前日に頼久から送られてきたドレスを見て更に落ち込んだあかねは、それでも約束を破るわけにはいかないとドレスを着て玄関に立った。
別にドレスを見て落ち込んだのはドレスが気に入らなかったからじゃない。
頼久が選んで送ってきたドレスは淡いブルーのとても可愛らしいものであかねもすぐに気に入ったのだが、その本格的な感じがこれから出席するパーティの盛大さを物語っているようだった。
髪型もセットして可愛らしいイヤリングもつけてみた。
それでもやはり子供っぽい感じは抜けなくて、あかねは鏡の前で溜め息をつくとドアチャイムに呼ばれたように玄関に立ったのだった。
「こ、こんばんわ…。」
小さい声でそういいながらドアを開けるとそこにはきちんとスーツを着た頼久が立っていた。
きちんと正装した頼久を見るのはこれが初めてで、そしてそれは頼久も同じ事で、二人は互いに目を大きく見開いたまま数秒立ち尽くした。
そして驚きから立ち直ると同時ににっこり微笑んだ。
「神子殿、よくお似合いです。」
「頼久さんも。あ、ドレス有難うございました。すみません、わざわざ用意してもらっちゃって。」
「いえ、私が無理を言って出席して頂くのですからこれくらいは当然です。お気に召しましたか?」
「あ、はい、とってもステキで。私なんかが着るのもったいないくらいです。」
「いえ、よくお似合いです。」
嬉しそうに微笑みながらそういわれればあかねも悪い気はしない。
なんだか嬉しくなってうながされるまま頼久の車の助手席に乗った。
「神子殿はただ立って微笑んでいて下さればそれでかまいませんので。私も特に挨拶などはありませんから。」
「あ、はい、わかりました。」
「立食とはなっていますが座るところも用意されているそうですから。」
「はい。」
頼久の説明を聞きながらあかねは小さなバックを手に緊張していた。
説明されればされるほどどうしていいのかわからなくなる。
そんなあかねをよそに車はホテルへ到着した。
「ほ、ホテル?」
「はい、ここの広間が会場ですので。」
すっかり出版社の建物でやるのだと思っていたあかねは更に緊張が増すのを感じていた。
ホテルで本格的にパーティ。
これはとんでもないところへきてしまったかも…
「さぁ、どうぞ。」
気付けば頼久が助手席のドアを開けて手を差し伸べていて、あかねはその手をとるとされるがままに車を下ろされ、あっという間に会場へ連れて行かれてしまった。
その間、何を考える暇もない。
ただ頼久の腕につかまって歩いているだけのようなものだ。
受付を済ませて会場へ入ればそこには物凄い数の正装をした人がいて、あかねは息をのんだ。
「神子殿?」
耳元で心配そうに頼久がそう呼ぶのが聞こえて、あかねはやっと笑顔を取り戻す。
「ごめんなさい、なんか圧倒されちゃって…。」
「大丈夫ですか?体調を崩されたのならすぐ…。」
「あ、いえ、体調は全然大丈夫です。ちょっと驚いただけですから。」
ここで頼久に心配させてはいけないとあかねは今できる精一杯の笑顔を見せた。
それでやっと安堵の溜め息をついた頼久はそのままあかねの手を引いて会場の隅においてある椅子へあかねを座らせた。
「飲み物でもとってきましょう。ここでお待ちを。」
あかねが引き止める間もなく頼久はすたすたと食事が用意されているテーブルへ向かって歩き出してしまった。
一人会場の隅に座るあかねはというと、特にやることもないからとりあえず辺りを見回す。
するとなんだかかなりの数の人の視線を感じた。
やたらと人に見られている気がする。
自分のいでたちがおかしいのかと心配してあちこちチェックしていると、すっと隣に若い男性が座った。
「あなたが元宮あかねさんですか?」
「あ、はい、えっと…。」
「あ、僕、源さんの担当です。」
隣に座った男は人懐っこそうな笑みを浮かべていて悪人には見えない。
あかねはただただ目を丸くしながら眼鏡をかけた人のよさそうな男の顔を見つめた。
「あぁ、こんばんわ。」
「こんばんわ。一つ聞いてもいいですか?」
「はい、なんでしょう?」
「あなた、源さんの婚約者って本当ですか?」
「……。」
キョトン。
あかねの思考は一瞬停止した。
なんで初対面の人にそんなことを聞かれているのかが全くわからない。
そしてここでハイと答えていいのかどうかも。
「えっと、どうして…。」
「もし違うなら、そう言ってください。まぁ、僕もまさかとは思うんですけどね。」
「はい?」
「源さんにストーカーみたいなことされたりしてませんよね?」
再びキョトン。
あかねには何がなんだか話が全く見えない。
「えっと…ストーカーはされてませんが…。」
「やっぱりそうですよね。あんな真面目な人がそんなことするわけないって言ったんですけど、僕の周りにはヤバイんじゃないかって疑ってる人がけこういましてね。」
「あの…話が全然見えないんですけど…。」
「あぁ、すみません。実はですね、源さんの記事は一部のファンからの評価が高いんです。それで今回の創刊雑誌にも連載を持ってもらうことになったんですが、担当が女性なら引き受けないといわれましてね。」
「……。」
「源さん、あの容姿でしょ、女性で担当したいって人がけっこういたんですが、全部NGで。最初は源さん、同性愛者なんじゃないかって噂が立ったんですよ。」
「…それは絶対ないと思いますけど…。」
あかねは引きつった苦笑を浮かべながらそう言うと小さく溜め息をついた。
「みたいですね。その噂がたった直後にあの書斎で、今度はストーカー疑惑が持ち上がりまして。」
「あの書斎?……あっ。」
「ええ、あなたの写真が書斎いっぱいにはられているのを見ちゃいまして、僕。確かに元宮さんはかわいらしいですけど、普通の女子高生でしょう?そんな女子高生の写真をあんなにたくさんはっているっていうのはちょっとね。」
「そう、ですよね…。」
それが普通の反応だとあかねも思う。
「で、ずっとどんなもんかと思っていたら急に源さんに説明されたんですよ。」
「説明、ですか?」
「ええ、一生を捧げると誓った御方だってね。」
「……。」
あかねは引きつった苦笑を浮かべたままハハハと乾いた笑い声をもらした。
確かにそれはストーカーとかちょっと病んじゃってる人と思われてもしかたないかもしれない。
「だから、あなたは承知しているのかなぁと。」
「えっと、なんと言ったらいいか…私はその…将来、私がちゃんと大人になった時にまだ頼久さんが今と同じように思ってくれてたらお嫁さんにしてもらえるといいなって思ってます。でも、今はまだ、私は全然子供だし…。」
何をどう説明したらいいのかわからない。
あかねはもうどう説明していいかわからず困り果ててしまった。
だが、そんなあかねをよそに人のよさそうな男はにっこり微笑んだ。
「なるほど、わかったような気がします。」
「はい?」
「源さんがあなたを選んだわけが。」
「はぁ…。」
「今時の高校生とは思えないほどしっかりしていらっしゃる。まぁ、だからといって一生を捧げるというのはちょっと行きすぎじゃないかとやっぱり思ってしまいますが。でも、あなたなら納得できる気がします。」
「はぁ……。」
何も言えずにいるあかねにもう一言何か言おうとしたその時、人のよさそうな男ははっと何かに気付いて苦笑すると、軽く手を上げて立ち上がった。
あかねが振り返ってみるとそこには飲み物を手に戻ってきた頼久が立っていた。
「では、またいずれゆっくり。」
厳しい目でにらみつけている頼久に手を振って、男は人込みの中へと去っていった。
「神子殿、彼が何か失礼を申しましたか?」
「いえ、ちょっとお話してただけです。」
あかねがそう言って微笑むと頼久はほっと安堵の溜め息をついた。
飲み物をあかねに手渡して頼久があかねの隣に座って人込みへと目を向けると、今まであかねに向けられていた視線がいっせいにそらされた。
「申し訳ありません。」
「はい?」
「どうやら好奇の目を向けられているようで…。」
「あぁ、事情はさっき担当さんから聞きました。」
「事情、ですか?」
「頼久さんがあんなにたくさん書斎に写真飾ったりするから、ストーカーと間違えられてたみたいですよ?ひょっとして自覚なかったんですか?」
「……だから神子殿をここへ誘えとしつこく言われたのですね…。」
「でももう大丈夫ですから。ちゃんと説明しておきましたから、私、ストーカーなんかされてませんって。」
「申し訳ありません、色々とお気遣い頂いたようで…。」
心底申し訳なさそうにしている頼久にあかねは微笑んで見せた。
「私、気にしてませんから。頼久さんはちゃんと私のこと説明してくれてたわけだし。説明のしかたには問題あったかもしませんけど……でもほら、せっかくのパーティ、楽しまないと。」
「神子殿…。」
優しく微笑んでくれる恋人に微笑を返して、頼久はほっと安堵の溜め息をついた。
それでも一息ついて周りを見渡して見れば、やはりまだ好奇の目が自分たち二人をとらえている。
頼久はすっと立ち上がると、あかねの手をとって歩き出した。
「頼久さん?」
「もし宜しければ。」
そう言って腕を差し出されたのであかねがその腕に手を置くと、頼久は嬉しそうに微笑んで歩き出す。
「えっと、どうしたんですか?」
「見たいと思っている人間が多いようですので、見せてやろうかと。」
「はい?」
満足げに微笑む頼久の顔を見てゆっくり考えて、あかねはどうやら頼久が自分を見せつけて歩きたいらしいことに気付いた。
辺りを見回せば確かにちらちらと自分達の方を盗み見ている人はたくさんいるようで…
あかねは顔を赤くしてうつむきながら、それでも頼久の腕は離さずに歩く。
頼久が人前で堂々と一緒に歩いてくれることは嬉しかったから。
そして、どうやらあかねが嫌がっているわけではないらしいと気付いた頼久は、パーティの間中、ずっとあかねに腕をまかせたままそばを離れようとはしなかった。
いつの間にかパーティが終わる頃には、誰もが二人を暖かい眼差しで見守っているのだった。
管理人のひとりごと
初めて二人に正式な場所へ出席してもらいました(^^)
スーツ着てエスコートする頼久さん、いかがでしたでしょうか♪
ストーカーネタは以前に書いたことのあるネタを引っ張ってます(笑)
興味のある方はそちらも探してみて下さい♪(マテ
あそこまで神子殿馬鹿(天真談)だとね、周囲から見たらちょっと異常(爆)
でもいいんです、あかねちゃん了解してますから(’’)
プラウザを閉じてお戻りください