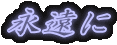
庭に咲く桜の花が花びらを散らし、新緑が少しずつ見え始めた頃。
あかねは泰明が指定した婚儀の日を迎えることになった。
待ちに待った婚儀の日なのだが、いざ当日となるとやはり緊張するもので、手放しで喜んでばかりはいられなかった。
朝から屋敷中がざわついていて、みんな忙しそうだ。
たくさんの調度品が新しいものに入れ替えられたし、あかね自身も綺麗な十二単に着替えさせられた。
最近は寒さもやわらいできたから十二単じゃなくてもいいと言っても聞いてもらえなかった。
夕方にはまた着替えることになるからと説き伏せられたのだが、頼久がやってくるのは夜のはずで、だとしたらどうして今十二単を着なくてはならないのかさっぱりわからなかったが、それでも女房達に楽しそうにされてはあかねに断ることができるはずもなかった。
婚儀だと冷やかしにくるかと思っていた友雅を始め、八葉の皆は誰も姿を見せていない。
それどころか藤姫もだ。
ただ、泰明からだけは大切な儀式の夜を何者にも邪魔されないように結界を強化しておく旨を書いた文が届いた。
藤姫は裏方に回って色々と手配してくれているようだから、この儀式が一段落するまではゆっくり会えそうにない。
一応、あかねは左大臣家の養女ということになっていたから、この婚儀は左大臣家と源武士団棟梁の家との婚儀でもあるのだ。
それでも、頼久があかねの元に通うという形をとったため、あかねが頼久の両親に挨拶をするとか頼久の家に入って源姓になるということはない。
そんな自分から離れていくような形の婚儀は許さないと藤姫が絶対に譲らなかった結果だった。
あかねにしてみれば、自分の世界では旦那様の所へお嫁入りをするイメージでいたから、少しばかり予想外の結婚になったけれど、それでも頼久と一緒にいられるようになるのなら別にかまわない。
普通であれば通い婚ということで、頼久は武士団からこちらへ通うことになるはずだったのだが、それではあかねが寂しかろうと周りが気を使って、婚儀が終了しだい、頼久はこの屋敷であかねと共に暮らすことになっている。
嫁入りはしなくても、あかねは元いた世界の常識と同じように頼久と共に暮らせることになっているのだ。
だから、少しばかり面倒なことがあっても、十二単を着せられても、とりあえずあかねは浮かれていた。
今までずいぶんと待たされた気がするのに、女房達が騒いでいるのを眺めている間に一日はあっという間に過ぎた。
夕方、まるで違う部屋のようになった自分の局であかねはほっと安堵の溜め息をついた。
局中が磨き上げられて調度も新しくなって、女房達もいつもよりこぎれいな格好をして、それでやっと屋敷中が落ち着きを取り戻した感じがした。
実際のところは女房達はまだあくせくと動き回っているし、浮ついた感じでいるのだが、それでも陽が落ちてしまうとさすがに物を動かす音や人の声は聞こえなくなった。
一人でゆっくり夕餉を取って、一人ニコニコとしていたあかねはだが、夕餉の後、いつものように縁で暗くなっていく庭を眺めているとそれを見かけた女房の一人が大声を上げた。
「神子様!まだそのようなお姿で!」
「へ?だって十二単着ててって…。」
「いけません!もうすぐ頼久殿がいらっしゃいますわっ!もう大変!」
気付いた女房は同僚を呼びつけて、あかねを局の奥へと連れ込むと、さっさと着替えを開始してしまった。
もうこうなるとあかねには抵抗のしようがない。
されるがままに着替えを済ませると、満足げにうなずいた女房達はさっさと局を出て行ってしまった。
しかも蔀戸は全て閉じられてしまって、小さな明かりがいくつかあるだけの薄暗い中に放置されたあかねは何がなんだかわからずに深い溜め息をついた。
ただ、今日から三日間、夜になると頼久が訪ねてくるということだけは聞かされていたから、とりあえず頼久がやってくるのを待つことにする。
頼久が来てくれるのなら何が起こっても安心だ。
頼久に会うのだからとあかねが自分の今のいでたちに気を配れば、どうやら女房達の手で寝巻きを着せられてしまったようで、またあかねは溜め息をついた。
何も結婚式の夜に寝巻きで旦那様を迎えさせなくてもいいのに。
あかねが胸の内でそんなことを考えていると半蔀の向こうでかさりと衣擦れの音がした。
「頼久、さん?」
「はい、お待たせ致しました。中へ、宜しいでしょうか?」
宜しいも何も入ってもらわなくては結婚式が始まらないのに、などと思いながらあかねは頼久に入室の許可を出す。
かたりと音がして半蔀をくぐった頼久が中へと入ってくると、その姿を見てあかねは目を見開いた。
「うわぁ。」
「は?」
「あ、ごめんなさい、頼久さんがそういう格好してるの初めて見るから。」
「はぁ…。」
あかねの前へ姿を現した頼久は単を着ただけのラフな格好で、それはいつもきちんとしている頼久には見られない姿だ。
「お見苦しいようでしたら着替えて参りますが…。」
「み、見苦しくなんかないです!素敵だなぁと思っただけです…。」
顔を赤くしながら最後は声を小さくするあかねを見つめて頼久は優しい笑みを浮かべた。
素敵だなどと言われて気分の悪いはずがない。
「頼久さんせっかくそんなステキなかっこうしてるのに、ごめんなさい、私、なんかみんなに寝巻き着せられちゃって…。」
「は?」
「昼間は十二単着てたんですよ、みんながどうしてもっていうから。それなのに、さっき、頼久さんがくる直前に着替えさせられちゃったんです。寝巻きで結婚式なんてもう…。」
「……。」
あかねの前に座った頼久が何やら難しそうな顔で考え込んでしまった。
これはやはり自分のいでたちに問題があるのかとあかねが不安そうな表情で小首をかしげ、目の前の許婚を見上げる。
すると、はっと我に返った頼久がぶんぶんと頭を振った。
「頼久さん?やっぱり私、着替えてきましょうか?」
「いえ、そういうことではなく…。」
「はい?」
「一つ、お尋ねしても宜しいでしょうか?」
「はい、どうぞ。」
「神子殿は今宵の婚儀がどのように進行するか何者かにお尋ねになりましたか?」
「えっと、一応聞いたんですけど、みんな忙しそうで。とにかく今日から三日間、夜だけ頼久さんが通ってくるっていうことしか聞いてないんです。私、自分の世界でも結婚式ってちゃんと出席したことなくて、どんな感じなのかあんまりよく知らないんですよね。でも、みんな朝からずっと忙しそうだし、それに頼久さんが来てくれれば教えてくれるかなと思って詳しいこと聞いてないんですけど…まずかったですか?」
「いえ…。」
再び黙り込んだ頼久はさっきと同じく難しい表情で何事か考え込んでしまった。
これは自分があまりに何も知らないからあきれられたのかとあかねが不安で目に涙さえ浮かべてうつむいても、頼久が気付く気配はない。
「ごめんなさい、ちゃんと勉強してなくて…あの…教えてもらえればちゃんとしますから…。」
か細い声にはっとして頼久はふっと息を吐き出すとその顔に微笑を浮かべて見せた。
「いえ、お気になさらず。」
「それで、こっちの結婚式って、どんなことをするんですか?」
「は?」
「だから、三日もずっと結婚式なんでしょう?しかも夜ばっかり、三日も何するのかなぁと思って。」
「はぁ…その…。」
「私の世界では結婚式って一日で終わるんです。だから三日もかけるなんて何するのかなって不思議だったんですよねぇ。」
「そうでしたか…。」
「で、これから私、どうすればいいんでしょう?頑張りますから。」
「いえ、その…頑張って頂くようなことはないかと…。」
「そう、なんですか?だって三日ですよ?しかも夜通し、何するんですか?」
「そうですね…では話でも。」
「はい?」
「神子殿の世界の話などお聞かせ頂ければ。」
「私の世界の話、ですか?でも、頼久さんそんなの聞いててもつまらなくないですか?」
「いえ、神子殿のお話がつまらなかったことなど一度もございません。それに、三日後には共に暮らすことになるのですから、これまで以上に神子殿のことを理解したいと、そう思いますので。」
そう言って優しく微笑まれてはあかねに拒む理由などない。
もともと年頃の少女であるあかねはおしゃべりが好きでもある。
「そうですねぇ、何から話せばいいかなぁ。」
「さきほどお話されていた、けっこんしき、とやらのことでも。」
「あぁ、こっちでいう婚儀のことです、結婚式。綺麗な服を着て、友達とか親戚とかいっぱい呼んで、それでおいしいものを食べたりとかして。あ、形式は色々あるんです。詳しいことはよくわかりませんけど。でもお嫁さんってみんなとっても綺麗なんですよね。」
「神子殿も十分にお美しいですが。」
「そ、そんなことないですよ!だいたい、私の世界のお嫁さんは結婚式に寝巻きなんて着ないんです。こっちで言ったら十二単になるのかなぁ、ああいう豪華って言うかとっても綺麗な衣装を着て、一生に一度の晴れ姿!っていう感じなんです。」
「では、明日は晴れ姿になさいますか?」
「ん〜、でも十二単は冬中着てたし…身動きとれないし……頼久さんはどんな格好がいいと思います?」
「神子殿はどのようなお姿でも清らかで愛らしくていらっしゃいますので、衣装などなんでも。何をお召しになっても内からにじみ出る清らかさが淀むことはございませんので。」
「ま、また頼久さんはそういうこと言ってっ!」
「いけませんでしたか?」
さらりとそう言って小首を傾げる許婚にあかねは真っ赤な顔で溜め息をついた。
二日後にはこの人と一つ屋根の下、共に暮らすことになるのだ。
毎日毎日こんなふうに嬉しいやら恥ずかしいやらというセリフを聞かされたらどうしていいかわからない。
そう思って顔を真っ赤にして上目遣いに許婚の表情を盗み見てみると、恥ずかしいことを言った自覚のない頼久はただきょとんとあかねを見つめていた。
「こ、今度は頼久さんのお話も聞かせてください。
「私の、ですか?」
驚きで目を見開いている頼久にあかねはこくりとうなずいて見せる。
「私の世界の話は知らなくても頼久さんはなんにも問題ないかもしれないですけど、私はこっちの世界のことなんでも知っておきたいです。だから、頼久さんが私と出会うまでどんなふうに生活してたかとか、武士団の人達は普段どんなふうに生活してるかとか、色々聞きたいです。」
「はぁ…では、あまり上手く説明できるかはわかりませんが…。」
そう前置きして頼久はぽつりぽつりと語りだした。
もともと話をするのがあまり得意ではない頼久だが、途中、あかねがわからないところはきちんと質問することで特に不都合は感じなかった。
それどころか、あかねとゆっくり向かい合って語り合う時間は頼久にとって心地いいものとなった。
頼久にとって誰かとこんなふうに差し向かいで話をしていて気まずさを感じないどころか、ゆったりと心地いいのは初めてのことだ。
目の前には楽しそうに微笑みながらあいづちをうってくれる愛しい人。
夜の静けさの中で聞こえるのはただ互いの声だけ。
頼久は予想もしなかった穏やかな夜をいつの間にか満喫していた。
そうして互いに他愛もない話をすること数刻。
あかねが眠そうに目をこすり始めると、頼久はくすりと笑みを漏らした。
「ずいぶんと遅くなってしまいました。神子殿はもうお休み下さい。」
「え、でも…いいんですか?朝まで起きてないといけないとかないです?」
「はい、特にそのようないことはございませんので。」
「そうなんだ。じゃぁ、眠いから寝ちゃおうかな……。」
そういいながらあかねは何故か躊躇している。
頼久が小首を傾げてあかねを見つめていると、あかねは赤い顔でちらりと頼久を見るとすぐにうつむいてしまった。
「どうか、なさいましたか?」
「せっかくこんなふうに一緒にいるんだし、その…なんというか…もう少ししたらずっと一緒にいられるっていうのはわかってるんですけど…。」
「はぁ…。」
「三日間は昼間は会えないじゃないですか?」
「はい。昼は武士団の方の仕事をしておりますので。」
「だからその…私が寝るまで側にいてもらえませんか?」
一瞬、何を言われているのか理解できずにきょとんとした頼久は、湯気さえ上げそうなほど赤くなっているあかねをじっと見つめてから微笑を浮かべるとすっとあかねの隣へその身を移した。
「へ?」
今度はあかねが驚きできょとんとしている間に、頼久はすっとあかねの小さな体をその膝の上に抱き上げてしまう。
「よ、頼久さん?」
「お休みになられるまでこうしておりますので、安心してお休み下さい。神子殿がお休みになりしだい、褥にお運びしますので。」
「えっと……ね、眠れるかなぁ…。」
「眠れませんか?」
「わ、わかりません…なんかドキドキしちゃうし…。」
「…夜が明けきる前に武士溜まりの方へ戻らねばなりませんので…できればこのまま……。」
「え、そうなんですか?」
「はい。今宵と明日はまだ空が暗いうちに戻ります。」
「そうなんだ…。」
「明後日にはもう戻りませんので。」
頭上から降ってきたその言葉にあかねはやっと安心したような笑みを浮かべてうなずいた。
そしてそのまま頼久の胸に頬を寄せて静かに目を閉じる。
すると、今までドキドキしていたはずなのに、全身に伝わる頼久の体温が心地良くて、あかねはすぐに安らかな寝息をたて始めた。
頼久は自分の腕の中で幸せそうな顔で眠る許婚を見下ろして満足げに微笑むと、そのまましばらくその小さな体を抱きしめていた。
今宵はもっとたくさんあかねに触れるつもりできていたのだから、このまますぐにこのぬくもりを褥に寝かせて去ることなどできない。
頼久は春の空に陽が昇るその寸前まであかねを抱き続けるのだった。
翌朝。
褥の上で目を覚まして、自分一人きりであることに気付いたあかねは、なんとなく寂しくてすぐに身支度を整えて外へ出ると、待ってましたとばかりに女房達に囲まれた。
そして昨夜の首尾はどうだったのかと問い詰められ、あかねが正直に話すと、女房達は顔色を青くしたり白くしたり赤くしたりして大騒ぎした。
あかねは京ではもう結婚適齢期の年齢だったから、当然心得ているものと皆勝手に判断して昨夜が夫婦の契りを交わす夜だと誰も教えていなかったのだが、異世界からやってきたあかねはその話を聞いてやはり顔色を赤くして青くして白くした。
恥ずかしい話を聞いたのと頼久に申し訳ないことをしたという思いと、頼久の優しさに心うたれたのとであかねの感情は軽くパニックになり、頼久から届けられた文のおかげでそのパニックはなんとかおさまった。
女房達が後朝の文と呼ぶそれには頼久の几帳面な字で、あかねにわかりやすく歌ではなく文をしたためた旨が書いてあり、あかねの体調を気遣う優しい言葉が並んでいた。
あかねは急いで昨夜のことを謝る文を書いた。
あかねがそうして文を書いている頃、頼久はというと友雅に昨夜の顛末を上手く聞き出されてしまい、散々からかわれていた。
結局のところ友雅にはっぱをかけられた頼久と、女房達にきっちり教育されたあかねとが夫婦の契りを交わしたのは婚儀二日目の夜のことだった。
管理人のひとりごと
ということで、結局書いちゃいました(’’)
紫暗に書けるこれが精一杯です(マテ
裏っぽいことやる気が全くないので、婚儀どうしようかと思ったのですが、他にないちょっと面白おかしい感じでと思いまして…
期待はずれだった方、すみません(’’;
静かな夜に誰の目を気にすることもなく静かにおしゃべり。
この二人にはお似合いかなぁと。
抗議は受け付けませんので(っдT)
プラウザを閉じてお戻りください