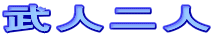
「では、行って参ります。」
「はい、いってらっしゃい。」
頼久はいつものようにあかねに見送られて屋敷を出た。
朝から愛らしい妻に見送られて頼久は上機嫌だ。
今日は特に警護の任務も入っていないから、雑務を処理して後輩達の面倒を見たらすぐに帰宅できるだろう。
朝からそんなことを考えながら頼久はすぐ近くの土御門邸へと足を踏み入れた。
向かうは武士団の棟だ。
後輩達と挨拶を交わして早々に支度を済ませるとすぐに道場へ向かう。
後輩達の面倒を見るのは次期棟梁たる頼久の重要な仕事の一つだ。
先にきて黙々と鍛錬をしていた若い武士達ははっと支度を終えた頼久へと目を向けた。
いつものように仏頂面で木刀を構える次期棟梁は迫力だ。
これでも妻を娶ってからはずいぶんとやわらかくなったものだと古参の武士に聞かされて、妻を娶る前を知らない若者は震え上がったものだ。
そして同時にこの次期棟梁をやわらかくしたというその妻とやらはどんな魅力の持ち主かと最近入ってきた若い武士などは興味津々だ。
「どうした、相手になるぞ。」
誰もかかってこないので頼久がそう叫んでみると、顔を見合わせた若い武士の中から一人が進み出て一礼した。
ここからは次期棟梁直々の稽古開始だ。
次々に倒される仲間を苦笑して眺めながら順番を待っている若い武士達は雑談を開始した。
「それにしてもあの若棟梁を和ませたっていう奥方はどんな方なんだろうな。」
「噂だと何やら神と対話する巫女様だったらしいぞ。」
「まぁ、まんざら間違いでもないけれどね、神と対話というよりは神に愛でられた神子殿だね。しかも天より舞い降りてこられた。人柄はまぁ気さくで愛らしい。容姿はというと、どちらかというと幼気が残っていて可愛らしい方だね。」
優雅に響く声に若い武士達が一斉に声のする方へ視線を向けた。
そこにいたのは、長い髪の先をもてあそびながら優雅に微笑んでいる美丈夫だ。
「橘少将様…。」
「ああ、かしこまらないでもらいたいね。今日は友人に会いに来たのだから。」
そう言って苦笑する友雅に武士達は一斉に深々と一礼した。
「おかたいね、この武士団は。」
そう言って同意を求めようとして友雅は視界に入れた頼久も他の者と同様に深々と礼をしているのを見てため息をついた。
「友人に会いにきたと言っただろう?堅苦しいな頼久も。」
「…友人とは私のことでしょうか?」
「……頼久、言い方に棘があるよ…。」
「いえ、友人になった覚えがありませんでしたので…。」
「命をかけて共に神子殿をお守りした八葉の仲間に冷たいことだ。」
そう言って友雅は深い溜め息をついた。
「そのような冗談をおっしゃるためにいらっしゃったのですか?」
「いやね、藤姫に呼び出されてね。」
「藤姫様に…。」
「神子殿に触発されたようでね。」
「は?」
「頼久のところは誕生日とか言って頼久の生まれた日を祝われなかったかい?」
「はぁ、祝いますが…。」
「それをね、藤姫もやりたがってね。今日は私が生まれた日だったのでね。」
「それは…おめでとうございます。」
「全くめでたくなさそうに言ってくれるね。」
「そのようなことは…。」
眉間にシワさえ寄せて頼久は黙り込んだ。
急の闖入者に稽古をつけられていた若い武士達は棒立ちだ。
「藤姫にこれでもかと祝ってもらったのでね、そろそろ帰ろうかと思ったのだが、せっかくここまで来たのだから友の顔を見ていこうかと思って寄ってみたというわけさ。」
「……。」
「しかし、見ていたら少し、私も体を動かしたくなったね。」
友雅はそう言って辺りを見回した。
「友雅殿?」
「頼久とはこれまで何度も共に戦ってきたが、ついぞ手合わせをしたことがなかったね。いい機会だ、一度手合わせ願おうか。」
「……。」
「なに、軽く一本。手加減は必要ない。同じ八葉の仲間だからね。」
友雅はそう言って近くにいた若い武士に手を伸ばした。
何を言うでもなく、自然と若者が自分が手にしていた木刀を友雅へと手渡す。
源武士団の次期棟梁と左近衛府少将との手合わせなどそう見れるものではない。
その場にいる誰もが息を呑んだ。
「友雅殿。」
「いいだろう?私と頼久の仲だ。」
「どんな仲ですか…。」
そういいながらも友雅が木刀を構えれば、頼久もそれ以上は何も言わずに木刀を構えた。
木刀を構えて立つ二人は立ち姿も美しく、一分の隙もない。
周囲を取り巻く武士達は二人の構えに見惚れた。
どちらが何を言うでもなく、自然と手合わせは始まった。
二人同時にゆっくりと足を開き、同時に互いに打ち込む。
木刀が激しくぶつかる重い音が当たりに響くのと同時に、打ち込んだ二人はもう体勢を立て直していた。
「やるねぇ。」
「友雅殿も。」
友雅はニヤリと笑ったが、頼久の表情が動くことはない。
互いに一撃打ち込んだだけでその腕がなまっていないことを感じ取ったらしい。
周囲の武士達が息を飲む中、友雅は笑みをおさめるのと同時に頼久の右腕めがけて木刀を繰り出した。
それをまるで当然のことのように木刀で受け流した頼久は、そのまま友雅の方へと一歩踏み込んで突きを繰り出す。
頼久の一撃を体を横へ滑らせてかわして、友雅は頼久のわき腹めがけて木刀を薙ぎ払った。
これは入ったと思われた刹那、頼久は身を伏せ、床を転がるように友雅の一太刀をかわしながら距離をとると、すぐに立ち上がって再び綺麗に木刀を構えた。
その時にはもう友雅も体勢を立て直している。
どう見ても二人の実力は互角。
周囲の者にはそう見えた。
「手加減は不要と言ったはずだがね。」
「手加減をした覚えはございませんが。」
「ふむ。」
短い会話を終えると二人は同じタイミングで浅く息を吸い込み、同時に前へ踏み込んだ。
構えは正眼、互いに互いの方へまっすぐに踏み込んだのだ。
『はっ!』
同時に同じような短い声を発して、二人の木刀は激しく打ち合わされた。
重い音が響き、それと同時に二人の手から木刀が弾き飛ばされた。
二本の木刀は回転しながら宙を舞い、呆然と二人を見守っていた若い武士達の間へカランという音をたてて落ちた。
勝負はついた、引き分けだ。
だが、周囲の者は皆、圧倒されて動けない。
勝負をつけた二人だけがただ、ほっと息をはいて緊張していた表情を緩めた。
「今日のところは互角ということにしておこうか。見事だったよ、頼久。ただ、本気ではなかったね。」
「友雅殿こそ、力を抜いておいでのようにお見受けしました。」
「まぁ、大事な夫に怪我をさせては神子殿にどれほどのお叱りを受けるかわからないしね。それに、頼久が手を抜いてくれているのに私だけ本気ということもないだろう?もともと私は本気だの懸命だのというのが苦手なのだし。」
そう言ってニヤリと笑う友雅に頼久は軽く一礼した。
今の手合わせで互いに手を抜いていたとは…
見守っていた周囲の者達は深い溜め息をついた。
「久々にいい鍛錬になったよ。」
「私も勉強させて頂きました。」
「いや、武士団の若棟梁の相手は私にはつとまらぬよ。」
そう言って軽く手を上げて友雅が去ろうとすると、頼久は少し思案した末に友雅を呼び止めた。
「友雅殿。」
「ん?」
「これから何か予定がおありでしょうか?」
「美しき姫君との逢瀬がといいたいところだが、今日は特に予定はないよ。何か私に用かい?」
「いえ、もしよろしければ我が屋敷においで頂けぬものかと…。」
「ほぅ、これは珍しい。頼久が私を招待してくれるとはね。神子殿を口説いてもよいというお許しが出たのかな?」
「…違います。」
「冗談だ、そう真面目に殺気を放つな。それで、またどうして私を誘う気になったのだい?」
「夕餉など御一緒頂ければ妻も喜ぶかと…。」
そう言って顔を赤くする頼久に友雅はクスッと妖艶な笑みを浮かべた。
この生真面目な男はいまだに自分の妻を妻と呼ぶことに照れがあるらしい。
「なんだい、結局は神子殿のためというわけか。頼久が私の誕生の日を祝ってくれるのかと思ったよ。」
「私は……妻は祝いたいのではと…。」
「ほぅ、妻が他の男の誕生の日を祝うのを許すとは心の広いことだ。」
「友雅殿…。」
「まぁ、せっかくのお誘いだ、断る理由は…。」
「頼久さん!友雅さんきてませんか?って、あ…。」
急に聞こえた愛らしい声にその場にいた全ての人間が声のする方へ視線を向けた。
『神子殿…。』
頼久と友雅がそう口に出さなければ縁に立っているのが頼久の妻であり、この京を救った神子だなどとは誰も思わなかっただろう。
慌てて走ってきたらしいあかねは水干姿で縁に仁王立ちしていたのだ。
その姿を見て頼久と友雅は苦笑を浮かべながらそそくさとあかねに歩み寄った。
「やっぱりここにいたんですね、友雅さん。」
「どうしたんだね?私が恋しくて探してくれたというわけではなさそうだが。」
「こ、恋しいとかそういうんじゃないです!たまに会ってお話したいなとはおもいますけど…って、そうじゃなくて!」
「私に何か用かな?夫の頼久を差し置いて神子殿の関心を向けて頂けるとは光栄だ。」
「また友雅さんはそういう言い方を…今日は友雅さんのお誕生日だって聞いてたから、お祝いしようと思って準備してたんですけど、招待するのをすっかり忘れてて、藤姫に聞いたらさっきまで藤姫のところにいたっていうからもしかしたらここに寄ってるかなと思って。」
「ほほぅ。それなら慌てる必要はなかったよ。今、頼久にお誘いを受けたところだからね。」
「へ、頼久さんが?何も話してなかったのに…。」
そう言って可愛らしい目を大きく見開くあかねに頼久は優しく微笑んで見せた。
「神子殿が友雅殿を祝おうとお考えになるだろうと思いましたので。」
「お、お見通しですね…。」
真っ赤になってうつむくあかねを頼久と友雅は優しく見守る。
そしてそんな二人を若い武士達は口を開けたまま呆然と見つめるのみだ。
最近入ってきた若い武士達にとってはこの妻を見守る優しい若棟梁の笑顔は奇跡に近い。
とんでもないものを見たような気にさえなっていた。
「皆はこのまま鍛錬を続けるように。」
頼久はそう言い残してさりげなくあかねを伴って歩き出した。
「さ、友雅さん、おいしいものたくさん用意したんです。」
「おいしいものをたくさんもいいけれどね、できれば今日だけはあまり見せ付けないで欲しいものだね。」
「はい?何をですか?」
歩きながらあかねがキョトンとした顔で友雅を振り返る。
見れば同じように頼久もわけがわからないというような顔をしていて、友雅は苦笑した。
「二人の仲がよいところをだよ。」
「そそそ、そんなに見せ付けてないです!」
「友雅殿…。」
怒るあかねにあきれる頼久。
二人の反応を楽しみながら友雅はクスッと笑みをもらした。
「神子様ぁ。」
3人が歩みを再開したその時、ちょうど門の向こうに牛車が止まり、中から聞き覚えのある声がした。
牛車から顔を出したのは藤姫だ。
「藤姫!どうしたの?」
「や、やはりわたくしも神子様のお屋敷で一緒に…。」
赤くなりながらそう言う藤姫に3人は優しい笑みを浮かべて見せた。
あかねと頼久が許可を出そうとしたその時、友雅が優雅な身のこなしで牛車へ乗り込んでしまった。
「友雅さん!」
「頼久との手合わせで疲れたのでね、私はこちらで藤姫と一緒に向かわせてもらうよ。」
「手合わせ?」
あかねが小首を傾げているうちに牛車は出発してしまい、頼久が苦笑しながらあかねを伴って歩き出した。
「頼久さん、手合わせってなんのことですか?」
「さきほど、友雅殿に少々稽古をつけて頂いたのです。」
「へ?」
「詳しいことは帰りましてから。」
「あ、はい。そうですね。」
頼久と二人並んで歩くことが嬉しくて、あかねはそっと頼久の腕を抱いて上機嫌だ。
そんな様子を牛車の中から見つめる友雅と藤姫は、二人顔を見合わせて微笑んだ。
この日、友雅の誕生の日はあかねの屋敷で夜通し祝われることになるのだった。
管理人のひとりごと
気がつけば少将様のお誕生日!
ということで一日で作成(@@;)
誤字脱字はご容赦下さいm(_ _)m
たまにはお二人が武人らしいところを書いてみようかなと。
少将様のお誕生日ではあるんですけど、どうしても頼久さんも書きたかったのです(’’)
少将様、お誕生日おめでとうございます(^^)
あかねちゃんと藤姫に祝ってもらえばそれでいいかもしれないけど、一応、管理人も(’’)
プラウザを閉じてお戻りください